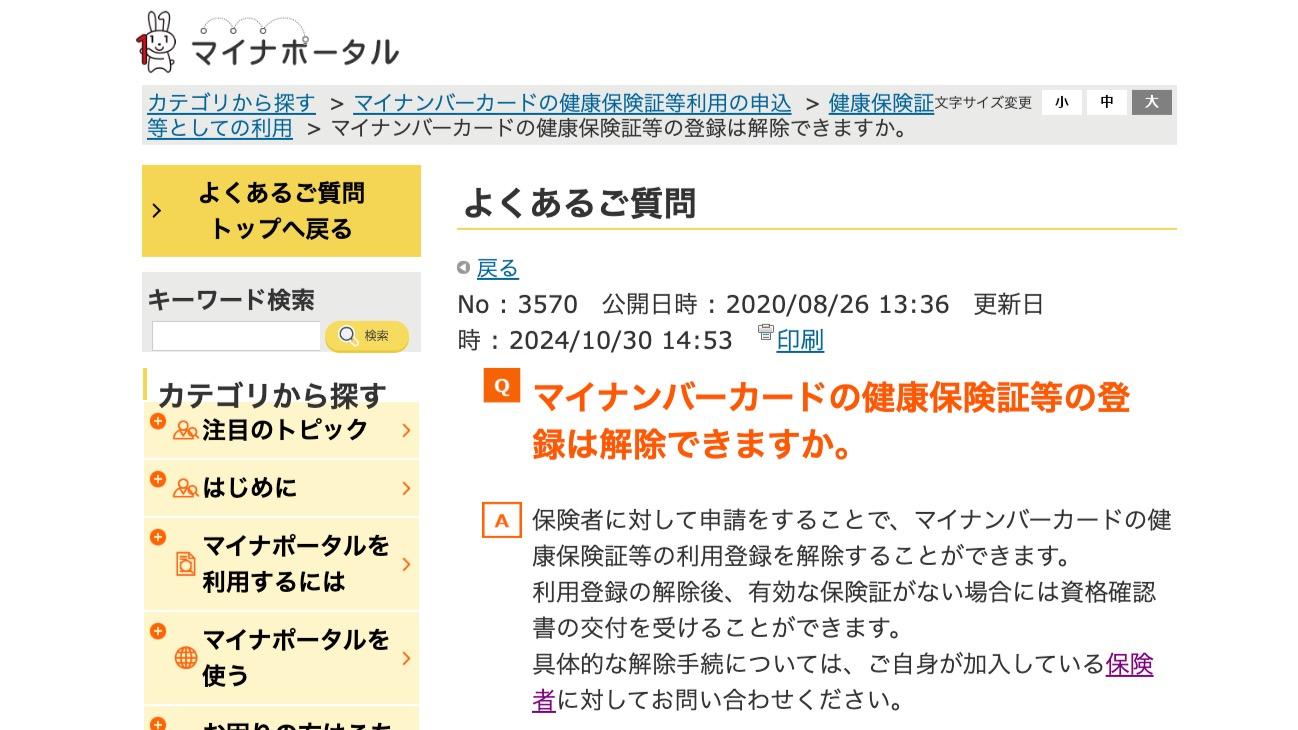食費や交通・通信費の割合が増加中…30年以上にわたる二人以上世帯のお金の使い道の変化

二人以上世帯のお財布事情
生活をしている以上、食費や交通・通信費などさまざまな支出が発生する。二人以上世帯、つまり夫婦世帯ではどのようなお金の使い方をしているのか。総務省統計局が2021年5月までに発表した全国家計構造調査(※)の結果を基に、その実情を確認する。
今回支出について確認するのは「二人以上の世帯」。勤労者世帯の他に、年金生活をしている世帯も含まれることに注意。その世帯を対象に、1か月の消費支出(税金や社会保険料(=非消費支出)をのぞいた「世帯を維持していくために必要な支出」)が具体的にどのような項目に割り振られているのかを示したもの。現時点で取得可能値は1979年以降のものであることから、それ以降のものをすべて用いる。また個々の額が少数のため、「その他消費支出」独自の項目以外に「家具・家事用品」「光熱・水道」「保健医療」「教育」もまとめて「その他消費支出」に合算している。
各値を再計算した上でグラフ化したのが次の図。

現在に近づくにつれて「食料」が減り「住居」が増えていたが、2004年が底となり、それ以降は増加しているのが分かる。食の多様化や中食の多用化に伴う食費の純粋な増加に加え、元々エンゲル係数が高めな高齢層の、全体に占める構成比率の増加が、全体値を底上げしているようだ。
「交通・通信」の増加(直近では前回比で減少しているが)は公共機関やガソリン代の値上げの他、今世紀に入ってからは携帯電話の使用料金が影響しているものと思われる。子供がいればそれだけ携帯電話の負担も増えることになる。子供が小遣いから融通する(≒家計の上で消費支出にはカウントされない)ことはあまりない。また子供の小遣いが低迷、漸減している主要因は、保護者が携帯電話料金を負担する分があるからに他ならない。
一方、「住居」の割合が漸増しているのも確認できる。一般に「家賃は収入の2割から3割がバランス的に優れている」とされている。今グラフの割合は「消費支出」であり、「収入」ではない(収入は今件消費支出以外に、税金などの非消費支出や貯蓄などにも割り振られる)ことを合わせて考えると、「住居」の負担は決して小さくない。
電話通信料と食費
全体的な流れで気になるポイントを2つほど抽出し、詳細を見ていくことにする。
まずは「交通・通信」。昨今携帯電話関連の料金で世の中が色々と騒がしいが、その実情をかいま見る結果が出ている。次に示すのは「交通」「自動車など関連費」「通信」に細分化した上で、世帯主の年齢階層別に区分した、消費支出に対する費用比率。収入や所得に対する比率ではないことに注意。とはいえ、各属性における負担の度合いは十分推し量れる。

自動車関連の負担は年齢階層でさほど変わらない。29歳以下と70歳以上でやや落ちているが、これは保有世帯そのものが少ないのが主要因。また、交通費も負担度合いに大きな変わりはない。
年齢階層で違いが見えるのは「通信」。50代まではほぼ同じ割合で高い値が示されている。その中でも29歳以下はさらに高め。これは携帯電話(特にスマートフォン)の保有率が現役世代では高いのに加え、若年層ほど収入、さらには消費支出が低いからに他ならない。定年退職後の世帯も消費支出は抑えられるが、携帯電話の保有率は低く、また料金負担の軽い従来型携帯電話を使っているケースが多いため、「通信」の比率が底上げされることはない。
次いで「食料」、つまり食費。最近になってエンゲル係数が上昇していることについて、主に元々値が高い高齢層の構成比率が上昇したと説明した。実のところどの年齢階層でも「食料」の比率は増加している。

上記でも触れている通り、食料品価格の引上げよりもむしろ、食の多様化による支出増加の結果といえる。内食比率が減り、中食が大きく増えているのがその裏付けとなっている。
各データから分かることを箇条書きにまとめ直すと、
・被服、履物の割合は漸次減少。
・食料は減少から増加に転じる。
・住居費の割合は漸次増加。
・交通、通信や教養娯楽は漸次増加。
などとなる。「教養娯楽」が減り「交通・通信」が増えているのは、携帯電話の利用が多分に娯楽要素もあることから、実質的には娯楽としての支出が通信費にカウントされている面もあるのだろう。「食料」の増加への転換とあわせ、ライフスタイルの変化、多様化の実情が見て取れよう。
■関連記事:
【「自分の資産・貯蓄に満足」4割強、高齢者ほどより満足に(最新)】
【生活意識は全体と比べややゆとり…高齢者の生活意識の変化(最新)】
※全国家計構造調査
家計における消費、所得、資産および負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布および消費の水準、構造などを全国的および地域別に明らかにすることを目的としている。調査間隔は5年おきで、直近となる2019年は10月から11月にかけて実施されている。対象世帯数は全国から無作為に選定した約9万世帯。調査票は調査員から渡され、その回答は調査票に記述・調査員に提出か、電子調査票でオンライン回答をするか、郵送提出か、調査票ごとに調査世帯が選択できるようになっている。
(注)本文中のグラフや図表は特記事項の無い限り、記述されている資料からの引用、または資料を基に筆者が作成したものです。
(注)本文中の写真は特記事項の無い限り、本文で記述されている資料を基に筆者が作成の上で撮影したもの、あるいは筆者が取材で撮影したものです。
(注)記事題名、本文、グラフ中などで使われている数字は、その場において最適と思われる表示となるよう、小数点以下任意の桁を四捨五入した上で表記している場合があります。そのため、表示上の数字の合計値が完全には一致しないことがあります。
(注)グラフの体裁を整える、数字の動きを見やすくするためにグラフの軸の端の値をゼロではないプラスの値にした場合、注意をうながすためにその値を丸などで囲む場合があります。
(注)グラフ中では体裁を整えるために項目などの表記(送り仮名など)を一部省略、変更している場合があります。また「~」を「-」と表現する場合があります。
(注)グラフ中の「ppt」とは%ポイントを意味します。
(注)「(大)震災」は特記や詳細表記の無い限り、東日本大震災を意味します。
(注)今記事は【ガベージニュース】に掲載した記事に一部加筆・変更をしたものです。