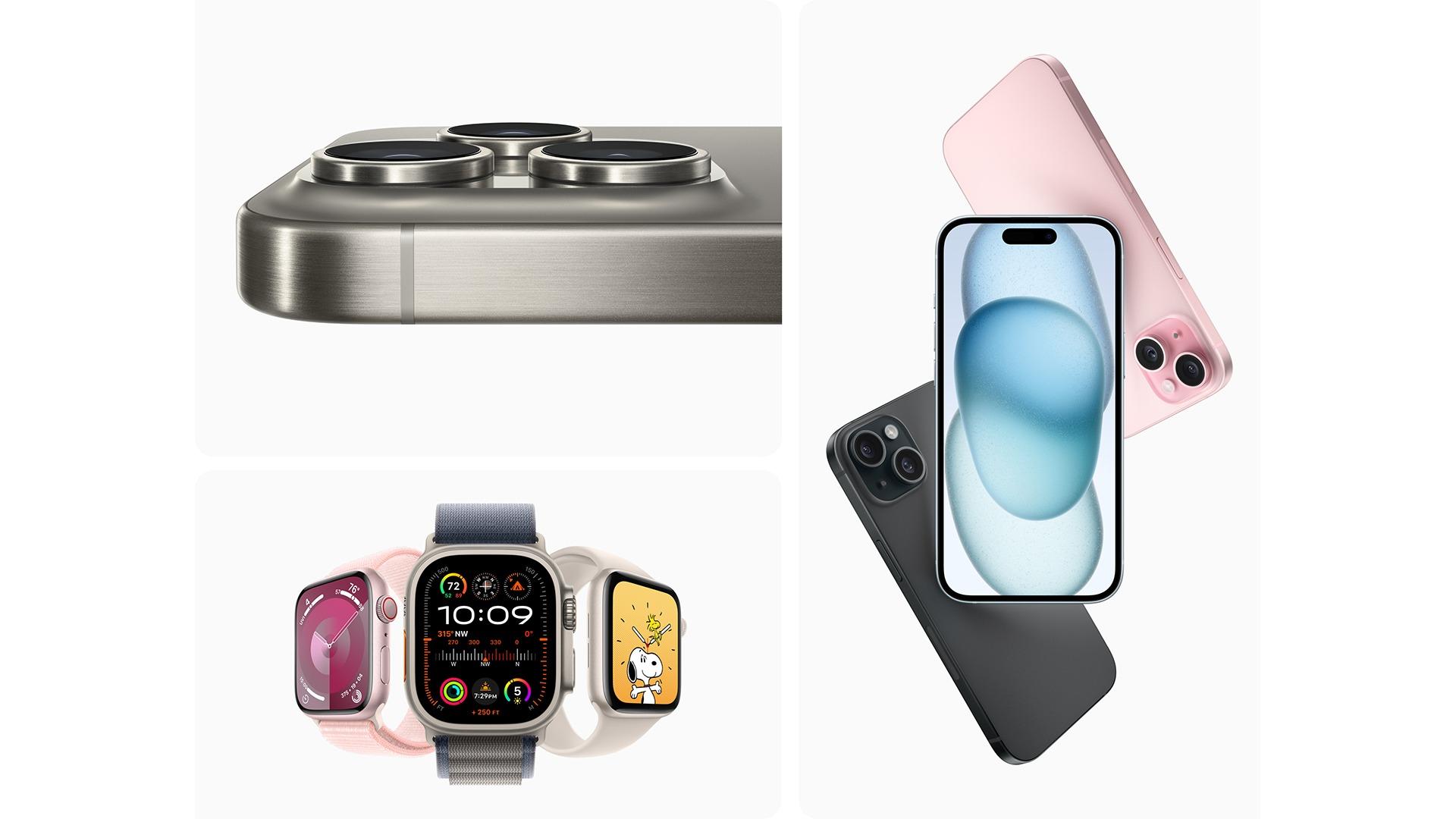Twitterの凍結騒動で考える性善説と性悪説の分岐点

ここ数日、Twitterの新しい取り組みが次々に話題になっています。
18日朝には、ツイッタージャパンが自殺願望のつぶやきを相談窓口に誘導する新機能を検討していると産経新聞が報じたと思ったら、18日中に、米国では暴力やヘイトに関する新ルールの適用が開始。
米国では多数の極右アカウントが次々に凍結されているようです。
参考:Twitter、トランプ大統領もRTした極右リーダーなど、新ルールに反するアカウントを多数凍結
一方で、日本のTwitterユーザーの間で最も注目されているのは、先週の12月13日夜からTwitterのアプリ開発者アカウントの凍結が相次いでいる点でしょう。
参考:Twitter、「APIポリシー違反」一斉取り締まり Togetterもログイン不可に アプリ開発者に不信感広がる
■日本最大規模のTwitter関連サービスもアカウント凍結
特にビックリするのは、日本でTwitterを使っていれば必ずといって良いほど、ツイートの発言まとめを目にすることが多いTogetterも今回の一斉凍結でアカウントが凍結され、一週間近くたった今でも凍結が続いてしまっている点です。

私個人も、Togetterのアカウント凍結のニュースは目にしていましたが、明らかにTogetterは日本におけるツイッター普及に一役買っているサービスですし、記事を読む限りポリシー違反もなかったという認識のようなので、てっきりすぐに凍結が解除される物だと思い込んでいました。
しかし、それが1週間近く音沙汰なく放置されるというのは、明らかに異常事態といえるでしょう。
Togetterとか月間で1億PVとか超えるみたいですからね。
結構Twitterにとっても重要なサービスなはずなんですよ。
それが、Togetterも普通のスパマー扱いされて一週間近く放置されてしまっているというのは、1ツイッターユーザーとしてもかなりショックです。
(おかげで、昨日開催したメディアミートアップのイベントでのツイートまとめが未だに作れないという、個人的なストレスが影響しているのもありますが)
実は恥ずかしながら、筆者の勤めるアジャイルメディア・ネットワーク株式会社のTwitterアカウントも、数ヶ月前に凍結されてしまっています。

幸いというか恥ずかしいというか、弊社では企業アカウント自体はAPI利用には使っていたものの、表のツイッターアカウント自体はホームページの更新情報の自動ツイートぐらいにしか使っていなかったので、現在までほとんどの人に気づかれずに今日に至っているのですが(汗)。
この凍結の際も事前の予告は一切無く、いきなり凍結されてしまってかなり戸惑っているのが正直なところ。
その後、いろいろと関係者の方々にアドバイスをもらいながら、API利用のアプリケーションの削除等の対応はしてみたものの、この記事を書いている現時点でまだ音沙汰無しというのが現状です。
会社としても、個人としても、結構Twitter普及に貢献してきたつもりだったので、今回の凍結はかなりショックでしたが。
Togetterですら凍結と言うことを考えると、うちなんか仕方が無いかなと、ついつい思ってしまったり(苦笑)。
ただ、正直、これが運営を委託されているクライアントのツイッターアカウントで発生したらと思うと、背筋が凍ります。
■米国におけるヘイト問題の緊急度と日本のズレ
関係者の方々の発言を総合するに、やはりTwitterにとって米国を中心に議論になっているヘイト問題への対応が最優先になっているというのが、おそらく現状なのでしょう。
その結果、その対応を機械的にスケールさせるため、ある程度ヘイト団体のユーザーや、そういった団体が使いがちなスパム手法に近いAPI活用を、一斉に凍結しているのではないかと想像しています。
ただ、日本においては米国ほどヘイト問題は深刻な社会問題と捉えていないTwitterユーザーが多いのもあり、Twitter上の発言を見る限り、今回のような一斉凍結は明らかに行き過ぎと受け取っているユーザーが多いようで、Twitterに対して辛辣な発言が多数見受けられます。
特に個人的にも残念なのは、9月頃からの一連のTwitter凍結騒ぎを受けて、11月にジャック/ドーシーCEOが来日し、アカウント凍結を施行する際にミスがあったので、改善しなくてはならないと思っているという発言をし、改善されることを期待したにも関わらず、一ヶ月たったらまたしても、というか以前よりもさらに酷いアカウント凍結祭に発展してしまっていることです。
参考:アカウント凍結「日本でもミスがあった」 TwitterのドーシーCEO、「改善に注力」
■性善説ベースから性悪説ベースへのシフト
Twitterのようなウェブサービスが、ユーザーが増えたり知名度が上がる過程でトラブルが増え、従来の性善説ベースでの対応から、性悪説ベースでの対応にシフトしなければいけなくなるタイミングというのは、歴史を振り返ってもいろいろ存在します。
似たような話で言うと、mixiが2006年9月に上場した後に、画像流出騒動などmixiユーザーの騒動が注目され社会問題になった結果、mixiが登録時に携帯電話の個体識別番号を必須にした例が象徴的です。
これにより、mixiは誰でも手軽に登録できる性善説的な登録の仕組みから、携帯の個体識別番号を持っていない人は登録できない性悪説的な登録の仕組みに舵を切ったといえるでしょう。
最近ではメルカリが、現金や盗難品などの不適切出品が相次ぐ問題に対して、従来の性善説的な簡易ユーザー登録の仕組みから、個人情報の登録を義務化する方向に舵を切ることを発表しましたが、メルカリ側が思っていたよりも、「社会からメルカリがプラットフォーマーとして見られている、ということに気づくのが遅れた」と山田CEOが反省の弁を述べています。
当然、サービス運営者の側からすると、ユーザーの利便性を考えて、できるだけ性善説で敷居が低いサービスにするのが望ましいわけですが、残念ながら世の中には悪意を持ってそのサービスを使おうとする人が存在するため、どこかで性悪説の視点で、悪意を持った人を排除する仕組みを導入していかなければいけなくなるわけです。
ただ、問題はその性善説から性悪説へのシフトに失敗すると、サービスが力を失うことが多いことも良くあると言う点です。
前述のmixiは、社会批判に対応するため携帯電話の個体識別番号を必須にした結果、海外やスマホからは登録できなかったり登録が面倒というサービスになってしまいました。
これにより、その後のスマホ化の流れに大きく乗り遅れてしまった印象があります。
日本の大企業が開始するウェブサービスがユーザーを集めるのに失敗する典型的なパターンというのは、最初のユーザー登録でやたらとたくさんの個人情報を入力させられることが多いからというのも、良くある話です。
大企業だとリスクヘッジのために、性悪説的な視点になりがちで、それがユーザーからすると大きなハードルになってしまうわけです。
■日本でTwitterではなくツイッターとして運用できないのか
個人的には、ある意味、初期のTwitterというのは、ネット的な典型的な性善説前提のウェブサービスだと思っていました。
FacebookやGoogle+のように実名を強制するわけでもなく。
運営側のルールや価値観をユーザーに押しつけるわけでもなく。
ユーザーと共に使い方を開発し、ユーザーと共に進化してきたサービスだと思います。
そのTwitterもサービス開始から10年が経ち、上場し、利益を出すことを求められ、社会的責任を追及される立場になり、トランプ大統領という象徴的な問題児を代表的なユーザーとして抱えてしまい、昨今のヘイト騒動の責任者の一人としての非難が高まる構造になり、おそらくTwitter社内では、性善説的なポリシーから、性悪説的なポリシーに一気に舵を切らざるを得ない状況に追い詰められてしまっているような気がします。
だからこそ、ヘイト騒動に対する解決の姿勢を見せるのが最優先で、ヘイト騒動とは一件無関係そうなTwitter開発者やTwitter関連のウェブサービスも、巻き添えを食らって一斉に凍結されてしまったりする事態が起こってしまい、Togetterのようなユーザーからは重要なTwitter関連サービスも一週間放置されてしまうような事態になってしまうのでしょう。
正直、米国の騒動やTwitterのおかれている立場を考えると、今の米国Twitterの対応方針はある程度は仕方ないのかな、という印象もあります。
ただ、それでも、2007年3月から10年以上Twitterを使いながら、日本独自のツイッター文化の広がりを目の当たりにしてきた1ツイッターユーザーからすると、なんかここまでドライなやり方はどうなんだろうと思ってしまう今日この頃。
なんとかTwitter Japanの方々には、世界有数のTwitterアクティブな国である日本において日本独自の自治を確立し、米国「Twitter」のドライなやり方とは異なる日本の「ツイッター」としての聞く耳のある運用方法を見つけて頂きたいと強く感じる今日この頃です。
ということで、またも無駄に長くなってしまいましたので今日のところはこの辺で。
とにかくメディアミートアップのツイートを早くまとめたいので、Togetterだけでも早期に凍結解除されることを祈っております。
追記
無事に12月21日、Togetterの凍結が解除されたようです。良かったです。