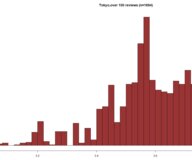空想科学対談2025年のIT批評(1) 『ゲーミフィケーション』が言われなくなる世界で
(2013年に発刊された雑誌『IT批評 vol.3』掲載の出版社の許可を経て転載させていただきます)
本稿は、今より12年未来、2025年における、『IT批評』を想定した架空の対談である。
テーマとなるゲーミフィケーションとは、人と人のコミュニケーションのみならず、さまざまな事物に関わるコミュニケーションを更新させるものである。その考えを延長すれば、あらゆる現実と人の関わりを調整する概念が視野に入る。
本稿で『リアリティ・チューニング』と呼ぶそれは、システムと個人、制度と人間の関係、さらには情報とコミュニケーションの連携の未来を考察させるものだ。
登場人物
池上 梓(53) 1972年生まれ、専門は情報社会学。慶早大学客員教授。著書に『リアリティの権利とテクノロジー』(2020)、『〈わたしの世界〉はいかにあるべきか』(2021)。コメンテーターとしてTVなどでも活躍する。
牛邊芳紀(28) 1997年生まれ、ウェブクリエイター/RTTデザイナー。多数のゲーミフィケーション/RTTの設計に関わる第一人者。2013年麻布高校在学中に『最もエキセントリックな高校生』としてメディアで紹介されたのをきっかけに各方面で活躍をはじめる。
■なぜ、『ゲーミフィケーション』という言葉は消えていったのか
――ここ数年、ゲーミフィケーションという言葉に代わって新たにリアリティを調整するためのテクノロジー群(リアリティ・チューニング・テクノロジーズ:以下RTT)という言葉がよく普及しています。『さまざまなものにゲームの要素を付け加える』という意味のゲーミフィケーションという言葉は一時期、騒がれたわけですが、最近は、誰も言わなくなりました。
RTTとゲーミフィケーションが共通に持っている問題は何なのか、という点について本日はお伺いできればと思っております。
議論全体を俯瞰していただくための論者として池上梓教授。そして、実際にリアリティ・チューニングのサービス実装の実務に関わる第一人者である牛邊芳紀さんに、議論の整理と実際ということでお伺いしていきたいと思います。
池上「まず、『ゲーミフィケーション』という言葉の解説から改めて入ろうか。やはり、ゲーミフィケーションというのが騒がれ始めた2011年頃というのは、それ相応のインパクトのある背景があった、と。そのとき何が言われたのか。井上明人の『ゲーミフィケーション』(2012)では次のような事例がとりあげられているんだよね。
一つは、行動を具体的に起こさせる行動デザインの話です。オバマが2008年の選挙戦で、ゲーミフィケーションを活用した、という事例。選挙支援者150万人を動かすためのSNSを作ったというもの。
でも、150万人をSNSに招いたとしても、単にSNSで日記を書いてもらうだけだと選挙支援の効果がないわけ。具体的に選挙支援行動をしてもらう必要があって、支援者の行動をデザインしなければいけない。そこで、オバマSNSでは『勧誘電話をかける』『メールを出す』『献金をする』といったアクションを、SNSを通じて具体的に行なってくれた支援者に対してポイントを与えたり、協力してゲームを遂行するような仕掛けを組み上げた、と。これが大きくあたりました。なんと、マケイン陣営の7倍近いネット献金を達成した。
オバマは、選挙戦ではじめてネット献金の力を大幅に活かして勝利した米国大統領として知られてるけど、その選挙支援者をとりまとめるためには、ネットのような『関係性の薄い場』でうまく行動をしてもらう必要がある。そこでは、行動をデザインする技術が必要になったわけだね。
そこで、こういったものをまとめてゲーミフィケーションと呼びましょう、という機運が生まれた。
また、この本はちょうど東日本大震災のあった直後の話なので、著者自身が手がけた節電行動を効率化するゲームという話なんかも出ていて、現実をどう解釈し、その解釈した世界観を現実の世界と融合させていくか、という一つの思想的実践としても、意義を主張しようとするものだったよね」
牛邊「いや、まあ、確かにそういう話もあるにはあるんですが、何をピックアップして語るかという認識からしてちょっと私と既に違う。井上の2012年の話っていうのは一言でまとめると、インフラコストの低下の話ですよね。実は、この本の根幹は、メインの主張だけを抜き取るとそのことしか主張していない。『現実空間にセンサーがつきました。ビッグデータです。O2Oです』と。『だから、現実空間をゲームの素材にするための各種のインフラコストが低下しましたよ。だから、今、ゲーミフィケーションの成功例が多くなってきたのだし、いま、推進する意味があるんだよ』という世界観で貫かれている。
だから、ビジネスチャンスも出てきましたよ、という話です。
今ではあたりまえですが、バッジヴィルのような、ありとあらゆるサイトのアクセスログデータなど、記録可能なデータを『ポイント化』して、ゲームにしてしまおうというようなプラットフォームサービスが出てきたのがちょうどこの頃です。センサー技術や、スマートフォンといった技術インフラが整ってきたことによって、そうしたサービスがちょうど拡大しやすくなる。
また、この時期に前後してFoursquare や、ケータイ国盗り合戦といった地理情報を利用したゲーム的サービスのプラットフォーム競争が激化します。なぜ、この時期にこうした競争が起こったのかには明確な理由があります。現実空間を実際に測り、ゲームのデータとして変換しなおす、各種のセンサー技術の普及と、そのデータを常時確認できるスマートフォンの普及がありました。
それらが『ゲーミフィケーション』の大きな背景になっているわけです。
『現実空間を新しいゲーム空間として使えるようになりましたよ』という事態がまず最初にあって、そこにゲーミフィケーションという話がのっかっています。2011年当時は、そう言ってもまだみんなピンとこなくて、新手のポイントカード商法か何かだとしか思われていなかった。
それまでになかったインパクトのある事例がでてきた、というのがまず、最初に宣伝されたわけですね。実際、2010年以前だったら、ゲーム的な要素を現実に取り込むって、超大変なわけですよ。スマートフォンも普及してなければ、センサーでの行動把握もできない。SNS加入者率も低い。現実空間にゲームのレイヤーを重ねることができないわけじゃないけれど、『ハンコを押す、ポイントカード』みたいなサービスしか、みんなパッと思い浮かばない。ただ、具体的にどういう手法をとるかみたいな部分の想像力は、2012年時点だと、未来像のイメージみたいな話が多くて、なかなか当時は共有されなかった。
この後も、たぶん、いろんな話になると思うのですが、ゲーミフィケーションとかRTTの話というのは、技術変化だとかの社会的な話と、リアリティを操作する現場レベルの手法の話との二本立てなんです。ずっと。
今日は、どちらの話をメインにすればいいですか?」
■利用者のイメージができなければ、リアリティのチューニングはできない
池上「牛邊くんは、手法のスペシャリストだから、手法の話をぜひしてほしいと思います。技術変化のほうは私のほうでフォローさせてもらえれば、いいかな」
牛邊「いや、どっちかにしたほうがいいじゃないですか。後者の話と、前者の話で読者層そのものが違うはずです。前者の話は、社会科学的視点で、経営戦略レベルの興味です。後者の話は戦術レベルの話で、RTTのデザイナーとかの現場担当者レベルの話です。そもそも、この雑誌の読者はどちらなんですか?」
――そこは特に絞っていません。
池上「経営サイドに近い人にとっても現場の情報が大事だと思ってるし、現場に近い人は経営サイドが何を考えているかを知る機会になるということでは、重要なのではないだろうか」
牛邊「一般論としてはわかりますが、ここは一般論ではなくて具体的で、ローカルな場所ですので、その捉え方には反対ですね。
単に両方を提示しても、うまく話が連動してないと読み飛ばされますよ。興味ないところが半分あると、内容が半分に薄くなって『ぬるい対談だな』と思われて終わると思います。両方あって、バランスがいいものもできなくはないでしょうが、難易度が高い。
すごく手間が必要です。たぶん、この対談を何度もやって、我々も編集も苦労して対談原稿を編集しないと、いいものができないと思います。しかし、締切が近いでしょう」
――牛邊先生は、一昨日にお父様がお亡くなりになられたということで、本日はお通夜があるとのことですので、今日は手短に……。
牛邊「いえ、大丈夫ですよ。名義上は、私が喪主ですけど、うちの母親が仕切りたがりなので、お通夜開始の10分前まで大丈夫です」
――いえ、それはさすがに申し訳がないので。
牛邊「いえ。大丈夫です」
池上「今日は牛邊くんの時間をとるわけにもいかないし、確かに難しいかもしれないね」
牛邊「いえ、通夜の話はいいです。読者のリアリティとどう接続するのか、のビジョンが私に見えていない。そのビジョンが見えないと、何を話していいかわかりません」
池上「まさしく、いま、この瞬間がリアリティのテクノロジーの現場だ、ということだね(笑)」
牛邊「いや、そこの感覚はたぶん、池上さんとの違いだと思います。いま、わたしは20代後半ですが、読者層の島宇宙化が池上さん世代よりも激しいというのが基本認識です。70年代生まれの池上さんの世代のほうが、『一般教養』的なものの残滓がまだ活きますね。だから、読者層に対するこだわりが違うのかもしれませんが。『多角的な視点』の演出をする難易度が昔より上昇しています。
池上 そうかもしれない。ゲーミフィケーションの話は当時の日経新聞(2012年4月1日朝刊)の一面にもある。新聞の一面、という場所は『一般教養』『みんなが知るべきニュース』という位置づけをもっていた。新聞の凋落とともに、こういった討議のための教養前提をみんなで知っておきましょう、みたいな前提が共有できなくなってしまった。こういった、『みんなが知っておくべき論題』という位置づけのものを復活させよう、というのもゲーミフィケーションや、RTTのデザインによってできるのではないか。牛邊くんには、そういうリアリティのチューニングを今日はしてもらうつもりでいてほしいと思う」
牛邊「それは、思想的な立ち位置の話でもありますね。新ハーバーマス主義者である池上さんらしいご発言です。確かに、私も新聞的な、公共的なアジェンダ・セッティング機能を改めて再調達しようという話自体には賛成です。
しかし、それは、いまここでやれることではないです。池上さんがNHKで、そのコメントをされるのなら反対しませんが、この雑誌のような専門誌のメディアの役割は、基本的には公共的興味よりは、もっと狭い興味で手にとるわけです。ここで公共圏の再設計を願うのは、場所が違っている。ごく、具体的な読者の興味に応えるような話として、徹底させていくのが正攻法だと思っています」
――編集サイドの意図としましては、先ほど池上先生に言っていただいたような役割分担でお願いしたいと思っております。とりあえず、その役割分担でお話していただいて、文字起こしして編集をする際に、改めてどちらに焦点化した編集をするか、ということではダメでしょうか。
どうせ、ソーシャル・リーディングによってカスタマイズされるわけです……。
牛邊「いや、だからですね。わからないかな。それだと中途半端な内容だと思われるだろうと言っているのです。ちょっと勘弁してよ」
池上「牛邊くんの言いたいことはわかりました。いずれにせよ、牛邊くんには、手法的な部分をしゃべってほしいということで本日は呼んでいるわけです。私のほうで、論点をあげながら、牛邊くんには、手法的な部分をメインにしゃべってもらうということでお願いしたいと思う。
この雑誌の性格的に、ある程度、思想的な部分への広がりを意識しつつ、なぜ一つの現象が転換点を迎えているのかということを考えられるようにしよう、というのが意図です」
牛邊「わかりました。さすが池上さんです。ゲーミフィケーションから、RTTへの変化は、ごく単純に起こるべくして起こったあたりまえのことで、古いとか新しいとかの話じゃない。技術条件の変容と、ノウハウの発展。この2つに尽きると思っているので、これを読んだ人が『いまさら日経とかで騒いでる奴らはバカなんだな』ということを思える内容に落ち着かせたいですね」
池上「はい。では、お願いします。それにしても、いまの牛邊くんのコメント自体がやはり、RTTを体現したものですね。『リアリティをチューニングします』といったとき、多くの場合技術単体とか、サービス単体の問題で捉えられがちです。だけれども、実践的にはサービスが消費される文脈そのものをきっちりと定義することから、リアリティの構築プロセスははじまる、ということだね」
牛邊「あたりまえです。ユーザーがどのようなコンテクストやリテラシーの連続性をもっているかどうか、というのはRTTにおいて必須となるスタート地点です。これは、もう、ないと話にならない。だから、こだわってるんです」
■強制力をもったゲーミフィケーションは最悪〜失敗の中心的問題
池上「話を戻して、ゲーミフィケーションの成功例だけど、2010年代半ばには、評判の悪い言葉になっていった。なぜか、というとゲーミフィケーションの成功例自体は、ある程度の頻度で出てくる一方で、残念ながら『誰でもゲーミフィケーションで一定の成果を上げられますよ』という部分にかなり限界があったから。
たとえば、その嚆矢になったのが、2013年はじめに行われたマクドナルドの『60秒キャンペーン』。マクドナルドで注文をした後、60秒以内に商品が出てこなかったら、バーガー類の無料券を贈呈するというサービスだった。しかし、これが、実際には現場では混乱を引き起こしたんですね。ドリンク類だけの注文などならまだしも、アップルパイだとか60秒で難しいメニューも実はかなり多かったし、熟練度の低い店舗だと難しかった。結局、お客さんをイライラさせ、現場のスタッフにストレスをかける結果につながってしまった」
牛邊「『ゲーミフィケーション』という言葉の反省は、一般のビジネスマンの『ゲーム』という言葉への想像力が乏しかったことに尽きると思います。一般の人は、『ゲーム』というと、どうしても競争の仕組みとか、クイズとか、そういうところに発想がとどまってしまう方が非常に多い。
私のところに相談に来る人も、まずクイズゲームとか作ってしまわれる方が未だに多い。クイズゲームや競争のゲームを嫌味なくきっちりと作るのは、実は素人にはハードルが高い。
一方で、ポイントカード的な手法はあまり絶大な効果があるわけではないですが比較的どういう状況下でも激しくネガティヴに機能することは少なめですね。そこの手法間の違いみたいなものが、『ゲーム』と言う言葉によって逆に見えなくなってしまった」
池上「なるほど。では、どういった具体的な対応が良かったと牛邊くんは思ってる?」
牛邊「要するに、競争をさせたりするんじゃなくて、いい雰囲気になれるリアリティを構築するステップを踏ませろ!というRTTの基礎中の基礎の話ですね。人が真剣にやってるのに、『これはゲームなんです』って言ったらやっぱり怒る人もいるわけですよ。私は真剣なゲームって沢山あると思うけど、そう考えない方も大勢いる。そういう問題はあるけど、発想自体は援用できる。
たとえば、60秒キャンペーンの一番よくなかったのは、マクドナルドのスタッフ側に、ゲームからの退出可能性が担保されていなかったこと。要するにやめたくてもやめられない。そのうえ、やたらとハードモード仕様のゲームになっていた。難しいゲームを強制でやらされたら、そりゃ反感を招くほうが多いに決まってる。
基本的に、『退出可能性を担保する』というのは、RTTのリスク設計において、RTTのリスクを少なくするためのオーソドックスなやり方です。もちろん、退出可能性のないケースも一部にはあります。たとえば、『車の運転手に制限速度を守って運転してくれていたら、クジがあたります』という試みがありましたが、あれはそもそものゲームの難易度を変えているわけではない。そのなかで、報酬を与えている。
ゲーム設定を新規に構築するのではなく、既に存在する状況にポジティヴなイメージを与えるだけ、という場合なら退出可能性が低い状況でも、不可能ではない」
池上「なるほど。似たような議論は、井上の本の中にも先取りして書かれてはいるね。確かに、それが世間的にじゅうぶん伝わっていなかった。当時の説で、『ゲーム』といった時に、エリート層が、イメージするものが、たとえば受験勉強だったり、出世レースだったりする人が多かったという説があります。そういった『難しいものにチャレンジできる』人々の特有のバイアスが妙な形で展開してしまったのではないか、という議論でしたね。
そういう『競争』とか『クイズ』じゃなくて、利用者のリアリティをきちんと気持よくしてやるための一連の手法群を『リアリティ・チューニング』と呼ぼうということで、2020年頃から、この話が出てきたんだよね」
牛邊「まぁ、『ゲーミフィケーション』という言葉が、聞き手に与える、リアリティのチューニング自体が、すごく失敗しやすかったわけですね。RTTという言葉自体も、一応、いまのところ生き残ってはいますが、言葉のニュアンスというのはナマモノなので、この言葉を2010年ごろに言っても、たぶん意味が通じにくい。2020年当時だったからこそ、というタイミングの問題は大きいです」
池上「その話は、デザインの歴史に近いものを感じるね。19世紀末のデザインといえば、アール・ヌーヴォーといわれる『いかにもデザインしました』という装飾性をもったものが一つの美術運動だった。その後に『アールデコ』が流行り、そして近代デザインがあり……と、しだいに見た目が派手なものではなくなってきた歴史があって。現代の一流デザイナーのなかには、『デザインの役割は、利用者にデザインをされていること自体を気づかれずに、利用者に意図どおりの行動をとってもらうことだ』という人が非常に多いわけ。利用者にどう行動してもらうかが重要であり『いかにもデザインしました』という見栄えこそが重要だという人は、ほとんどいない。RTTも、派手なものから、一見、地味なものになってきているように思うよね」
牛邊「その観察は一理あります。デザインの話で言うと、たとえばうちのバカ親父ですら『華美な装飾文字で、レストランのメニューが書いてあると読みにくい』ということは理解していた。デコレーションと、デザインは違う。あたりまえです。でも、デザインという概念を理解するために、デコレーションというステップは必要だったかもしれない。
概念が普及するためのプロセスということを考えると、現代におけるうるさくない、気づかれない『デザイン』のあり方と、19世紀のゴテゴテとした『デザイン』はもはや半分別のものだけれども、19世紀に『ああ、これがデザインってことね』という概念が理解されなければ、『デザイン』という概念そのものが社会的に成立しなかった可能性がある。
いま、デザインにおいて『誰にでも目に見えてわかるデザインっぽさ』というのは、デザイン手法のワンオブゼムですが、ゲーミフィケーションも『誰にでも目に見えてわかるRTT』という、RTTの一手法です。いまや、一手法でしかありませんが、歴史的意義としてはなくてはならなかった。未だに、無理解なクライアントだと『いかにも、それっぽいもの』が欲しいという人も多いのですけどね。リアリティのチューニングってのは、そういうこっちゃない。
みんなが、やりたいことのメインはプロセス制御なんです。そのツールも出てきた。でも、それをトータルに使うためのコアとなる全体プロセスの設計思想が必要で、たまたま最初に出てきたのがゲーミフィケーションだった。一番わかりやすかった。そういうことだと思いますよ」
※この記事は『IT批評 VOL.3 乱反射するインターネットと消費社会』(2013/3/20)に掲載された記事をもとに構成しています。
(続きは翌日以後に掲載させていただく予定です。)