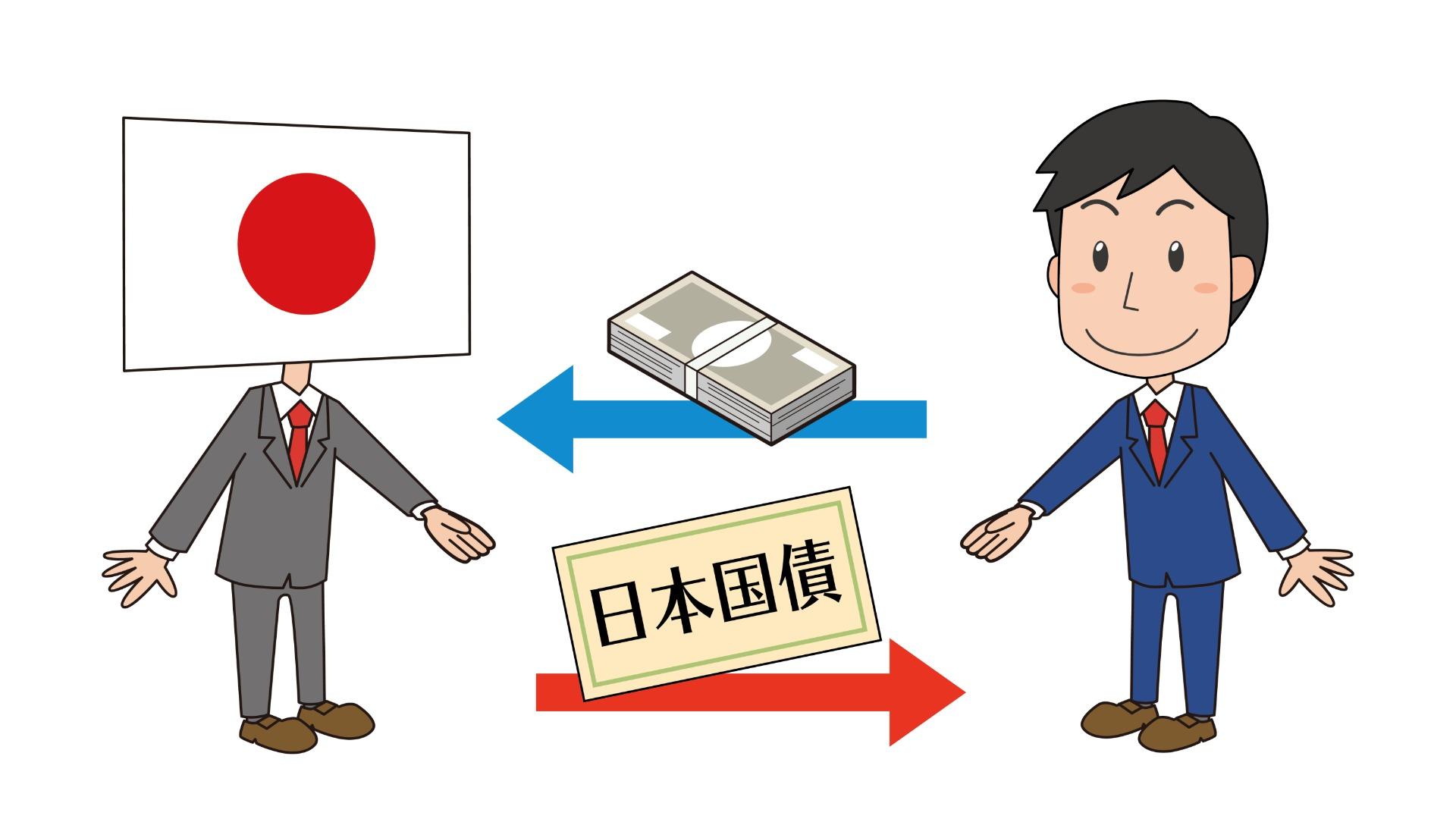無力感を覚えて抵抗しないのは「普通」のこと 名古屋・性犯罪無罪判決、控訴審で精神科医が証言

12月13日、今年3月に相次いだ4件の性犯罪事件の無罪判決のうち、実父が19歳娘への準強制性交等罪に問われた裁判の控訴審、2回目の公判が名古屋高裁で行われた。
検察側の証人として、性暴力の被害者心理に詳しい精神科医の小西聖子氏が出廷した。
名古屋地裁岡崎支部の1審では、娘が中学2年生の頃に性的虐待が始まったことや、事件より前に、抵抗した被害者の顔や足に被告が暴力をふるった事実を認定。性交が被害者の意に反していたことや、心理的に抵抗できない状況だったという精神科医の証言についても信用性を認めた。
一方で、被害者が抵抗して拒否できたこともあった事実などから、事件当時に抗拒不能の状態だったと断定するには「合理的な疑いが残るというべき」として、懲役10年の求刑を避け、無罪が言い渡されている。
【判決の詳細など】性犯罪の無罪判決とともに知ってほしい 被害者支援の現場のこと
小西氏は、被害者に適応障害があったと診断。これは1審で証言した精神科医とは異なる診断となり、その理由について小西氏は、被害者の「回避」傾向が強く、聞き取りや診断に時間がかかるタイプであることを挙げた。小西氏の診断は3日以上かけて行われたという。
「回避」とは、恐怖を覚えるような出来事があったときに、それを思い出すことを避けるといった対処行動。「被害者女性の回避は著しく、被害時について考えないようにしている。また、被害者自身はその回避を理解していない」「一見淡々としているため、周囲に誤解を与えやすい」と複雑な心理状態を説明。これらが長年、性虐待を受け続けた被害者によくある傾向であることを述べた。
また、被害者が「(父親から)ペットのように扱われた」「人間として扱われていない」と被害感情を口にしたと証言。一方で、普段は事件を思い出さないようにしているため怒りなどの感情が表に出るまでに時間がかかり、診断1日目では、「(父親に)興味がない」「(父親が)どういう性格かわからない」と淡々と答えていたことなどから、PTSDの診断基準には当てはまらないものの、「話の仕方や感情の表現の仕方」が複雑性PTSDに見られる傾向であることを指摘した。
実父は、娘への性虐待は高校生の頃からであり、事件当時には被害者と性交の同意があったと主張している。前述の通り1審では、被害者が抗拒不能だったとは認められないと判断された。
小西氏の証言では、「お父さんはあなたが嫌だと思っていると気づいていた?」という質問に対し、被害者が「どうだろう。気づいても無視していた。私がどれだけ嫌でも関係なかったと思う」と語っていたことが明らかになった。
このほか小西氏は、繰り返される性虐待において、被害者が無力感を抱き、諦めて抵抗しなくなるのはむしろ「普通」の状況であると指摘。他の性虐待事例について、「抵抗しないほうが早く終わるという理由で自分から応じることや、加害者の機嫌を損ねてさらに危険にさらされないように笑って応じることもある」といったケースを紹介した。
また、今回の事件では、「幼少時からの不適切な養育、虐待」「学費を出したことを借金とされるなどの心理的圧迫」「抵抗を試みて暴力をふるわれた経験」など複数の要因から精神的・心理的に抵抗できなかったと結論付けられると説明した。
検察側からの「母親に頼れなかったことや、父親の逮捕が弟たちの将来にかかわるかもしれないといった心配が抵抗できない心理状況に影響するか」という質問には「影響する」。「嘘をついたり過大申告の可能性」について、「むしろ過小申告していると思う。本当は治療しながら(被害内容を)聞けば、もっと言語化できるはず。嘘をつくには事実を自分の中で構成して、それに付け加えなければならないが、今はその段階ではない」と話した。

傍聴席には、被害者支援の関係者らの姿もあった。カウンセラーの具ゆりさんは、「小西先生の話は被害者支援の中では当たり前のこと。司法の場で通じるのか不安」と話した。
1審で否定された「抗拒不能」。虐待を受け続けた被害者の心理状態や言動が司法の場でどのように判断されるのかに注目が集まる。