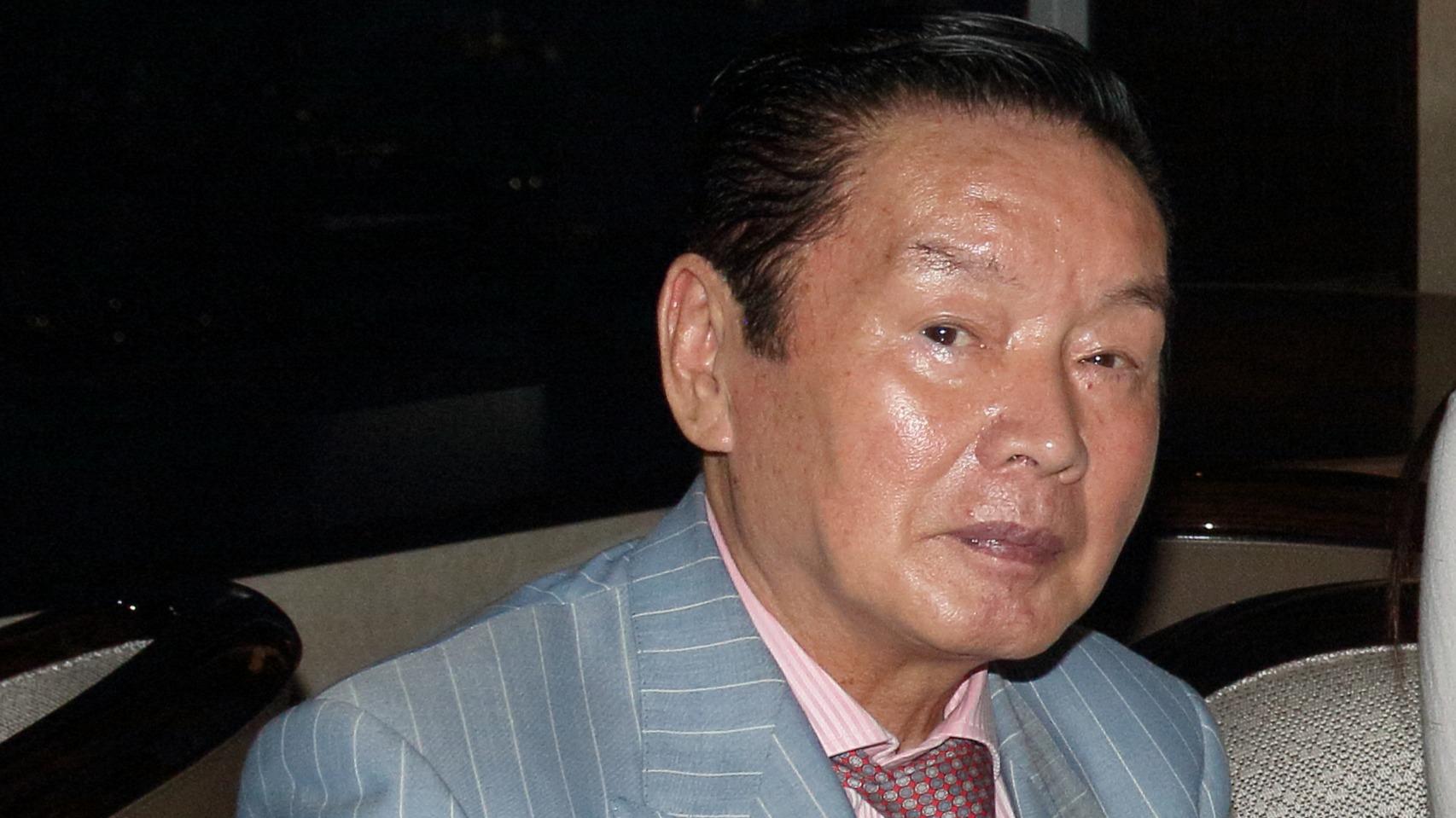登校・下校時間帯の実情(2021年公開版)

子供達の学校への登校時刻や学校からの下校時刻は昔も今も同じなのだろうか。通学時刻の実情をNHK放送文化研究所が2021年5月に発表した2020年国民生活時間調査(※)の報告書を基に確認する。
通学行為者における、通学行為率の動向を、平日の15分区切りで確認したのが次のグラフ。朝時間帯の登校時と、夕方時間帯の下校時に分けている。なお通学行動は「自宅と学校の往復」と定義されているため、部活動などで授業の終業後も学校に残っている場合もあることから、遅めの時間も行為者率が生じている。あるいは学校から自宅に戻らずそのまま塾に足を運び、その後に帰宅する人も想定される。


まず登校時だが、ピークは7時45分から8時。ピーク時の登校率は前回調査分の2015年に至るに連れて少しずつ上昇し、それ以前の時間帯もおおよそ増加を示していた。一方、ピーク時以降は逆に、昔の方が高い値を示しており、登校時間が少しずつ早まっていたようすが分かる。
そして直近の2020年では明らかにこれまでは大きなずれが生じ、ピークは7時30分から7時45分となり、ピーク前の通学行為者率が増え、それ以降が大きく減っている。通勤・通学ラッシュに巻き込まれることによる新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、意図的に登校時間を早めた結果が出た可能性がある。
他方下校ではピーク時間はおおよそ16時台で変化はなかったものの、それ以降はいくぶん直近につれて通学行為者率が落ちていたようにも見える。ただし登校時のように、法則を特定付けるまでの動きとは言い切れない。他方2020年では明らかにピーク時間が早まり、ピーク時間前の通学行為者率が増え、ピーク時間後が減るという、登校時と同じパターンが確認できる。これも通勤・通学ラッシュを避けるため、そしてあるいは学校における部活動が停止されて授業が終わった後は自宅に直帰できる人が多くなったからかもしれない。
あまりに長い通学時間は生活、学業上の負担となるが、学生生活においては通学時間もまた、貴重で楽しい時間ともいえる。無理をせずに自分自身のライフスタイルに合わせ、有意義な時間として活用してほしいものだ。
■関連記事:
【都市近郊はかえって通勤時間が長いらしい…通勤時間の移り変わりをグラフ化してみる(最新)】
※2020年国民生活時間調査
住民基本台帳から層化無作為二段抽出法によって選ばれた10歳以上の日本国民7200人を対象に、2020年10月13日から18日にかけて郵送法によるプリコード方式で行われたもので、有効回答数は4247人分。過去の調査もほぼ同様に行われているが、2015年以前は配布回収法によって実施されている。
(注)本文中のグラフや図表は特記事項の無い限り、記述されている資料からの引用、または資料を基に筆者が作成したものです。
(注)本文中の写真は特記事項の無い限り、本文で記述されている資料を基に筆者が作成の上で撮影したもの、あるいは筆者が取材で撮影したものです。
(注)記事題名、本文、グラフ中などで使われている数字は、その場において最適と思われる表示となるよう、小数点以下任意の桁を四捨五入した上で表記している場合があります。そのため、表示上の数字の合計値が完全には一致しないことがあります。
(注)グラフの体裁を整える、数字の動きを見やすくするためにグラフの軸の端の値をゼロではないプラスの値にした場合、注意をうながすためにその値を丸などで囲む場合があります。
(注)グラフ中では体裁を整えるために項目などの表記(送り仮名など)を一部省略、変更している場合があります。また「~」を「-」と表現する場合があります。
(注)グラフ中の「ppt」とは%ポイントを意味します。
(注)「(大)震災」は特記や詳細表記の無い限り、東日本大震災を意味します。
(注)今記事は【ガベージニュース】に掲載した記事に一部加筆・変更をしたものです。