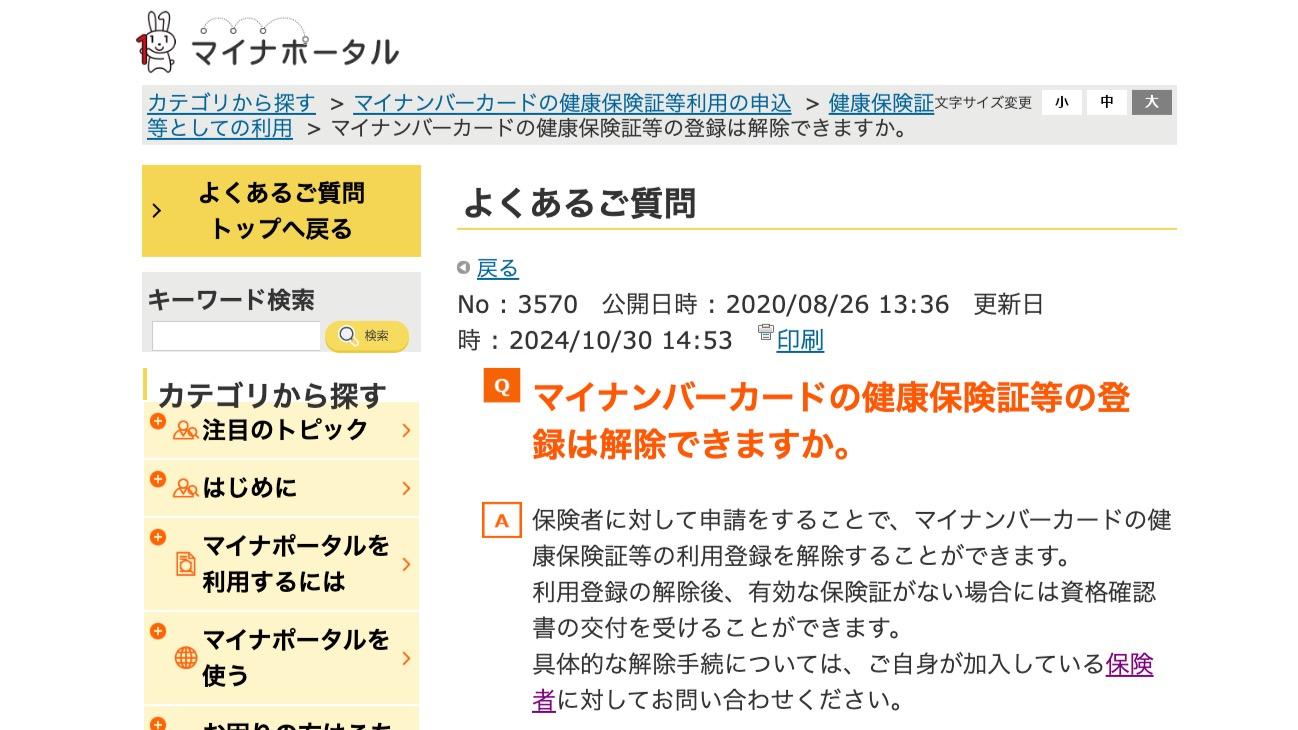防衛費増額における建設国債発行の可能性と60年償還ルールの行方

財務省は防衛費増額に向けて、2023年度からの5年間で決算剰余金など増税分以外で約11.1兆円を確保する方針だ。防衛費の5年間の伸び幅は17兆円程度で、この前提では差額の約6兆円を増税などで確保する必要がある。施設整備費を賄う建設国債の発行も検討する。これまで防衛費に建設国債は充てておらず、予算編成の方針転換となる(13日付け日本経済新聞)。
建設国債は公共事業などの財源となり、国の資産を形成するために発行される。道路や下水道、ダムの建設といった公共事業は多額の資金が必要とされるが、我々は将来も出来上がった設備・施設の恩恵を受ける。また、このような社会基盤が整備されれば、産業の育成などに貢献し、我々の生活にもプラスとなり、将来の税収入が増える要因となることも期待されるというのが、建設国債の発行を正当化する理由となっていた。
財務省はこれまで自衛隊施設は「耐用年数が短い」として活用を認めておらず、防衛予算の大きな方針転換となる(13日付読売新聞)。
財務省は自衛隊施設は有事に損壊する恐れがある「消耗品」とみて建設国債の適用を認めてこなかった(14日付日本経済新聞)。
戦時国債を乱発し、戦争に邁進した戦前・戦中の反省を踏まえ、政府は戦後、防衛費を国債で賄わない方針を貫いてきた。自衛隊施設についても「消耗的な性格を持つ。国債発行の対象としない」(1966年の福田赳夫蔵相の国会答弁)として、建設国債を用いることは断固、認めてこなかった(16日付日刊ゲンダイ)。
自民党の萩生田光一政調会長が11月11日に「国債償還の60年ルールを見直して償還費をまかなうことも検討に値する」と発言した。発行から完済までの期間を延ばすことで浮く償還費を、防衛費増額の財源に回す発想とみられる(13日付日本経済新聞)。
1965年度に戦後初めて発行された国債(特例国債、7年債)は、その満期が到来する1972年度に全額現金償還されたが、1966年度以降に発行された建設国債については、発行時の償還期限にかかわらず、すべて60年かけて償還される仕組みが導入された。
これは公共事業によって建設された物の平均的な効用発揮期間、つまり使用に耐えられる期間が、概ね60年と考えられたためである。これが国債の60年償還ルールと呼ばれるものである。これに基づいて発行される国債が借換国債もしくは借換債と呼ばれている。1985年からは建設国債だけでなく特例国債(赤字国債)にも借換債の発行が認められることになった。
鈴木俊一財務相は13日の閣議後の記者会見で、防衛費増額の財源捻出をめぐり自民党内で浮上している国債の60年償還ルールの見直しに慎重な見解を示した。「国債に対する信用に影響してくる」と述べた(13日付日本経済新聞)。
いわゆるリフレ派は今回の防衛費増額に対して防衛国債を発行し、60年償還ルールを廃止させようと目論んでいたようだが、それは回避されるようである。