“詩織さん”から伊藤詩織へ 本人が語った、今著書を出版する理由

私が伊藤詩織さんに初めて会ったのは、今年の2月初旬のことだ。彼女はある海外メディアの記者と2人で、日本で取材を行っていた。
「性被害は、被害に遭った人が話さないとなかったことになってしまう。話したくない人に無理をさせることはできないけれど、話せる人は話すことがとても重要」
記者と詩織さん、私の3人でそんな話をしていたときだったと思う。詩織さんが少し黙ったあと、自分の身に起こったことを、記者と私の両方にわかるよう、英語と日本語で話し始めた。
性暴力の取材をしていると、「誰にも言ったことがないけれど、実は私も」と告白されることがしばしばある。だから私は彼女がそのときに初めてそれを話しているのかと思ったが、よく聞いてみると、それまでの約2年間この問題のおかしさを訴え続け、メディアにもすでに話をしていたことがわかった。
その後、5月10日発売の「週刊新潮」が事件を報じ、5月29日には詩織さん自身が司法記者クラブで記者会見を行った。会見は、準強姦容疑で書類送検された男性が不起訴となったことを検察審査会に異議申し立てするものだった。しかし、この申し立ては実らず、9月22日に「不起訴相当」の判断が出たことが報道された。9月29日のイベントで詩織さんは民事訴訟を起こすことを明らかにしている。
そして先週末、文藝春秋から『Black Box(ブラックボックス)』というノンフィクションが発売されることが発表され、今週から書店に並ぶ。事件について、ジャーナリストである詩織さん自身が取材と調査を行った一冊だ。これまで家族の意向から伏せてきた名字を、この本では明らかにしている。彼女はどんな思いでこれを綴ったのだろう? インタビューを申し込んだ。
■「発信する側に戻りたい」
――これまで伏せてきた名字を明らかにすると知ってうれしいです。ジャーナリストとしてこれからも活動していく詩織さんが、いつまで「詩織さん」でいればいいのだろう?と思っていたので。
詩織:家族には申し訳ないと思う気持ちはあります。ギリギリまで悩んだけれど、名前だけの表紙を想像して「やっぱり違う」と思いました。でも、「詩織さん」でメディアに出たら、みんな「詩織さん」って呼んでくれて、これまで日本では「伊藤さん」って呼ばれることが多かったので、それはうれしかったですよ(笑)。
――出版の話はいつからあったのですか?
詩織:記者会見の後に話をもらいました。本はいずれ書きたいと思っていたけれど、ゆっくりプロセスを踏んでと思っていたので、まさか今書くとは思っていませんでした。躊躇していたら編集者の方が、「詩織さんは今このトピックについて扉を開けたから、今なら人が聞いてくれる。伝えたいことを言うのは今が一番効果的」と言ってくださった。本当はもう自分の仕事に戻りたいとも思っていました。書かれる方ではなくて発信する方に戻りたいと。でもそう考えたら、これも自分の仕事の一部かなと。

――「不起訴相当」の報道が出た翌日に、性暴力被害の当事者団体「Spring」のキックオフイベントに来てくださいましたね。※イベントの詳細記事はこちら
詩織:夜中に海外へのスカイプ取材が2件あって、寝ないで行ったんですよ(笑)。メディアの人に囲まれるだろうから出ない方がいいと言われたけれど、私はどこに出ても話すことは変わらないからと思って行きました。
■中学時代に1年以上の入院生活
――本の中では生い立ちも語られています。私はこれまでの数カ月間で「こういうかたちで社会に問題提起できる人は、どんな育ち方をしてきたのだろう」と思っていたので、この部分がとても興味深かったです。
詩織:編集者の方にも、「どうしてあの会見ができるのか、それを世間の人は知りたいと思う」と言われました。私も自分でドキュメンタリーを撮るので、そうだろうなと。詮索されるのはすごく嫌だとも思ったけれど、結局初稿からほとんど削っていません。全部真実しか書いていないから気が楽です。
――中学校時代に1年間以上入院生活を送ったことが一つの転機になったと書かれています。その後退院してからは老人ホームなどでのボランティアが楽しかったと。
詩織:隣の病室に昨日いた人が今日いない。こんなに簡単に命が亡くなってしまうと考えたときに、それまでの学校生活の複雑さがバカバカしくなって。院内学級がすごく楽しかったというのもあります。何の競争もなくて自分でいるだけでいい。生きているだけでいい場所でした。学校に戻ったときに、もう進学をどうするかとかに興味がありませんでした。もともと合わなかったのだと思います。入院中はしょっちゅう倒れていたから、頭を打ちすぎてこんなになってしまったのかな(笑)。
■性犯罪は「よくあることだから難しい」?
10代半ばで決断し、渡米。その後も留学し、NYの大学でジャーナリズムを学んだ。ジャーナリストとしての道を模索する中で、いったん日本に戻った際に、事件が起こった。2015年4月3日のことだ。
彼女の身に起こった事件。逮捕状は執行直前に「上」からの連絡で取り消しとなり、書類送検後は監視カメラの映像や第三者の証言がありながらも嫌疑不十分で不起訴となっている。男性が政権と近しいジャーナリストだったことから、何らかの便宜があったのではないかという疑惑が持ち上がり、大きな話題となった。
しかし、この事件はもう一つの問題点も提示している。性犯罪の立証が難しい現状があることだ。詩織さんは、最初に駆け込んだ警察で警察官から「よくあることだから難しい」と言われている。これは男性がどんな人物かを警察が知る前のことだという。日本では、知人と飲食した際に意識を失い、そのまま強姦されることが「よくあること」で、捜査は「難しい」のだろうか。性犯罪は知り合いから被害を受けることも多い犯罪であるにも関わらず、知り合いからの被害は特に立証しづらいという壁がある。性犯罪に関するこの問題点は、実はこれまでも繰り返し指摘されてきている。
――政権と絡む疑惑の方に注目する人が多いのかもしれませんが、私はこれまで性暴力について取材をしてきているので、もう一つの方の問題について聞きたいです。詩織さんはインタビューなどでも、今年110年ぶりに大幅改正された性犯罪刑法の問題について触れていました。性犯罪における捜査や司法の問題点に気付いたのはいつ頃からですか?
詩織:最初からずっと思っていました。捜査員の人になんでそんなに捜査したくないのかと聞いたら、立証が難しいからと。「自分も検察官と被害者との板挟みで苦しいんだ」と打ち明けられたこともありました。これは法律の問題だなと。法律が捜査に反映しているんだなと思いました。
■「今勝とうと思わないで、生き続けて」
強制性交等罪(旧強姦罪)には「暴行脅迫を用いて」という定義がある。しかし裁判では暴行脅迫があったことの立証が難しいことも多く、これを見越して起訴が断念されることがある。
また、準強制性交等罪(旧準強姦罪)は「心神喪失・抗拒不能」の状態に乗じたり、その状態にさせて、という定義があり、これも立証の難しさがつきまとう。詩織さんの事件では、2人を乗せたタクシー運転手の証言や監視カメラの映像から詩織さんがほとんど意識のない状態だったことが明らかとなっているが、事件の現場は密室だった。
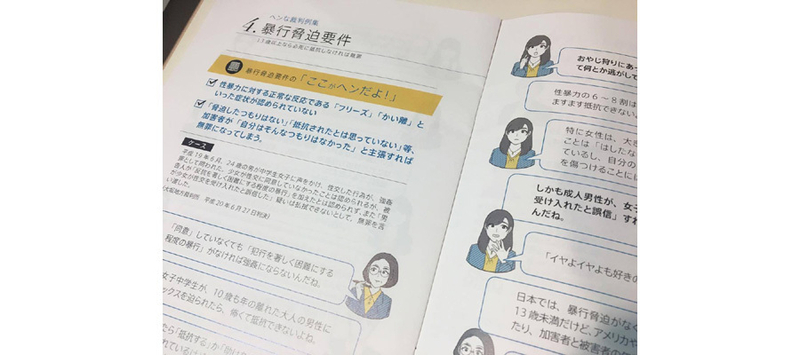
性犯罪事件に詳しい雪田樹理弁護士は詩織さんの事件について、こう話している。
「レイプドラッグを使用していなかったとしても、意識朦朧とした女性と性行為をしたのですから、抗拒不能に乗じて性交をしたといえる可能性があります。ですが、密室での出来事であるため、抗拒不能の状態にあったかどうかを客観的に立証できず、また、『抗拒不能状態に乗じたつもりはない』『同意の上でのことと思っていた』と加害者が弁解すれば、『故意がない』ので不起訴にする。それが検察の現状だと思います」※コメントの全文はこちらの記事。
――被害を話しづらいと感じる人もいるし、被害の立証も難しい。本当に暗数の多い犯罪だと思います。
詩織:(カウントされていない被害は)たくさんあると思います。私に協力してくれる人たち、どうしてこんなに熱心にやってくれるのだろうと思っていたら、それぞれ何かしらの(被害)経験を持っている方も多くて。やっぱりそうだったのかと思います。こんなにも多いのかと。同じような被害に遭った人のひとりは、「今勝とうと思わないで、生き続けて」と言ってくださいました。
■レイプドラッグ、海外のことではない
詩織さんはレイプドラッグを使われた可能性を疑い、詳しい専門家らに取材。『Black Box』で取材した内容を示している。
日本ではまだ「レイプドラッグ」の存在を知らない人も多いが、今年7月には、仕事の打ち合わせ中に女性に睡眠薬入りの飲み物を飲ませ、強姦した男が懲役5年の実刑判決を受けている。
特定の薬物を指すわけではなく、意識を失わせる目的で用いられるものの総称。レイプ目的で過度にアルコールを摂取させることも「レイプドラッグ」であると言う人もいる。

――「レイプドラッグ」という名称を知っていても、外国で使われるものというイメージを持っている人も多いと思います。
詩織:私も海外のことだと思っていました。検査ができなかったので結論は出せませんが、なんでこんなに(ぷっつりと)記憶がないのだろうと思ったときに、その可能性をすぐには思いつかなかった。認知や教育の問題だと思います。レイプドラッグについて取材したことを本に書くと、情報を悪用する人が出るかもしれないとも思いましたが、知らない方が怖いと思ったので書きました。
――日本ではまだ、性被害やレイプドラッグなどの検査について、きちんとした対応の取れる機関が少ないです。また、国連が女性人口20万人に1つは必要と唱えるワンストップセンター(性暴力被害の緊急対応を行う施設)もまだ全国に40カ所ありません。
詩織:被害後に電話で相談した性暴力に特化したある機関からは、「こちらに来て面談しないと何の情報も教えられない」と言われました。緊急でどんな処置をすれば良いかだけでも教えてもらいたかったのに、それも電話ではできないと言われた。(ワンストップセンターやレイプドラッグの検査ができる機関は)これから増えてくると思いますが、現状を海外の人に話すと、これが先進国かと驚かれます。こんなにテクノロジーの進んだ国で、どうしてここまで遅れるのかって。
■日本の「しょうがない文化」
――海外のメディアでも働かれた経験から、日本の報道に思うところはありますか。
詩織:海外でもテレビなどは特に広告ありきだから、同じことは起こります。でもそこを精査するメディアがある。日本の場合、記者クラブがあり、同じ時間に同じニュースをやる。同じ方向しか向けないのでは? メインストリームのテレビで事件があまり報じられないことについて、日本のメディアの人は「しょうがないですよ」って言います。「しょうがない文化」がある。
――言われてみれば、「しょうがない」の一言で説明責任がうやむやになるようなところがありますね。
詩織:NHKのあさイチで「“性行為への同意があった”と思われても仕方がないと思うもの」(※)というアンケートがありました。こういう問題が採り上げられるのはうれしいけれど、「仕方がない」って? 「そう思うもの」ってはっきり言いなさいよって。なんでそんなに人のせいみたいにするんだろう。「あなたはこの行為を同意だと思いますか?」では、本音を答えづらいと思ったのかもしれないけれど。
(※)アンケートは、5つの行動について「“性行為への同意があった”と思われても仕方がないと思うもの」を聞いたもの。「2人きりで食事」は11%、「2人きりで飲酒」は27%、「2人きりで車に乗る」は25%、「露出の多い服装」は23%、「泥酔している」は35%の人が「“性行為への同意があった”と思われても仕方ない」と答えた。
■ジャーナリストとして映像表現を選んだ理由
記者会見の前に詩織さんと話した際に、彼女が「取材したいと思っていることは性暴力だけではない。でも記者会見をすればどうしても『性犯罪被害者』のイメージがついてしまうと思う。それはジャーナリストとしてどうなのだろう」と葛藤していたことを覚えている。
『Black Box』は紛れもなく名著だが、彼女は映像で伝えることをメインとするジャーナリストだ。今後はどのように活動するのだろう。

――手法として映像を選んだ理由を教えてください。
詩織:言葉だけじゃ語りつくせない出で立ちや表情も伝えたいという思いがあります。言葉で表現してしまうと私の声しか聞こえない。でも映像だと、見ている人がそれぞれで受け取ってくれます。
――これまで印象的だった取材は何ですか?
詩織:去年一年間は日本の孤独死の取材をしていました。追っていくと、これはコミュニケーションの問題、人とのつながりの問題だと思いました。社会やテクノロジーが発展していく中で溝が生まれている。他にも、高齢者の犯罪や、前科のある人のサポートをしている、自身も刑務所に入った経験のある男性の取材で、人とのつながりや地域のコミュニティに関する時代の変化を考えました。
――今後取材したいテーマはありますか?
詩織:週刊新潮の記事が出た頃、コロンビアでゲリラの女性兵について取材をしていました。いろいろあって途中になってしまったけれど、本当はもう少し取材したいと思っています。彼らの中では“男女平等”の意識がすさまじくて、女性でも闘うし、逆に男性もキャンプで炊事などをする。もともとは貧しい農村出身の人たちなのですが、その背景にある事情を掘り下げてみたいです。
――いろんな面で注目を集める本だと思うのですが、私は「今の状況、なんだか息苦しいな」と思っている若い人に読んでほしい一冊だと思いました。詩織さんが10代半ばで、自分で稼いだお金で海外に出たように、今いる場所だけがすべてではない。
詩織:いろいろな報道があったときに苦しかったのが、今までだったらすぐに友達に相談したり散歩したり映画見たりできたのに、外に出られなくなってしまったし、人を誘えなくなってしまったこと。外に出れば無言で写真を撮られることもありました。被害に遭った後とはまた違った苦しさで、自由がないって苦しくなってしまって。
でも、それは今いるこの場所で対応しようと思っていたからで。自分が生きている場所だけが自分の世界って思ってしまったらつらいけど、私はラッキーなことにそう思わなかった。
■たくさんの変えたいと思ってきた人たち
詩織:私が今回思ったのは、みんな心のどこかでもうたくさん、もう変えたいって思っていた矢先にたまたま私の事件があったんじゃないかと。どこかでいろんな問題が少しずつ浮き彫りになって、きちんとした性能のカメラなどのある時代だから残った証拠もあったし、ネットメディアが報じてくれたこともあったし、今だからできたこともあった。私の事件のことだけじゃなくて、私が出会った人やそうでない人、多くの人がおかしいと思っていたこと。今で良かったと思います。
――おかしいと思っていた人がたくさんいたから、詩織さんを応援する人も多かった。
詩織:若い方からも高齢の方からも、男女問わずいろんな方から手紙をいただきました。「許せない」とか「本当に法治国家なのか」とか。思いを受けとれてうれしかった。変わるといいな。性暴力の話を、もっと普通に話せるようになるといいと思います。

――交通事故が起こるように性暴力も毎日起こっているけれど、隠されているしなかなか話されない。
詩織:今年の夏に取材したスウェーデンではいろんな議論を聞きました。スウェーデンでは男性も普通に「フェミニスト」と名乗るし、性暴力の議論に男性も参加していて、たとえば「“レイプ”という名称ではなく、“性暴力”に変える」という提案をしている男性たちがいました。理由は、自分が「“レイプ”をした」ことは認めづらくても「“性暴力”を行った」なら認められる人もいるから。認める人を増やすために、そうしようと。
でもこれにはもちろん反対意見もあって、取材した政治家志望の若い女性は絶対反対と。理由は「レイプはセックスではない」から、意味を和らげる言葉にすり替えるべきではないって。私もそれはすごくそう思います。
――日本では今年、「強姦罪」が「強制性交等罪」に名称変更されましたが、この新名称に反対意見もありました。理由は同じで、強姦は暴力であり、性交とは全く違うものだから。同一視されることで、被害が軽視されてきた歴史があります。
詩織:この間、週刊誌の取材を受けたんです。そうしたらタイトルがすさまじくて、「セックスを強要された」って書いてあって。不起訴相当となったからレイプという言葉を使えないという判断だったと思うのですが、私は「レイプはセックスじゃない」っていうことを言いたかったんだけど。
■白いシャツでずっと泣いているわけじゃない
――そこをすんなり理解する人もいれば、なかなかピンと来ない人もいるように思います。この本をゴシップ目的で手に取る人もいるかもしれないけれど、その中の10人に1人でも、今ある性暴力を取り巻く問題に気付いてくれるといいなと思っています。
詩織:そうだといいな。「被害者が語る」とか、「被害者の本」って言われるのがすごく嫌で。といっても被害者の本なんだけれど。
――「性犯罪の被害者」って言葉からイメージされるものが一面的過ぎるように感じます。
詩織:そう。それをどうしても壊したかった。中にはステレオタイプな反応もやはりありました。ネットでは「白シャツをきちんと着て泣いて、終始言葉を詰まらせてれば、今頃みんなこの人の話を信じたのにね」ってコメントもあったりして、やっぱりそういうものを求めているのかって。
――だから「被害者」が見えなくなるのかもしれません。「白シャツでずっと泣いているのが被害者」だと思っていたら、性暴力の存在は見えない。
詩織:気付いていないだけで、もしかしたら家族にも(被害に遭った人が)いるかもしれない。残念だけどよく起こってしまうことだから考えて、変えていかないといけないのに。警察に行ったときに言われた「よくある話だから難しいよ」って、逆でしょって思いますよね。

詩織さんはインタビューの途中、何度も笑顔を見せた。「性犯罪被害者」が笑わないわけではない。けれど私は、笑顔の写真を撮って記事に載せることは躊躇してしまう。なぜ笑っているのか。そう思う人の存在を、まだ無視できないからだ。なぜ被害に遭ったのに、元気そうにしていたのか。仕事を続けられていたのか。そんな疑いをかけられ、被害を信じてもらえなかった人たちがこれまでにはいる。しかし「そんなの被害者らしくない」と考える人の、どれだけが実際に被害者の言葉に耳を傾けたことがあるだろう。性暴力の実相は、小説や映画の中ではなく、彼女ら彼らが語る言葉の中にある。
伊藤詩織(いとうしおり):1989年生まれ。ジャーナリスト。 フリーランスで、エコノミスト、アルジャジーラ、ロイターなど主に海外メディアで映像ニュースやドキュメンタリーを発信する。










