延命?生命維持?悩む医師に道筋示した院内「臨床倫理委員会」――終末期認知症の人の意思決定支援・その2

2023年12月、筆者は社会福祉士の成年後見人として、重い認知症がある被後見人の看取りに関わった。その際、多くの専門職と共に「意思決定支援」と向き合った。これは、このケースについて振り返る記事の第2部である。
延命を望まない親族、後見人である筆者の思いとは反対に、入院した急性期病院、川崎市立多摩病院(以下、多摩病院)で経鼻経管栄養(鼻からの管で栄養剤を注入する処置)が開始された被後見人・Aさん。果たして、入院まで8年間暮らしていた特別養護老人ホーム菅の里(以下、「菅の里」)に戻ることはできるのか? <第1部はこちら>
多摩病院の「医療倫理委員会」とは
まずAさんの経管栄養の開始、継続等について検討した多摩病院の「臨床倫理委員会」について説明しよう。
多摩病院の「臨床倫理委員会」は、様々な領域を専門とする医師、看護師、理学療法士、医師事務作業補助者、医療ソーシャルワーカー、総務課職員等、多職種で構成されている。
医師の独断にならないよう、多職種で話し合いを通して検討することを目的に、2019年に設置された。
この委員会にかけられる案件は、現場から「倫理的に気になる」「何かモヤモヤする」と、電話や電子カルテから依頼がくる。また、毎日、医療ソーシャルワーカーが新規入院者の電子カルテをスクリーニングしており、介入の必要性を感じて能動的に介入するケースもある。
相談件数は月5~6件。各ケースにつき、倫理カンファレンスが必要に応じて数回開かれる。

治療方針決定のためには情報収集が必要
Aさんの場合、入院早々に医療相談センター師長の藤井真樹看護師(以下、藤井看護師)から筆者に電話があった。「明らかに口からはもう食べられない。そして、身寄りがなく、本人の意向も確認できない状態。まずは後見人に本人の背景を聞こうと連絡した」と、藤井看護師は言う。
一方で、医療相談センターの川上加奈医療ソーシャルワーカー(以下、川上MSW)は、「Aさんを担当する代謝・内分泌内科(以下、代謝内科)は、高齢でターミナル(看取り期)の患者を診ることが少ない。そのサポートの意味で、Aさんのケースへの退院調整までの介入の必要性を感じていた」と語る。
17日(金)に開催された倫理カンファレンスの目的は、主にAさんの周辺情報の整理だった。
「家族関係が不明。後見人がついている理由も不明。施設入所の経緯も不明。一方、医療同意権がない後見人から様々な意見と情報が提供されている。これをどう扱うべきなのか。そんなやりとりがあり、治療方針を決定する上で本人の周辺状況を把握する必要があるという話になった。
そこで、私から施設に連絡して入所の経緯や本人の状況を確認し、代謝内科の担当医である楠田修平医師から後見人に連絡をした上で、親族に確認することになった」と川上MSWは振り返る。

経管栄養をしないなら「しない根拠」がいる
このときのカンファレンスでは、入院後3日間の情報から、Aさんは“老衰”ということが予想できる、何もしないことがおそらくいいのだろう、という漠然とした共通認識があったという。
しかし、カンファレンスに不参加だった楠田医師への伝達後、結果として経鼻経管栄養が開始された。楠田医師は、このときの判断についてこう語る。
「Aさんはパーキンソン病があり、専門外の代謝内科として、軽々に末期の状態かどうかの判断はできなかった。パーキンソン病の薬の調整を加える必要もあった。また、食事を摂っていた場合、まず栄養を入れることが医療の原則。後見人と、後見人経由の親族の延命拒否の意思は聞いたが、それを鵜呑みにすることはできない。代謝内科としては、明確な延命拒否の意思確認ができていない、その時点の判断として経管栄養を開始した」
今、終末期の医療では、「タイムリミテッドトライアル(TLT)」という処置がある。治療の効果が不透明な重症患者に対して、期限を区切って有効と思われる治療を行って効果を確認し、積極的治療を継続する意義を判断するための処置だ。Aさんの経管栄養も、このTLTとして行ったものだったと、後の取材の際に藤井看護師が説明してくれた。
「私たち医療職にとっては、経管栄養イコール延命治療というわけではない。Aさんの場合は、状態が改善するかどうかを見るために、期間を区切って実施していたものだ。
TLTには、もう一つ意味がある。命の終わりにつながる治療の中止を決める上での医療者の葛藤を、軽減する意味だ。それは、患者の家族にとっても同じ意味を持つ。そうしたことも、患者やその家族に理解しておいてもらえたらと思う」(藤井看護師)
Aさんは、施設では時間はかかっても食事を摂れていた。入院中、食事の分の栄養を入れないのなら、「入れない判断」には根拠が求められる。それは医療職には常識である。しかし、医療職ではない筆者には、その時点で「医療職の常識」に思いを致すことはできなかった。
17日のカンファレンス以降、川上MSW、楠田医師は「栄養を入れない」根拠集めに動いた。
一方、このころ筆者は、Aさんが入所していた「菅の里」に、退院後、看取り対応で受け入れてもらえるかを何度か確認している。一般に、特別養護老人ホームでの看取りには、様々な受け入れルールがあるからだ。
対応した「菅の里」の小島千晴生活相談員は、「食事を摂れないのが、老衰ではなくパーキンソン病によるものだと、看取りの対象にならない可能性がある。また、夜勤帯にのどの奥の痰吸引が頻回に必要だと、受け入れるのは難しい」との回答。
ほとんどの特別養護老人ホームでは、夜勤帯に看護師の勤務はない。また、「菅の里」には研修を受けて痰吸引ができるケアスタッフが複数いるが、制度上、ケアスタッフにのどの奥までの吸引は許されていない。特別養護老人ホームに看取りの場としてのニーズが高まっているにもかかわらず、それに応えうる制度が今もまだ整備されていないのだ。
「個人的には、慣れ親しんだ当施設に戻って最期まで過ごせるのがAさんにとっていいのではないかと思うが…」と、小島生活相談員は申し訳なさそうに言う。
ニーズと制度のギャップが、終末期を迎えた利用者、家族等の関係者、そして、施設職員を苦しめている。
「菅の里」に戻るには、まだいくつものハードルがある。そう感じた。
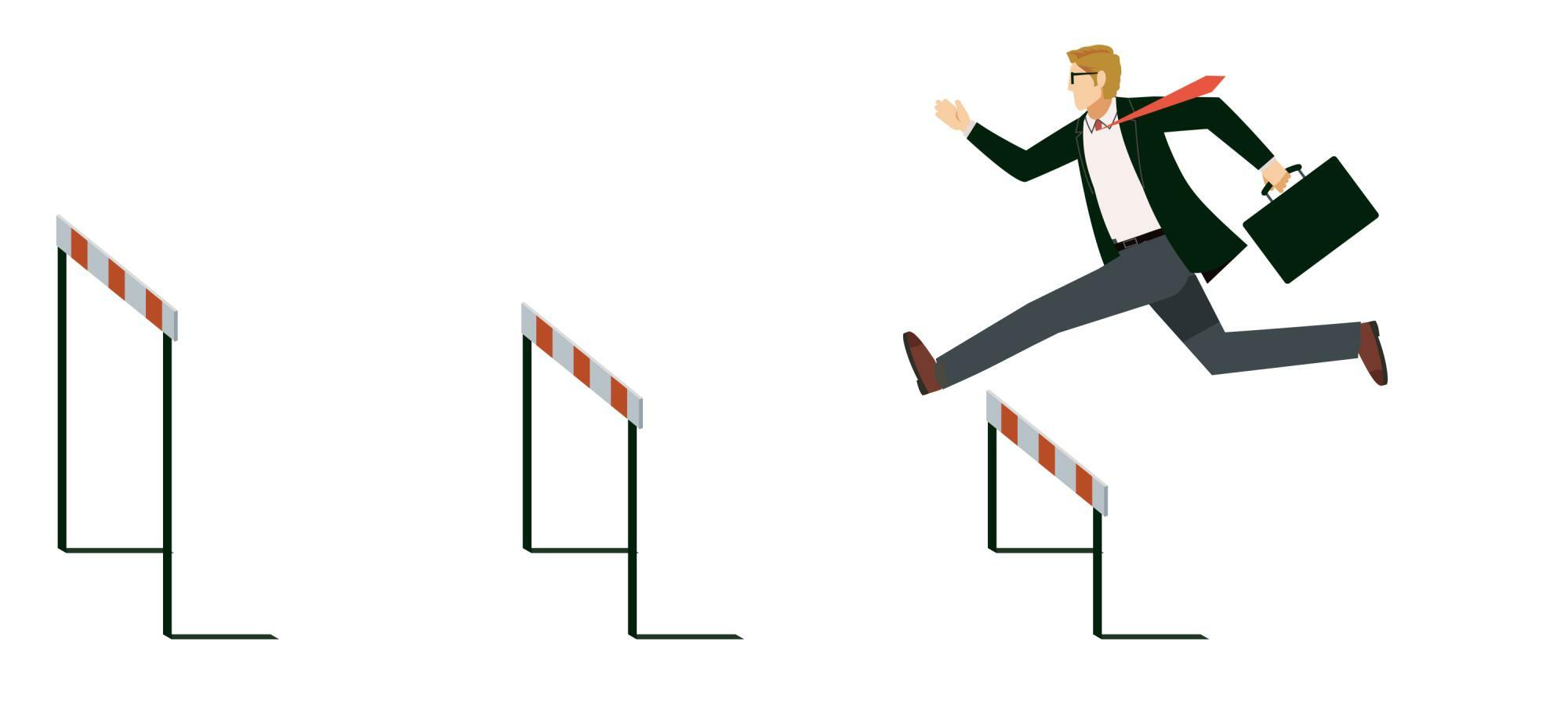
経管栄養開始。転院先は療養型病院か
21日、楠田医師から電話があった。
経管栄養の開始前に連絡したAさんの親族から、折り返しの連絡があった、事情を説明したところ経管栄養で良いという回答だった、とのこと。そして、経管栄養継続だと施設には戻れないので療養型病院への転院の方向になる、と告げられた。
楠田医師の説明を聞き、やはり避けたかった療養型病院への転院しかないのか、と落胆した。
延命を拒否している親族が、いざとなるとやはり延命してほしいと望むケースは少なくない。今回もそういうことなのだろうかと考えた。
筆者も直接、親族の思いを聞きたいと考え、電話してみた。
すると、親族はこう語った。
「今の状態は医師から説明を聞き、理解している。自分としては、食べられなくなったらそれが寿命と考えているが、病院では何もしないわけにはいかないという。もともと食事をしていたからまず経管栄養を開始したと言われたので、受け入れた。しかし心肺停止になっても心臓マッサージなどは必要ないと伝えた」
結局、本人の意思が確認できないために、経管栄養を受け入れざるを得なくなっている。
後見人として、Aさんの意思確認を試みなかったことが悔やまれた。
もしやという思いで、「菅の里」の小島生活相談員に、施設内でAさんの延命の希望の有無を聞いたことがある人はいないかを聞いてみた。本人の意思が確認できれば、経管栄養は中止してもらえるかもしれないと考えたからだ。
しかし、そうした話を聞いた人は誰もいなかった。

医師への回答と違った親族の真意
親族にも再度電話し、Aさんの延命に関する意思を聞いたことはないかと尋ねてみた。
するとこんな話をしてくれた。
「自分は聞いたことがないし、Aの兄夫婦もないと思う。ただ、以前、親族の集まりの時にAのことを話したら、親族一同、医療の力を借りてまで命を長らえなくていいのではないか、そんなことをしたらかわいそうではないかという意見だった。Aは自由に生きてきた人。もう十分生きたのではないか」
後見人としての筆者も同じ思いだった。
そこで27日、多摩病院の川上MSWに親族から聞いた話を伝えた。
すると、川上MSWは驚いたように「それはいつの時点の誰の話か」と聞いてきた。Aさんの親族一同の総意だと今日聞いたところだ、と伝えると、「この情報を院内で共有してまた連絡する」とのことだった。
後に振り返って、川上MSWはこう語る。
「医師からは、親族も経管栄養で良いという回答だったので開始すると聞いていた。しかし、後見人の話を聞き、親族が医師に述べた回答と真意は違うと感じた。そこで、もう一度親族の意思を確認した上で、倫理カンファレンスを開き、検討する必要があると考えた」
親族には、楠田医師が再度、Aさんの延命についての意思確認をした。
連絡を受けた親族は、後に筆者にこう語った。
「医師と話して、ふと思いだしたことがあった。祖母(Aさんの母)の看取りの時、尿が出なくなっても点滴を続け、体が風船のように膨れる様子を見て、Aは『あんな風にはなるのは嫌だ』と話していた。そのことを伝え、親族一同、経管栄養も点滴も望まない、これ以上の医療はかわいそうだと考えていると話した」

「本当に療養型への転院というゴールでいいのか」
親族からこうした話があった頃、楠田医師は病棟の看護師長からも、「本当に経管栄養を続けて療養型病院に転院するというゴールでいいのか」と声をかけられていた。そしてそれ以前から、楠田医師自身、Aさんの治療について迷いがあり、診療科内で何度も相談を重ねていたことを、後に明かしてくれた。
「療養型病院には非常勤で勤務したことがあり、医療処置を受けながら長期療養する病院であることを承知していた。Aさんの場合、慣れ親しんだ施設があり、また、親族も積極的な治療を望まないことがわかってきた。命は長らえるが、経管栄養で療養型病院で過ごすのと、完全に栄養を切って看取りという形で施設に帰るのと、どちらがAさんにとって幸せなのか。そこに葛藤があった」(楠田医師)
施設に帰すためには、意図して経管栄養を中止しなくてはならない。
楠田医師は、そのことにもためらいを感じていたという。
「しかし、親族の話、病棟師長からの問いかけに加え、神経内科の診断からパーキンソン病も終末期にあるとわかった。経管栄養を開始しても状態の改善が見られないこともあり、代謝内科としても、経管栄養を続けることが第一選択ではないという判断になった」(楠田医師)

多職種での検討で経管栄養を中止。施設へ
29日、改めて院内倫理カンファレンスが開かれた。
複数の診療科の医師や看護師、医療ソーシャルワーカーなど多職種での検討の結果、これ以上経管栄養を継続してもAさんのQOL※の向上は望めないだろう、と意見がまとまった。経管栄養は中止。住み慣れた「菅の里」で最期の時を迎えることがAさんにとっての最善だろう、という結論となった。
カンファレンスでは、看取りの経験が豊富な総合診療医から、楠田医師に対して丁寧な説明がされたという。親族や後見人の話から、Aさんの「推定意思」が明確になったこと。入院以来トライアルで経管栄養を入れてみたが、Aさんの嚥下機能や意識レベルが回復しなかったこと。こうしたことを根拠に、栄養管理をはずしても倫理的に問題になることはなく、最期に向かう際にたどるプロセスと考えられる、という説明だ。
「急性期病院に救急搬送され、治療のために入院している以上、治療しないこと自体が倫理的に問題だと感じる医師もいる。それだけに、実際のこうした事例を通して学び、次の患者への対応につなげていくのはとても大切なことだ」と、藤井看護師は振り返る。
楠田医師は、「自分はまだ医師としての経験年数が短く、終末期の対応について不慣れな部分があった。知見をもっと深めるべきだと感じた」と語る。
「多職種での倫理カンファレンスを開いてから、方向性が決まるのがとても早かったという印象だ。今は本人のことを第一に考え、当科だけで抱え込まずに多職種で方針決定していくことが大事だと感じている」(楠田医師)
11月29日に経鼻経管栄養は中止。
施設で看取るべく退院するということで、12月5日に病院と施設の専門職、後見人が集まり、退院に向けたカンファレンスを開くことになった。
しかし、実はこの時点で「菅の里」から、“確実に看取りで受け入れる”という確証は得られていなかった。
退院の方向性は決まったものの、筆者はまだ不安を拭い切れずにいたのである。
※QOL…クオリティ・オブ・ライフ。人生、生活の質。体の苦痛がないだけでなく、精神面、社会面なども含めた満足度、質の高さをいう。
→次の記事へ続く










