世界一男女平等な国で、なぜ「主婦の学校」が人気なのか アイスランド映画が伝える背景とは

最初は「どうして?」と思いました。女性も働くのが当たり前の時代に、世界で最も男女平等な国で、なぜ主婦業を学ぶ学校が今も残っているのだろう?と。
映画「<主婦>の学校」は、アイスランドの首都レイキャビクにある、その名の通り「主婦の学校」に密着したドキュメンタリーです。学校は美しい白壁が特徴の大きな家で、生徒の定員は24人。生徒たちの多くは10代後半から20代初めの若者で、家が近い人は通学、遠い人は相部屋の寮で暮らしながら、料理や裁縫などの家事全般を習います。

「それって、昔の花嫁学校みたいなもの?」と思うかもしれません。かつて女性が高等教育を受けるのは珍しく、結婚するのが当たり前だった時代、家庭の切り盛りを教える花嫁学校がたくさんあったからです。映画に登場する「主婦の学校」も、花嫁養成の役割を果たした時代もありました。1947年にこの学校で学んだ女性は、実際に結婚して主婦になっています。
歴史を振り返れば、キャリアを持った女性もいます。1967年に在学した女性は寮生活の中で、友達の髪を切ってあげたのを機に美容家になり、長年、メディア業界で働くことになります。家庭生活の運営に必要な技能を教えつつ、女性達に「家庭に入る」価値観を押し付けるわけではない「主婦の学校」は、驚くことに現代も若者の関心を集めているのです。

映画の冒頭近くに登場する女性の言葉は、特に印象に残ります。
「主婦の学校へいくけど、主婦になるためじゃない」「だらしない主婦になったっていい」……。どうやら、花嫁学校というわけではなさそうです。
生徒たちの声を総合すると「手仕事」への関心という共通項が浮かび上がります。例えば洋服に穴があいたら、捨ててしまわず、アップリケをつけたり、かがって直したりして使う。そういうことを、この学校では大事に教えています。
伝統的な手仕事も、現代的なリテラシーも教える
裁縫の先生によれば、入学時には針に糸を通すこともできない学生もいるそうですが、最終的には皆、素敵なワンピースや子ども服などを作れるようになります。生徒たちが、共同生活をするリビングルームでおしゃべりしながら編み物をする風景もありました。

アイスランドの伝統料理やお菓子を作り、原っぱにブルーベリーを摘みに行ってジャムを作るなど、古くから家庭内にある手仕事の継承を主軸にしつつ、現代に必要とされる知識も身につけられるのが、この学校の特徴と言えます。例えば消火器の使い方を習ったり、セックスと避妊、薬物乱用防止、平等や信仰の自由、いじめ防止、お金やクレジットカードの使い方についても学びます。
1990年代からは男性の生徒も受け入れてきました。1997年にこの学校で学んだ芸術家は、初の男子学生でした。「失われていくものに興味がある」「主婦の仕事は失われつつある」と話しており、伝統的に主婦が担ってきた家庭内の仕事を、貴重な手工芸の一種と認識しているようでした。

彼が家事について「分からないままだとつまらなくなる」と話すのを聞いて、思い出したのは、私自身が、料理の経験が浅かった13年前のことです。当時私は10年ほど会社員をした後、初めて出産し、仕事に復帰したばかりでした。それまで、朝から晩まで仕事ばかりしていたので、料理のレパートリーが少なく段取りも悪くて日々の家事が苦痛でした。夫婦で半々に分担していましたが「これをやらずにすめばいいのに」と思うことが多かったです。
仕事を自営業に変えて郊外に引っ越したことで「家の中のことがつまらない」感覚に変化が生まれました。子どもにお弁当を持たせたり、園で使うバッグやリュックを作ったり、他の保護者と一緒に並んで座って刺繍をしたり、これまで「手間がかかるだけ」と敬遠していたことの多くは、実際にやってみると私にとってはとても楽しい作業だったのです。
やはり90年代に主婦の学校へ通った男性は、後にアイスランドの環境天然資源大臣になりました。この人は「料理を習いたくて」入学したと言います。特に楽しかった「機織り」は、今でもやることがあるそうで「機織りをすると力がわいてくる。すごく充実感が得られる」と笑顔を見せていました。

最初に書いた通り、アイスランドは世界経済フォーラムが発表している「グローバル・ジェンダー・ギャップ指数」で、12年連続、男女格差が世界最小となっています。世界一男女平等な国で「主婦の仕事」が重視されているという事実は、私たちのジェンダー観に、これまでとは違う見方を提供してくれます。
真の男女平等は「ケア」の再評価と再分配あってこそ
家事は自分だけでなく、同居する家族のために行う「ケア」であり、そこには機械化しきれない様々な仕事が含まれています。それらは意義深い仕事ですが、市場経済で価値づけるのは難しい「無償ケア労働」です。その負担の大部分は、世界の多くの国々で女性が担ってきました。
つまり、真の意味でジェンダーの平等を考えるなら、無償ケア労働を再評価しつつ、それを男性にも再分配する必要があるのです。また、単に外で働いてお金を稼ぐだけでなく、自分や家族の身の回りのことを自らの手で行うことこそが、人間としての自立であり、平等へ向かう道なのです。
これは「女性活躍」という言葉に違和感を覚える人も、納得できる方向性ではないでしょうか。

ただし、この映画には、このような理屈は登場しません。
環境天然資源大臣は「主婦の学校」での経験を振り返って言います。「金曜日は残り物を食べていた」。この学校では、食事をホームレスシェルターに届けて、捨てないようにしていました。
「ここで学んだことを使って、環境保護活動をすることができる。そうすれば、総合的に良い市民になれる」
大臣の話は、食品ロスの問題にも及び、分かりやすく説得力がありました。
映画を見ているうちに、思い出したのは、日本の学校における家庭科の授業です。少し前、中学生の息子に家庭科の教科書を見せてもらったら、驚きました。料理は和洋中、様々なメニューと作り方が載っていて、栄養についてもしっかり習います。裁縫はもちろん、赤ちゃんの発達や離乳食の作り方まで載っていたからです。
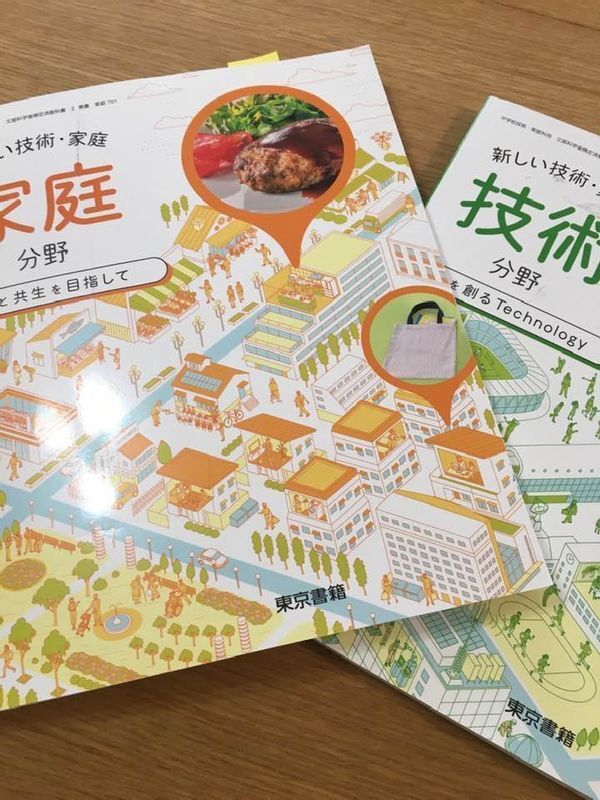
家庭科の教科書に載っていることができるようになれば、男の子も女の子も生活者として自立できそうです。
家庭内で発生する仕事について学ぶ日本の「家庭科」の授業と、アイスランドの「主婦の学校」には、共通点があります。それは、自立した人間は、単にお金を稼ぐだけでなく生活力がある、という価値観です。真の自立には、経済力だけではなく、生活全般の様々なことを理解し、実行する技能が必要なのです。
実は、この映画には「ジェンダー」や「SDGs」という観点の解説は登場しません。それでも、家の中の手仕事に意義を見出し、男女共に取り組む様子からは、自然と、本当のジェンダー平等や持続可能な社会に必要なことが、見えてくるのです。
オンライン試写に際して入手した資料には、ステファン・ホイクル・ヨハネソン駐日アイスランド大使のインタビューが収録されていました。大使は次のように話しています。
「現在のアイスランドの男性たちは、大体が女性と同じくらい家事をすることは普通だと考えています。この3 - 40年でアイスランドの社会は大きく変容したと言えるでしょう。」

映画の中では誰も「あなたも家事をしなさい」とか「男性も家事や育児をすべきだ」と言いません。交際相手との出会いについておしゃべりしながらブルーベリーを摘んだり、自作の素敵なワンピースを見せてくれる女性たち。「機織りが楽しい」「子ども服をいろいろ作った」「最初はトーストもうまく焼けなかった」と楽しそうに話す男性たち。
彼女・彼らの様子から、「ケア」を大事にする社会のありかたや、本当の意味での男女平等を考えさせる静かで楽しい映画です。
家庭科・技術の教科書以外の写真は全て(c) Mús & Kött 2020
10月16日(土)より、シアター・イメージフォーラム他全国順次公開
https://kinologue.com/housewives/










