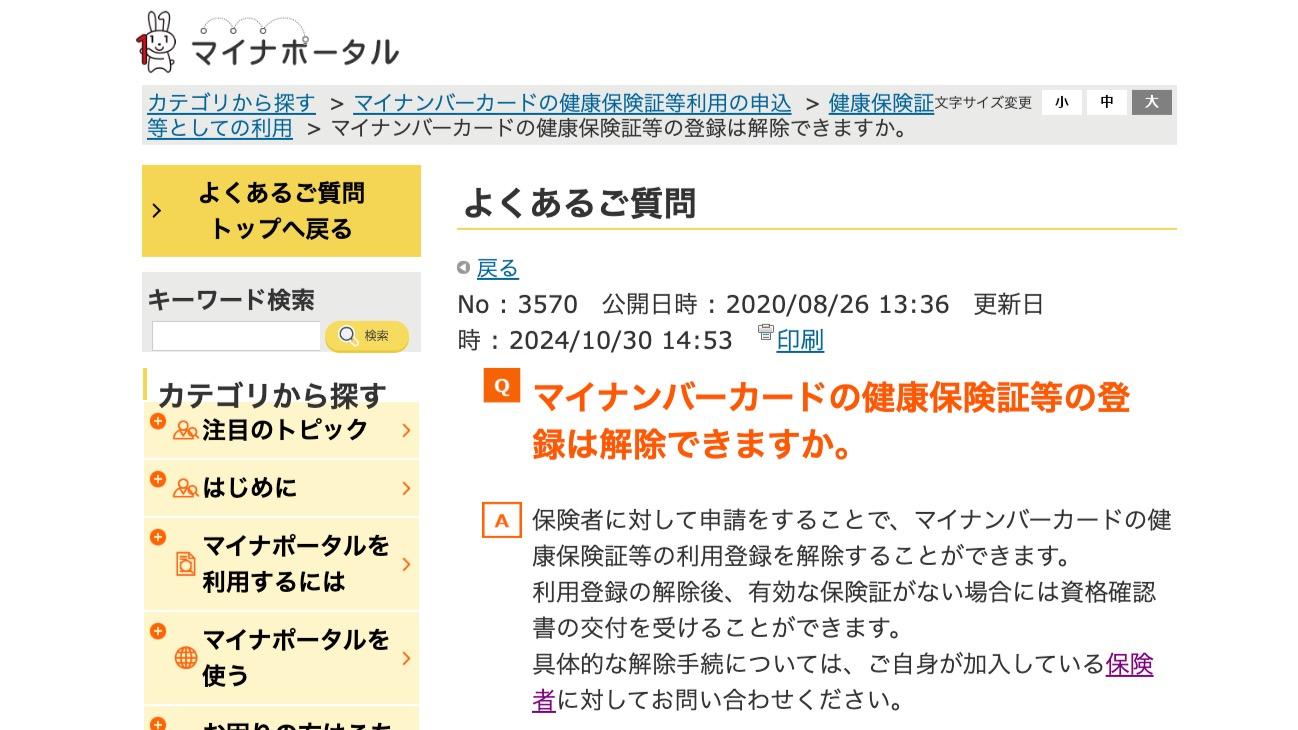世帯主の年齢で貯蓄額はどこまで変わってくるのだろうか
全体比率で世帯数と貯蓄額を見ると
高齢化社会の到来とその状況変化に伴う社会の仕組みの移り変わり、姿勢の変貌を受け、世代間の格差に注目が集まっている。その格差の指標の一つとなる貯蓄総額の違いについて、総務省統計局による「家計調査」の「貯蓄・負債編」における公開値から、「二人以上世帯」における現状などを確認していく。
用語のうち、気になる、誤解を受けやすい言葉についていくつか補足しておくと、次の通りとなる。
・「勤労者世帯」…世帯主が勤め人の世帯。ただし社長などの役員は「勤労者以外」や個人の自営業者、無職世帯は含まれない。
・「勤労者以外世帯」……世帯主が役員、個人営業世帯、無職世帯(年金生活で世帯主が働いていない場合も含む)など。上記「勤労者世帯」に該当しない世帯全般。
・「貯蓄」……負債を考慮しない、単なる貯蓄の額。預貯金だけでなく、生保の掛け金、有価証券、社内貯金、さらには共済などの貯蓄の合算。また負債をいくら抱えてても相殺されることはない。
次のグラフは「該当世帯数全体における、各世帯主年齢別の世帯数比率」、そして「各世帯主年齢階層別の、貯蓄総額に占める金額比率」を算出した結果。
これらのグラフには「単身世帯」は含まれていない。従って日本全体の状況を指し示しているわけではないが、昨今の状況における概要的なものは十分把握できる。
元々若年層は蓄財の機会・期間が少なく、実入りも少ない。当然貯蓄も少なくなる。さらに高齢者世帯が増加し、若年層世帯の数が減少しているので、世帯数割合が減少する。結果として「年齢階層別の貯蓄総額比率」も、高齢層が増えていく結果になるのは明らか。
直近の2014年分に関しては、70歳以上の世帯数が大幅に増加したことを反映し、世帯数比率・貯蓄比率共に、ますますシニア層の比率が高まっている。
高齢層「全体」の貯蓄額増加は、人数増加+経年蓄積の結果
上の2グラフから「世帯主が高齢層の世帯は皆が皆、ますますお金持ちになっていく」「若年層がさらに年々圧迫を受けている」と誤解をするかもしれない。しかしこの結果は、2002年以降時間の経過と共に個々の高齢者世帯が富んでいくことを意味しない。
つまり「所属世代層全体では無く、個々の1世帯単位で比べれば、元々高齢層は若年層と比較して貯蓄額が大きい。その高齢層の世帯数が増加し、若年世代層の世帯数が減っているのだから、二人以上世帯全体に占める高齢層世帯群の貯蓄額比率が増えても当然」という次第である。「(個々の)お年寄り世帯がますます裕福になっている」とは構成要素一つ一つの値の比較と、各世代属性全体による値の比較を混ぜ合わせてしまうことで生じやすい、誤解の一つといえる。
一方で同時に、世代別全体で見た場合、直近2014年では「二人以上の世帯の総貯蓄の7割近くは、60歳代以上の世帯だけで有する」「二人以上の世帯の総貯蓄の約85%は、50歳代以上の世帯だけで有する」ことになる。
今件は単なる「貯蓄」であり、上記にある通り負債の考慮は無い。そして負債の多くは住宅ローンであり、50歳代前後にはほぼ完済していることから、実質的な「純貯蓄額」(貯蓄から負債を引いた額)の総量はさらに50歳代以上に偏ることになる。
内需喚起が叫ばれる昨今だが、若年層に無理な支出を強いるより、「60歳代以上で7割近く」「50歳代以上で85%」(二人以上世帯のみ)の貯蓄を市場に、無論サービスなどの対価として、吐き出させるかを考えた方が効率は良い。やせ細ったまだ成長過程の樹木から未成熟の果実をもぎ取るより、熟した果実が実った大人の木々から収穫を得た方が、はるかに健全なのは言うまでもない。
誤解を受けかねないので付け加えておくが、これは「高齢層に無駄遣いをさせろ」を意味しない。支払いの価値がある効果・満足感を得られる商品・サービスを考察し、提供していき、お財布のひもを緩められるだけの社会的安心感を提供し、さらには資産を市場、そして特に若年層に還流させる仕組みを多数創り上げることを意味するものである。
■関連記事: