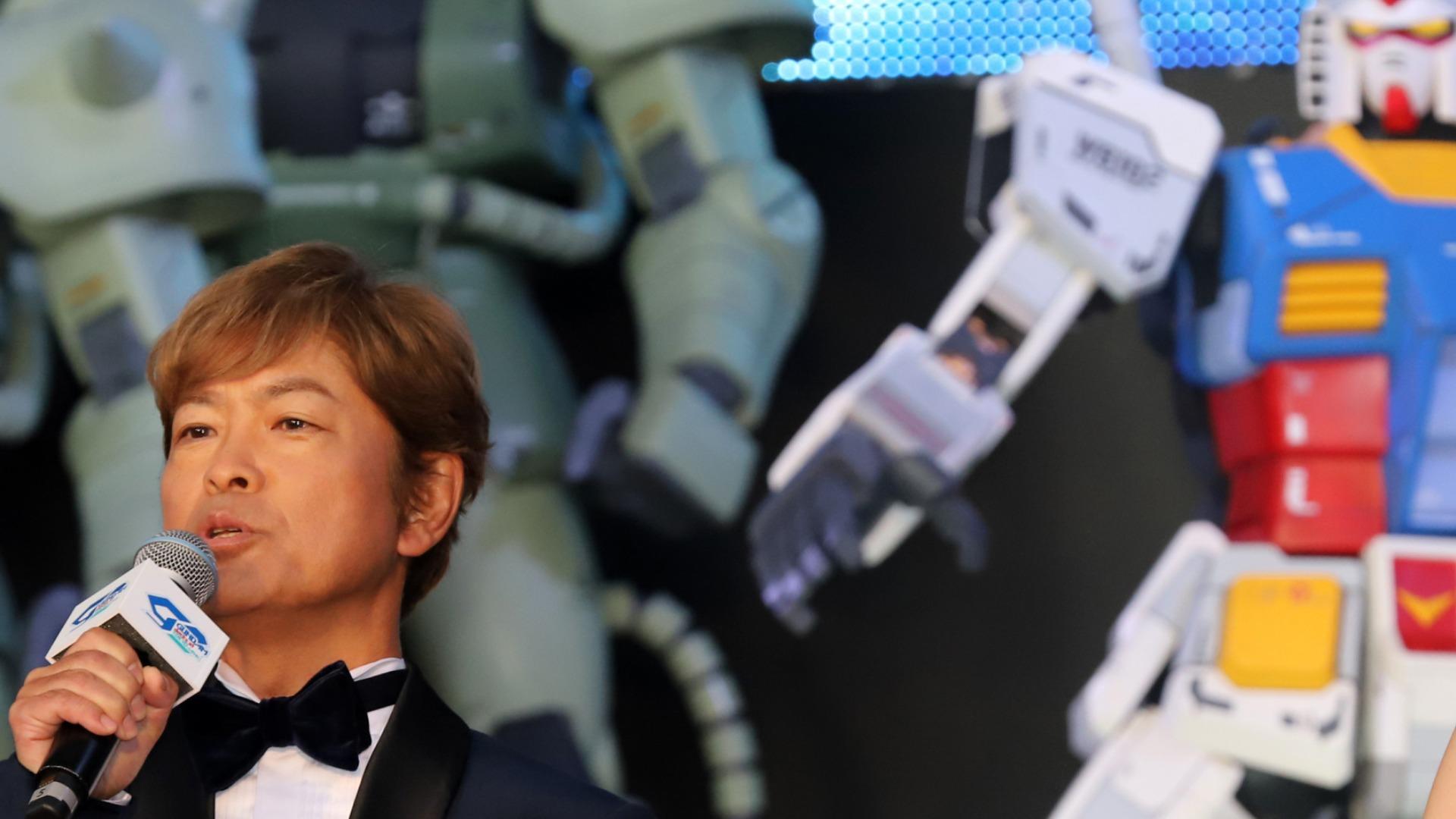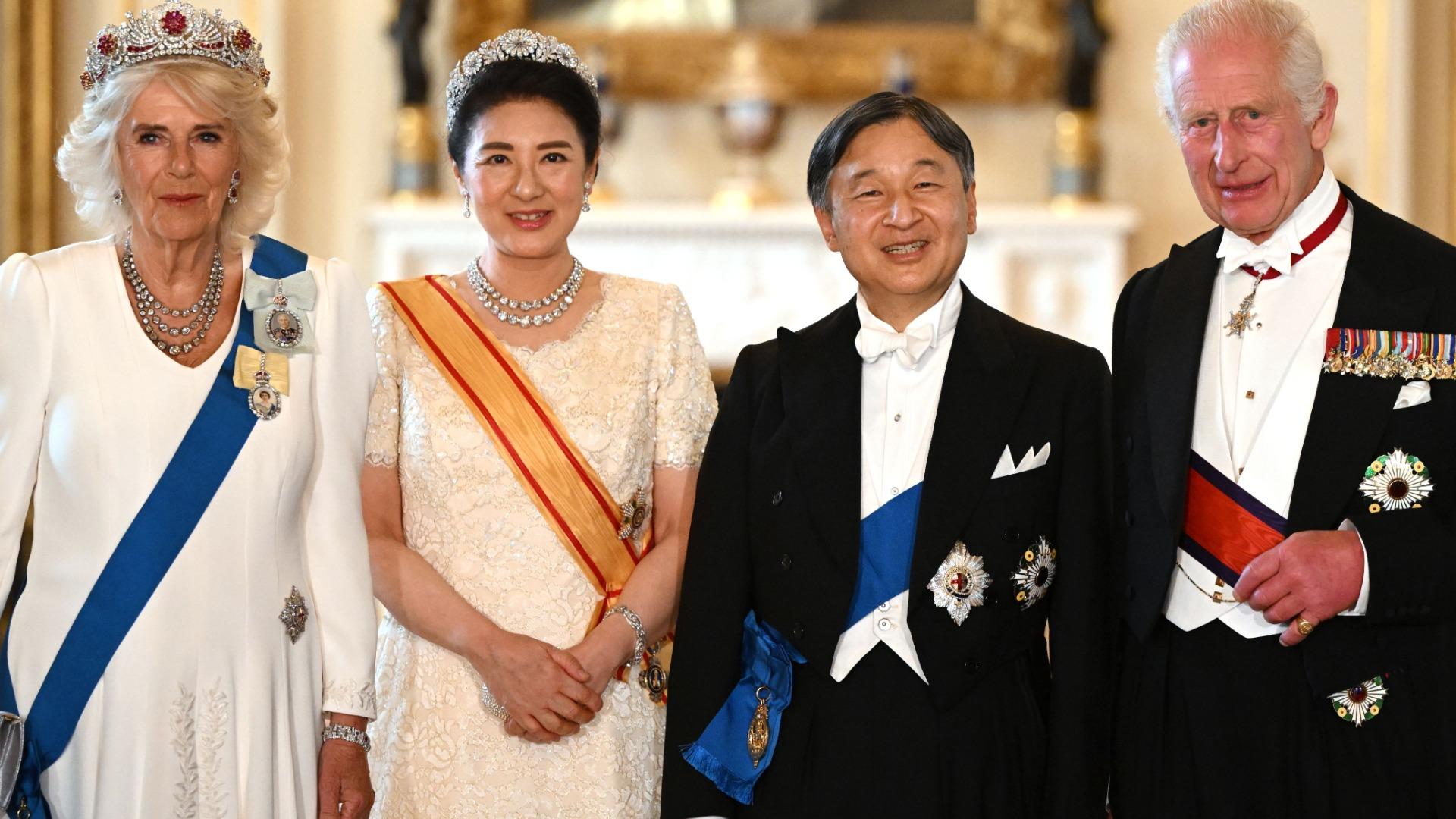IoTを正しく認識しよう
「IoT(インターネットオブシングス:Internet of Things)はもう古い」とか、「今はIoE時代だ」、「IoTは冷蔵庫や掃除機をインターネットにつなげることでしょ」など、間違った認識を持つ人が多いことに驚いた。非常に残念である。IoTはインターネットにモノをつなげることが目的ではない。インターネットのクラウドに上げたデータを利用してモノやサービスをインテリジェントにし、サービスの質を上げること、がIoTの最大の目的である。新しいビジネスやサービスを通して、経済を活発にすることもその一つ。
IoTの定義がいまだにあやふやな日本に対して、米国では定義がほぼ固まってきた。IoT(日本ではCPS:サイバーフィジカルシステムともいう)を利用して、製造業の生産性を上げる目的を持つものをインダストリー4.0あるいはスマートファクトリーと言う。GE(General Electric)社は、さらに製造した製品をこれまでのように販売するのではなく、ジェットエンジンや風力タービン製品について、例えば千マイルごとに、あるいは1kW発電するごとに料金を決める従量制ビジネスを展開する。これがインダストリーインターネットである。
また、米国ではIoEと言う人はほとんどない。Internet of Everythingとは言うが、IoEとは言わない。CPSはかつてIBMが言っていた言葉ではある。最近では霞が関の人たちがよく使っているが、世界的にはあまり言わない。むしろ、スマートグリッドという言葉が登場した頃、Smarter Planetと言っていたが、これこそIoTそのものである。つまり、IoTとは、インターネット(クラウド)にデータを上げ、そのビッグデータを解析することで、モノをインテリジェント化しようというコンセプトである。モノをインテリジェントするだけではなく、解析したデータを提供するサービスも含み、最近ではInternet of Servicesとも言われている。
これらを総称する言葉がIoTである。図1にIoTシステムをイメージした。つまり、センサ端末あるいはIoT端末からゲートウェイを通して、集めたデータをクラウド(つまりインターネット)に上げる。物理的にはクラウド上にはデータセンターのサーバーやストレージなどがあり、データセンターでビッグデータを処理すなわち演算・解析する。その解析結果を、ユーザーにサービスとして提供する。ユーザーは、個人だけではなく商業施設から始まり、農業や建機、鉱業、製造業、医療・ヘルスケア、スポーツ医学、電力、ガス、水道など個人向け・企業向けから社会全体へと広がる。新しい革新的なインテリジェンスが広がることになる。だからIoTのインパクトは大きい。
このインテリジェンスはビッグデータを解析する技術をデータセンターだけではなく、最近はIoT端末やゲートウェイ側でも持つ必要があると言われてきた。これがエッジコンピューティングである。これはIoT端末やゲートウェイでもデータ解析を行い、整理された形のデータをクラウドに上げようというモノ。従来は生のデータをそのままクラウドに上げ、クラウド上でHadoopをはじめとするデータ解析を行う考えが強かった。しかし、ここ1年で、エッジコンピューティングでビッグデータを予め整理するという考えに代わってきた。新しいコンセプトといえよう。一方のビッグデータ解析には、ニューラルネットワークをベースにしたマシンラーニングやディープラーニングなど人工知能手法が求められる。どちらも効率よく演算し、解析する技術がこれからますます求められるようになる。
National Instruments社は、技術開発に必要な要素はSTEMだという。STEMとは、Science(科学)、Technology(開発技術)、Engineering(生産技術)、Mathematics(数学)の略である。Scienceは、文系のPhilosophy(哲学)とも共通する言葉であり、物事の道理を追求し自然の原理を解明する。TechnologyはScienceに基づき物理的に具体化する。Engineeringは製品としてビジネスに載せる技術である。そして、MathematicsはScienceを具体化するのに必要な表現方式であり、ソフトウエアでアルゴリズムとして表現する。幸いにも半導体にはDSP(Digital Signal Processor)という積和演算専門のマイクロプロセッサがあり、数値演算に使う級数展開をプログラマブルに計算するチップがある。DSPは、数学的なアルゴリズムとは密接なつながりがある。IoTシステムにはSTEMが必要で、ただ単にインターネットにつなげるものではない。目的と手段をきちんと区別すれば、IoTのインパクトを理解できるはずだ。
これらを概観し、解説する本を出したい、とある出版社に提案したら、IoTはもう古い、と言われた。残念ながらIoTのインパクトを理解していただけなかった。これだけではない。エレクトロニクス技術に疎い人たちと話をしたあと、「これまでIoTはインターネットとつなげるモノのことでしょ、というだけで、それがなぜインパクトをもたらすのか全く分からなかった」、と言う。IoTの正しい姿を描く本は、どなたでも構わないが、やはり発行すべきだと思う。IoTやワイヤレスセンサネットワークなどを研究している人たちに正しい知識の本を書いていただいてもよい。さもなければ米国にもっと遅れる恐れがある。それが怖い。
(2015/11/02)