12年ぶりの紅白出演にみる「新しいはじまり」 2020年代のMr.Childrenの行方は
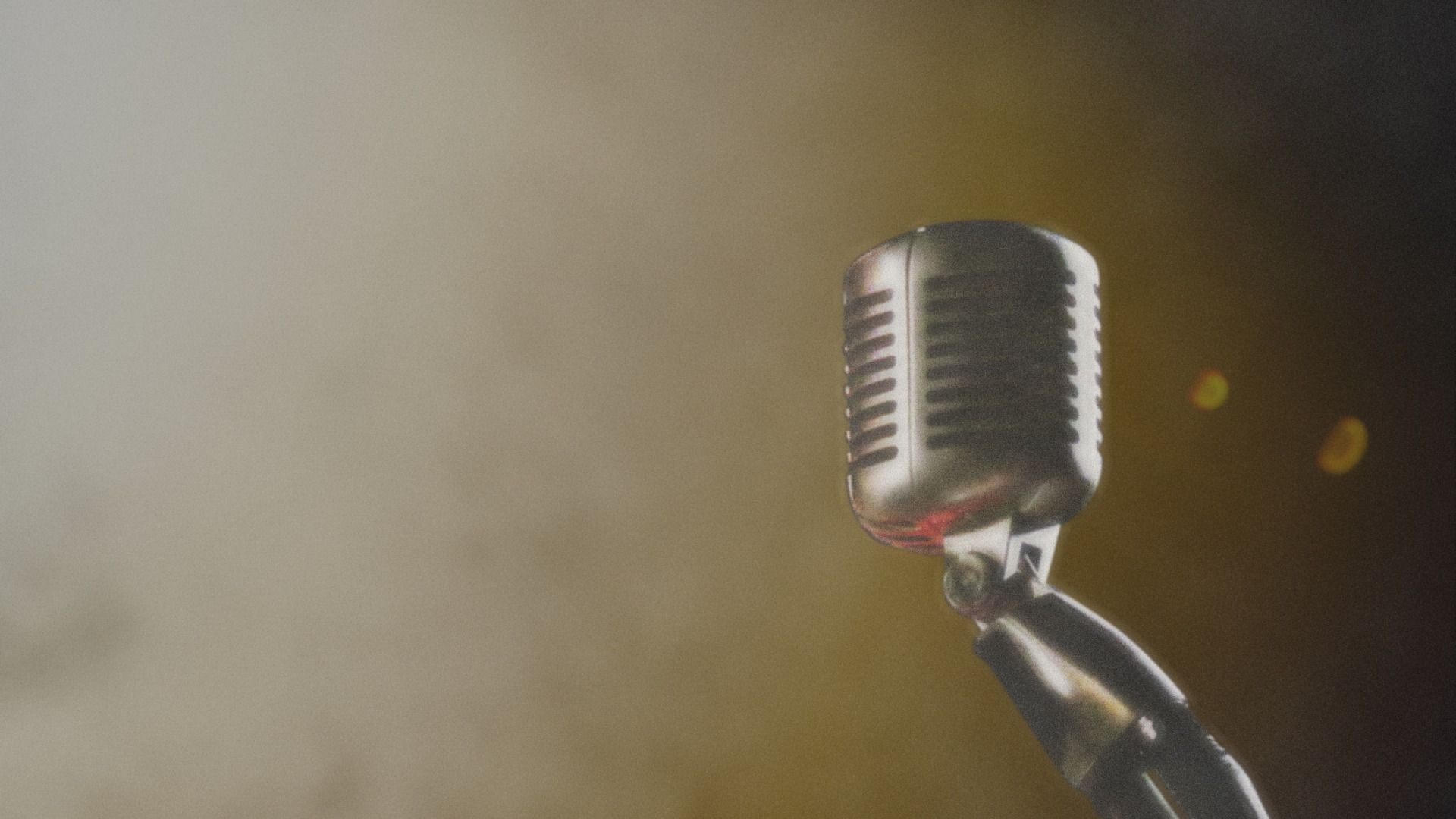
2008年以来、12年ぶり2度目の出演となった紅白歌合戦で最新アルバム『SOUNDTRACKS』の収録曲「Documentary film」を披露したMr.Children。その12年の間に、社会のあり方、そして音楽業界のあり方は大きく変化した。常に「国民的バンド」として時代の空気と向き合ってきた彼らは、コロナ禍に揺れる今の日本においてどんなメッセージを届けようとしているのか。メジャーデビューから28年が経過した大ベテランバンドの「新しいはじまり」を振り返る。
「今まで当たり前にあった日常を慈しみながら」
「こんばんは、Mr.Childrenです。今年は、いつもとは違う異常な年だったと思います。でも、何の変化もない、いつも通りのことなんかこの世の中にないのではないかと考えたりもします。だからこそ、今まで当たり前にあった日常を、いつもすぐ近くにあったものを、人を、今生きているということを、切実に慈しみながら次の曲をお届けしたいと思います」
2020年12月31日の22時44分ごろ、2回目の紅白歌合戦出演を果たしたMr.ChildrenはこんなMCとともに「Documentary film」を披露した。
「Documentary film」は紅白直前の12月2日にリリースされた最新アルバム『SOUNDTRACKS』の中の1曲。今作全体を貫いている「生と死」といったテーマが表現された言葉にはヘビーな色合いもあるが、そんな歌詞が桜井和寿の歌う雄大なメロディと組み合わさることで身近さを帯びてくる不思議な魅力をたたえた楽曲である。
コロナ禍が世界中に広まる直前に海外でのレコーディングを終え、その後は「余韻に浸っているだけの1年」(12月25日に放送された「MUSIC STATION ウルトラSUPERLIVE 2020」での桜井和寿の発言)となってしまったMr.Childrenの2020年。多くの人々にとってイレギュラーな1年となった2020年のラストに、彼らはバンドの最新モードを日本中が注目する場所で響かせた。紅白という舞台に合わせた派手な演出を施すアーティストも複数登場する中、Mr.Childrenはあくまでも歌と演奏をじっくり聴かせるステージをお茶の間に届けた。
2008年と2020年 社会、そして音楽業界の大きな変化
Mr.Childrenが紅白歌合戦に初めて出場したのは12年前の2008年。歌唱したのは同年にリリースされた「GIFT」で、この曲はNHKの北京五輪中継のテーマソングとなっていた。彼らのパフォーマンスとともにオリンピックの名場面が流され、加えてメンバー以外の大勢の人たちとともに「合唱」する演出(同五輪のフェンシングで銀メダルを獲得した太田雄貴もステージに参加していた)が施されるなど、「皆で一つになる祭典としての五輪」「それを彩るMr.Childrenの音楽」という側面が強調されていたのがこの年の彼らのパフォーマンスだった。
Mr.Childrenが紅白に出演した2008年と2020年のマクロな社会環境を比較すると、いくつかの共通点、およびそれゆえに際立つ相違点が見えてくる。2020年は新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るい世の中のあり方を大きく変えることとなったが、2008年も9月にリーマンショックが勃発してその後の不景気に突入するきっかけとなった年である。一方で、ともに「オリンピックイヤー」にもかかわらず、2020年はその点において大きな喪失感を伴う1年となった。
2008年というのは日本でiPhoneが発売された年。つまり当時はまだ「ガラケーの時代」で、この一点からも12年前の社会が今とまったく違ったものであることがわかる。そして、その「今とまったく違ったもの」という描写は音楽シーンに関しても当てはまる。AKB48の「選抜総選挙」が始まるのは2009年で、当時の音楽業界は減少を続けるCD売上に対する明確な対処方法を見つけ出せずにいた。そこから12年の時を経て、CDの複数枚商法を定着させた48グループはもはや一つの役目を終えた状況になっており、2010年代の音楽産業をけん引したライブ・フェス市場もコロナ禍により壊滅状態に陥るなど、日本の音楽シーンはまた新たな問題と直面している。
ネガティブな状況が多数現出した2020年の音楽シーンだが、ライブやフェスの停滞とは対照的に、ストリーミングサービスやTikTokなどのデジタルプラットフォームが連動した新しい生態系が形成されるという大きなトピックもあった。2010年代半ばから少しずつ進んでいた日本の音楽を取り巻く環境のデジタル化の帰結が一気に2020年にやってきたという側面もあり、そういった地道な蓄積を踏まえて瑛人やYOASOBIといった新時代のスターが生まれた。
世の中、そして音楽シーンのあり方が大きく変わる中で、Mr.Childrenの立ち位置やその視界の先にあるものも微妙に変化している。前回の紅白出演の直前である2008年12月にリリースしたアルバム『SUPERMARKET FANTASY』が2009年のオリコン年間チャートでオリジナルアルバムとしてはトップ(総合2位、1位は嵐『5×10 All the BEST! 1999-2009』)になるなど名実ともに「みんなのうた」を生み出していた12年前のMr.Childrenに対して、2010年代の彼らは引き続き「国民的バンド」としての地位を維持しながらもその活動から時折「迷い」が垣間見える瞬間もあった。
「どこにボールを投げていいのかわからないっていうのはすごくありましたけどね。『今、必要とされてるポップソングってなんだろう?』っていう」(『ROCKIN’ON JAPAN』2015年7月号 桜井和寿の発言)
「ファンが求めること」「バンドとしてやりたいこと」の狭間で
『SOUNDTRACKS』をリリースした2020年12月、Mr.Childrenの面々はいつになく積極的にメディアでの露出をこなした。各局で放送される年末の大型特番にも軒並み出演し、アルバムの収録曲を多数披露した。
昨今の大型歌番組は、それが年末の放送であっても「その年のヒット曲を振り返る」のと同等もしくはそれ以上に「みんなが知っている歌で盛り上がる」というお祭り的な要素が強い。広く世の中に知られるヒット曲のあるアーティストにはそういった役割が期待されており、たとえば前述の「MUSIC STATION ウルトラSUPERLIVE 2020」においても、30年ぶりにMステに出演した久保田利伸は2020年リリースの「Boogie Ride」とともに96年リリースの大ヒット曲「LA・LA・LA LOVE SONG」を披露し、2020年の象徴的な1曲となった「うちで踊ろう」をパフォーマンスした星野源は自身のその日のセットリストに「恋」を組み入れている。
Mr.Childrenの同番組での演奏曲は「Birthday」と「Documentary film」。「お祭り」であっても「innocent world」も「終わりなき旅」も「HANABI」も歌わないそのスタンスは「FNS歌謡祭」「CDTVライブ!ライブ!クリスマススペシャル」から紅白歌合戦に至るまで徹底的に貫かれた。
Mr.Childrenと同じく長年「国民的バンド」の地位を維持している存在としてサザンオールスターズがいるが、彼らが2018年の紅白歌合戦に出演した際の歌唱曲は「希望の轍」と「勝手にシンドバット」だった。後者ではステージ上に北島三郎や松任谷由実といったその日の出演者が勢ぞろいし、日本の歌謡史に残るようなゴージャスなパフォーマンスが実現したことは記憶に新しい。「平成最後の紅白」というテーマがあったからこその選曲だったとはいえ、サザンオールスターズの紅白に向き合う姿勢と比べるとMr.Childrenの禁欲性の高さが際立つ。
もっとも、Mr.Childrenは最近の活動において「国民的バンドとしてのふるまい」を単に拒否しているというわけではない。2017年に行われたメジャーデビュー25周年を祝うスタジアムツアーではバンドの代表曲(彼らにとっての「バンドの代表曲」は「Jポップの代表曲」と同義である)を出し惜しみなく繰り出し、多くの人々を喜ばせた。「ファンが求めること」「バンドとしてやりたいこと」の狭間でどうバランスをとるか考えるのはどんなアーティストにとっても当たり前の行為であり、Mr.Childrenも例外ではない。
2020年代のMr.Children
前述のとおり「どこにボールを投げていいのかわからない」といった2010年代の状況に比べると、『SOUNDTRACKS』およびそれにまつわる活動の中でMr.Childrenが見据えているものはよりクリアになっている。「これまで以上に日常がベースになっていて。起伏のない日々が少しでもカラフルに見えるようなサウンドトラックになればいいなと思って、このタイトルを付けました」との通り(『ナタリー』2020年12月 桜井和寿の発言)、リスナーの暮らしに寄り添った音楽のあり方を考え抜いた作品として『SOUNDTRACKS』というアルバムがあり、そこに対する確信があるからこそ不特定多数の目に触れるメディア出演でも「今のMr.Children」を見せることにフォーカスしているのだろう。
改めてリスナーの目線に立ち、そして海外のエンジニアとの共同作業により今までとは全く異なるサウンドの感触を手にしたアルバム『SOUNDTRACKS』は、Mr.Childrenの新しいはじまりを告げる作品である。紅白歌合戦を含めた年末の活動を通じてMr.Childrenのそんな現状を多くの人に伝えることができたのは、この先のバンドのキャリアに大きな意味をもたらすはずである。
「いつもアルバムを出す時って、特に最近は『単なる大御所のバンドでしょ?』って惰性でやってるようには絶対に思われたくないから、何か新しいトライをしようと意気込んでやってきたわけだけど、気づけば自分たちが自然と『僕らはレジェンドバンドです』って胸を張って言えるような、そういうアルバムになった気がしますね」(『MUSICA』2021年1月号 桜井和寿の発言)
周囲からの期待を受け入れたうえで、バンドとしてやりたいことも追求する。「大ベテラン」の域に入ってきた段階で、Mr.Childrenは改めてそんな理想的なゾーンに突入しつつある。2020年代は、これまでも十分すぎる足跡を残してきた彼らがまた新たな魅力を開花させる時代になるかもしれない。
【この記事は、Yahoo!ニュース個人編集部とオーサーが内容に関して共同で企画し、オーサーが執筆したものです】










