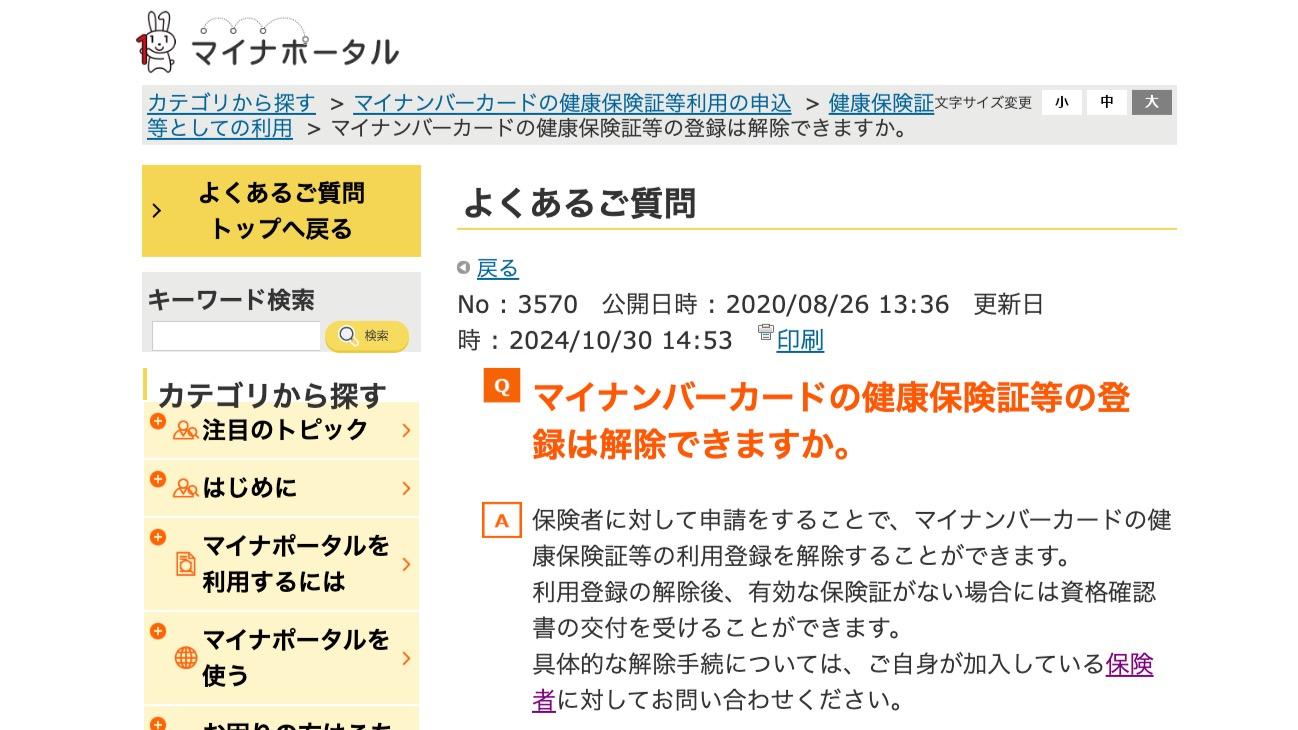「知人との交友」「情報探索」…ソーシャルメディアの利用目的をさぐる

目的は「知人との交友」が8割強
スマートフォンやタブレット型端末の普及で加速度的に浸透しつつある、ウェブサービスの一つ「ソーシャルメディア」。今や寝食を忘れてアクセスを続ける人も多い。そのソーシャルメディアについて、そもそも論として「なぜソーシャルメディアを利用するのか」を、総務省が2017年6月に詳細値を発表した「通信利用動向調査」(※)の公開値を基に、確認していく。
今件における「ソーシャルメディア」だが、補足説明の用語集では「インターネット上の交流を通して社会的ネットワーク(ソーシャルネットワーク)を構築するサービスのことである。Facebook やTwitter、LINE などが代表的」(ソーシャルネットワーキングサービス(SNS))とある。LINEなどのようなチャット系コミュニケーションサービスは厳密な解釈では定義から外れるが、社会全般的には同一視されていること、質問の上でもそのような区分がなされているため、該当するものとみなす。他方、広義では含まれることになる掲示板や動画投稿・共有サイト、ブログは他項目で別途言及されていることもあり、該当しないものとする。
今調査によればソーシャルメディアの利用率は、インターネット利用者においては51.0%(無回答者除く、以下同)。見方を変えると、インターネットにアクセスできる機会を持ちながら、ソーシャルメディアの類を使っていない人は5割近くに及ぶことになる。

年齢階層別では20代がもっとも利用率が高く7割超え、40代までは過半数で、50代でも4割を超えている。むしろ60代以降でもインターネット利用者の1割から2割が利用している実態には驚かされる(もっとも高齢者にとっては、インターネットの利用そのものが高いハードルなのだが)。
それではソーシャルメディア利用者は、何を目的としてアクセスしているのか。全体的な回答が次のグラフに示されているが、最上位の同意率を示している項目は「従来からの知人とのコミュニケーション」。つまり利用者のうち87.3%は、ソーシャルメディアで身近な知人とのお話、交流を望んでいることになる。

これは手紙やメール、電話と比べると利用ハードルが低く、気軽にコミュニケーションができるのがポイントとなり、多くの人に使われていると見て良い。また、自分の状況を披露しておくことで、自分の知人に間接的な意思表示(例えば「忙しい」「元気だ」「明日は暇だ」)をすることも可能となる。
次いで多い目的は「知りたいことについて情報を探す」で46.1%。ソーシャルメディア内で知的好奇心の充足を望んでいることになる。昨今ではソーシャルメディア上で情報を直接、あるいは間接的に(URLなどでガイダンスする形で)公知する場合も多く、これらをたどることで望んだ情報を取得できることになる。あるいは関連する情報を得られそうなアカウントに追随し、日頃からチェックをする場合もあろう(芸能人、著名識者、関連会社、報道関係、事例はいくらでも想定しえる)。
一方、はっきりとした目的意識は無い「暇つぶし」との回答率も3割強と高い。交通機関を使った移動の際に雑誌や新聞を読み進めるような、あるいは休日の午後、特にすることも無く外出するのも面倒な時の時間の経過を過ごす際に、ソーシャルメディアをざっと眺めて場の雰囲気を楽しむ人は案外多い。
やや回答率は下がるが、「同じ趣味や嗜好を持つ人を探す」も2割近く。いわゆる「類友」「同好の士」を探す主旨。趣味が同じならば有益な情報交換もでき、共に語らうことで有意義な時間を過ごせる。さらにこれと類するものだが、相手を特定せずに情報発信をし、自己顕示欲の充足やストレス解消と共に、「自分と同じ立場にある人」を探す(探してもらうきっかけを作る)動きもある。
震災以降その役割が重要視されるようになった「災害発生時の情報収集・発信」は14.7%と1割強。普段から意識して利用する、明らかな目的として認識した上で注視する人はさほどいないとの意味であり、使うことが無いわけではあるまい。
年齢で変わる、変わらない利用目的
この結果についていくつかの属性別で再計算を行い、その動向を確認する。まずは年齢階層別。

どの年齢階層でも「知人との交友」が最多回答項目であることに違いは無いが、歳と共にその値は下がっていく(6~12歳でやや低めなのは、実社会でも交友範囲が限定的なのが原因)。他方「情報探索」は歳を経るに連れて上昇していく動きがある。一番高い値を示しているのは、意外にも70代。シニア層にとってソーシャルメディアは、情報の名前を冠する宝物が散在している場所に見えるようだ。
いわゆる「同好の士」を探す動きも「知人との交友」と同じ流れで、若年層ほど高い。ソーシャルメディアを使い、新規にしても従来のつながりにしても、積極的にコミュニケーション網を広げていこうとする意志が見える。
一方値そのものは低いが「自分の情報や作品の発表」は13歳以降年齢階層間の格差があまりない。世界へ向けた情報発信への意欲、期待は年齢を超えている。これはシニア層においては、注目、そして評価すべき流れと言える。
「災害発生時の情報収集・発信」だが、こちらはシニア層の方が高い値を示している。80歳以上が最大値で6割に迫る勢い。先の震災時には千差万別ではあるが、情報の確認や発信にソーシャルメディアが役立ったことは誰もが認めるところ。特に高齢層はそのありがたみを強く覚えたようだ。
男女別では?
男女別ではどうだろうか。こちらは同一性別内における年齢階層別の流れを見やすくするため、上記のグラフとは項目の表記を変えてあることに注意。また「上位陣」と「下位陣」では回答率に差異がありすぎるため、縦軸の区切りも変更してある。


「知人との意思疎通」とのコミュニケーションは全般的に女性の方が高め。女性がデジタル・アナログを問わずコミュニケーションを好むことはすでに知られている通りだが、それがソーシャルメディア内でも結果として表れている形。一方で「情報探索」は中堅では男性の方がやや高くなるが、壮齢層以上ではやはり女性の方が高い。また6~12歳の差異は印象的。
コミュニケーションのテーマとして用いられることが多い、趣味趣向に関して「同好の士」を探す動きではやや男女間の差異は大きい。若年層は女性が、中堅層以降は男性の方が高い値を示している。一方「暇つぶし」は男女の差があまり見られない。やや中堅以降で女性が高めを示す程度の違い。
また上位陣では13~19歳で「知人との意思疎通」以外の項目にて女性の値が大きく男性を抜きんでる結果が出ており、この年齢階層における女性のソーシャルメディアの利用目的が多様に及んでおり、積極的に活用している様子がうかがえる。
他にも「災害発生時の利用は、シニア層が高いが、特に男性は歳を経るほど利用する人が多くなる」「自作品や自情報の発信意欲は若年層に強く、男性は高齢層でも高値を維持する」などの動向が確認できる。
法的に、そして規約的に問題が無い限り、ソーシャルメディアをどのような利用目的で使おうと、他人がそれを束縛する権利はない(無論、昨今問題視されている盗用コンテンツの悪用や、詐称的なリンク掲載による釣り行為は問題外である)。一方、ソーシャルメディアはあくまでもツールでしかなく、そのツール経由で伝達される情報の真偽性は、ソーシャルメディア自身が担保しているわけではないことに注意しなければならない。例えば「世界最大規模のFacebookで語られていた話だから、この情報は絶対に真実だ」と盲信すると、痛い目にあう可能性は十分にある。
情報の「確からしさ」を精査するには経由されたサービス以上に、情報発信源について、確認をすべきであることはいうまでもない。
■関連記事:
20代女性の6割近くは「ソーシャルメディアが生き方に影響を与える」
※通信利用動向調査
2016年11月~12月に世帯向けは都道府県及び都市規模を層化基準とした層化二段無作為抽出法で選ばれた、20歳以上の世帯主がいる世帯・構成員に、企業向けは公務を除く産業に属する常用雇用者規模100人以上の企業に対し、郵送・オンラインによる調査票の配布及び回収の形式によって行われている。有効回答数はそれぞれ1万7040世帯(4万4430人)、2032企業。調査票のうち約8割は回収率向上のために調査事項を限定した簡易調査票が用いられている。各種値には国勢調査や全国企業の産業や規模の分布に従った、ウェイトバックが行われている。