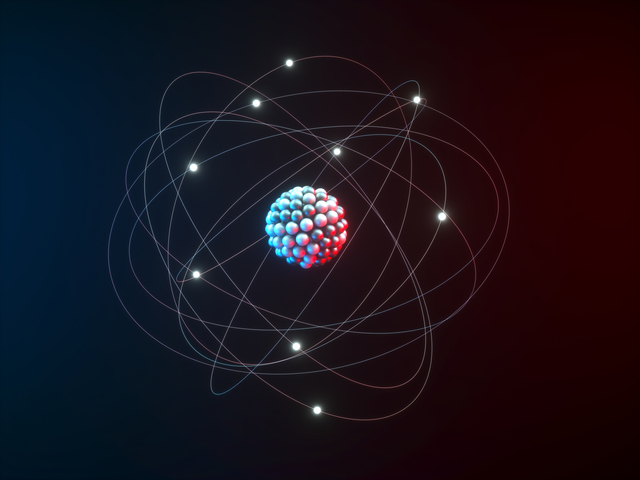日本の哲学者にはこの不条理な世界がどう映っていたのか…生き方が変わる「最強のヒント」
明治維新以降、日本の哲学者たちは悩み続けてきた。「言葉」や「身体」、「自然」、「社会・国家」とは何かを考え続けてきた。そんな先人たちの知的格闘の延長線上に、今日の私たちは立っている。『日本哲学入門』では、日本人が何を考えてきたのか、その本質を紹介している。 【画像】日本でもっとも有名な哲学者がたどり着いた「圧巻の視点」 ※本記事は藤田正勝『日本哲学入門』から抜粋、編集したものです。
「心」について考える
私たちは通常、一方に自分の外にある対象を表象する、あるいは認識する「意識」、別の表現を使えば、「心」というものを考え、そして他方に、意識によって表象される「物」を考え、そのあいだに認識なり、行為という関係が成立すると考えている。 その考えを徹底していくと、意識の外部には、私たちが見たり、聞いたり、触ったり、味わったりする以前の、単なる物体の世界が広がっていることになる。目の前の梅の花が白く、あるいは赤く見えたり、かぐわしい香りがしたりするのは、私たちがそれを見たり、その匂いを嗅いだりするからである。つまり、外から与えられた情報が脳に伝えられるからであって、それ以前には、色も味も香りもない単なる物体──それを細かく分析していけば、原子の世界、さらにはクオークの世界に行きつく──が広がっているだけであるという自然科学的な見方につながっていく。それに対して私たちの方は、その外部の世界の情報を感覚器官を通して受け取り、それを脳に伝える。そこに色や匂い、味で満たされた意識の世界、「心」の世界が作りあげられていくと考えられる。 両者を区別する立場からは、当然、前者が原因であり、後者はたまたま生じた結果である。したがって前者こそが第一次的な存在であり、後者は第二次的、あるいは派生的な存在であると考えられる。 また、外部世界は、誰が計測しても同じ結果が得られる客観的な世界であるのに対し、意識の世界は、それを見たり聞いたりする人によって異なる。たとえば物の見え方は、立つ位置によっても異なるし、光の当たり方とか、目の病気とか、その状況に大きく左右される。味や匂いは、文字どおり、受け取り方が人によって大きく違う。そこから意識の世界は、主観的であいまいな世界であるという見方が生まれてくる。つまり、物理の世界が絶対確実であるのに対し、私たちの意識の世界は不確かで、信頼性に欠けるものだと言われることになる。