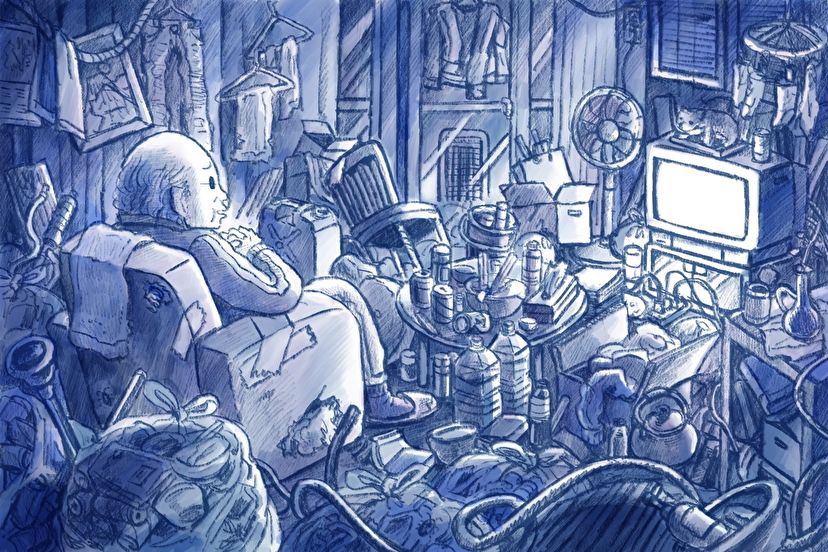毎年5月の初旬、宮崎県延岡市は「熱狂の季節」を迎える。陸上競技の中・長距離の記録会「ゴールデンゲームズinのべおか」が開催されるのである。同市が推進する「アスリートタウン」構想に基づくこの大会は、期間中、全国から約2万5000人のファンが押し寄せ、好記録が続出することで知られる。率いるのは日本陸上史にその名を残す宗兄弟。今年で28回目、人口わずか12万に過ぎない延岡市が、どうして大規模な陸上競技大会を継続して成功させることができたのか。
(ライター・中村計/Yahoo!ニュース 特集編集部)
ランナーと観客を鼓舞するマイクパフォーマンス
絶叫、歓声、騒音。そして、ランナーが駆け抜ける音が、場内に渦巻いていた。
「ペースが落ちてる! 前出んか!」
声に尻を叩かれたランナーは、顔を歪め、ぐいと前へ出る。
「ゴールデンゲームズinのべおか」(以下、GGN)の立ち上げに尽力した旭化成陸上部の元総監督で、昭和の名ランナー・宗茂は、トラック内のフィールドをせわしなく動き回る。そして、ランナーの顔につばがかかるのではないかというぐらいの距離まで近づき、ヘッドマイクを通してがなり立てるのだ。
叱責の矛先はときに観客にも向かう。
「お客さんは、拍手っ!」
自己ベストタイムが近い選手同士でレース表を組む。先頭が遅れ始めると、誰かがすかさず代わりに前に出るため、ペースが落ちない(撮影:比田勝大直)
西階(にししな)陸上競技場の一周400メートルのトラックは、横3メートル、縦50センチのスポンサー名が書かれたブリキ製の看板160枚で囲まれている。そして、ランナーが通過するたびに、観客はスタッフから配布された硬い紙の管で看板をガンガンと叩き、声援を送る。まるで、暴れる洗濯機のような音は、レース序盤、高速で駆ける選手の固まりの動きに合わせて、ぐるりとトラックを一周する。後半になり集団がバラけてくると、場内のあちらこちらからけたたましい音が鳴り響くようになった。場内全体が、興奮状態に陥っているかのような光景だった。
毎年、最前席に陣取るという延岡在住の岩崎ファミリー(撮影:比田勝大直)
今年のGGNは、中学生から社会人まで744名の選手がエントリーし、9種目29レースが行われた。第1レースは12時15分にスタート。重要なレースほど好記録が出るよう気温が下がる後半に組まれている。残り7レースとなった午後7時過ぎ、4台の移動式照明車に囲まれ、闇夜に浮かび上がった競技場は観客席に1万5000人、さらにグラウンドレベルに約1万人の観客がひしめき合っていた。
トラックは全8レーンだが、7、8レーンは観客スペースとして開放されているため、ファンから走者までは、まさに目と鼻の先。全天候型トラックを叩く硬質で軽快な足音と、リズミカルな呼吸音までが聞こえてくる。
2000本用意された旭化成の繊維工場で糸を巻くときに使う紙の管(撮影:比田勝大直)
目の肥えた陸上ファンが選手を育てる
グラウンドまで観客を入れたのは宗兄弟(茂と、旭化成総監督の宗猛)のアイデアだった。
「ノルウェーのオスロで体験した競技場(ビスレット・スタディオン)の雰囲気を再現したかった。観客がとにかく近くてね。そこはトラックの外がすぐスタンドで、観客はその床板を踏みならして応援する。それをイメージして、看板を叩かせた」
そう話すのは、兄の宗茂だ。
兄の宗茂は「延岡市民で、ゴールデンゲームズの開催日を知らない人はいない」と胸を張る(撮影:比田勝大直)
シドニー五輪のマラソン日本代表で、旭化成陸上部のコーチを務める川嶋伸次は、現役中、GGNで何度となく自己新記録を更新した。
「延岡のファンは、みんな目が肥えている。しんどいところになると、一層、声援をくれる。だから、ここで走ると、一種のゾーンに入るんですよ」
GGNでは主要レースにペースメーカーとして、一線級の外国人ランナーを投入する。旭化成のヘッドコーチで、大会運営を任されている小島忠幸は「額までは言えませんが、うちはフルマラソンのペースメーカーより高いお金を払っています」と自負をのぞかせた。
日本企業チームに所属する外国人選手が多く出場する組は、毎年、大会一の高速レースになる(撮影:比田勝大直)
「1人で押すことが苦手な日本人ランナーにとって、ペースメーカーはとても重要。日本人ランナーの特性を理解し引っ張ってくれる人でないとダメなんです」
昨今はマラソンブームで、マラソン大会の実施は地域おこしの定番となった。しかし、GGNのようなファンと選手が一体になった記録会は、国内では類を見ない。
「最初はこんなに大きな大会になるとは思っていなかった。ある選手が『国立競技場でもこんなに人は集まらない』と驚いていたときは、感無量でしたね」
第1回大会から、運営に関わっている旭化成陸上部のマネージャー・楠光代は感慨深げに語る。
愛宕山からの眺め。小規模なイオンショッピングセンターが、ほぼ唯一の商業施設(撮影:比田勝大直)
なぜ「アスリートタウン」を構想したか
延岡市は県庁所在地の宮崎市の北約80キロに位置する。三方を山に囲まれ、高速道路が整備されるまで「陸の孤島」と呼ばれた。小説『坊っちゃん』の中で、うらなり君の左遷先として登場し、<山の中も山の中も大変な山の中>と書かれているほどだ。
延岡市は、かつて城下町だった。大正時代に旭化成が創業し、以降は、企業城下町として栄えた。城に代わって、赤と白の高さ約180メートルの巨大な煙突が街のランドマークになった。しかし1970年代に高度経済成長の時代が終わると、工業一色の街は、少しずつ停滞感が漂い始める。
東京で生まれ育った茂木圭次郎は、強豪大学の誘いを断り、「練習に集中できると思った」と旭化成に入社。関東出身の有力選手が高卒で入社するケースはまれ(撮影:比田勝大直)
そんな中、1990年代に入り、「アスリートタウンづくり」を提唱し始めたのは、青年会議所(JC)のメンバーたちだった。
「延岡では宗兄弟を始めトップアスリートが何人も育っていたので、彼らを地域資源として活用できないかと思った」
そう説明するのは、現在の延岡市長で、当時、JCの理事長を務めていた首藤正治だ。
高校まで延岡市で育った首藤正治市長は、アスリートタウン構想によって「(市内外の)交流人口を増やしたい」と意気込む(撮影:中村計)
「ただ、街の規模からいっても、世界大会を開催するとか派手なことはできない。だから、合宿を誘致したり、中規模の大会を開催して、よそから人に来てもらおうと」
旭化成陸上部は、70年代から80年代にかけて宗兄弟が活躍しただけではない。1991年の世界陸上で谷口浩美が金メダルを獲得し、1992年のバルセロナ五輪では森下広一が銀メダリストとなった。新星が次々と現れ、正月恒例の全日本実業団対抗駅伝競走大会でも90年代は、96年を除き、すべて優勝するなど黄金時代を築いた。
旭化成の練習グラウンドから川沿いに延びるオリンピア・ロードコース(40キロ)には「ランナーに注意」の看板やのぼりがいくつも設置され、市民ランナーにも人気だ(撮影:比田勝大直)
その時代、延岡市民の記憶は、旭化成陸上部の活躍とともにあったと言っていい。延岡市民のランナーへの理解は深く、車を運転中、ランナーを見かけると反射的に徐行運転に切り替えるのだという。
1990年に開催されたGGNの第1回大会は、そもそも旭化成グラウンドの改修を記念して行われた、単なる「長距離記録会」だった。すると、参加者の6割以上が自己ベストを更新した。翌年から、参加者の要望に応える形で記録会は継続されていく。噂が噂を呼び、年々、エントリー数は増加。比例し、観衆もどんどん増えていった。
市の補助金は、4台で660万円かかる移動式照明のレンタル料で、ほぼ使い切る(撮影:比田勝大直)
GGNがあったからこそ、災害ボランティアが集まった
JCのアイデアに後から乗る形で、延岡市は93年に「アスリートタウン研究会」を発足。アスリートタウン化を推し進めるためにも、97年から、運営費の一部を負担するなどGGNのバックアップを申し出る。市の協力を得たGGNは、その年から、市が管理する西階競技場へ会場を移した。
「我々としては、そのままでもよかった」と話すのは宗茂だ。
「でも、だいたい地域おこしというのはそういうものでしょう。行政が音頭を取って始めたって、うまくいかない。金がない、人がいないという中で、有志たちが、知恵をしぼり、汗をかいてやった方が、うまくいく。そうすれば、いずれ行政がバックアップしてくれるようになる」
レース間隔は、約20分。その合間に随時、表彰式も行うため、進行に無駄がなく、非常にスピーディー(撮影:比田勝大直)
スポーツで「地域おこし」をする場合、必要な条件は3つだと言われている。「(スポーツに取り組んできた)歴史」「トップチーム」「集客力のある競技場」だ。行政を味方につけたことで、最後の1つが手に入った。
現在、GGNの運営費は2000万円弱だ。そのうち約700万円を市が負担している。それ以外はスポンサーやグッズの売り上げでまかなっている。
延岡は鮎つりが盛ん。表彰式では、延岡のPRを担う「のべおか若鮎レディ」がプレゼンターを務めた(撮影:比田勝大直)
GGNは再来年、30回大会を迎える。ただ、大会規模をこれ以上大きくすることは考えていない。ひたすら質の向上をはかり、旭化成の総監督・宗猛は「悲願の日本記録を誕生させることが当面の夢」だと語る。
「アスリートタウン」のアスリートに含まれるのは、陸上選手だけではない。Jリーグに所属するベガルタ仙台や、柔道日本代表を筆頭に、市が補助金を支給し、さまざまな世代、さまざまな種目の合宿を誘致している。大会を開催する際も、市から一定の補助金が出る。ただし、それらの経済効果は、首藤市長に言わせれば「市の財政からすれば微々たるもの」だという。
総監督で、弟の宗猛は「お客さんを喜ばせるために、ああしよう、こうしようと変えてきたことが、結局、好記録を生む雰囲気をつくった」(撮影:比田勝大直)
「Jリーグのチームなどを誘致できれば、あるいは50億とか、100億とか、定量的な経済効果も期待できるのかもしれませんけど、延岡市のロケーションでは難しい。だからうちは、スポーツで飛躍的な活性化を望むのではなく、もっと地道でいいので、持っている資源を磨き上げていく道を選んだ。今ではゴールデンゲームズは、市の顔となり、誇りとなった。長い目でみたら、こちらの効果の方が大事だし、大きいと思うんです」
GGNの入場料は無料だ。それゆえか、観客もスタッフの一人のように映る。声援で選手の背中を押し、「おらが町」で何とか自己記録を更新させてやりたいという情熱が伝わってくるのだ。
ブリキ看板のスポンサー料は、1年目は製作費込みで3万6000円かかるが、2年目以降は更新手続きのみとなり1万5000円に減額される(撮影:比田勝大直)
2006年9月、首藤市長が就任してすぐに、延岡市で死者3人を出す九州では史上最悪の竜巻被害が起きた。竜巻が発生したのは午後2時だが、翌朝8時には約1000人の地元ボランティアが集結。他の自治体を驚かせた。GGNは毎年、市民ボランティア団体「NATS」を中心とした500人近いボランティアによって支えられている。そこで培われた底力だった。
GGNは、確かに直接的な経済効果は乏しい。しかし年1回でも、このように行政と市民が一体となって何かを成そうとする地域は、目に見えない糸で結束しているものだ。だから、いざというときに、強い。それはイベントだけにとどまらない。災害や財政難など、地域がピンチに立たされたときこそ、本領を発揮する。
地元名物の「破れ饅頭」と好記録が続出するレースをかけて横断幕を製作。社長の直筆だという(撮影:比田勝大直)
(文中敬称略)
中村計(なかむら・けい)
1973年、千葉県船橋市生まれ。同志社大学法学部卒。スポーツ新聞記者を経て独立。スポーツをはじめとするノンフィクションをメインに活躍する。『甲子園が割れた日』(新潮社)でミズノスポーツライター賞最優秀賞受賞。近著に『勝ち過ぎた監督 駒大苫小牧 幻の三連覇』(集英社)がある。
[写真]
撮影:比田勝大直
写真監修:リマインダーズ・プロジェクト
後藤勝