終戦間際、東海地方を襲った二つの地震がある。1944年12月の東南海地震と、1945年1月の三河地震だ。いずれも1000人以上の死者・行方不明者を出したにもかかわらず、戦時下ゆえに大きく報じられることなく、「隠された地震」とも言われている。南海トラフを震源とした地震が懸念されている中、かつての「隠された地震」がいま、地域で「忘れられる」危機に直面している。地域の中で災害の記憶を継ぐ意味とは何か。(ノンフィクションライター・山川徹/Yahoo!ニュース 特集編集部)
発生から74年、“忘れられた地震”
愛知県西尾市の願王山妙喜寺は、田畑に囲まれた小さな住宅街に立つ曹洞宗寺院である。
近所に暮らす三輪賢伍さん(87)は、2003年に再建されたまだ新しい本堂で振り返った。
「地震の話って、あんまりしねえんだ。あの地震で、オヤジとオフクロ、妹2人と生まれたばっかの弟が家の下敷きになって亡くなったから……。いま思い出しても涙が出てくる。でも、覚えている人もずいぶん少なくなったな」

三輪賢伍さん(87)。国民学校初等科6年生のときに東南海・三河地震で被災した(撮影:幸田大地)
“あの地震”とは、1945年1月13日にこの地域を襲ったマグニチュード6.8 の三河地震である。内閣府の資料によると、2306人が犠牲になった災害だった。にもかかわらず、いま地元でも記憶する人はわずかだ。
発生からすでに74年の歳月が流れている。
三河地震は、三輪さんが語るように“忘れられた地震”になってしまっているのだ。
妙喜寺が立つ西尾市江原町は、三河地震で大きな被害を受けた地域の一つである。住職である佐久間桂祥さん(76)はこう語る。
「この辺りにあった約100世帯の住宅のうち約半数が倒壊し、60人以上が亡くなりました。5歳だった私の姉もつぶれた庫裏(くり)の下敷きになって犠牲になりました」

妙喜寺の住職・佐久間桂祥さん(76)。1歳のときに被災した三河地震で5歳だった姉を亡くしている(撮影:幸田大地)
当時、妙喜寺の本堂では、名古屋市の大井国民学校(現・平和小学校)の子どもたち約30人が生活を送っていた。空襲の恐れがある都市部から学童疎開を受け入れていたからだ。しかし、三河地震で本堂が全壊。就寝中だった児童12人と教員1人が犠牲になった。佐久間さんの姉も含めて、妙喜寺だけで14人が亡くなっている。
佐久間さんは被災時1歳。直接の記憶はない。
「地震を経験した人はいるにはいるのですが、歳月とともに記憶が薄れてしまっている。私は毎年1月13日に執り行ってきた三河地震の法要で、被災した人や遺族から地震の話を聞いてきたんです」
妙喜寺の近辺を歩いてみても、地震の痕跡を見つけるのは難しい。境内の片隅に保存される幅6〜7センチ、長さは10メートルほどの地割れ跡が数少ない名残だった。

妙喜寺に残る三河地震の地割れ跡(撮影:幸田大地)
戦時中の三つの大地震
三河地震の37日前の1944年12月7日にも、三河地方は震度7相当の揺れに見舞われた。三河地震を誘発したともされる東南海地震である。
東南海地震は、南海トラフを震源とするマグニチュード7.9の地震だ。静岡県、愛知県、三重県、和歌山県などの沿岸部が大きな津波に襲われて、死者・行方不明者は1223人に上った。
太平洋戦争中に1000人以上の人的被害をもたらした地震は三つ。東南海地震、三河地震に加え、1943年9月10日に発生し、1083人が犠牲になった鳥取地震だ。いずれも戦時下で、ほとんど報じられなかった震災である。
東南海地震5カ月前の1944年7月7日、サイパン島を守る日本軍が玉砕。米軍に占領されたサイパン島を含めたマリアナ諸島が、日本本土空爆の基地となった。そして11月24日、東京はマリアナ諸島を飛び立ったB29による初めての空襲をうける。それが、東南海地震2週間前のことだった。

焼け跡でバラック生活。米軍のB29の本土空襲も始まり、被災した家はトタン板や木片を拾い集めてバラックを造った(写真:読売新聞/アフロ、1944年11月24日撮影)
大地震が“隠された”理由
名古屋大学減災連携研究センター長の福和伸夫教授は次のように解説する。
「災害時におけるメディアには、被災地の状況を正しく伝えて、支援につなげる、または被害を記録して、後世に残していくという役割があります。しかし、当時の日本には厳しい報道統制が敷かれていた。新聞社も例外なく報道統制下にあったのです」
東南海地震発生翌日の12月8日の新聞各紙の1面を見ていくと、太平洋戦争開戦4年目の記念日を取り上げた記事が目立つ。

1944年12月8日の毎日新聞朝刊(東京本社版)の1面(右)と3面。東南海地震の発生翌日にもかかわらず、1面では地震について報じることはできず、3面の最下段での掲載(赤枠部分)となった
『毎日新聞』(東京本社版)を開いてみても、マグニチュード7.9の大地震が起きた切迫感や危機感はない。1面には開戦記念日を祝う記事をはじめ、〈七機で七艦船屠る〉〈敵飛行場を炎上〉など、戦意を発揚する見出しが並ぶ。地震の記事がようやく掲載されたのが、3面の最下段。〈きのふの地震〉と題された記事は、わずか26行しかなかった。福和教授は続ける。
「結果的に一般市民に地震の存在や被害がほとんど伝えられなかった。ただし、メディアが被害を報じ、支援を訴えても、被災地に支援に行くべき人たちは戦地に送られている。さらに空襲が始まっていた。かつてない戦禍を前にして、メディアが災害を伝えようにも限界があったのです」
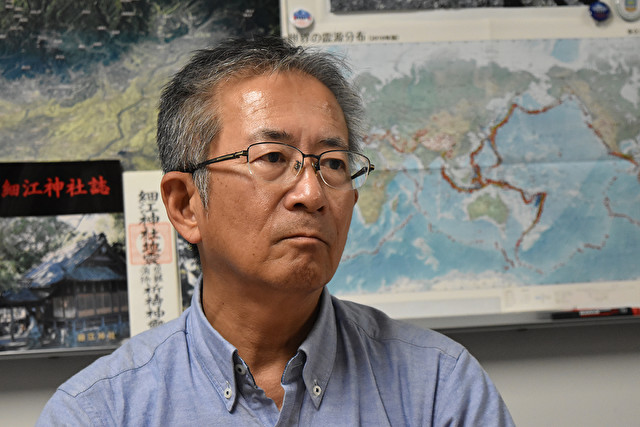
名古屋大学減災連携研究センター長の福和伸夫教授(撮影:編集部)
こうして隠された震災が掘り起こされたのが、約30年後のことである。愛知工業大学の教授(名古屋大学名誉教授)だった飯田汲事氏が、散逸した資料を収集し、現地調査を行って、被害の全貌を明らかにしようとした。
さらに1982年春、名古屋市内の古書店で、古い冊子が発見される。
それは、愛知県が二つの震災の被害状況をまとめた極秘資料だった。すぐに中日新聞社会部が88回にわたる長期連載をスタートした。被災者や遺族の証言は『恐怖のM8 東南海、三河大地震の真相』という書籍にまとめられる。また、津波史家の山下文男氏が『戦時報道管制下 隠された大地震・津波』『家も学校も焼けてしまった ある学童疎開ものがたり』などを刊行した。
二つの地震に対し、社会の関心が改めて集まったのは2001年だったと福和教授は指摘する。
「2001年に東海地震の想定震源域の見直しが検討されました。次の地震がどこで発生するのか。それと同時に、過去に同じエリアで発生した地震がどのような被害をもたらしたのか。ここでようやく、これらの地震が注目され始めたのです」
家が倒壊、砂煙で辺りが暗く
東南海地震と三河地震。冒頭で紹介した三輪さんは12歳で、二つの隠された地震を経験した。
ハーフパンツを少しめくると、右太もものえぐれた傷痕があらわになる。三河地震で生き埋めになったときの傷だ。いまも、右膝が90度ほどしか曲がらないなどの後遺症が残る。

三輪さんの右太ももには地震で負った傷痕が残る。「当時、お医者がなかったんですよ。だからこれ、産婦人科行っちゃった。産婦人科(の医者が)、一番いかんとこ切っちゃった。運が悪かった」(撮影:幸田大地)
1944年12月7日午後1時36分、三輪さんは、国民学校初等科6年生の同級生たちと勤労奉仕に従事していた。稲刈りが終わった田んぼで、「稲架(はさ)」を撤去していく。「稲架」とは、刈った稲を掛けて乾かす「稲架掛け」を行うために田んぼにしつらえる木組みである。
あれ、めまいかな……。三輪さんは、地面が揺れているような違和感を覚えた。次の瞬間、「ドン」という音とともに地面が突き上げられた。同時に、近くの家屋が音を立てて、一気に崩れ落ちた。三輪さんが語る。
「転んだ(倒壊した)のは古いうちだったね。どえらい砂煙が出て辺りが暗くなったのを覚えとる」
妙喜寺がある、現在の西尾市から西へ15キロほどに位置する半田市では、軍用機を生産する中島飛行機山方工場が倒壊し、学徒動員で働く中学生や女学生96人を含めた153人が亡くなった。行政は、生き残った人に対して、被災した事実を一切口外しないように、と箝口令(かんこうれい)を敷いた。
三輪さんも証言する。
「ほかの町の被害も、津波がきていたなんてことも、ぜんぜん知らんかった。新聞で読んだ覚えも、誰かに聞いた覚えもないね」
「夢じゃねえか、夢じゃねえか」
その東南海地震が誘発したともされるのが、翌1945年1月13日の三河地震だ。
数日前、三輪さんの母が男の子を出産。家族が1人増え、父母と祖父母、そしてきょうだい8人の合わせて12人が一つ屋根の下に暮らしていた。
みんなが寝静まっていた午前3時38分。6畳の仏間に1人で眠っていた三輪さんはパッと目が覚める。地響きのあと、天井が崩れ落ちてきた。
三河地震で全壊した住宅(撮影:萩原律氏、提供:西尾市)
すぐに布団に潜り込んだが、天井や柱が邪魔で立ち上がれない。這って進んでみると、祖母と二つ年下の妹が寝ている隣室へは、落ちた鴨居(かもい)が遮っている。祖母と妹の部屋の辺りから「夢じゃねえか、夢じゃねえか」と祖母のうわ言が聞こえた。
「夢じゃねえで」と声をかけた三輪さんの耳に「うー……」と妹の苦しそうなうめき声が途切れ途切れに届く。しばらくすると祖母が悲痛な声を上げた。
「よし子(三輪さんの妹)が冷たくなってきとる……」
三輪さんは「これはいかん」と力任せに天井を破った。光が漏れていたガラスの小窓を素手で割って助けを求めた。近隣の人たちにより、三輪さんが救出されたのは、午前7時ごろ。
2時間ほどしてようやく父母が掘り出された。しかしすでに息はなかった。近所の人たちに人工呼吸を受ける父を呆然(ぼうぜん)と見守ったが、両親が目を覚ますことはなかった。

笑いを交えて話す三輪さんだが、「今だからこういうこと言っとるけどね。あの時分にそんな笑い事の騒ぎじゃないよ。涙、涙だよ」(撮影:幸田大地)
「ずいぶん耄碌(もうろく)していた」祖父母には頼れない。父の死によって、12歳の三輪さんが家で最年長の男性としての責任を果たさなければならなくなる。
三輪さんは、前夜まで元気だった父と母、そして2人の妹と生まれたばかりの赤ん坊をリヤカーの荷台に乗せて、妙喜寺に運んだ。境内に敷いた戸板に5人を寝かせて、枕経をあげてもらった。
三輪さんたち被災者は昼に河原や空き地で、米軍のP51戦闘機の機銃掃射に怯えながら、倒壊家屋の廃材や稲わらを燃やして大切な人の亡骸(なきがら)を荼毘(だび)に付した。
戦後は、姉たちの援助で西尾実業学校(現・鶴城丘高校)を卒業し、土木現場などで働いてきた。三輪さんは、三河地震から生活が大きく変わったと述懐する。
「オヤジが死んでから生活はエラくなった(大変になった)。家もわら小屋で、食えるものといったら、おかゆか、ダイコンや白菜の味噌煮。オヤジが元気だったころは、食卓に魚や肉が上ったから余計みじめに感じた。哀れなもんじゃったよ」
三河地震犠牲者の火葬(撮影:萩原律氏、提供:西尾市)
「爆弾が落ちた」と思った
家を失った被災者は「わら小屋」と呼ばれた仮設の住宅に暮らした。文字通り屋根や壁となる板材の代わりにわらを編んでつくった小屋である。
1936年に西尾市北部の徳次町に生まれた高須和(かのお)さん(83)も「わら小屋」の記憶を語る。
「うちは東南海地震で母屋が倒壊したんです」
高須さんが稲の脱穀作業を行う親の手伝いをしていたときだった。ごう音とともに地面が揺れた。
「伏せろ!」
誰かの叫び声で、とっさに地面に這いつくばった。高須さんは「ついに爆弾が落ちた」と思った。
母屋には住めなくなってしまったが、近所の人たちや親戚が片付けを手伝ってくれた。
「まだ小さかったし、そんなに気落ちはしなかった。二間ある離れは無事だったので、住む家もある。食べる物もある。みんなも気にかけてくれる。お互いに助け合う時代だったのがよかったのかもしれません」

高須和(かのお)さん(83)は、70年以上がたっても「ほんとに地震のことは忘れんね」と当時を振り返る(撮影:幸田大地)
37日後の三河地震では、残った離れも倒壊。高須さんはその下敷きになり、意識を失った。ふと目を覚ますと布団の上で、頭の皮がめくれていた。
リヤカーで病院に担ぎ込まれると、待合室や廊下にはたくさんのケガ人が寝かされていた。医師は「痛いけど、ちょっとがまんせえ」と麻酔もせずに縫合手術をはじめた。
「グッと頭の皮を引っ張って縫っていくんです。あれは、本当に痛かった」と高須さんは苦笑いする。
二つの地震で住まいを失った高須さんの家族は、自らの手でわら小屋をつくった。
「稲架掛けで使う木の棒を組んで、わらで囲って縄で絡める。広さは8畳くらいかな。地面にもわらを敷く。ものすごい暖かかったよ」
三河地震で倒壊した住宅(撮影:萩原律氏、提供:西尾市)
被害が報じられず、行政からの支援も、ましてやボランティアも期待できない時代である。被災した家族は親戚や隣近所の力を借り、自助努力で生活再建していくしかなかった。
「2カ月後か3カ月後か、救援の工作隊がやってきて小さな家を建ててくれたんだけど、ぼくはしばらく、わら小屋で寝起きしていた。余震が怖くって、瓦屋根の家では寝てられなかったんですよ」
東日本大震災や熊本地震などでも、いつ終わるとも分からない余震に、不安や恐怖を覚えた子どもがたくさんいた。戦時下でも、地震が被災者に及ぼす影響は変わらなかったのである。
同じエリアで繰り返し起きる地震
妙喜寺から1キロほどの場所にある安楽寺でも、三河地震で8人の疎開児童が亡くなった。本堂には、妙喜寺や安楽寺などで犠牲になった31人の疎開児童の名が並ぶ法名軸がかけられている。
住職の伊奈祐諦(ゆうたい)さん(72)は1946年生まれ。東南海地震も三河地震も体験していない。未経験の災害をどのように地域で語り継いでいくか。伊奈さんの言葉の端々に、その難しさがにじんでいた。
「阪神・淡路大震災や東日本大震災など、私にとっても最近の大地震が、三河地震に思いを馳せるきっかけになりました。体験者はどんどん少なくなっている。次の世代に証言以外にも、映像や写真の資料を通して、かつてここで大変な地震が起きたことだけでも伝えなければならないと取り組んでいるのですが……」

安楽寺の住職・伊奈祐諦(ゆうたい)さん(72)。地震で犠牲になった31人の疎開児童の名が並ぶ法名軸(写真左)を見せてくれた(撮影:幸田大地)
いま、南海トラフを震源とする地震の発生が危惧されている。歴史を振り返ると、地震に限らず、台風や津波、土砂崩れ……。自然災害は、同じ地域で同じような被害を繰り返すケースが多い。だからこそ、過去の災害を知る必要があるのだ。
兵庫県立大学の木村玲欧教授(防災心理学、防災教育学)は、2003年以降、東南海・三河地震の被災者数百人以上に聞き取り調査を行ってきた。
「被災した人たちの多くは、地震よりも戦争に強烈な印象を覚えました。地震を戦争の記憶の一つとして受け止めている方もいるから、地震について改めて語ろうとする人はあまりいない。なかには、村長などの有力者に『被害を口外するな』と言われたまま発言する機会を逸してしまった人もいる。その後、彼らは戦後復興、高度経済成長で忙しく働いてきた。災害の記憶を振り返る場がほとんどなかったのです」

伊奈さんが集めた地震に関する資料。寺では写真展なども行なってきた(撮影:幸田大地)
大きな自然災害は頻繁に発生するものではないが、ひとたび起きれば、命を失うリスクもある。木村教授は、地域に暮らす若い世代に災害の記憶が伝わっていない現状を危惧する。
「防災には、災害を自分に身近な問題として考える『わがこと意識』が重要になってくる。自然災害のシミュレーションやハザードマップを提示することも重要ですが、それと同時に、人間が大きな災害に遭ったときに、それをどう感じて、どう乗り越えていったのか。東南海地震と三河地震に限らず、自分が生活する地域の地震や自然災害を掘り起こし、かつて何が起きたかを人間のストーリーを通して知ることが『わがこと意識』を高め、自分の身を守る第一歩になるのです」
山川徹(やまかわ・とおる)
ノンフィクションライター。1977年生まれ。山形中央高校2、3年時に全国高等学校ラグビーフットボール大会に出場。東北学院大学法学部卒業後、國學院大學二部文学部史学科に編入。在学中からフリーライターとして活動する。著書に調査捕鯨に同行した『捕るか護るか? クジラの問題』(技術評論社、2010)、『東北魂――ぼくの震災救援取材日記』(東海教育研究所、2012)、『それでも彼女は生きていく――3・11をきっかけにAV女優となった7人の女の子』(双葉社、2013)、『カルピスをつくった男 三島海雲』(小学館、2018)、『国境を越えたスクラム ラグビー日本代表になった外国人選手たち』(中央公論新社、2019)など。
撮影:幸田大地
写真監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝












