地震、台風、豪雨……。大規模災害が続くなか、多くの人が犠牲になった。そして、被災した人々はそろって「まさか自分が」と口にする。この「まさか」の心理とは、いったい何だろうか。被害が拡大する背景には「正常性バイアス」という心理が影響している――。そんな実態も専門家の研究によって次第に分かってきた。西日本豪雨の被災地を歩き、「まさか自分が」の現場と心理、その対策を考えた。(廣瀬正樹/Yahoo!ニュース 特集編集部)
防災無線の「避難指示」は聞こえていた
200人以上が死亡した西日本豪雨から2カ月近くが過ぎた8月下旬、岡山県倉敷市の真備町に足を運んだ。瓦礫などはもう片付いていた。それでも、住宅の壁や道路に泥がこびりつき、町全体が茶色っぽい。どの建物も1階の内壁は落ち、柱や梁が剥き出しになっている。真備町の浸水は5000棟以上。災害の痕はそう簡単に消えるものではない。
この町に住む丸畑孝治さん(59)は「もう本当にダメかもと思いました」と振り返る。

丸畑孝治さん(右)と息子の裕介さん(左)。浸水した自宅前で(撮影:廣瀬正樹)
記録的な大雨が降り続いていた7月6日、丸畑さんは宿直の仕事を終え、昼ごろ自宅に戻った。テレビのニュースは豪雨への警戒を促していたが、特に危機感を覚えることもなく、対策らしきことは「何一つしていなかった」と言う。
夕方、同居する息子の裕介さん(36)が「せめて家財道具を2階に上げておこう」と言った。これを丸畑さんは「考え過ぎだ」と一蹴する。夜10時、町に避難勧告が出た。防災無線のスピーカーは自宅のすぐ裏手。避難を呼び掛けるアナウンスは丸畑さんの耳にも届いていた。

丸畑さんの自宅裏には防災無線のスピーカーがある(撮影:廣瀬正樹)
「でも、そこまでする必要はないだろうと思って、自宅に残りました。夜中の1時半になって、避難勧告が避難指示に変わって、さすがに少しドキッとしましたけど……。それでも『ここは大丈夫だろう』と思い込んで、そのまま寝ました」
翌朝、丸畑さんが起きると、雨は上がっていた。ところが、すぐに自宅裏の公園が浸水し始めた。自宅から1.6キロほど離れた末政川の堤防が決壊し、水が押し寄せていた。
「嫁は『怖い、怖い』と言って避難しましたけど、私は『ばかたれー、そんな必要ない』と。念のためと思って、車を近くの堤防に上げたりはしていましたが」
午前10時ごろ、自宅の床下が浸水した。

民家の軒先のブドウには浸水による泥がこびりついていた=7月、真備町(撮影:廣瀬正樹)
「死ぬわけねぇが。おまえ、基本が分かってない」
丸畑さんの息子・裕介さんは、町の様子を見るため、一晩中、車で動いていた。母から携帯に電話があったのは翌日の午前だ。ひと足先に自宅を出て避難していた母は「お父さんが避難してくれない。連れ出して」という。
裕介さんが膝まで水に浸かりながら自宅に戻ると、父の丸畑さんは家電製品を2階に上げようとしていた。裕介さんはこの時の様子を映像で撮影しており、頑なに避難を拒む父の様子が記録されている。

避難を拒む丸畑さんの様子。息子・裕介さんが撮影した映像から(提供:丸畑裕介さん)
息子「もう逃げんといけんて」
父「(ずぶ濡れの息子に)靴下、着替え」
息子「着替える余裕もねぇよ、外は。はよ、逃げよう。死んだら終わるで」
父「死ぬわけねぇが」
息子「そう言って何人死んどるん?」
父「死にやせん」
息子「だって、まだ水来るんで」
父「来る言うて、土手を越えるわけなかろうが」
息子「じゃけど、潮が上がってきたら川が……」
父「おまえ、アホじゃないか。潮が上がっても1メートルじゃ。ここは関係ない。おまえは基本が分かってない」
息子「基本は逃げることや。こういう時は」
結局、「テレビだけでも2階へ」となり、親子2人でいくつかの家電製品を担ぎ上げた。その最中、水はついに床上まで上がってきた。丸畑さんは言う。
「絶対に起きないと思っていた床上浸水が起きて、ようやく、『あ、これは』と。そこからは、裕介に対しても強い口調でモノを言えなくなって」

胸まで水に浸かり避難する父を息子が撮影した(提供:丸畑裕介さん)

1階部分が浸水した丸畑さんの自宅(提供:丸畑裕介さん)
それでも丸畑さん親子はすぐにその場を離れない。今度は、近所の家で家財道具の担ぎ上げを手伝い、避難を後回しにした。15分ほどの手伝いを終えてその家を出ると、腰の高さだった水位は胸の辺りまで上がっていた。親子は一緒に胸まで水に浸かりながら、泳ぐようにして近くの堤防へ逃れた。
丸畑さんは振り返る。
「そのとき初めて、死ぬかも、と。服も着ているし、何かにつまずいて転んだら溺れるかもしれない、と」

川の決壊現場の近く。災害から2カ月余りが過ぎても、損壊した住宅があちこちに残る=9月、真備町(撮影:廣瀬正樹)
実は、西日本豪雨では、丸畑さんのような事例は珍しくなかった。丸畑さんと同じ地区に住む70代の夫婦も、避難指示を知りながら避難しなかった。翌日朝から浸水が始まり、午後には2階に取り残された。結局、2階の窓からボートで助け出されたという。
真備町では亡くなった51人のうち、8割以上が屋内で見つかっており、「逃げ遅れ」がその原因とみられている。
「正常性バイアス」と「経験の逆機能」
人はなぜ逃げ遅れるのか。そこには「正常性バイアス」が影響していると指摘するのは、防災システム研究所の山村武彦所長(75)だ。
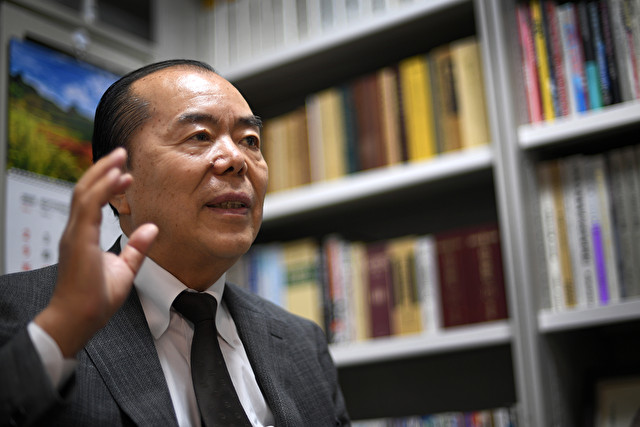
防災と人の心理に詳しい山村武彦所長(撮影:穐吉洋子)
「『正常性バイアス』とは、何らかの異常事態が起きた時、『これは正常の範囲内だ』と思い込んで平静を保とうとする心の働きのことです。誰でも持っています」
日々直面するさまざまな出来事。その全てに心を反応させていると、不安や恐怖を感じ過ぎ、神経が持たなくなる。そのため、ある程度の事象に対しては自らの経験などをもとに「これは正常の範囲内であり、特に反応する必要はない」との判断を下し、平静を保つ。このメカニズムが「正常性バイアス」である。
「正常性バイアスは人間にとって必要なものですが、問題は、これが通常の範囲を逸脱して働いてしまうケースです。災害などの非常時にも現れます。本当に危機が迫っているにもかかわらず、『正常の範囲』と判断してしまう。結果、避難が遅れます」

「人の行動判断には知識や経験、性格などが影響する。正常性バイアスもその一つ」と山村所長(撮影:穐吉洋子)
山村所長はこう続ける。
「人間は都合のいい生き物です。物事を都合のいいほうへ、楽なほうへ考える。何か行動を起こすには、労力が必要だし、面倒臭い。頭では『避難したほうがいい』と思っていても、避難しないほうが楽です。つまり、安全だと思っているから逃げないのではなく、逃げるのが面倒だから逃げない。だから、逃げなくても済むように、『自分だけは大丈夫だろう』といった思い込みを勝手に積み上げて、自分で『安全だ』ということにしているんです」
避難行動を妨げる要因は、正常性バイアスだけではない。「経験の逆機能」もその一つだ。
「過去に遭った災害を過大評価するのが『経験の逆機能』です。過去の経験に固執して、それ以上の災害が起きる可能性を考えることができないのです」
実際、真備町では、1976年にも台風による水害が発生している。町内を東西に流れる小田川の堤防が決壊し、町の全域で50センチほどの浸水被害が出た。丸畑さんを含め、今回の取材で話を聞いた町民の多くもこの水害を覚えていた。そして、ほとんどの住民は「あれより大きい水害はないと思っていた」「あの時でも床下浸水だったから、その程度だろうと思っていた」と語った。

浸水した住宅の廃材が積み上げられていた=7月、真備町(撮影:廣瀬正樹)
「正常性バイアス」や「経験の逆機能」にとらわれやすいのは、一般的に若年層よりも高齢者が多い。「人は年齢を重ねるほど、『自分は経験があるから大丈夫、たいていのことに対応できる』と思ってしまう。その自信が、結果として他のものを受け入れようとしない頑なさを生む。自分を過信しているんです」
避難を拒んだ丸畑さんも、自身をこう振り返る。「私は年齢のせいか頑固で、普段から息子の言うことを素直に受け止められずにいたんです。今回も正直言うと、悔しいんです。息子のほうが上手(うわて)だったというのが」
生死を分けた避難
西日本豪雨のとき、広島市安佐北区に住む木戸敏明さん(83)、順枝さん(77)夫妻も当初は避難を拒んでいた。順枝さんはこう振り返る。

広島市安佐北区で、山際に密集して立つ住宅。広島市周辺にはこうした地区が多い(撮影:廣瀬正樹)
「夕方ごろから近くを消防の車が無線で何か叫びながら走ったんよ。避難せえってことかなと思ったけど、雨の音も強くて、何言ってるのかよく分からなくて……。お父さんに『逃げる?』って聞いたら『大丈夫じゃ』と」
離れて暮らす娘からは何度も「避難して」と電話があった。順枝さんはことごとく、「そこまで必要ないわ」と返していた。
夜になって雨はさらに強まる。家の前が浸水を始め、敏明さんがようやく避難を決めた。ところが、順枝さんは「家が心配じゃけ、私は家におる」と言い、逃げない。夜10時ごろ、娘が車で駆けつけ、ようやく自宅を後にした。

木戸さんの自宅跡。流れ込んだ土砂が積み上げられていた=9月、広島市安佐北区(撮影:廣瀬正樹)
翌朝、自宅近くまで来て、夫妻は仰天した。大量の土砂が流れ込み、自宅は丸ごと押し流されていた。すさまじい破壊だった。順枝さんの恐怖は今も消えていない。
「何にも残ってませんでした。『避難せん』と言っていた近所の友だちは、家に残って、流されて亡くなりました」
「知っている」だけでは動かない
では、メディアの情報や防災無線で「避難勧告」などの発令を知ったとき、実際はどの程度の人々が避難行動を起こすのだろうか。
広島県では西日本豪雨によって、109人が犠牲になった。雨が激しさを増した7月6日以降、県内各地の市や町で「避難勧告」「避難指示」が発令された。県によると、避難対象者は7日早朝の時点で約187万人。そのうち実際に避難したのは、最大で約1万7千人、対象者の0.9%に過ぎない。広島県減災対策推進担当の藤谷吉秀課長も「突き付けられている現実を非常に重く受け止めている」と話す。

広島県が配布していた防災パンフレット(撮影:廣瀬正樹)
77人が亡くなった4年前の土砂災害以降、広島県は災害死ゼロを目標にした「『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」に取り組んできた。新たにパンフレットを作成したり勉強会を開いたりして、災害危険箇所や避難場所を細かく知らせた。その結果、避難場所などの認知率は4年前の13.2%に対し、最近は約60%にまで増えていた。
それでも今夏の西日本豪雨では、避難の「勧告」や「指示」に直面しても1%未満の人しか避難しなかった。藤谷課長は「避難場所などを『知る』ことについては浸透してきましたが」と言って、こう続けた。
「実際に避難行動を起こしてもらうには不十分だった、と反省しています。避難場所などを『知っている』だけでは、人は動かない。では、どうすれば避難してもらえるかというと、正常性バイアスなど人の意思決定プロセスにまで踏み込んだ対策が必要だと感じています」

藤谷吉秀課長。「命を守るには、砂防ダム建設などハード面だけでは限界」(撮影:廣瀬正樹)
西日本豪雨の後、広島県は災害に対する県民の心理調査を行うことを決めた。自治体による同様の調査は過去に例がなく、全国初の大掛かりな調査になるという。避難した人の行動のトリガーは何だったのか。避難しなかった人はなぜそこにとどまったのか。「それぞれに理由や心情をお尋ねして結果を分析し、今後の防災に生かしていきたい」。近く、行動心理学の専門家なども含めた調査チームを立ち上げ、この秋から実際の調査に乗り出す。
「ネット社会」「報道慣れ」も危機に
「正常性バイアス」や「経験の逆機能」は、若年層より高齢者に現れやすいとされる。ただし、と山村所長は言う。

多くの災害現場を歩いてきた山村所長(撮影:穐吉洋子)
「若年層にも別の危険がある。ネット社会の今、検索すればたいていのことが分かります。災害や防災についても、検索結果で知ったつもりになって、『自分は行動できる』と思い込んでいる人が実に多い。本当は何も理解していないし、体感もしていないのに……。その妙な自信は『経験の逆機能』と似た影響を与えています」
災害が相次いだことで、「慣れ」への懸念もある。
「小規模な地震などが続くと、『あぁまたか、すぐ収まるだろう』と危機感を抱けなくなってしまう。もう一つ怖いのは『報道慣れ』です。マスコミで災害報道が続いていると、人はどこかで『あれは向こう側の世界。私とは関係がない』と思ってしまう。映画を見ているような感覚です。さらに『(報道を通して)自分は知っているから何か起きても対応できる』と思い込んでしまうわけです」

ニュースを見て避難した人は決して多くなかった=7月、真備町(撮影:廣瀬正樹)
どうしたら正常性バイアスなどにとらわれず、的確に行動できるのだろうか。
「素直になれるかどうか、です。警報や周囲の注意喚起を、素直に受け入れることです。そのためにもまず、人間には正常性バイアスなどの心理的傾向があるということを知り、自分の中にもそれがあるのだと意識することが必要です。もう一つ重要なのは、自問自省することです。災害時だけでなく、日頃から『今自分はバイアスにとらわれていないだろうか』と意識することで、行動が変わってきます」
避難勧告や避難指示は、空振りに終わることも少なくない。それに慣れてしまい、避難を怠るケースも見受けられる。
「訓練だと思うことです。本当に避難が必要な時のために、訓練ができたと思えば腹も立たないはず。そういう考え方が大切です」
「家族がいれば立ち直れる」
福島県南相馬市に住む上野敬幸(46)さんは、「災害による犠牲者」のニュースに接する都度、歯がゆい思いになるという。東日本大震災による津波で、両親と息子、娘の家族4人を亡くしてから7年。「あの震災が教訓として生かされていない」と感じるからだ。

上野敬幸さん。震災以降、講演会で自分の経験を語ってきた(撮影:廣瀬正樹)
大震災の日、強い揺れの直後、上野さんは職場から自宅へ向かい、家族の無事を確認した。「津波が来るから避難する」と言う母親の言葉に安心し、避難所へ送ることもせず、職場に戻った。母親たちはいったん避難したものの、避難所から自宅に戻った際、津波にのまれた。
自宅まで津波が来ることはないだろう、家族は避難しているだろう、自分の家族に限って被害を受けることはないだろう……。振り返れば、いくつもの思い込みがあった。

上野さん宅の祭壇。両親と長女(8歳)、長男(3歳)の遺影と骨壺が並ぶ(撮影:廣瀬正樹)
「あの震災で誰が亡くなったとか、どんな被害があったとかは、忘れてくれてもいいんです。悲しむのは僕たち遺族の役目なので。でも、絶対に教訓にだけはしてほしい。次に何か災害があった時に、死者がゼロっていうのが僕らにとっては一番うれしいことなので。自分の子どもの遺体を抱いて遺体安置所に運ぶような思いは、もう誰にもしてほしくないんです」
上野さんは「『まさか』なんて言葉、二度と聞きたくない」と語る。一方、西日本豪雨を生き延びた丸畑さんは、いま、「家族がいれば何とでもなる」と思っている。
「家族が無事だったこと、それが何より。浸水していく家を見ていた時も、『自分にはまだ妻も子どももおる。なら、頑張れる』と思いました。もし誰かが行方不明とかになっていたら、立ち直れない。命を守ることがいかに大事か、よく分かりました」

広島土砂災害現場に残った水溜まり。災害はいつ起こるか分からない=9月(撮影:廣瀬正樹)
廣瀬正樹(ひろせ・まさき)
ノンフィクションライター、カメラマン。1984年生まれ。日本テレビ報道局で記者、カメラマン、ディレクターとして勤務。2018年5月、独立。同年8月、著書『捜す人 津波と原発事故に襲われた浜辺で』(文藝春秋)を出版。
[写真]
撮影:廣瀬正樹、穐吉洋子
提供:丸畑裕介さん









