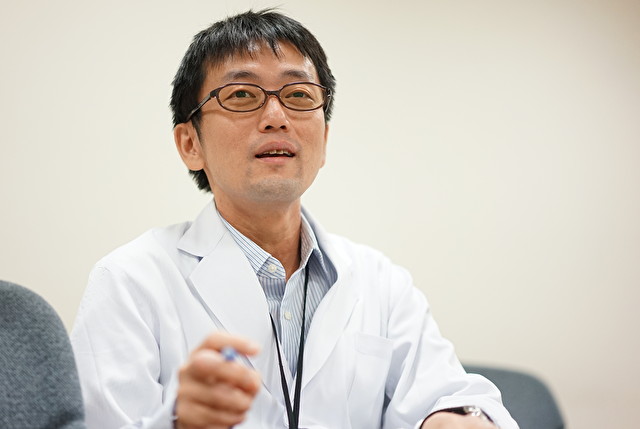子育てに専念する「母親」の中には、深い孤独に陥る人が少なくない。家族も含め、大人との会話がほとんどない人もいる。そんな母親たちの声には、誰が耳を傾けるのだろうか。声が誰にも届かないとしたら?──。育児のストレスでメンタルを病む母親たち。その要因が「家事・育児への夫の不参加」ではなく、「妻の孤独」という調査もある。現場を歩いた。(取材:伊澤理江/Yahoo!ニュース 特集編集部)
あの日、緊張が切れた
橋本由紀子さん(仮名、30代)の自宅マンションは、東京の23区内にある。壁や家具などの調度品は、白で統一。いつ訪れても掃除は行き届いていた。子どものおもちゃも、いつも決まった場所にしまってあり、絵本も乱れなく本棚に並んでいる。
その部屋で由紀子さんは夫に泣きながら、「起き上がれない、力が入らない」と訴えたという。2015年の春。前日から一睡もできないまま、朝を迎えた日のことだ。

(イメージ撮影:穐吉洋子)
生後10カ月の息子を抱けない。授乳もできない。食事を作る気力もない。精神科の病院に行ったが、家族の誰と一緒だったのかの記憶もあいまいだ。その前後のことは「よく覚えていない」と言う。振り返ると、心身が正常ではなかった。
医師には「産後うつ」と診断された。
結婚後、会社員の夫は中国に赴任することになった。由紀子さんも仕事を辞め、中国へ。そこで妊娠し、出産前に一人で一時帰国した。産後は、慣れない育児に追われていく。同時に中国へ戻る準備も進め、荷物も全て現地に送った。
その直後、事態は変わる。
「辞令が出て、夫の帰国が急に決まったんです。気を張って(中国に戻る)準備をしていたのに、はしごを外された。赤ちゃんを海外に連れて行く緊張感がブツッと切れました。ずっとネットで、予防接種をどうするの、ミルク用の水はどうしたらいいの、って調べていて、ピリピリしていたんです。その頃から気持ちのバランスが崩れたんだと思います」

(イメージ撮影:穐吉洋子)
日本で家族3人の生活が始まった。そして、思いもしなかった「現実」に由紀子さんは直面する。営業職の夫がなかなか帰宅しないのだ。接待や社内の飲み会で、深夜の2時、3時まで帰ってこない。
「(育児は)任せた、という感じで。子どもの夜泣きがすごくて、私は寝られない。お皿のカチャッという小さな音でも起きちゃうんです。やっと寝かしつけても、夫が帰宅した時のドアの音、ドタドタという足音で起きてしまう。酔っ払って、『ただいまー』と大きな声……。殺意すら感じて。『お金さえ入れてくれれば帰ってこなくていい』と言ったこともある」
仕事という別世界を生きる夫。由紀子さんの声は、最も身近な人にもなかなか届かなかった。
SOSをうまく発信できない
夫は朝7時過ぎに出掛けた。帰宅時は、たいがい酔っ払い。その日にあったことや子どものことを聞いてほしいのに、聞いてくれない。誰か大人と話したいとの思いが募ると、疲れていても無理して子どもを連れて外出し、友人と会った。そうした予定がない日は朝から真夜中・未明まで子どもと2人きりだ。

(イメージ撮影:穐吉洋子)
由紀子さんによると、息子は怖がりで、とにかく母親を求めたという。
体から離すとすぐに泣く。4時間おんぶしてやっと寝たと思い、布団に置くと、また泣きだす。夫や由紀子さんの母では泣きやまず、2人とも手を貸さなくなった。
掃除、洗濯、炊事は、子どもが泣くたびに中断される。やがて、由紀子さんには赤ちゃんの泣き声を耳にすることが恐怖に変わった。
「私はSOSをうまく発信できないタイプなんです。夫に大変だとは伝えていたけど、家にいないから(夫には)実感がない。私の母には『子育ては一生続くから大変。自分の時間もなくなる』と何度も言われてた。母は親に頼らず子育てをしたから、私も母に頼っちゃいけない、と。実家は近いのに一人で問題を抱え込んでいました」
そして、あの「起き上がれない朝」を迎え、「産後うつ」と診断されたのだ。

(イメージ撮影:穐吉洋子)
「問題は妻の孤独。家事・育児への夫の不参加ではない」
「産後うつ」という言葉と存在は最近、広く知られるようになってきた。産後のホルモンバランスの急な変化や子育てへの不安、ストレスなどにより発症するうつ病で、出産直後から数カ月以内に起こることが多い。
出産した100人の女性のうち十数人が「産後うつ」になるとも言われる。また、2018年9月には、2015〜16年の2年間に全国で102人の妊産婦(妊娠中と産後1年未満)が自殺していたことが、国立成育医療研究センターの調査で明らかになり、大きな衝撃を与えた。妊産婦の死因の3割が「うつ」などを原因とする自殺だったからだ。
これとは別に、同センターは興味深い調査を実施している。2013〜14年、東京都世田谷区の全分娩施設において、妊娠中期から産後3カ月までの女性約1700人を対象としたメンタルヘルスの調査である。その結果、家庭内での「孤独感」がうつ発症の大きなリスク要因となることが判明したのだ。
この調査に関わった同センターこころの診療部乳幼児メンタルヘルス診療科診療部長の立花良之医師(44)にとっても、思わぬ結果だったという。何が「意外」だったのか。
国立成育医療研究センターの立花良之医師(撮影:伊澤理江)
「僕たちの予想としては、旦那さんが家事・育児をしないことが産後うつのリスク要因に直結するだろうと思っていたんです。そうしたら意外にもその調査結果では、(夫が家事・育児をしないことは)リスク因子になっていませんでした。これまでの国内外の調査と違う新しい知見が『家族としてのまとまりを感じるかどうかが重要』ということでした」
これは日本特有かもしれないという。
「欧米の調査とは、傾向が違っています。欧米では、旦那さんが家事・育児をしないことがうつのリスク因子になっていることが多い。日本では、例えば、旦那さんが忙しすぎて、家事・育児に十分な時間を割いてなくても、妻や母としての役割、家族としての絆を感じていればメンタルヘルスが良い状態に保たれやすい。逆に、それが損なわれているとうつになりやすい。これは、日本の『家』や『家族』に関する社会文化を反映しているかもしれませんし、日本の女性の強さを示唆しているのかもしれません」
立花医師の分析によると、日本では、残業の多さなどによる夫の不在、家事や育児に参加しない風潮などが根強く、夫が家事・育児をしないことが家庭内でそもそも「問題点」として認識されていない可能性もあるという。

(イメージ撮影:穐吉洋子)
「夫と妻、暮らしている世界があまりに違う」
あの苦しかった時期、夫は由紀子さんの苦境に気付かなかったという。そうしたケースは、由紀子さん夫妻に限らない。なぜ、そんなことになるのだろうか。
恵泉女学園大学の大日向雅美学長(69)は「夫と妻の生活が分かれているからです」と話す。
「妻は家の中で家事・育児、夫は家の外で仕事。真逆の世界だから言語も違ってくる。外で働いている夫は、機能的で合理的な言語で暮らしていて、その世界は高速道路を突っ走っているみたいなものです。脇目をふらず、起承転結を明確にし、いち早くゴールに到達することが求められている。妻と子は一般道路です。渋滞、右折左折もある。生きている世界があまりにも別世界。そんな社会環境で、妻の状況を理解しろと言っても夫には難しい」

恵泉女学園大学学長・大日向雅美氏(撮影:アートスタジオ・鈴木徹)
由紀子さんは「産後うつ」と診断された後、せきを切ったように周囲と会話したという。夫だけでなく、自分の親やきょうだいにも。どんなにつらかったか、どうやって寝られない日々を過ごしたか。
由紀子さんは「恥を捨て、弱ったところを全部見せたんです」と明かす。
「『いい母親、一人前でいなきゃ』という気持ちを捨てられて、肩の力が抜けました。やっと、弱音を言えるようになって。それからは夫も協力的になった。物理的なヘルプもうれしい。でも、『今までやらせすぎて悪かった』と言って、やっと私がつらかったことを理解してくれた。それがうれしかった」
孤独だった時期、由紀子さんはSOSを全く発しなかったわけではない。孤独な育児があまりにつらく、行政の広報誌を見て、育児相談に電話した。すると、「担当者が今いません」とだけ言われたという。
「ドキドキしながら掛けたのに、目の前でシャッターを閉められた感じで。あの時、親身になって相談にのってくれる窓口があったら、私は随分救われたんじゃないかと思います」

(イメージ撮影:穐吉洋子)
前出の立花医師は、由紀子さんのケースについて「担当者がいなければ、電話を折り返すこともできたはずです。問題のある家庭が多い地域では行政側の感度が低くなりすぎている」と語り、こう付け加えた。
「頑張りすぎてしまう人は、SOSも出しづらいことが多い。自尊心が低かったり、人間関係を築くのが苦手だったりする人は『SOSを出していいんだ、人に頼っていいんだ』と思えないことがある。そして自分で全部抱え込み、破綻してしまう。そういう人がいることを周囲は理解すべきなんです。うつは『心の風邪』などとよく言われます。誰でも風邪を引くように、うつも、どんな健康な人でも誰でもなりうる。それを社会全体が認識していることが大切だと思います」
立花医師によれば、周りからはごく普通に見える母親であっても、育児で精神的に極度に追い詰められていくと、赤ちゃんの口をふさいだり、衝動的に強く揺すったりして死に至らせることが実際に起きている。そして、母親が追い詰められていく様子は外から見えにくい。
「小さなSOS」 拾うのは誰か
この問題をさらに考えようと、大正大学人間学部の西郷泰之教授(65)も訪ねた。キャンパスは東京・巣鴨。研究室は正門から入ってすぐの建物にあった。
西郷教授はNPO法人「ホームスタート・ジャパン」の代表理事でもある。
大正大学人間学部の西郷泰之教授(撮影:伊澤理江)
このNPOのスタッフは子育て中の母親を訪問し、悩みや苦しさを聞き続ける。家事や育児の肩代わりはしない。どうしたらいいかのアドバイスもしない。「傾聴」と「一緒に家事・育児」によって、まずは母親たちの気持ちを落ち着かせる。
「児童館や子育てひろばなどの拠点型支援は、お母さんたちの孤立防止が主な目的です。でも、地域によって異なるにしても、1回だけの利用も含めて3~5割のお母さんたちしか利用していない、という調査がある。(拠点型支援のように)待っているだけだと、ピンチになった親たちが見えてこないんです」
訪問型の子育て支援であるホームスタートは、拠点型の弱点を補いつつ、母親を孤立から救う試みだ。利用者の半分はゼロ歳児の親。利用ニーズの1位は「孤立感の解消」で、全体の7割にもなる。
「ホームスタートでは、30時間を超える研修を受けた一般の市民が家庭に行きます。権威のないところがいい。専門家が訪問すると、お母さんたちは『専門家に話すなんて私はそんなに大きな問題を抱えているわけ?』と構えてしまう。ボランティアが話を聞き続けることで、気持ちが元気になる。ちょっとした悩みでも、分かってくれる人が世の中に1人いるだけで、母親は安心できる。問題そのものは解決していなくても、ホッとできる」

1999年に始まった英国の福祉政策「Sure Start」では「家庭訪問型子育て支援(ホームビジティング)」を重視。今では「ホームビジティング」という名称でわざわざ呼ばれないほど一般化しているという=西郷教授の研究室で(撮影:伊澤理江)
西郷教授は続ける。
「ホームスタートのボランティアが話を聞いていると、お母さんたち、結構泣くんです。『夫の帰宅は23時過ぎで、そのまま寝てしまう……』と言っているうちに泣く。家庭の重い話をママ友にはしないじゃないですか? ママ友に言えない話を聞いてほしい、というニーズがある。心が安定してくると、人間は適切な判断ができるようになりますから、お母さんたちも外に出て、いろんなサービスを活用したり、相談に行ったりできるようになるんです」
1000団体以上が加盟するNPO法人「子育てひろば全国連絡協議会」(事務局・横浜市)理事長の奥山千鶴子さん(56)も、違う角度から同じことを言った。奥山さんは自身の子育て中、公園以外に行く場所がなく、子育て中の親たちと「ひろば」づくりに奔走し、その後も活動を続けている。
「産前は、夫婦とも赤ちゃんのために一生懸命です。両親教室ではパパの参加率は9割にもなる。そこでは、『産後、メンタル的に厳しくなる人も多いし、そんな妻を支えていくのが父親の仕事』と伝わることが大切です。それと地域の子育て支援情報。産後派遣ヘルパーなど、もしもの時に活用できるサービスがあり、事業者のことを調べておくといいですよ、といった話をする。いざという時に頼れる先、先の見通しを持つことが大切なんです」

(イメージ撮影:穐吉洋子)
由紀子さんの息子はいま、5歳になる。泣き続けた日々もやや遠くなった。
今になって、「息子はHSCかも」と感じることがある。Highly Sensitive Child。「ひと一倍敏感な気質を持つ子ども」という意味だ。
「少し落ち着いてから本を読んだら、すごく当てはまるんです。赤ちゃんなのに、リスクを先回りして考え心配するそうです。音、光に敏感。大きな音には今でも敏感です。臆病。赤ちゃんはしゃべれないから、不安なときは泣くしかない。今思えば、そういうことで泣いていたのかな、って」
ただ、当時はネット以外に相談先がなかった。本を読む暇もなかったし、ホームスタートのような存在も知らなかった。大きくなった息子はもう泣かず、つらい日々の感覚も薄らいできた。
こうやって、社会全体で考えるべき問題は「たくさんの個人史」の中に埋もれていくのかもしれない。

イメージ(撮影:穐吉洋子)
[協力]山縣文治・関西大学教授
【連載・子育て困難社会 母親たちの現実】
子育てをめぐる家庭の「危機」は、全国のあちこちにあり、そして「私ごと」の世界に埋もれたままになっているに違いない。どうして母親たちにとってつらい出来事が起きるのか。その素朴な疑問を解くために、多くの母親たちに会い、カウンセラーなどの専門家も訪ね歩いた。
【11月5日(火)公開】見知らぬ土地への転勤と激務で帰らぬ夫 「アウェイ育児」に苦しむ妻
【11月6日(水)公開】「育児は女性のもの」が覆い隠す社会の歪み──見え始めた「母性愛神話」の限界
【11月7日(木)公開】母親が直面する孤立子育て……全てを抱え込んで破綻、「妻の孤独」の泥沼
【11月8日(金)公開】ワンオペ育児の中で「こうでなきゃ」が苦しめる “理想の母親像”の呪縛
伊澤理江(いざわ・りえ)
ジャーナリスト。新聞社、外資系PR会社などを経て、現在は新聞・ネットメディアなどで執筆活動を行う。英国ウェストミンスター大学大学院(ジャーナリズム専攻)で修士号を取得。フロントラインプレス所属。