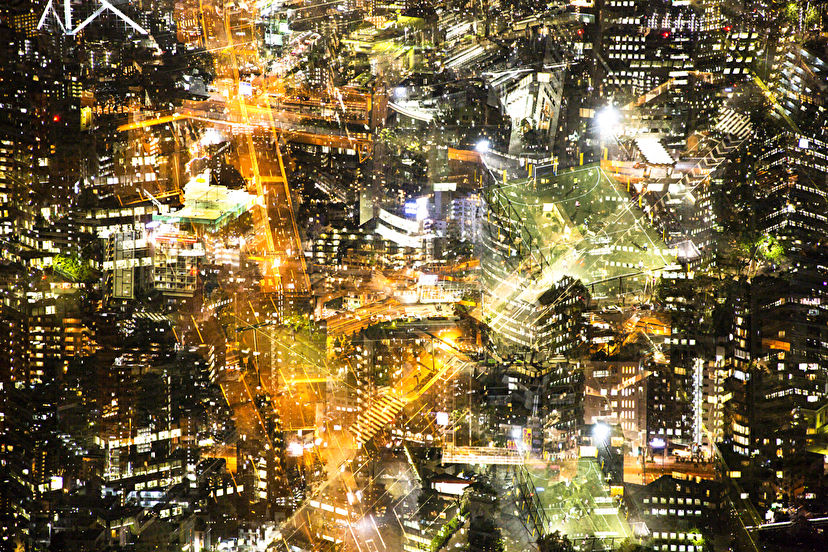センサーを用いて気温、湿度、土壌の状況などを把握し、そのデータを栽培に生かす農家が登場している。地勢や天候などの自然条件に大きく左右される農業。作物の生育環境を正確につかみ、ある程度コントロールできるようになれば、ロスの少ない効率的な農業が実現するかもしれない。データに基づく農業は働き方をどう変え、どこに課題があるのか。(ノンフィクションライター・熊谷祐司/Yahoo!ニュース 特集編集部)
田んぼの水量チェックにかかる人手が3分の1に
太平洋に面した白い砂浜が約66キロつづく九十九里浜。その中央に位置する千葉県横芝光町は、白ネギの生産高で国内トップを誇る千葉県のなかでも、指折りの白ネギ産地として知られる。

取材で訪れた日も、海から強い潮風が吹いていた(撮影:後藤勝)
25人が働く農業法人GREEN GIFTも、23ヘクタール(サッカーコート約32面分)の畑で、年間を通して途切れることなく20種類の白ネギを栽培している。主な出荷先は、スーパーマーケットやラーメン店、焼き鳥屋、たこ焼き屋など。食材にこだわって契約している出荷先もある。
「この一帯の砂地は白ネギ栽培に適しているうえに、強い潮風は海水のミネラルを豊富に含み、それがネギの味をよくしてくれます」
代表の鈴木敏弘さん(33)は、自分たちが作る「白砂ねぎ」の特徴をそう説明する。
父から農業を継いだのは12年前。当初から法人化を視野に入れ、近隣のリタイア農家などから次々と畑を借りて作付面積を増やしてきた。

「白砂ねぎ」の特徴を説明する鈴木敏弘さん。ここは九十九里浜の近くにある20アール(テニスコート約8面分)ほどの畑で、約7万本の白ネギが植えられている(撮影:後藤勝)
3年ほど前までは、ネギ栽培の拡大を妨げる悩みの種があった。ほかに20ヘクタールの水田でコメも作っているため、ネギを苗床から畑に移す定植作業のピークが、田植えのシーズンと重なってしまうのだ。
「水田は、田植えから1カ月ほど水量の管理に神経を使います。水田は広範囲に点在するので、以前は3人のスタッフが毎日4時間かけて見回りをしていました。最も遠い水田は、本社からクルマで30分以上かかる場所にあります。田植えを終えてしばらくは、この見回りに人手を取られ、ネギの定植作業が思うように進みませんでした」
鈴木さんの悩みを解消してくれたのは、農業系ITベンチャーのベジタリア(東京都渋谷区)が開発した「水田センサー」だった。このセンサーを導入したことで、水量管理の担当者は従来の3人から1人に減り、そのぶん定植作業のスタッフを増やすことができた。

田んぼの水位や水温を測る「水田センサー」(撮影:後藤勝)
水田センサーは長さ2メートルほどの金属製の棒についた装置で、水田の一角に刺しておけばセンサーが自動で水位や水温の変化を記録していく。それらのデータはインターネット経由で定期的に送信され、離れた場所にいてもスマートフォンやパソコンがあれば、リアルタイムで水位などの数値を確認できる。気温や湿度なども同時に計測されている。
「使用するセンサーは3本だけ。各エリアで最も水が抜けやすいなどの条件が厳しい水田に刺してあります。そのデータから周辺の状況もおおよそ把握できるので、必要に応じて水を加減します」
水量不足などの異常が通知されると、担当者が現場に急行して対応する。この仕組みがあるだけでも安心だ。その時期が過ぎれば、センサーは必要ないので抜いてしまう。

広範囲に散らばっている田畑をデジタル技術で管理する(撮影:後藤勝)
鈴木さんは、センサー導入の前から農業のデジタル化に積極的だったという。
同じベジタリアのシステム「アグリノート」を使い始めたのは8年前。これは営農支援システムの一つで、航空写真のマップ上で圃場を管理し、農作業の記録をデータとして保存・活用できる。
「例えば、何月何日にどの農薬をどれだけ散布したかといった記録は、長年続ければ作物の生育状況を判断するうえで貴重なデータベースとなります。その日の気温や天気、台風などの気象状況も含めて過去のデータを参照できるのは強力な武器です」
これまでベテラン農家では、農薬散布のタイミングなどを長年の経験と勘で判断してきた。これからは農業を始めたばかりの人でも、データを参照することで同じように判断できる可能性が広がってきた。

鈴木さんは一般的なトラクターを使用しているが、自動運転アシスト機能がついた農機にも興味があるという(撮影:後藤勝)
今では、各スタッフが日々の作業内容と所要時間をスマートフォンで入力し、誰もが見られるように共有している。
「同じ作業でも、担当者によって仕事の品質や所要時間は異なります。もし作業効率が低いスタッフがいれば、その原因を突き止めて改善できます。一方で、担当者ごとの生産性も“見える化”される。将来的には、スキルが高い人や頑張った人に相応の報酬を払う公平な評価のしくみも作りたいと考えています」
センサー技術でトマトの収穫量が5割増し
京都駅から西南方向に10キロほど。京都市西京区に本社事務所を構えるオーガニックnicoでは、ビニールハウスの有機栽培で温度、湿度、日射量、CO2量などを自社開発の高度なセンサーで測定し、その環境データに基づいてミニトマトなどの収穫量アップを図っている。

センサー活用のおかげでミニトマトの収穫量は多く、味もよい(撮影:遠藤智昭)
代表の中村新さん(59)は、センサーを用いた栽培方法についてこう説明する。
「センサーから得られるデータを読みながら、作物の光合成が最大化するようにハウス内の環境を整えていきます。これによって通常のハウス栽培より、収穫量は5割ほどアップしています」
生育環境をコントロールすると、味も向上するという。
「昨年と今年、あるスーパーで売られている一番高価なミニトマトと、当社のミニトマトとを味比べしてもらうブラインド調査を実施しましたが、当社のものが2年連続でおいしいと評価されました」

ハウス内を見て回る中村新さん(撮影:遠藤智昭)
オーガニックnicoの畑があるのは、京都西山と呼ばれるエリアのなだらかな斜面。7棟続くビニールハウスが目印だ。30アール(テニスコート約12面分)のハウスでは、売り上げの4割を占めるミニトマトのほかにベビーリーフ、九条ネギ、イチゴなどを有機栽培する。
露地栽培も手がけている。取材で訪れた8月中旬には、40アール(テニスコート約16面分)の畑でオクラの黄色い花が咲いていた。
ハウスに設置されたセンサーは、ボックス形、棒状、電灯の笠を重ねたような形など種類によって形状はさまざまだ。センサーによって収集されたデータはハウスの一角に備えつけた制御盤に送られる。

ハウス内のあちこちにさまざまな形のセンサーが見られる(撮影:遠藤智昭)
同社の強みは、収集したデータをもとに、その作物の最適な生育条件に合わせて、ハウスの環境を随時コントロールできるところにある。
温度が上がり過ぎた場合は、ハウス側面のビニールが自動で巻き上がり、風を呼び込んで温度を下げる。日射量が不足すれば、天井を覆っている遮光カーテンが開いて、太陽光を招き入れる。CO2量が足りなければ、CO2が噴き出す機械が作動し、栽培に最適な環境を作り出す。すべて自動制御も可能だ。
高度なセンサーと同様に、制御システムも自社で開発したもので、新技術はもともと技術者だった中村さんが考案することが多い。

作物の栽培状況から販売状況までがデータ管理されている(撮影:遠藤智昭)
中村さんが農業に就いたのは11年前のことだ。
大学を卒業後、精密機器のオムロンに入社し、22年間、工場の自動化で使われるセンサーの開発にかかわった。オムロンを退職し、ベンチャー企業でレーザーの研究開発に2年半携わったあと、静岡県の「自然農法大学校」(現「農業・環境・健康研究所 農業大学校」)で有機農業を1年間学び、2007年、48歳のときに京都府南丹市で農業を始めた。
最終的に農業の道に進んだのは「大学で農学を研究していた父の影響があったのだろう」と中村さんは振り返る。
「父はもともと、普通に農薬やホルモン剤を用いる慣行農法を研究していましたが、45歳のときにドイツで出合った有機農業にのめり込んでいったようです。私も父から有機農業の話はよく聞いたので、それが頭にあったのかもしれません」

大学院を修了したスタッフが出荷作業も担当する(撮影:遠藤智昭)
就農したての頃、中村さんは有機農業で試行錯誤する面白さに目覚めたという。
「当初は3年ほど普通の農作業を経験し、それからセンサーを使った栽培システムを完成させるもくろみでした。しかし結局6年も続けてしまいました」
野菜栽培の環境制御に関する技術開発とコンサルティングを手がけるオーガニックnicoを立ち上げたのは2010年のことだ。その後、ハウスでの最適な有機栽培システムを構築して世の中に広める活動を始めた。
「日本では長い間、農学など農業技術の研究と生産の現場が分離していました。私は農業技術とシステム技術、生産現場を融合していこうと考えました」
現在、同社ではパートを含め24人のスタッフが働き、その中に農学博士が2人、システム関連の博士が3人いる。高度な専門知識を持った人材がいるのは、農業とITを組み合わせた技術開発を行っているためだ。

制御盤を確認するnicoスタッフの植木正人さん(撮影:遠藤智昭)
「目下、ミニトマトのハウス栽培システムの完成を急いでいて、現時点で目指すレベルの5割は超えています。あと3年ほど、温度、湿度、日射量、CO2量がどう影響しあうかの解析を進めれば、理想とする栽培システムの8割まで到達できそうです」
さらに8割から9割を目指すため、土壌水分センサーも試験中で、近々、葉の栄養分を測って作物の健康状態を把握するセンサーの導入も考えている。
生産現場スタッフの植木正人さん(44)は「ハウスの外側からしみ込んでくる水の状態で作物の出来具合が大きく変わります」と言う。ミニトマトのハウス内の9カ所に、地面から15、30、50センチメートルと異なる深さにセンサーが刺してある。そのデータを読み込んで最適な水分量を補給しようと試みる。

地中の水分状況をデータで記録し、栽培に生かしている(撮影:遠藤智昭)
社名の「nico」には「日本農業において有機農業のシェアを2025年までに25%に上げる」という中村さんの思いが込められている。農林水産省によると、日本の全耕作面積における有機農業の圃場の割合は2016年の時点でわずか0.23%に過ぎない。
「あと7年で25%はさすがに無理ですが、2.5%くらいは広げたいですね。そのためにはしっかり採算が取れる有機農業のシステムを構築することが必要です」
それだけ生産性が高まるポテンシャルを持つのがセンサーだと中村さんは言う。とりわけ農家の若い後継者や新規就農者にとっては、ベテランが長年の経験で培ったノウハウを科学的に理解できるだけでも大きな利点だ。
採算も十分に成り立つと中村さんは試算する。
「このセンサーシステムを備えたビニールハウスは、2500万円ほどの初期投資で導入できます。それで毎年1000万円の売り上げが見込めれば、数年で回収できる計算です。軌道に乗るまでは手厚く指導するなどのサポートも必要でしょう」
中村さんは、複数の農家が入る“農業団地”も構想している。オーガニックnicoでビニールハウスを用意し、農家はそこに入ってセンサーを駆使した有機農法を実践していく形だ。ビニールハウスの利用は賃貸方式で、農作物の販売、出荷なども同社が面倒を見るなど、センサーを用いた“儲かる農家”の実現に知恵を絞る。

害虫捕獲は意外にアナログな黄色い粘着シート(撮影:遠藤智昭)
露地栽培で高い成果を出すことがセンサー普及のカギ
気温、湿度、光量、CO2量、養分量などセンサー技術の導入は、海外では積極的に行われ、生産性向上を実現してきた。米国では1990年代からセンサーなどの農業へのIT投資は伸び続け、1998年の約10億ドルから2013年には約70億ドルと7倍の規模になった。
米国のエアロファームというベンチャーの大規模な「植物工場」では、レタスなどの葉物栽培で各種センサー技術とLED照明、空調などを組み合わせ、それまでの露地栽培に比べて単位面積あたり130倍も生産性を向上させた。
一方、経営面積1.0ヘクタール未満の小規模農家が半分以上という日本では、採算性などへの懸念から、農業へのIT投資は伸び悩んだ。農業へのIT投資は1999年の728億円をピークに、2006年の264億円と下落傾向が続いたが、2011年には601億円と復調した(経済産業研究所調べ)。その多くをセンサーやIoTなどの「生産効率化」が占めた。

ハウス内に設置された制御盤(撮影:遠藤智昭)
センサーを利用し、科学的なデータを収集・分析すれば、栽培条件の最適解に近づいていくことも期待できる。それは農家に、収穫量の増大、農薬の効果的な散布といった恩恵をもたらす。
現在のところ、高度なセンサー活用は主にハウス栽培で開発が進んでいる。しかし、2016年の時点で全農地面積の約450万ヘクタールに対して、ビニールハウスやガラス室など施設栽培は約4万3000ヘクタールと1%に満たない。センサー活用が真に農業になくてはならない強力な武器だと認識されるには、残る99%以上を占める露地栽培で高い成果を出す必要があるだろう。
自社のセンサー技術に自信をもつ中村さんでも「露地での環境コントロールは相当に難しい」と話す。
露地栽培は日照りや豪雨など気象の影響が大きく、センサーの精度を高めても、ハウスほど温度や湿度をコントロールできない。病虫害の発生や雑草の繁茂を抑えることも困難だ。

ハウスではミニトマトのほか、ベビーリーフ、九条ネギ、イチゴなどを栽培する(撮影:遠藤智昭)
そのような露地栽培の課題は、今後デジタル技術で克服できるのか。
前出の水田センサーを開発した農業系ITベンチャー「ベジタリア」代表・小池聡さんはこう話す。
「世界の農作物は、病虫害と雑草の被害で3分の1が商品にならないと言われています。病虫害が予防できるだけでも、農業全体のロスはかなり防げるでしょう。これから各種センサーの精度が上がり、そのデータを分析していけば、病虫害の発生が予測可能になるかもしれません。少なくとも、被害が広がる前に処置できるようになることは期待できます」
GREEN GIFTの鈴木さんも病虫害予防はコスト面で効果があると話す。
「データベース化した過去の記録からでも、病虫害の発生時期がある程度は予測できます。農薬を使う場合でも、適切なタイミングで予防薬を用いれば、かなり被害を防げる。そのほうが、病虫害が広がってから全面的に散布する治療薬より安く、コストは段違いです」
気象条件で変化が出やすい露地栽培では、ハウス栽培ほどセンサーの効果は明確に出にくいだろう。しかし、センサーを活用する農家が増えていき、データを集積・共有していけば、露地栽培の環境条件と作物の生育状況との関係性が解き明かされていく可能性がある。
高度なセンサー技術とAI、IoT、ビッグデータ解析を組み合わせて、農業分野のデジタル技術が普及すれば、日本の農業が飛躍的に進歩する日はそう遠くないだろう。

九条ネギは一度掘り出して乾かし、また定植する(撮影:遠藤智昭)
熊谷祐司(くまがい・ゆうじ)
1966年、東京都生まれ。ビジネス誌の編集者を経てノンフィクションライターとなる。総合誌やWEBメディアで社会、経済、教育など幅広い分野の取材・執筆を担当。
写真監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝
[写真] 撮影:後藤勝、遠藤智昭