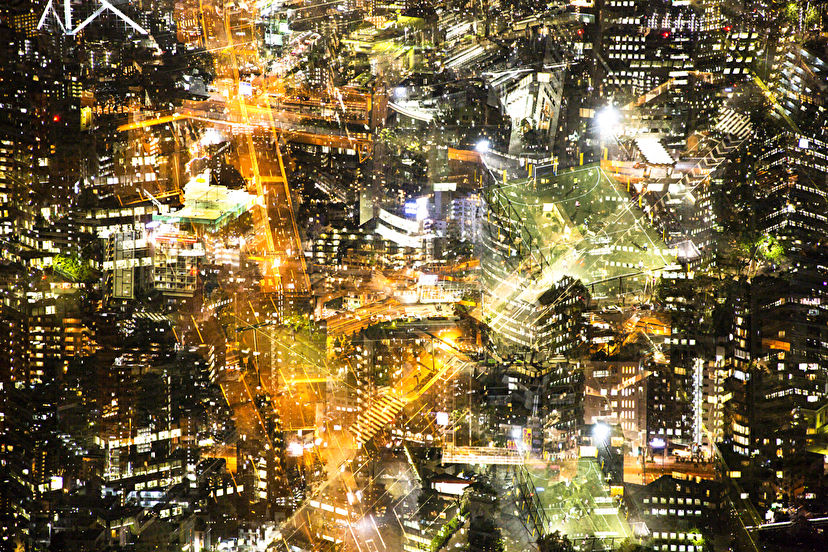農業にデジタル技術が広がりつつある。田植え機やトラクタといった農業機械にGPS(全地球測位システム)や自動運転技術が装備され、病虫害の監視や農薬の散布にドローンが使われる。新しい技術の導入は省力化、自動化を進めるだけでなく、収入の増加をもたらす期待が大きく、若者の参入を促すことにもつながっている。デジタル技術が変えつつある農業の現場を歩いた。(ノンフィクションライター・熊谷祐司/Yahoo!ニュース 特集編集部)
自動運転アシストで田植えが楽に
6月中旬、埼玉県北部の鴻巣市では、田植えの季節が終わろうとしていた。水田の一角に、梅雨時の晴れ間に急いで田植えを進める「みつぎ農園」の三ツ木宏之さん(54)と祐介さん(20)親子の姿があった。
宏之さんは長年、農業機械メーカーに勤めるかたわら、1.5ヘクタール(サッカーコート約2面分)の水田でコメをつくる兼業農家だった。2012年、農業専業に生きると決めて、会社を辞めた。
「まだ兼業だった頃、周りの廃業していく農家からだんだん水田を預かるようになり、全て合わせて3ヘクタールを超えたあたりから、忙しさで会社勤めが難しくなりました。これからも廃業する農家が増えるなら、専業農家として作付面積を拡大していくチャンスかもしれないとそのとき思いました」

クボタの最新型田植え機「ファームパイロット」を操縦する三ツ木祐介さん。GPSと自動運転アシスト機能がついており、手放し運転でも、泥に足をとられず、直進走行ができる(撮影:千賀健史)
宏之さんはその後もリタイア農家の休耕田を借り受け、現在は近隣に点在する計25ヘクタールの水田を作付けしている。それに伴って田植えに費やす時間も増え続け、今年は5月20日〜6月20日までの丸1カ月間を要した。
「水田が多い農家のなかには田植えをやり切れずに、一部の水田でコメづくりをあきらめることもあります。一定規模を超えると、高性能な機械の力を借りなければ難しくなると思いました」
専業となって農業の大規模化を志す宏之さんは昨年、最新型の田植え機を約400万円で購入した。GPS(全地球測位システム)が搭載され、自動運転アシスト機能が付いている。

多くの苗を搭載して走行できる(撮影:千賀健史)
ロボット農機で進む自動化、省力化
日本人の食生活を支える農業が岐路に差しかかっている。
食料自給率の低下、コメ消費の減少など食生活の変化、安全性の確保などいくつも課題があるなかで、最も大きな問題が農家の減少と生産者の高齢化だ。2005年に335万3000人、平均年齢63.2歳だった農業就業者は、10年後の2015年にはそれぞれ209万7000人、66.4歳となった。労働力不足は急速に進み、作物を栽培しない耕作放棄地は増加の一途をたどっている。
その打開策として脚光を浴びているのが、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)を活用するデジタル農業だ。コンピュータが動きを操るロボット農機が人間に代わって農作業を進める。進むのは自動化、省力化だ。
鴻巣市の三ツ木さん親子が活用しだしたGPS自動田植え機もそんな農機の一つだ。

(撮影:千賀健史)
作業時間は従来の半分以下
水田に出ると、最初の1列は自分でしっかりハンドルを握って運転する。苗をどこからどこまで植えるかを機械に覚えさせるためだ。2列目からはGPSの測位機能を利用して、ハンドルを握らなくても田植え機は直進しながら苗を植えていく。
「田植え機に乗ったことがない人にはピンとこないでしょうが、実はこのまっすぐに苗を植える運転技術はかなりの熟練を要するんです」と宏之さんは言う。田植え機は泥のなかで右に左に滑りやすく、気を抜くと蛇行してしまう。すると、植え付け可能な面積が減ってしまう。

両手を上げ、手放し運転をして見せる三ツ木祐介さん(撮影:千賀健史)
「私は子どもの頃から田植えを手伝ってきたのでまっすぐ植えられますが、それでも1カ月もの間、朝から晩まで神経を使ってハンドルを握り続けると心身ともにクタクタになりました。GPS付きは負担感がまるで違う」
従来の田植え機では、ベテランでも運転中に何度も振り向いて苗が一直線に並んでいるかを確認する必要があった。GPS付き田植え機では、コンピュータが指定した通り蛇行せずに進むので、その必要がない。植えるスピードも速く、同じ広さの水田なら作業時間は従来型の半分以下だという。
「高校を卒業して本格的に稲作を始めた息子でも、ベテランと同じか、それ以上の速さで田植えができます」
確かに最新型の田植え機に乗る息子の祐介さんは、余裕を持って操作しているように見える。後部に積んだトレイの苗が減ってくれば、ハンドルから手を離してトレイの入れ替え作業にかかる。従来の田植え機では、別の人も一緒に乗ってトレイを入れ替えるか、その場に停車して自分で入れ替えていたのだから、作業効率はまるで違う。
最新型の田植え機は、旧型より1割ほど高い。自動運転アシストのほかに、従来型には付いていなかった、IoTでオイル交換や部品交換の時期を事前に知らせる機能もあり、宏之さんは「重宝している」と言う。

技術の進歩で手間が減ってきたと語る三ツ木宏之さん(撮影:千賀健史)
農機の自動化がモノを言う
父の宏之さんは、長男の祐介さんが自分の後継者になることも計算に入れて投資に踏み切った。「息子には農業以外の世界も経験してもらいたかったのですが……」と言いながらも、うれしそうな表情をする。
主要作物のコメは、農業協同組合(JA)のほかに、商社や老人施設、個人の消費者にも販売し、顧客の要望や市場ニーズに応じて「コシヒカリ」「彩のきずな」「みつひかり」などの数種類を作っている。販売先には困らないというが、現在の収入に関しては「田植え機のローンや肥料代、田の借り賃を差し引けばトントンでしょうか」と笑う。これから先も「黙っていても水田が集まってくる」という状況が続けば、さらに作付面積は広くなり、収入増が見込める算段がある。宏之さんが「50ヘクタールを目指す」と言えば、祐介さんも「100ヘクタール」と負けていない。
「規模が拡大するほど、自動化された農機がモノを言う。これから5年で日本の農業は確実に変わるでしょう」

三ツ木祐介さん(撮影:千賀健史)
GPSトラクタの走行は誤差2〜3センチ
人間が操作しなくても自動運転が可能なデジタル農機は、田植え機だけでなく、トラクタやコンバインなどでも開発が進んでいる。たとえば自動走行トラクタでは、クボタが昨年「アグリロボトラクタ」のモニター販売を始め、ヤンマーは北海道大学と共同で実証実験を重ねた自動走行トラクタの発売を今秋予定している。
クボタの佐々木真治専務取締役は「自動走行の技術自体はかなり成熟してきた。アグリロボトラクタはあらかじめプログラミングした走行ラインを誤差2〜3センチで自動運転が可能」だと言う。直線走行を指示すれば、ほぼ直線に近い正確さで進むという点で、北海道の広大で斜面が多い農場などでは高いニーズがある。
ただし、安全性などの課題は多い。農林水産省は2017年、農機の自動走行に関して、安全性確保のためのガイドライン(「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」)を作成した。

(撮影:千賀健史)
レベル1はオートステアリング(自動操舵)、レベル2は圃場(ほじょう=農作物を栽培する田畑)内の監視下での無人走行、レベル3は遠隔監視下での無人の自動走行。
完全無人化には、自動運転に適した形状に圃場を整えることや、公道を走行する際の安全性確保など、いくつかの課題をクリアする必要がある。このガイドラインによって、現時点では、人間が乗らない状態での自動走行は認められていない。
佐々木専務は「現在はレベル1からレベル2に移ろうとしている段階です。一般の農場では、自動運転のトラクタなどが農場内の道路を横切る際に人が出てきたときにどう安全性を確保するかといった課題があります。最初は特区方式で、関係者以外の立ち入りがなく、運転手が乗っていなくても自動走行が許される圃場をつくるのが現実的かもしれない」と言う。

(撮影:千賀健史)
ドローンが病虫害の葉だけを消毒
鳥羽田(とりはた)龍太さん(28)は今春から農作業にドローンを活用し、農業の大きな変化を実感している。
鳥羽田さんの農場は、茨城県のほぼ中央に位置する茨城町。約5ヘクタールの畑でキャベツやジャガイモ、トマト、ホウレンソウ、コマツナなどの野菜、果物ではナシを栽培している。育てた作物はJAや農産物直売所に毎日出荷する。

茨城県茨木町の農場(撮影:後藤勝)
この地域でも高齢化が進み、リタイア農家は多い。そのなかで20代の営農者は珍しい。農家で生まれ育った鳥羽田さんは、東京の大学で経営学を学んだあと、県立農業大学校に入って2年間、農業を継ぐための準備をした。
ドローン導入に興味をもったのは、農業大学校時代の友人から聞いた話がきっかけだった。AI、IoT関連のソフトウェアを開発するベンチャー企業のオプティム(東京都港区)が提供する「アグリドローン」を導入した。
「ドローンのカメラで畑の隅々まで撮影できるので、目視が難しい畑の奥のほうまで作物の状態が把握できます。生育が悪い作物、病虫害が出ている作物など一目でわかります」

農場主の鳥羽田龍太さん(左)と農業用ドローンを開発するオプティムの星野祐輝さん(右)(撮影:後藤勝)
ドローンの画像分析で薬剤を散布
日々の農作業は慌ただしく、作物の状態を丹念に見て回る余裕はない。朝7時頃から3時間ほど農薬を散布し、昼食をはさんで17時頃までは収穫、その後に出荷作業をこなすというのが日課だ。
アグリドローンを使うと、3カ所に分かれている計30アール(テニスコート約12面分)ほどのキャベツ畑でも20分もあれば全体の撮影が終わってしまう。
鳥羽田さんがドローンを飛ばすのは3日に1回のペース。その画像を分析して、キャベツの葉に一定の割合以上に虫の食害が見つかれば、そこに害虫がいると判断して、農薬を積んだドローンを飛行させてピンポイントで薬剤を散布する。
現在、ドローンによる農薬散布は、ドローンの飛行に関わる航空法などの規制、農薬散布に関わる農水省などの規制があり、認定を受けた1人が操縦し、別の1人が監視する必要がある。それでも、省力化の効果は大きい。アグリドローン導入前、キャベツ畑には数日に1回、広範に農薬を散布していた。一般的な農薬散布の方法だ。
「現在は散布の数日後にドローンを飛ばせば、農薬の効果も一目瞭然です」

鳥羽田龍太さん(撮影:後藤勝)
使用農薬は10分の1に減少
オプティムの休坂健志執行役員は、「農薬を減らすことで、農作物の付加価値を高められる」と強調する。
「昨年、佐賀県の豆畑農家でドローンを使った農薬のピンポイント散布を実施したところ、使用農薬は従来の10分の1以下まで減りました。収穫した枝豆は低農薬ですから、通常の3倍近い値段で販売しても飛ぶように売れました」

オプティムが開発する農業用ドローン「オプティム・アグリ・ドローン」。ピンポイントの農薬散布や複数のカメラデバイスを装着し、画像解析もできる(撮影:後藤勝)
デジタル農業の壁は年齢か
JAグループの全国組織である全国農業協同組合連合会(JA全農)でも、デジタル農業の研究開発を進めている。ドローン活用などを推進する耕種総合対策部事業改革推進課の新川一也課長は「技術の進歩だけでなく、農家にとっての採算性が大きな課題」と話す。
「これから田植え機やトラクタなどの買い替え時期を迎える農家は、デジタル農機も選択肢の一つに入ってくるでしょう。しかし当然、費用対効果は検討される。年間にわずかの期間しか田植え機などを使わない小規模農家は手を出しにくい。そういう方たちには完全に自動化された高級機種ではなく、人手は多少かかっても、利便性と価格のバランスがとれた製品が求められるでしょう。採算性の重視がデジタル農業普及のカギかもしれません」

JA全農 耕種総合対策部事業改革推進課課長 新川一也氏(撮影:後藤勝)
デジタル農業の導入には、年齢の問題も大きく関わる。
鴻巣市の三ツ木さん親子は、父の宏之さんが54歳、息子の祐介さんが20歳。茨城町の鳥羽田龍太さんは28歳。農業者の平均年齢66.7歳(2017年時点)から見れば3人とも若く、デジタル機器を使い慣れている世代だ。50代の三ツ木宏之さんもサラリーマン時代は技術者で、メカやデジタルにはかなり強いほうだという。
省力化や自動化の恩恵は、リタイアを考えはじめる高齢の農家こそ多そうだが、そこには“デジタルの壁”が立ちはだかっている。
新川課長は言う。
「自分で情報を集めて最新動向にキャッチアップできる世代には、自然とデジタル農業が広がっていく期待があります。新規就農者は毎年6万人前後いて、49歳以下が4割近くいる。デジタル技術による自動化、省力化などが進めば、若い世代はもっと参入しやすくなるでしょう。一方のベテラン世代には、より人間的なアプローチが必要だと考えています。信頼できる人が勧めてサポートしていけば、デジタル農業の便利さに自然と触れられるかもしれません」

(撮影:後藤勝)
JAグループには、TAC(Team for Agricultural Coordination)という地域農家を訪問するアドバイザーの組織がある。全国に約1千800人のスタッフがいて、訪問先で得た年間65万件以上のニーズをデータベースにリアルタイムで蓄積していく一方で、農家の悩みを解決するためにアドバイスするのも重要な役割の一つだ。そのなかで最新の農業技術や農業機械が紹介されることも多いという。このような組織を通して、デジタル農業が普及していくことも十分に期待できそうだ。
技術進歩と規制緩和によって、現状の課題が解決されていけば、やがて圃場に人影がなくなる可能性もある。デジタル農機が田畑を耕し、上空をドローンが飛び回り、農家の人たちはその様子をオフィスのモニターで監視する──そんな近未来図が農業関係者の間では共有されつつある。
事実、デジタル農業の恩恵は、自動化や省力化にとどまらない。IoTで集めた機械のデータ、圃場に設置した各種センサーからのデータなどを活用し、農作物の品質向上や効率的な育成を図っていく動きも見られる。
高付加価値の農作物が、最小限の人手とコストで収穫できれば、収益性が高い仕事として農業に人気が集まる日がきても不思議ではない。多大な可能性を秘めたデジタル農業の今後が注目される。

(撮影:後藤勝)
熊谷祐司(くまがい・ゆうじ)
1966年、東京都生まれ。ビジネス誌の編集者を経てノンフィクションライターとなる。総合誌やWEBメディアで社会、経済、教育など幅広い分野の取材・執筆を担当。
[写真]監修:リマインダーズ・プロジェクト
後藤勝
撮影:後藤勝、千賀健史