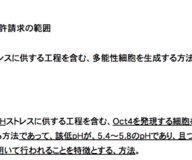STAP騒動『あの日』担当編集者に物申す
STAP細胞をめぐる一連の騒動で、当事者の一人である小保方晴子氏が手記を刊行した。彼女は、かつて所属していた理化学研究所(理研)の調査で論文に不正があったとの判定が下された人である。このことから、手記刊行という企画そのものを疑問視する人もいた。
しかし、私は企画そのものに難点をつける気にはなれない。渦中にいた人物が中で起きていたことを当事者の立場で語るのは価値がある。彼女は研究不正をした。しかし、だからといって、彼女の容姿や人格までを面白おかしく叩く一部のネット住民の行為は明らかにやり過ぎだった。その恐怖や悔しさ、理不尽さを本人が本にするのは意味がある。それに、誰であれ、自分の意見・弁明・批判を著す権利はあるはずだ。私は雑誌編集の世界に長くいた人間だ。青臭いことを言うようだが、これは「出版の自由」にかかわる話だ。
だが、この本の内容はどうだ。担当編集者はいったいどういう仕事をしていたのだろう?
この本に関しては、著者である小保方氏の豊かな表現力と置かれた境遇の過酷さから彼女に共感する声がある一方で、「全方位を敵に回した」「極端な自己愛」「嘘だらけの自己保身」「印象操作」などと評する声もある。たしかにそう読めてしまう表現が頻出するのだ。
編集者には著者を守る責任がある。著者をさらし者にするような本を出して良いはずがない。
『あの日』では編集者がきちんと仕事をしているとは思えない。「てにをは」レベルや「頭痛が痛い」レベルの不備が散見するが、それはこの際どうでも良い。実験手順の箇所だけに見られる不自然に受け身形の多い文章は、日本語としてどうかとも思うが、まあ許容しよう。生命科学の知識があれば気づくはずの明らかな誤字も、今回は脇に置く。
だが、公開されている報告書の内容との矛盾がある。この本の中での書き手の主張に矛盾が生じているところもある。本人自身やその代理人の三木弁護士の言葉として報じられていることとの矛盾がある。さらには、小保方氏本人がどこまで自覚しているか不明だが、まさに「全方位を敵に回している」。こうしたものを担当編集者はなぜ、そのまま本にするのか。
この本では、非常に伝聞が多い。誰それさんからこう聞いた、という表現が多いのだ。書いた本人さえ確認できていない非常にデリケートな内容も、ぽんと書かれたままになっている。
この本に書かれていることが本当だとすると、理研は情報管理がガタガタであることがわかる。著者は、自分に不利な情報がメディアにリークされていることを嘆くが、本人も「誰それから聞いた」という形でさまざまな情報を得ている。PI(研究室主催者)の採用面談を受けるときには、事務方から他の候補者の情報まで得ている。さまざまな研究者が連名でSTAP論文の疑義を伝えるメールを理研CDB上層部に送ったようだが、疑義の対象者である本人に、メールの送り主まで見せてしまっている。本当であれば、上層部の人間としてこの対応はマズいだろう。このあたりの事実確認を編集者がした形跡はない。
さらには、たとえば「事務の人からは(略)笹井先生の人としての尊厳が踏みにじられるような発言や行為を強いられる場面もあった、と聞いた」(157ページ)などの記述もある。
他人に「人としての尊厳を踏みにじるような発言や行為を強いた人」は、まず当人がその品性を疑われる。そしてこの箇所では、文脈からある著名研究者(本では実名)が笹井氏にそのようなことを強いた人だと読めてしまう。書き手自身が確認していないのに、ある人を実名を出して品性の卑しき人として描写してしまっているのだ。
担当編集者はこれの事実確認をしたのだろうか?
実名を出されたその研究者が、かなり怒っていたことは事実だろう。あるいはその怒りを鎮めるために、笹井氏が自らそうした発言や行為に出た可能性もある。もちろん、その研究者が怒りのあまり品性を欠く真似をした可能性もゼロではない。一方で、当時の著者はかなり混乱した精神状態にあったし、この著者は大げさな表現を好むことは編集者ならばすぐに気づくだろう。
笹井氏自身は2014年4月の会見でこの件に関しては、通常の謝罪で和解できたように話していた。事実がどうであったのかは、その場にいた者にしかわからず、この記述は小保方氏本人の言葉でさえない、ただの伝聞だ。確認できない内容であれば「尊厳を踏みにじられる発言や行為を強いられた」という強い表現は、別な言い方に変えるよう提案すべきだと、担当編集者は考えなかったのだろうか。
本人の主張の破綻している箇所、過去の発言などと矛盾している箇所も、編集者は見逃してはならない。そういうものが1つでもあれば、本全体の信頼性は大きく損なわれるからだ。そして、この本にはそうした不備が1カ所や2カ所ではない。
たとえば、この本では「STAP細胞からSTAP幹細胞を樹立したのは若山先生」と出てくる(この点は、種々の報告書や若山氏を含むほかの論文著者の発言とも矛盾はない)。著者はこのSTAP幹細胞にはそれほど興味がないのに、若山氏がSTAP幹細胞に夢中になっているような記述が頻出する。この点は、理研CDBの自己点検委員会の報告書の記載とニュアンスが異なるので違和感を覚えるが、当事者たちでないとわからないので、読み進めるしかない。
STAP幹細胞をつくったのは若山氏で、著者の主張に立てば、そのSTAP幹細胞に強い関心を持っていたのは小保方氏ではなく若山氏だ。
ところが、山梨大に移転した若山氏がSTAP幹細胞を第三者機関に解析に出すと知る段になると、「若山先生が冷凍庫内の私の名前が書いてあるサンプルボックスから、凍結保存されていた細胞サンプルを抜き取って」(154ページ)「若山先生は私のサンプルボックスを開け、中味の一部を私には相談なく抜き取り」(156ページ)と、あたかも若山氏が彼女の所有物を盗み出したかのような記述になる。本人はもちろん、そうしているのを見たと誰かが小保方氏に告げたわけでもないのに、ここは断定調だ。
この2回にわたる記述は、問題のSTAP幹細胞が小保方氏のサンプルボックスにしか存在しないことが前提になっている。だが、本当にそうだろうか? STAP幹細胞は無限に増える細胞で、いくらでも分けることができる。これをつくった若山氏本人が、彼女の主張するように強い関心を持っていたのならば、すべての細胞サンプルを彼女に渡さずに、自分の手元にも分けて持っていたと考えるのがむしろ自然だ。自己点検委員会の報告書にあるように、若山氏が自分の役割を単なる技術支援と認識していた場合でも、貴重な細胞であれば小保方氏が安定して維持・培養ができるようになることを確認するまで、万一に備えたバックアップを残しておくだろう。何より、このSTAP幹細胞をもとにキメラマウス実験をしたのも若山氏であることを考えれば、すべてのSTAP幹細胞を小保方氏のサンプルボックスに入れておく方が不思議だ。
「STAP幹細胞はすべて私(小保方氏)のもののはずなのに、若山先生は私に無断で手元に残しておいた」ということに愕然とするのならば理解できるが、『あの日』での主張はそうではない。自分の関心はSTAP細胞で、STAP幹細胞に固執していたのは若山氏だとしている。それなのに、自分のサンプルボックスから無断で抜き取ったと書いてしまっているのだ。これでは、小保方氏は「印象操作をしようとしている」などと批判されても仕方ない。
こうした点は、注意深く読めば、細胞の知識がなくても気がつく。必要な知識はちゃんと本文に書いてあるのだから。そして、担当編集者は最も注意深い読者であるべきなのだ。
学位論文をめぐる早稲田大学に関する記述も看過できない。「過熱するマスコミ報道を受けて、『外部からの強い圧力で小保方さんの博士論文に対し調査委員会が立ち上がることになった』と連絡を受けた」(157ページ)とある。これでは、本来ならば調査の必要はないがマスコミが騒ぐから早稲田は調査をすることにしたかのように読めてしまう。だが、『あの日』では一切ふれていないが、彼女の博士論文では序章のほぼすべてが米国立衛生研究所(NIH)のウェブサイトにある文章の丸写しだった。マスコミが過熱報道をしたのは事実なので、担当編集者がこの件を知らないということはないだろう。早稲田は「序章が丸々コピペ」でも、自主的には調査を開始しないような大学なのだとでもいうのだろうか。何より、「調査されるとは、潔白を証明できる機会を与えられたことでもある」という考えを彼女が全くしていないことに、なぜ疑問を持たないのか。
担当部署が科学書を扱うところではないので、すぐに疑問も感じないのは仕方がないのかも知れないが、STAP論文の中味、実験の中味を知っていれば「おや」と思うところがいっぱいある。「光る精子」をめぐる記述や、「若山先生からChIPの実験は行ってもいいが、シーケンサーによる解析は行わないように」といわれて「疑問に持ちながらも」指示に従ったというような記述などだ(科学の部分は長くなってしまうので、また別の機会にふれたい)。
講談社には、ブルーバックスという科学書シリーズの編集部がある。社内のつてをたどっていけば、専門家に見てもらうこともできただろう。なぜ、それをしなかったのか。
この本の担当編集者は、ろくに仕事をしていなかった、というのが私の印象だが、一方で「ここは手を入れたのだろうな」と勘ぐりたくなる箇所もある。メディアスクラムの章だ。彼女の感じた恐怖と理不尽さがよく伝わってくる章で、NHKや毎日新聞、週刊文春、週刊新潮などが出てくる。私が勘ぐっているのは、なぜここに講談社のFRIDAYがないのか、という点だ。先日、警察が彼女に任意の事情聴取を求めたというニュースが流れたが、その発端は、彼女が刑事告発されたことにある(最終的な告発書では、被疑者不明となった)。その告発者に取材した記事を載せたのはFRIDAYだった。告発者の言い分を丸々紹介する記事で、あの記事が(そして告発されるという事態が)彼女にダメージを与えていないとは、考えにくい。
講談社の社員である担当編集者が、自社のFRIDAYの記事に関する記述だけには手を入れたというのは、まぁ私の妄想かも知れない。しかし、この本の刊行以来、いろいろが動き出したのは事実で、それが彼女にとって好ましい方向であるかは疑問だ。(※当初、誤って「好ましくない方向」としていたのを「好ましい方向」に訂正しました。2月28日11時30分頃)
Harukoと名前の書いてあるテラトーマ試料に実験では使わなかったはずのES細胞や大人のマウスの腸が入り込んでいた点など、明らかにおかしい点にはほとんど触れず、その一方で、「全方位を敵に回す」記述をし、あたかも若山氏が混入の犯人であるかのような記述をすれば、そういう流れになるのも仕方がない。
なぜ、彼女があのような書き方をするのを止めなかったのか。なぜ、あのまま発売をしてしまったのか。この編集者は著者を守らずに、さらし者にしたのだ。
※ご指摘を受け、1カ所「和歌や詩」となっていたのを「若山氏」に修正しました。大変失礼いたしました。(2016年2月27日22時頃)