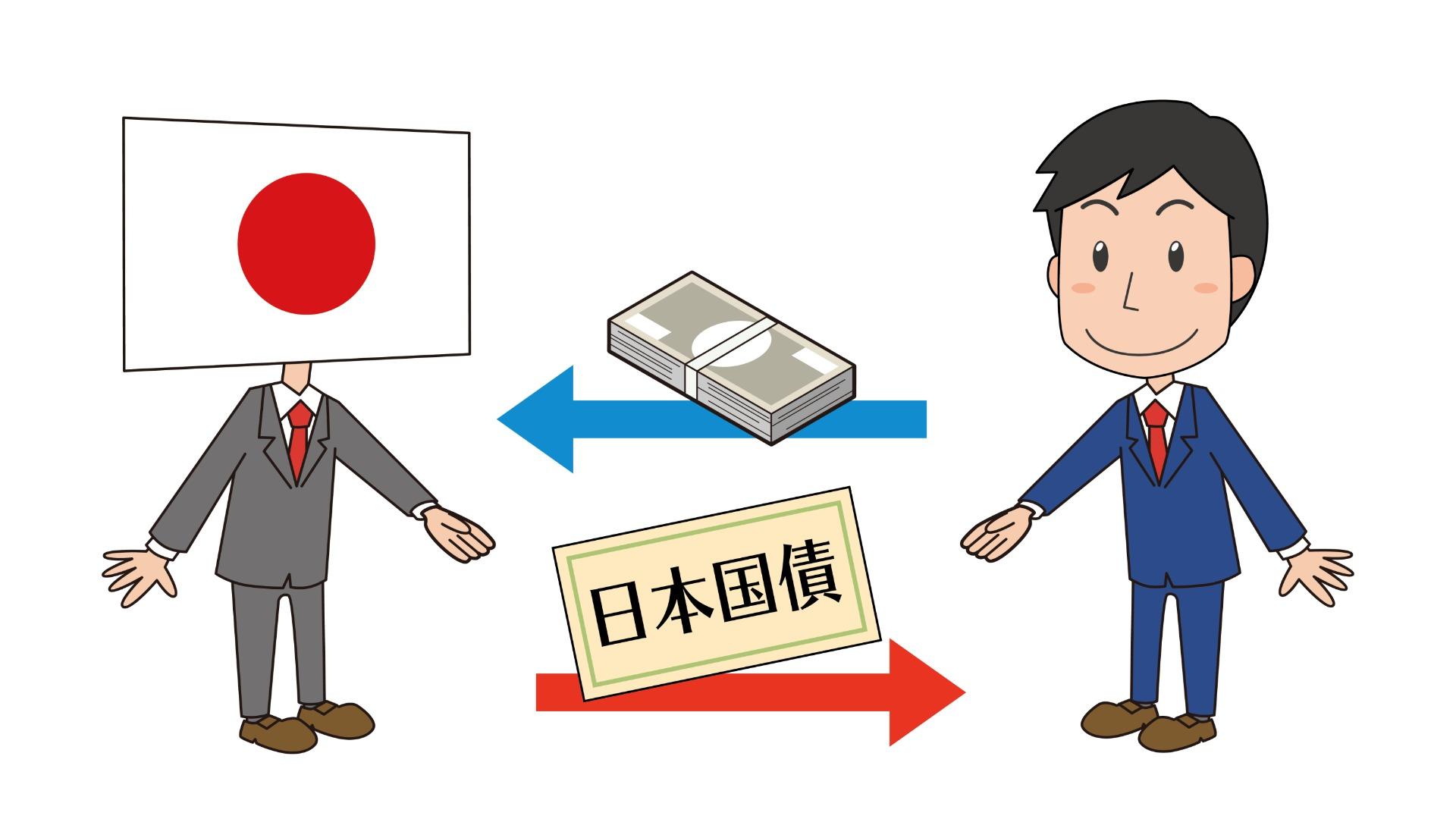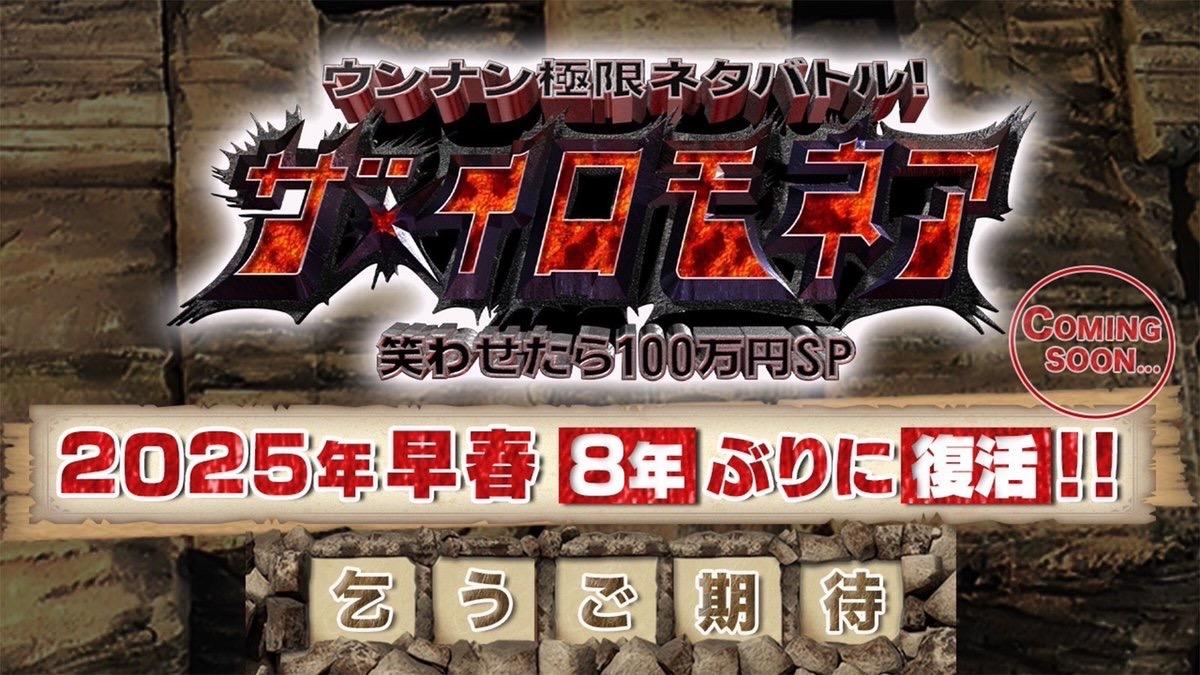ネットと新聞、広告市場規模はどちらが大きいか
メディアとして飛躍的に拡大を続けるインターネット、そして勢いを減じ規模を縮小していると評せざるを得ない新聞。この両者は広告媒体としての市場規模の観点で眺めると、この数年の間に立ち位置を逆転する関係にある。次以降のグラフは経済産業省が定期的に公開している「特定サービス産業動態統計調査」の値を基にしたものだが、直近発表分の2013年9月では4大従来メディア(新聞、雑誌、テレビ、ラジオ)とインターネット広告で比較をすると、トップはテレビ、次いでインターネット広告、そして新聞の順位となっており、広告市場規模では新聞はインターネットに及ばないポジションについてしまっている。
メディアの立ち位置の変化を推し量る、この新聞とインターネットの広告費のここ数年の動向について状況を確認していく。
同調査で「インターネット広告」の項目が個別に設けられたのは2006年1月。それ以前は他の項目に分散計上されていた。そこで2006年1月以降について新聞とネットの動向を一つにまとめたのが次のグラフ。
インターネット広告は2009年まではじわじわと、2010年以降は上下変動幅を大きくしつつ、上げ幅そのものは拡大する流れ。そしてこの1年ほどの間は再び上昇幅を縮小し、再びゆっくりと、しかし確実に規模の拡大を続けている。
一方、新聞広告は静かに減退。2010年に入るとようやく下げ止まったものの、低迷傾向は継続し、さらに時折大きな下げを見せる。「新聞の推定購読者数の推移」などでも解説している通り、新聞の購読性向は支持が厚い高齢者層ですら減退する動きを示しており、今後さらに下落する可能性は高い。
新聞は下げ、インターネットは上げとの動きが継続し、現時点で何度となく両者がクロスを続け、そして今年に入ってからはインターネット広告が新聞を上回る機会が多々生じている。そこで「インターネット広告」から「新聞広告費」を差し引いた結果の推移をグラフ化した。この値がプラスの場合、「インターネット広告」は「新聞広告費」を上回っていることになる。青い線が薄い赤の領域(マイナス)から抜き出ている月が、「インターネット広告」優勢の月となる。
現時点で二者間の立ち位置が逆転し、インターネット広告が新聞の広告を上回った月は2011年3月が初めて。以降、全部で18か月分(2013年9月分まで)。2013年に入ると2月以降は継続してインターネットの優勢が続いている。1月は新聞が約45億円の優勢だったが、直近ではこれが最後の新聞優勢の月となっている。7月は両者の差が6.3億円にまで縮まったが、インターネットが優勢には違いない。
少なくとも昨今では、「従来型4マスとインターネット」という仕切りに限れば、「広告市場規模で比較してテレビの次に来るのは新聞では無く、インターネット広告」という状況は、固定化されつつある。
新聞広告は選挙期間など、特定の時節イベントで大きく跳ねる傾向がある。またインターネット広告は月による変動が大きいことが経験則から確認されている(それだけ柔軟性が高いことをも意味するのだが)。今後何らかのきっかけで短期間「新聞広告>>インターネット広告」という月が生じるかもしれないが、大勢に変化は無く、この状況は継続していくことになる。
そして広告費が概してメディアの影響力、拡散力と深い関係にあることを考えれば(影響力の無いメディアに広告を出す酔狂なスポンサーはさほど多くない)、この広告費の状況・立ち位置は、ほぼそのまま双方メディアの影響力の位置関係と等しいと見ても良いだろう。
■関連記事: