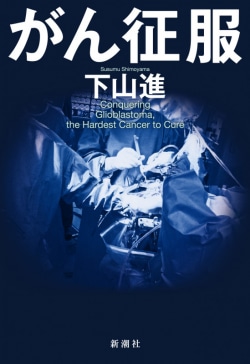平均余命15カ月……標準療法では治せない最凶のがん「膠芽腫」に対抗する3つの最新治療とは?(レビュー)
「がんvs.人間」の最前線に迫った『がん征服』(新潮社)が刊行された。 平均余命は15カ月……標準療法では治せない「最凶のがん」がある。悪性脳腫瘍の「膠芽腫」だ。 手術や抗がん剤、放射線では治すことができず、未だに効果的な治療法が見つかっていない。 この膠芽腫に挑む研究者たちがいる。原子炉・加速器を使うBNCT、楽天の三木谷浩史が旗を振る光免疫療法、そして「世界最高のがん治療」と礼賛されるウイルス療法はいまどこまで進んでいるのか?
仲野徹・評「がん治療の最前線で闘う三人の日本人研究者」
基礎医学研究に長年従事していたこともあって、医学ノンフィクションには尋常ならざる興味がある。欧米で出版される作品には、医学的レベルの高さに驚かされるものも少なくない。だが、日本には残念ながら、それらに伍するようなものはあまり見あたらない。おそらく大きな壁は二つある。まずは論文読解だ。数多くの原著論文を読みこむのは、ネイティブではない日本人にとっては、よほど専門知識がないと容易いことではない。もうひとつは、インタビュー。執筆のために、数多くの関係者――通常その多くは日本語が通じない――から詳細な話を聞き出す労力は膨大だ。 しかし、この本の著者である下山進の『アルツハイマー征服』(角川文庫)はこれら二つの壁を打ち破った快作である。20年にもおよぶ綿密な取材に基づいた内容は、欧米の一流医学ノンフィクションに決して引けを取らない。それどころか、日本での遺伝性アルツハイマー病の研究についての詳細な記述もあるという点で、外国ものを凌駕さえしていた。その下山が次に選んだテーマは膠芽腫であった。 膠芽腫は進行度が速く、極めて悪性度の高い、いや、最も悪性度が高いと言っていい脳腫瘍だ。標準療法としては、まず手術で腫瘍をできるだけ摘出し、抗がん剤による治療と放射線治療をおこなう。その5年生存率はわずか10%、平均余命は15ヵ月でしかない。がん治療は過去数十年の間に著しく進歩したが、膠芽腫は未だに効果的な治療法がない悪性腫瘍なのだ。『がん征服』は、膠芽腫の新しい治療法開発に挑む日本人研究者三人の物語である。 その三人とは、大阪医科薬科大学の宮武伸一、NIH(アメリカ国立衛生研究所)の小林久隆、東京大学医科学研究所の藤堂具紀だ。それぞれが取り組んでいるのは、中性子を利用した「ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)」、独自に開発した光反応性の化合物を用いた光免疫療法、そして、がん細胞でのみ複製できて免疫能をも賦活する遺伝子組み換えウイルスG47Δによる治療である。「挑む」と書いたが、膠芽腫における治療実績がすでにあるのはBNCTとG47Δで、光免疫療法は検討中といった段階だ。 G47Δはすでに膠芽腫の治療法として承認を受けている。と書くと、医薬品の承認制度を知る人は、ランダム化比較試験であるフェーズ3の治験を経たと考えるだろう。しかし、G47Δではフェーズ3治験はおこなわれていない。それどころかフェーズ2の被験者はわずか19名で、驚いたことにPMDA(医薬品医療機器総合機構)の判断では治験の主要項目も副次的評価項目のいずれをも達成していない。なぜそのような治療法が承認されたのか? それは、「再生医療等製品」に限り、有効であると「推定」できれば「条件及び期限付き承認」できる制度があるからだ。再生医療ではないG47Δ療法がどうしてそのような承認を受けることができたのか、そして、どうして承認後も症例数が伸び悩んでいるかの謎が詳細に説明されていく。 まったく同じ条件ではないために正確な比較は難しいが、少なくとも見かけ上は、BNCTとG47Δのフェーズ2での治療成績は似かよっている。しかし、どうまげてもBNCTは再生医療等製品に該当しえないため、承認にはフェーズ3による治験が必須である。やればいいではないかと思われるかもしれないが、そのためには概算で40億円もの費用が必要だ。他にも実施が困難な理由がいくつかある。適用される制度が違うのだからしかたがないと言ってしまえばそれまでだが、どうにも釈然としない不公平感が漂いはしまいか。 膠芽腫ではなく局所進行再発頭頸部がんに対しては、BNCTも光免疫療法もフェーズ2で著効があったおかげで「条件付き早期承認」を受けている。しかし、両者には資金力で大きな違いがある。光免疫療法は、広く報道されているように、楽天の三木谷浩史社長が400億円もの強力なサポートをおこなっている。小林は光免疫療法による膠芽腫の治験をやってみればと勧めるが、「戦線をいきなり拡大することはできない」という理由で三木谷は興味を示さない。いつか小林は三木谷を説得することができるのだろうか。 いずれ膠芽腫の画期的な治療法が開発されるのかどうか。それは、これら三つの治療法の延長線上にあるのか、あるいは、まったく違ったアプローチによるのか。現時点ではなんとも判断することはできない。医療の進歩は一本道ではないためだ。しかし、それこそが科学としての医学の特性であり真骨頂なのである。 [レビュアー]仲野徹(生命科学者/大阪大学名誉教授) 1957年大阪・千林生まれ。大阪大学医学部医学科卒業後、内科医から研究の道へ。ドイツ留学、京都大学医学部講師、大阪大学微生物病研究所教授を経て、2004年から大阪大学大学院医学系研究科病理学の教授を務める。2022年に退官し、隠居の道へ。2012年日本医師会医学賞を受賞。著書に『エピジェネティクス』(岩波新書)、『こわいもの知らずの病理学講義』(晶文社)、『仲野教授の この座右の銘が効きまっせ!』(ミシマ社)など多数。 協力:新潮社 新潮社 波 Book Bang編集部 新潮社
新潮社