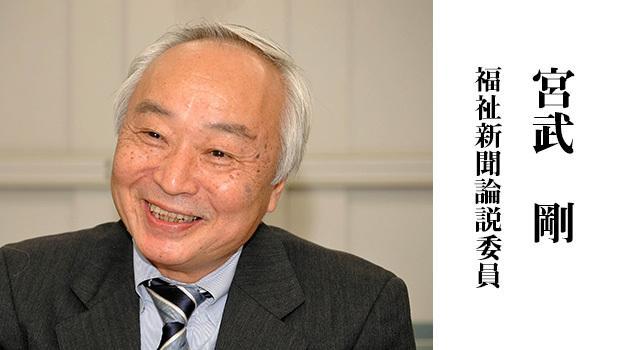非現実な「低負担高福祉」 将来世代が背負う「年金」 宮武剛 福祉新聞論説委員
年金制度を5年ごとに点検する2024年「財政検証」はやや好転した。高成長からゼロ成長まで、どの想定でも当面は堅守すべき所得代替率50%以上を守れる(現役男性の平均手取り収入に対するモデル年金の割合、現在61・2%)。 主因は女性、高齢者、外国人らの就労で支え手が増えたこと。今年の改正も担い手を増やす方策が焦点だ。自らの年金を得たい主婦ら短時間労働者、待遇や老後の安定を望む非正規労働者らをより多く迎え入れたい。 24年10月から主婦パートらは従業員51人以上の企業で、週に20時間以上働き、年収106万円以上であれば厚生年金と健康保険の加入対象になった。 さらに厚労省は、賃金要件と企業規模要件の撤廃を目指す。従業員5人以上の飲食、理美容、宿泊などの個人事業の全面加入も狙う(計200万人規模)。 労使折半の保険料はどうするか。一定収入までは使用者側に折半以上の保険料を課すなどが検討中。労使ともに戸惑いは残るが、勤め人でありながら勤め人扱いされなかった人々の権利向上は意義深い。 話題の「103万円の壁」は、所得税発生の最初の「階段」で、年1万円増で税500円。むしろ103万円超で妻手当を止める企業慣行や、バイト学生の親の特定扶養控除が外れる税制が「壁」だろう。 国民民主党は税務の怠慢を突いたが、178万円までの引き上げ案では、税収を毎年度7~8兆円激減させる。「手取り収入増で消費も企業業績も上がり税収も増える」(玉木雄一郎代表)。だが、内閣府試算は名目国内総生産1%相当(6兆1000万円)の大減税で、1年目は同0・2%(1兆3000万円)増にとどまる。 もともと「低負担」で「高福祉」を実現するマジックはない。 社会保障制度と税制は絡み合い、各種の「壁」は一体改革の必要性を教える。 「財政検証」の暗転部分は基礎年金の大幅低下だ。賃金・物価の伸び以下に年金増を抑える「マクロ経済スライド」は、厚生年金の報酬比例(2階部分)では機能した。 一方、基礎年金(制度共通の1階部分)は賃金下落時も物価に応じ改定され、抑え込めなかった(ルール改定済み)。 この先、自営業者、非正規労働者ら基礎年金だけの人々は減額が延々と続き、老後の生活苦につながる。 その対策で、当初は国民年金の加入期間20~60歳を65歳まで延長する案が有力だった。年金は確実に上積みできる。納めにくい人々は保険料を減免される(減免の割合に応じて給付に国庫負担が付く)。ただし、5年延長に伴う基礎年金の国庫負担は将来、年1兆円増と推定された。 より長く働いて老後に備える良策のはずだが、政府・厚労省は「負担増」の猛反発を恐れて断念した。 残るは「マクロ経済スライド調整期間の一致」だ。厚生年金の抑制期間を10年延ばし、基礎年金の抑制は逆に21年短縮し、36年度で同時に調整を終える。そのため、厚生年金の積立金65兆円を基礎年金に回す。厚生年金は減額が10年延長され、基礎年金は現状推移より3割底上げされる。 基礎年金だけで成り立つ国民年金の危機回避策だが、個別運営の厚生年金から積立金を回す〝禁じ手〟へ踏み込む是非は国会でも論議してほしい。 保険料の追加負担などはない代わり、基礎年金を底上げするに連れ、その半分に充てる国庫負担も年々増える。その額は60年度で2兆円、70年度で最大2兆6000万円(100年間で試算69兆円)に上る。 つまり、将来の年金水準は、現状推移より上がるが、その負担は将来世代が背負う事実をもっと明確に伝えるべきだ。しかも、この財源をどう調達するのか。政府は今や〝恒例〟の具体策なしで突っ走る構えだ。 09年、基礎年金の国庫負担割合は3分の1から2分の1に引き上げられた。必要な追加財源に目途をつけたのは12年、当時の野田佳彦首相が率いた旧民主党と自民、公明の三党合意だった(社会保障・税の一体改革と消費税10%アップ)。 現在の政治状況に照らすなら、石破茂政権が野田党首の立憲民主党と政策連携で財源確保を図る光景だ。 「初夢」は壮大な方が楽しい。 みやたけ・ごう 1943年、京都市生まれ。68年毎日新聞社入社。論説副委員長を経て埼玉県立大教授、目白大大学院教授。社会保障論を専攻し、社会保障審議会、財政制度等審議会、社会保障制度改革国民会議などの委員も務めた。