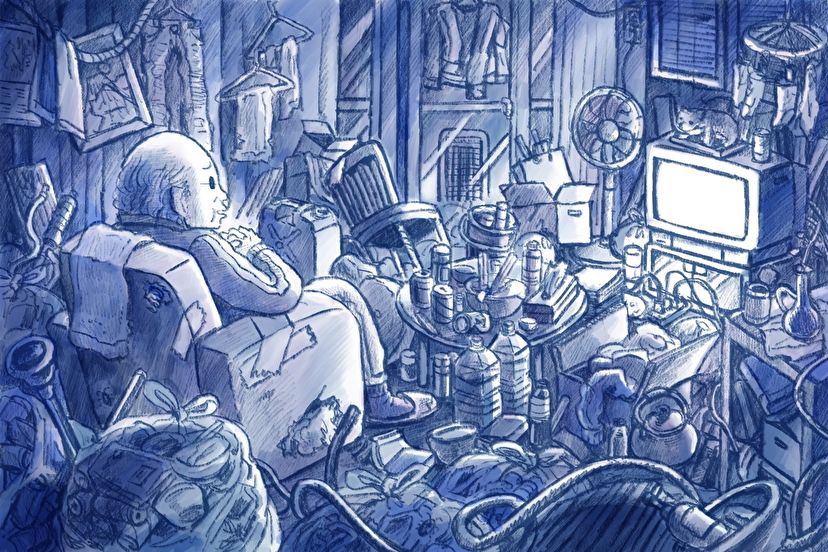斜陽と言われて久しい林業の世界に次々と新機軸を打ち出し、注目されている林業会社がある。舞台は東京の森。率いるのは会社勤めを経て業界に飛び込んだ39歳だ。
「林業の未来は、明るいですよ」
東京都檜原村に拠点を構える「東京チェンソーズ」代表の青木亮輔は、こともなげにそう言って笑う。創業から10年、業績は堅調だ。過疎化が進む村と底を打った林業の状況をプラスにとらえ、その先にある未来を見据えている。
(ライター清田麻衣子/Yahoo!ニュース編集部)
青木亮輔:「東京チェンソーズ」代表
青木が現在手がけているのは、自社で購入した10ヘクタールの山林に苗木を植え、都市部の住民に所有してもらうプロジェクト。その名も「東京美林倶楽部」だ。入会金5万円で年会費1,000円。参加者はまず3本の苗木を植え、木が育つまで定期的に手入れに訪れる。手入れ時は木に親しむイベントも開催される。そうやって木に触れ合いながら成長過程を楽しみ、30年後、自分の植えた木がある程度使える太さに育ったら、2本は間伐し、加工して参加者に渡す。「残りの1本は山に残すこととで、未来の人に繋いでもらうんです」

右手が東京美林倶楽部で植え付けをした後。さらに右手に今後の予定地が広がる
ほかにも「檜原村おもちゃビレッジ構想」では、檜原の木を使って木のおもちゃを作り、檜原村におもちゃ産業を興すことを目指している。人口の3分の2がおもちゃづくりに携わっているドイツのザイフェン村がヒントだ。
「檜原の木を使って木のおもちゃを作り、日本の木のおもちゃといえば檜原村、というようにしたいんです」と目を輝かせる。檜原の木と伝統工法を使った家造りのプロジェクトも進行中だ。
「地下足袋を履く仕事がしたかった」
青木に林業の仕事を始めた動機をたずねて肩透かしを食らった。東京農業大学で林学を学び、探検部で秘境を歩き回った青木は、1年間、出版社で営業を経験した後、檜原村で林業の世界に飛び込んだ。

東京チェンソーズ代表取締役の青木亮輔
「地下足袋を履く仕事がしたかったんです。高齢化が進む土地だから、自分みたいな若いのが行ったらチヤホヤしてもらえるんじゃないかなと思って」
青木は2001年、農業でいう「農協」のような共同組合である森林組合の緊急雇用職員として林業の世界に入った。探検部で培った体力を生かして作業面積を増やし、やがて正職員に採用された。「地下足袋を履く仕事」は楽しかった。
だが、いくら作業効率を上げても日給制で残業代も出ない。同年代の仲間とともに森林組合に待遇改善を求めたが認められなかった。与えられた山仕事や森林整備をこなすことに終始していては、林業に未来はないと次第に感じるようになった。

地下足袋は山での動きやすさが格段に違う
そこで独立し、2006年に「東京チェンソーズ」を立ち上げた。4人での船出。創業当時は森林組合の下請け仕事が中心だったが、2010年からは元請けとなって、東京都や自治体と直接仕事をするようになる。
初年度2千万円からスタートした売上高は順調に伸び、2014年度には約1億円に達した。正社員は8人、アルバイト2人と会社の規模も大きくなった。
60年前に植えた木が「使える木」になった
「子供の頃、釣りが好きだったんです。川にも湖にもここが釣れるという“ポイント”があって、そういう場所は僕にとって宝物でした。でもあるときポイントの岸がコンクリートで固められていた。また大学時代、探検部でメコン川の終着地を目指して行くと、ダムの建設途中だったということもありました。僕らはそういう状況に直面した世代でした」

東京チェンソーズの事務所は檜原村の山間にある
1976年生まれの青木が少年〜青年期を過ごした80〜90年代、下り坂だった日本の林業は、完全に冬の時代を迎えていた。森林が国土の3分の2を占める日本は、実は世界有数の森林保有国である。だが1950年代に90%以上だった木材自給率は下降の一途を辿り、2000年には20%を切った。
木は、植えられてから木材として使えるようになるまで約60年かかる。林業事業者は、春は苗木を植え、夏は苗木の周りの草を刈り、秋から冬にかけて育った木の余計な枝を切り落とし、出荷できる太さになると伐採する。季節ごとの作業を繰り返し、長い年月をかけて山を循環させる。林業は、ロマンのある仕事であると同時に、短期的な利益を求めると立ち行かなくなってしまう、非常に難しい仕事でもある。だが日本では戦後長きにわたり、この循環が断ち切られてきた。

木が倒れる方向を計算してチェンソーを当てる
高度経済成長期、1960年代前半の木材生産量は現在のおよそ3倍以上だった。需要が伸びた木材価格は高騰し、急激に過度な伐採を行って日本の山林は各地でハゲ山になった。そして60年間、日本の生産量は下がり、安い外材で需要をまかなうことで、総じて木材価格も下がった。
だが、いままさに、60年前に植えた木が「使える木」の太さに育ってきた。
「林業の最大の魅力は再生可能なことです。それがいっとき途絶えてしまった。ところがいま、循環が戻ってきているんです」

約60年前の林業者が植えた木が、現在使える木になった
地元に溶け込む
木の成長のみならず、現在、林業には新規事業者が参入しやすい状況が生まれているという。
「“林業”というフィールドを探検しているイメージです。林業には鎖国のような時代がありました。僕はその鎖国の地に入り込んで、魅力を人に伝えて状況を変えていくような役割をしたいと思っています」
東京都の多摩地域では2002年、過疎化と林業の衰退に伴い、地域と密接に関わっていた地域ごとの森林組合が「東京都森林組合」という大きな組織体となった。地域の強固な連帯は薄まり、都会から来た若者が始めたベンチャー企業も受け入れられやすい素地ができつつあった。

東京チェンソーズの事務所は、古民家を利用している
「東京チェンソーズ」が拠点とする檜原村は人口約2500人、10年で約1000人が村外に流出した。過疎化が進む中で、村に移住してきた青木ら東京チェンソーズの若いメンバーたちは待ちに待った「おまつり」要員だった。檜原村には代々受け継がれてきた能や神楽、獅子舞など、20を超える集落にそれぞれ催事があり、うち3つが無形民俗文化財に指定されている。また地元の人の歓待は、この土地に移住し馴染みたいと考えていたメンバーの喜びでもあった。
「東京の林業」だからできること
青木は、林業の理念、理想を自分の立脚点としつつも、つねに本気で、現実的に展望を抱ける林業を目指している。公共事業である森林管理には補助金がでる。だがその補助金によって守られながら一律に安い木材価格で勝負している現状に、林業の発展はないと青木は考える。
「山に暮らしていてお金を使わないから、また“いい仕事”をしているから稼がなくていいと思われるかもしれません。でも365日24時間山にいるわけではない。町に暮らしている友達と旅行に行ったら対等です。山で林業をやっていても、収益はあげなくてはならない。それには国の方針に従っているだけではダメなんです」

“いい仕事”に溺れず世の中も自分たちも良くなるのが青木の仕事観
現在、補助金がでる森林の保全の仕事は東京チェンソーズの主軸だが、それを青木は《林業サービス》だと言い切る。
「《林業》とは、木を生産して販売することです。《業=なりわい》というからには、きちっと収益をあげなくてはならない。森の保全に加え、僕らはアイディアを絞って《林業》をやっていきたいんです」
打開策を練っていた青木のヒントになったのは、都政モニターアンケートで、東京都民は木材生産よりも環境問題対策や森林体験への期待値がずっと高いことを知ったことだった。また、テレビで活動を見た高齢の女性から、幼い頃から愛してきた東京の山を守る東京チェンソーズに出資したいという申し出をもらったことも後押しした。東京の林業だからこそできることがある。それが、補助金からの脱却を目指した現在のさまざまなプロジェクトにつながっている。
檜原村をはじめ、日本の多くの山では切り出した木を運ぶための山道の整備が不十分で、せっかく育った木を外に出すことすら困難な状況だ。東京チェンソーズでは現在、林業の盛んな吉野の方法を学び、山道づくりを急ぐ。

この道があることで山林は利用可能な「生きた山」になる
この日青木は、できたばかりの山道を通り、スタッフとともに伐採の現場に案内してくれた。
「この道ができたことはとても大きな一歩なんです。いままで死んでいた山が、“在庫の山”になった」
青木にそう言われて林を見上げると、自然と人間の密接で理想的なあり方が目の前に広がっているように見えた。

山仕事のユニフォームを着た青木
撮影=田代一倫
取材・文=清田麻衣子
連載「未来を拓く」では、先頭に立って課題に取り組み未来を切り拓く各界の人物をとりあげます。