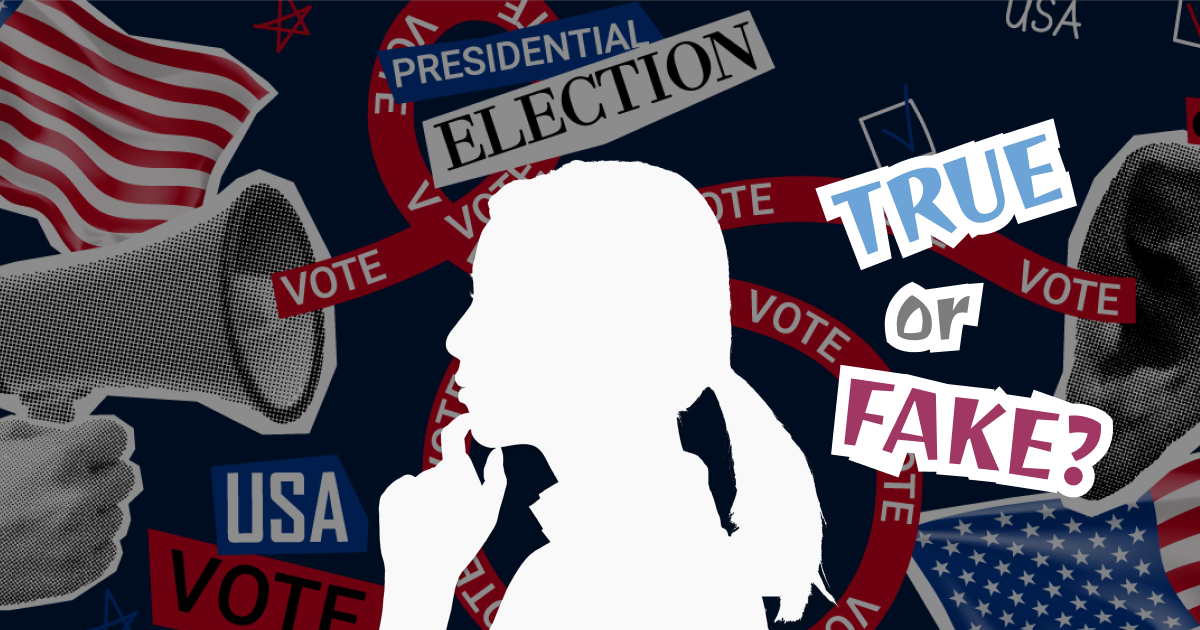知ることは関わること――「2019年ノンフィクション本大賞」をブレイディみかこさんの著作が受賞

11月6日、Yahoo!ニュース|本屋大賞「2019年 ノンフィクション本大賞」の授賞式がヤフー内にあるLODGE(東京・千代田区)で行われました。大賞作品は、イギリス在住のブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)に決まりました。ブレイディさんが取材対象に選んだのは、自身の息子さんです。彼が進学したのは「元底辺中学校」。貧困、人種差別などの社会問題と隣り合わせの場所で、息子さんは現実と向き合い、成長をとげていきます。ブレイディさんの授賞式スピーチに加え、昨年『極夜行』(文藝春秋)で大賞を受賞した角幡唯介さんとのトークセッションをお届けします。
構成・文:岡本俊浩(Yahoo!ニュース 特集編集部)
写真:高橋宗正
ブレイディみかこさん受賞の言葉【要約】

ブレイディみかこさん(保育士、ライター)
後ろに(他の)候補作が並んでいますけど、「ノンフィクション」という従来のジャンルでいうと、わたしの作品は王道ではなくって、こういう作品もノンフィクションって呼んでいいんだよっていうような位置にある作品だと思うんですね。
それを書店さんが、投票して、こういう賞をわたしに、この本に与えてくださったということは、書店員さんたちの、恐らくノンフィクションというジャンルを広げて、刷新していこうという気持ちの表れではないかと。「攻めているな」と思ったんですよ。わたしもこれに安住せず、ノンフィクションって普通こういう書き方をするよねとか、固定概念を壊していくものを書いていきたいと思います。
この本は、出る前に書店さんたちにうかがったんですよね。ゲラを読んでくださいと。そしたらものすごい数の書店員さんが手を挙げてくださって。……前で、営業担当が泣いているんですけど。新潮社の「ぼくイエ」チームっていう熱いチームがあるんですよ。みんなそれを読んで泣いたりしましたし、わたしも感想を届けてもらって、その気になったんですよ。最初から、書店員さんに背中を押していただいた本なので、この賞をいただけて、感無量です。ありがとうございます。

新潮社の営業担当さん。ブレイディさんのスピーチ中、感極まって落涙
トークセッション ブレイディみかこさん×角幡唯介さん
トークセッションも行われました。内容の一部を掲載します。
やっぱり「照れ」はある
――最初に角幡さんにうかがいます。ブレイディさんの受賞作を読んで、どんな感想をお持ちになりましたか?

- 角幡
-
読んでいてなるほどなと思ったのは、「エンパシー」という言葉ですよね。「シンパシー」と「エンパシー」は違う。シンパシーは「同情心」だとか、言ってみれば感情であると。エンパシーっていうのはそうではなくて「能力」とあるんですよね。(他者に)共感するとか、自己移入とか、感情移入とか訳されるけども、自然から湧き出てくるものではなくて、能力なんだと。
ぼくはね、「努力」だとも思ったんですよ。努力しないと湧き上がってこないものであって、相手の立場に立って理解する能力。息子さんは作品のなかでエンパシー能力を高めていくわけです。いつの間にかお母さんを追い抜いちゃっていて、最後はお母さんが教えてもらうみたいなところがありますよね。
ところで、本のなかで「息子」や「配偶者」と書いていますけど、固有名詞を使いませんよね。なぜなんですか。

- ブレイディ
-
(角幡さんは)娘さんの名前は出されるんですか?

- 角幡
-
ぼくは出しています。本(『探検家とペネロペちゃん』/幻冬舎)で「ペネロペちゃん」で通してはいるものの、本名は出していますね。

- ブレイディ
-
わたしが出さないって最初から決めていたのは……プライバシーの問題もあるから本名を出したくないし、ただ、やっぱり「照れ」なのかな(笑い)。それに「配偶者」。普通は使わない言葉ですよね。

- 角幡
-
ええ、「夫」とか書きますよね。

- ブレイディ
-
配偶者って、そもそも「リーガルな」言葉じゃないですか。だからこれ使うのはどうなのかっていうのはね、ちょっとあったところなんですよ。わたしは他の作品で、「つれあい」とか表現していて、そこで「配偶者」っていうと、くだけた文体の本ですから、固い印象がユーモラスになるかなって思ったんですよ。

角幡唯介さん(ノンフィクション作家、探検家)
地べたで成長する

- 角幡
-
エンパシー能力。イギリスではこういったものを育むための教育があるんですか?

- ブレイディ
-
はい。「シチズンシップ・エデュケーション」というのがあって、日本だと「公民」とか? わたしは聞いた話しかわからないんですけど、(日本の場合)議会の仕組みはどうなっているとか、そういうことは教わるんだけど、現在社会で起きていることをみんなで議論したりとか、先生が意見を述べてみんなに考えさせるとかはないんじゃないでしょうか。

- 角幡
-
そうなんですよ。「元底辺中学校」じゃないですけど、息子さんの通っている学校で移民の方が多いとか、LGBTの方が多いとか、いろんな属性の人がぶつかりあって、だからこそ他者を理解しようと努力もする。でも、娘が来年小学生になるんですけど、あまりにも……「健全」なわけですよ。ぼくはいま鎌倉に住んでいるんですけど、「超健全」で、こんな健全なところにいて、子どもの教育によくないんじゃないか、と思うぐらい「健全」なんですよ。みんな、同じような環境で育ったいい子ばかり。

- ブレイディ
-
教育ってすごく大事じゃないですか。(今回の本は)息子の1年半をカバーしているんですけど、あんなに短い間でも成長しているんですよ。元底辺中学校に入ったら、それこそ差別を体験したし、している子もいるし、格差もすごくあるし、そういうなかで「もまれる」っていうか、それこそ頭じゃなくて身体でぶつかっていくじゃないですか。机上じゃなくて、ほんとに地べたで体験していて……成長につながっているっていうか。

- 角幡
-
この本は、息子と親の物語として買う人が多いと思うんですよ。そのうえでいろいろと賛同の声が上がるっていうのは、考え方に共鳴している人が多いわけじゃないですか。いまの親世代って、他者をどう理解するのかっていうことに、すごい関心があると思うんですよ。だけど、それがなかなかね、国の教育とかに反映されていないというのもある。(この本が)もっと多くの人に読まれると、変わってくるんじゃないかと思いますね。
関わるために扉を開けよう
――多様性をめぐって、ブレイディさんの受賞作にはこういったくだりがあります。
「多様性っていうやつは物事をややこしくするし、喧嘩や衝突も絶えないし、そりゃないほうが楽よ」(ブレイディさん)
「楽じゃないものが、どうしていいの?」(息子)
「楽ばっかりしていると、無知になるから」(ブレイディさん)
一方、角幡さんは昨年の授賞式スピーチでこうお話ししています。
「検索したらすぐ答えが出てくることに慣れきってしまって、情報とか事実を手に入れるためにはものすごくリスクと労力をかけなきゃいけないことがわかんなくなってきている。見えなくなってきている。そこに対する想像力が働かなくなってきている」
お2人は近いことを話しているように思えます。いま、「知る」ということをどう受け止めたらよいのか。意見交換をしていただけますか。

- 角幡
-
この本の「はじめに」だったかと思いますが、(ブレイディさんは)子どもができるまでは子どもなんか大嫌い――というようなことを書かれていましたけど。

- ブレイディ
-
そうなんですよね(笑い)。

- 角幡
-
子ども、子育てなんかが典型的だと思うんですけど、ぼくは「知る」って「関わる」ことなんじゃないかと思うんです。人は何かと関わることによって関係性が生まれる。いままでは、関わらないと何かをわかるなんてことはできなかった。けれども、関わることってむちゃくちゃ面倒くさいじゃないですか。いまではテクノロジーが発達してきて、関わる必要がなくなってきている。面倒だから避けようと思えば、避けられるようになってきている。そこで文字列だけの情報で理解したつもりになる。これはね、危ないことじゃないかと思うんですよ。この本もまさに、関わることがテーマ。わけのわかんない混沌(とん)とした世界。そこに関わることで息子さんは強靭(じん)になっていった。そう考えると自分で扉を広げていかなきゃいけないのかなと。

- ブレイディ
-
わたしがあの場面で言った「無知」っていうのは、どこからきているのかなって思うのは、イギリスがEU離脱を決め、社会の分断が取り沙汰されていたころでした。たとえば「排外主義」。よく言われたのが「排外主義の大元には『無知』がある。それを恐怖、恐れという火でたきつけると抽出されるのが憎悪であり、ヘイトなんだよ」っていうのがあるんですよ。
誰かのことをよく知らないから……「あの人たちのせいでこうなっているよ」と言われると信じちゃう。それで「あの人たちがいなければ」という考え方になるわけですよね。でも、知ってさえいれば、「知っているけど、そんなことないよ」と言えるわけですよね。だから、みんなで無知をなくしていかないといけない。
そこで「関わる」ことが出てきます。うちの息子も、毎日の生活で(他者と)関わって、関わらないと生きていけないから、大変だけどそれで成長していくわけですよね。大人になっていく。さきほどのお話で、「強靭」という言葉が出ましたけど、無知な人って弱いんですよ。どっかから言われると行ってしまう。行ってはいけない方向に行ってしまう。だから、「強くなることは知ること」ですよね。

- 角幡
-
相手も自分も同じだという「地続き感」が持てるかどうかは、大切なことなんじゃないかと。そのときに身体で、「身体性」をもってぶつかっていけるかどうか。いざこざを通じて理解できるってことも、あると思うんですよね。

- ブレイディ
-
身体性ですよね。わたしも身体でわかっていかないと、机の上だけでわかりたくないっていうところがあります。だから、角幡さんも冒険をやってらっしゃるんだと思うし。
――トークセッションも残りわずかになってきました。ブレイディさんにうかがいたいことがあります。今回の受賞作、息子さんは読んだのでしょうか?

- 角幡
-
あ、そこ、ぼくも聞きたかったんですよ。

- ブレイディ
-
読みました。で、いろいろと注文はつきますよね(笑い)。こういうところは気をつけて欲しいとか。この話は、まだ連載が「波」という(新潮社の)PR誌で続いているので、息子からの反応がどこまで内容に反映されるかどうかは企業秘密ということにしておきます。

- 角幡
-
息子さん、いまおいくつなんですか。

- ブレイディ
-
13歳です。

- 角幡
-
やばい時期ですよね。

- ブレイディ
-
そうなの。11歳から12歳って、プレ思春期だったし、これから思春期。素直に話してくれないかもしれない。そうなったらね、この話は終わるんですよ。

- 角幡
-
子どものことって、書きたくなる話だと思うんです。ただ、子どもの目があるから怖い、書けないっていうのはあるかもしれませんね。

- ブレイディ
-
それわかります。でも、書いちゃうんですよね。面白いから。
お問い合わせ先
このブログに関するお問い合わせについてはこちらへお願いいたします。