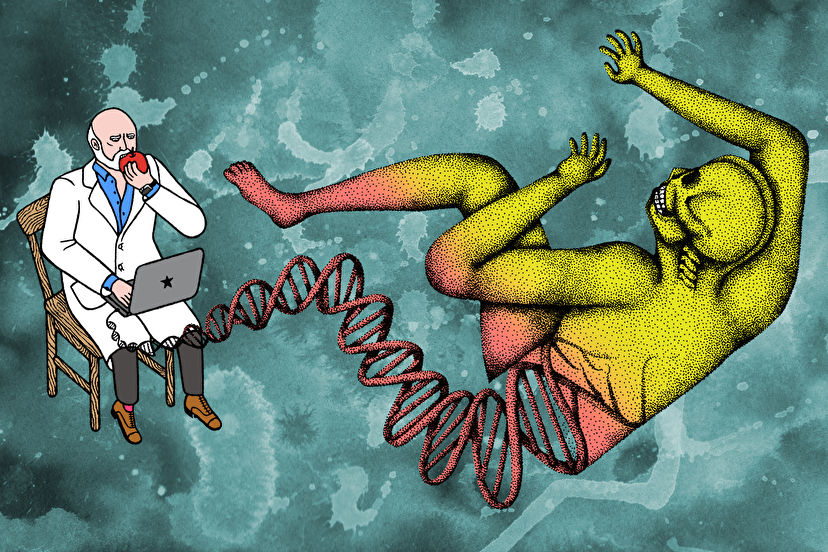辻村深月さん、若くしてエンタメ小説界の旗手になった小説家である。1980年生まれの38歳。2004年にメフィスト賞を受賞した『冷たい校舎の時は止まる』で鮮烈なデビューを飾り、32歳のとき『鍵のない夢を見る』で直木賞を受賞する。
華々しい受賞歴を持つ彼女にとっても、2018年本屋大賞を受賞した『かがみの孤城』は「自分の小説をどれか一冊、子供の頃の自分に手渡していいと言われたらこの小説にしたい」と語る会心の一作だ。
いったいなぜ? 作品に込めた思いを聞いた。(ライター・石戸諭/撮影・殿村誠士/Yahoo!ニュース 特集編集部)
ようやくたどり着いた「代表作」
この日、春らしい明るいピンクのワンピースに身を包んだ小説家は柔らかい笑みを浮かべながら語り出した。
「『代表作』って自分では決められないんですね。やっぱり、どの作品も一作一作、自分にとって大事な作品ですから。今回、本屋大賞をいただけたことで『かがみの孤城』が自分の代表作だって言えるようになると思うんです」
大きな賞の受賞作=代表作にはならないのがこの世界の常。自分自身の手応えが読者に届かない、あるいは完成度と読者の評価がずれることもある。
「直木賞は受賞後にすごく盛り上がりました。恩師からも手紙が届きましたし、これまでお世話になったいろんな人から連絡がきました。すごろくで例えれば、『上がり』って扱われ方をする。作家人生はこの先も続いていくのに、これでゴールなの?この先どうしたらいいの?と思っていました」
辻村さんが本屋大賞にノミネートされるようになったのは、2012年の直木賞受賞後からのことだ。彼女自身がこの賞に救われたという。
「そのおかげで、私はモチベーションが落ちなかった。直木賞を受賞しても終わりじゃない。代表作を書くんだって思えたんですね」
「もしも、中高生の自分に1冊だけ自分の書いた本を手渡せるとしたら、迷わず『かがみの孤城』に。この先、いろんなものを書くと思うけど、そこはずっと変わらない気がします。人生で一番楽しく本を読んでいた、中高生のときの私は『この作家、ちょっと展開マンネリかも』とか『前の作品が良かったね』とか平気で言っている不遜な読者でした。そんな彼女に『君は大人になったらこんなもの書くんだよ』って渡しても、きっと気に入って尊敬してもらえると思うんです」
人の心という繊細な「謎」
物語のあらすじはこうだ。
ある日、学校を長く休んでいる主人公の少女・安西こころの部屋の鏡が光り始める。手を伸ばすと、鏡の中に別の世界が広がっていた。主人公がたどり着いた先にあったのは、城のような建物。そこにいたのは、こころと同じように学校という場に馴染めなかった6人の中学生たちだった。
城を仕切っているのはオオカミのお面をつけた少女、自称「オオカミさま」である。オオカミさまは、彼らにこう告げる。城の中には、なんでも願いが叶う「願いの鍵」がある。それを見つけ出せば、何か一つ願いは叶うのだ、と。
鍵はいったいどこにあるのか。集まった7人は探し出すことができるのか——。舞台設定はファンタジー、鍵探しはミステリーの要素をふんだんに盛り込み、物語は動き出す。
表紙左に描かれた、オオカミのお面の少女が「オオカミさま」
小説の中で描かれる「謎」は鍵探しだけではない。
こころは、クラスの中心にいる真田美織たちが起こした決定的な出来事により学校を休むようになる。
こころがなぜ学校を休むに至ったのか。いったい何に傷ついてしまったのか。「不登校」や「いじめ」といった言葉を意識的に使わず、辻村さんは城に集まった少年少女の内面を丁寧に描き出す。
ストーリー展開、魅力的なキャラクターで読ませる王道のジュブナイル小説に、人の心という繊細な「謎」が織り込まれることで物語は深みを増していく。
「こころに起きたことを、一言でまとめてしまうと『クラスメートの女子が集団で家の前までやって来た』になります。だけど、それが彼女にとってどれだけ怖かったのか。彼女の人生にとってどれだけ決定的なことだったのか。簡単に『それはいじめだ』とか『ケンカだ』という言葉でまとめていいものではないんです」
小説の中で「いじめ」や「不登校」という言葉を多用すると「あぁメディアで報じられているあれでしょ」と受け取る読者もいるだろう、と辻村さんは考えた。「それで終わらせないために、こころに起きたこと、感じたことを丁寧に説明して、書こうと思いました」
複雑なことを複雑なまま書く
気をつけたのは、何かがあって学校を休むようになった子供を「かわいそうないじめの被害者」として扱わないことだという。
「周囲は気遣っているつもりでも、本人にとっては屈辱的なことかもしれない。そう扱うことが、かえって傷つけることになりかねないのです。本来、起きていることは一人ひとり違うはずなのに、わかったような気になる一言で括ってしまったら、中学生のリアルは見えてこないですよね。小説家の仕事は安易な名づけをすることではなくて、名づけられないものを、名づけられない形で、誰かに仮託して物語にすることだと思っています」
もし、小説の中で「いじめ」という言葉で起きた出来事を説明したら、こころが一人で抱え、押し殺していた恐怖心や嫌悪感は、物語からこぼれ落ちていってしまう。
550ページ超を費やして表現されたのは、エンタメ小説の枠組みを維持したまま、複雑なことを複雑なままに書くという挑戦だった。
「不登校する勇気」はなかった
果たして意図は読者に届いたのか。
辻村さんは、最も緊張したという取材のエピソードを語ってくれた。実際に不登校を経験した石井志昂さんが編集長を務めるメディア「不登校新聞」の取材だ。
「取材には、不登校だという10代の方も来てくれました。当事者からここが違う、あそこが違うと言われるのは当然のことだと思っています。何を言われても、彼らの感覚のほうが正しいのですから、批判があってもちゃんと受け入れようと審判を下されるような気持ちで取材に行ったんです。最初の質問は『辻村さんは、本当は言っていないだけで不登校の経験があるんですよね。ここでは本当のことを言ってください』でした」
この質問で、自分のことを「仲間」「味方」と思ってくれているというのが伝わっり、ほっとして、いろいろ話すことができた、と振り返る。
「私は多くの人と同じで、学校に行きたくないと思ったことはありますけど、不登校経験はないんです。中学生のときから、不登校は“逃げた”ではなく“休む勇気”を持った子たちだと思っていました。私にはその勇気はなかった」
不登校新聞の取材のなかで、辻村さんは物語に込めた最も大事なメッセージを彼らに明かしている。「私を不登校にした人を許せない、という思いを抱えたままでいいのでしょうか?」という質問に対する回答だ。
「傷つけた人にも事情があり背景はあるかもしれない。でもね、それでもあなたは許さなくていいんです。傷つけてきた人の事情をあなたが推し量ったり、背負う必要はありません。大人と呼ばれる年齢になって、私は満を持して、みなさんに言いたいことがあります。年齢にかぎらず『くだらない人はいます』と」
このメッセージを読み解く上で重要なことがある。この小説は主人公が善、その他が悪という単純な善悪二元論の構図を使っていないことだ。
例えば、こころが学校に行けなくなるきっかけを作った真田美織である。彼女の描写も根っからの「悪い人物」ではなく、あくまでこころの視点からみて理解ができない「合わない人物」として描写されている。
「こころには、美織たちが家に来て怖い思いをしたというストーリーがあります。一方で美織には、好きだった男子がこころと付き合った、付き合ってないということを巡って、彼女なりに行動に至るストーリーがある。悪意の有無ではなく、2つは混ざり合わないというのが大事なんですよね。美織だって、もし孤城のなかでこころと出会っていたら友達になれたかもしれない。誰かにとっては合わないけど、ぴったりくる人だっている。単純に誰が正しくて、誰が間違っているかっていうのは一言では言えないんです」
「大切なのは、大人の世界も子供の世界も分かり合えない人間はいるということ。世の中、嫌なことをされた相手であっても対話したら分かり合えるというファンタジーが溢れていますが、そんなことはありませんよね。これだっていう正解はどの世界にもない。私は、正解がない世界の中で分かり合えない人たちとは分かり合わなくていいんだって書けるようになりました」
「許さなくていい」というメッセージ
作品を書くにあたって、辻村さんはスクールカウンセラーに取材をした。その中で、いくつか印象に残った発言があったという。一つは「(嫌なことをされた相手を)許せないという気持ちを持てない子供もいる」と言われたことだ。これが「許さなくていい」という辻村さんのメッセージにつながってくる。
「嫌なことをされたはずなのに、どうしても自分を責めてしまう。自分に何かが足りなかったんじゃないか、何か問題があったから自分は人気がないんじゃないかとか、そんなふうに思う子供もいる。つらい状況に置かれると、相手よりも自分が下手にでてしまうということはありますよね。メディアや物語でも、人を許すことは尊いことだと描かれがちです。許したり、忘れたりしないといけないって思われてしまうんですけど、決してそんなことはない。忘れない、許せないから湧き起こる気持ちだって本当はあるはずだ、とスクールカウンセラーの先生から伺いました。不登校新聞さんの取材で、このテーマで質問がきたことが嬉しかったんです。私自身もきっぱりと『許さなくていいんですよ』って言い切れるようになっていました」
「正しさ」が答えではない
辻村さんは、この小説の中で何か正しい解決策を示すということもしなかった。不登校の子供たちが学校に戻るべきだ、とも、学校が受け入れるべきだとも書かない。登場人物それぞれの「痛み」を書くことだけに終始している。
「正義感も過ぎれば暴力ですよね。学校でも職場でも、正しさを押しつけられた何かにさらされて苦しんだっていう人も多いと思うんです。そのときに、自分はどうしたいのか。正義感ではなく、もっとしなやかな倫理観みたいなものを必要としている人もいるだろう。そう思いながら書いてきました」
許さなくていいし、分かり合おうとしなくてもいい。「正しさ」にすべて任せず、即効性のある解決も求めない。代わりに示されるのが、個々人にとって最良の道を考え続けるという選択肢だ。
「こころは、学校に行けなくなってしまったことで本当はできていた時間を奪われてしまっている。会えるはずの友達に会えない。一緒に過ごす楽しい時間も過ごせない。会えるはずの友達に会えないなら、代わりに出会える場所を作りたい。それが孤城だったんですね」
現実にも学校を休んだ先にどうするのか、という問題がある。
「それは誰にも分からない問題です。だけど、その子にとっての一番にいい道はあるはずだと信じて話を続けたり、考え続けたりすることが大事なんだという気持ちで私は書いています。考え続けるのをやめるとき、それは何かにギブアップしたときだと思います」
風のように読まれてほしい
苦しさや生きづらさ、痛みを感じているのはもちろん不登校を選んだ子供たちだけに限らない。学校に通っている子供にだって苦しさはあるし、大人の社会にもそれはある。会社で居場所を失う、理不尽な叱責や責任転嫁をされる、何かのハラスメントの対象になるというのは決して珍しい話ではない。
「こころたちが抱えている悩みは大人であっても、どこかでつながるはずです」と、辻村さんは語る。「スクールカウンセラーの先生から『この(スクールカウンセラーの)仕事は風のようであってほしい』と言われたのも、とても印象に残っています。『○○先生のおかげで今がある』と名前に感謝されているようではまだまだで、気がついたらつらい時が終わっていた、いつの間にか高校生になっていたと思われるくらいでちょうどいい。その時に自分を引っ張り上げてくれた風のような感触だけが残ればいいんだと。そのお話を聞いた時に、こころたちにとって城での記憶もそうあってほしい、この本も風のように読まれてほしいと思いました」
「私の家の鏡は光らなかったけれど、私にとっての鏡の世界は本でした。本はどこか違う場所に連れ出してくれて、今いる場所が全てではないってことを教えてくれたんです。学校で友達とケンカしたり、周囲の大人の理不尽さに苦しんだりしても、本の世界に入り込むことで、私にはまだ出会っていないだけで仲間がいると思えたんです。この作品も、そう思って読んでもらえたらいいですよね」
本は「バトン」になる
「本屋大賞ってその年の本の世界の観光大使みたいなもの」と辻村さんは言う。「『この子に観光大使が務まるのかなぁ、でも頑張ってこいよ』って送り出したい。私はエンタメ小説家だから、エンターテインメントである小説の力を信じています。本は『バトン』だって思っているんです。いつか、この本を読んだことで、本の世界が楽しいと思ったとか、創作の世界に飛び込んできましたという方と出会うのが楽しみです。これって『かがみの孤城』の内容とも重なりますよね。誰かから受け取ったバトンを、誰かに渡す……」
物語の終盤、こころは決断を自ら下し、仲間のために謎を解こうと行動を起こす。それは、城の中でまったく知らない他者とコミュニケーションを重ねる中で、彼女がみせた確かな成長だった。最後の最後で、こころはあるバトンを受け取る。しかし、そのバトンを渡していたのは……。これ以上は、いくつか仕掛けられたあっと驚くラストのネタバレになってしまうので控えておこう。
きっと『かがみの孤城』は「観光大使」の役目を果たし、多くの人の心に届いていくはずだ。ミステリー好き、辻村ファンだけでなく、この物語はなにかつらいことを抱えた、あるいはどこにも居場所がないと感じているすべての人に開かれているのだから。
辻村 深月(つじむら・みづき)
1980年山梨県生まれ。2004年『冷たい校舎の時は止まる』で第31回メフィスト賞を受賞しデビュー。11年『ツナグ』で第32回吉川英治文学新人賞を、12年『鍵のない夢を見る』で第147回直木賞を受賞。今年、『かがみの孤城』(ポプラ社)で2018年本屋大賞(主催:NPO本屋大賞実行委員会、オフィシャルメディアパートナー:ヤフー)を受賞した。幅広い作風と繊細な心情描写に定評がある。近作に『青空と逃げる』(中央公論新社)。
石戸 諭(いしど・さとる)
記者・ノンフィクションライター。1984年生まれ、東京都出身。2006年 立命館大学卒業後、同年に毎日新聞社に入社。岡山支局、大阪社会部、デジタル報道センターを経て、2016年1月にBuzzFeed Japanに移籍。2018年4月に独立した。著書に『リスクと生きる、死者と生きる』(亜紀書房)。