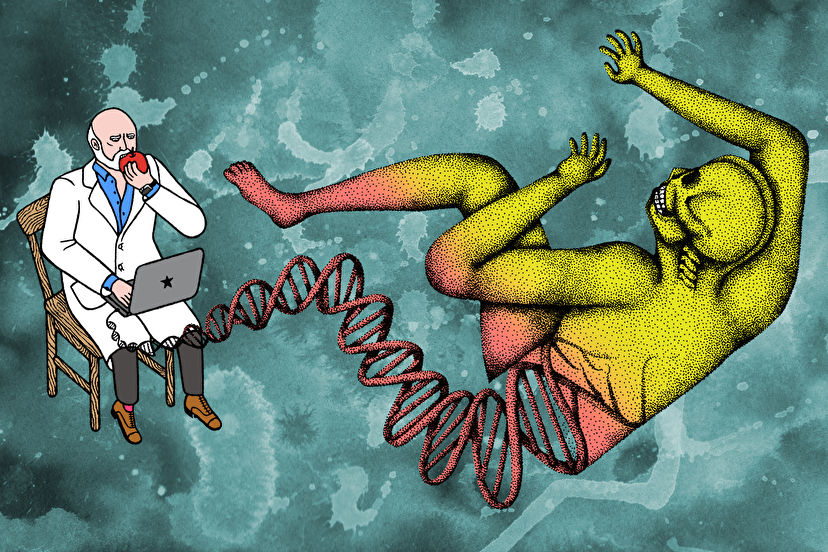芸人、作家 又吉直樹
ピースの又吉直樹が、小説第2作『劇場』を上梓した。売れない劇作家・永田が、女優を目指す大学生・沙希と出会い、共に暮らし始める恋愛小説。売れない芸人コンビを描いた『火花』は芥川賞を受賞し、発行部数300万部を突破した。売れっ子芸人である又吉が描き出す「売れる」ことへの感性とは――。
(聞き手:文芸評論家・藤田直哉、構成:長瀬千雅/Yahoo!ニュース 特集編集部)
「俺ら、ここで言い訳だけして生きててもあかんよな」
――『火花』でも『劇場』でも、売れなくても、自分にとってのお笑いなり演劇なりの「神」を強く信じる人物を書きながら、又吉さん自身は売れてしまった。本作は、その皮肉も含めて書かれているように読めました。
そういう感覚ももちろんありますし、そんなに簡単じゃないですよね、売れてない人が売れてる人を見るときの感覚というのは。ほんまにちゃんと捉えきれているのか。

売れない劇作家・永田は、一人暮らしの沙希の部屋に転がり込む。昼は洋服屋、夜は居酒屋でバイトする沙希に光熱費の負担を頼まれても、「人の家の光熱費を払う理由がわからない」という詭弁で言い逃れる駄目な男だ。沙希はひたすら優しいが、ふたりは次第に傷ついていく(撮影:長谷川美祈)
――主人公の永田は、悲壮な覚悟で自らの信じる演劇に賭けています。登場する人物もみんな熱い。純文学でもファンタジーの要素やSF的な設定を使った作品も多いなか、このような、リアリズムに徹した熱い作品をなぜ書こうと思いましたか。
そもそも僕は小説を古本で読んでいました。僕が感じる文学のおもしろさは、昔の人が書いたものが、いま流行っている何よりも強い強度を持って迫ってくることでした。だから、流行を追いかけることや、それを最前線でキャッチするということを、あまり信じられていない部分があって。
――一方で、『劇場』では、「時代の最先端」を体現するような劇作家がライバルとして登場し、永田は嫉妬に苦しみます。又吉さん自身は、流行や軽やかさを否定していない。
流行りに左右されたくないという気持ちは真実としてありますが、僕がその信念を掲げたとして、最先端で勝負している人たちに勝てるかといえば、それはまた別の話です。たとえば、みんなが構造的な小説を書いているとして、「それってほんまに書きたいことなん? 流行りなんちゃうん?」といううがった見方を僕がしたとしても、作品がおもしろければいいんですよ。どんなスタンスをとっていようが、「おもろいもん勝ち」。僕の中で、それだけが動かへんものなので。

『劇場』のテーマのひとつは「時間」。永田と沙希、ひとつの部屋に流れるふたつの時間がずれていくことで、関係が変化していく(撮影:長谷川美祈)
又吉直樹は1980年生まれ。高校卒業後、上京。2003年、綾部祐二とお笑いコンビ「ピース」を結成。2010年、「キングオブコント」で準優勝、「M-1グランプリ」で4位になり、お茶の間の知名度をあげていく。一方で文筆家としても活動、デビュー作となる自由律俳句集『カキフライが無いなら来なかった』(せきしろと共著)を刊行したのが2009年だから、文筆のキャリアは8年になる。
――「売れる」ことへの感性は、芸人として舞台に立ってきた経験が大きいですか。
すごく大きいと思います。文学の世界の美しさは、自分がおもしろいと思う芸術に対して、迷いなく追求していく姿勢だと思うんです。それがめちゃくちゃカッコよくて、そういうものを読みたいと思う。

5月11日、銀座・博品館劇場で「『劇場』劇場お渡し会」が行われ、300人が集まった(撮影:長谷川美祈)
同じような感覚を持って、芸人を志す人もたくさんいます。ただ、客前に立ったらウケないんです。ウケへんから、こんなものはおもしろくない世界だと言って去ってしまう。でもその中で、「じゃあ、どうやったら伝わんねやろ」と努力し始める人がいて。
僕はテレビに出るまでに10年かかりましたが、劇場こそお笑いのコアな部分が表現できる場所で、テレビはもう少し軽いものやという認識は、20代半ばの頃にはもう消えていました。たまにテレビに出ている人が劇場に来ると、圧倒的に強いんです。それを見て、「俺ら、ここで言い訳だけして生きててもあかんよな」ということはわりと早い段階で思いました。自分の好きなことをやりつつ、どうしたら鑑賞する側を巻き込んでいけるのかということを考え始めた。

主人公・永田がサッカーゲームに「漱石」「芥川」などと名前をつけてプレイする場面がある。笑いを誘う描写にすれ違いの予感がにじみ、ほろ苦い(撮影:長谷川美祈)
――芸人として「尖る」部分と、広く売れようとする部分、両方がある。
芸術性を高めた上で、商業性を無視せずに、どういろんな人に伝えるか。その作業が実はいちばん難しいと思っているんです。
――『劇場』はそれに成功しているから、驚いています。
全然できたとも思っていないんですが、『火花』で言うと、1作目を書いた時点で、「2作目は?」と言われる状況でした。芸人が小説を書いたことが注目されていた。書いた僕としては、寂しいな、作品読んでほしいなという気持ちもある。でも僕は芸人ですから、そこで意固地になってもおかしいですよね。だから、(文学に対しては)「ちょっと待っててくださいね、僕、ちゃんとやりますから」という意識はありました。
それに、芥川賞は僕だけのものでもない、これからとっていく人のためのものやとも思っているので、そこはちゃんとやろうと決めていました。それであかんかったら、ボコボコにされるだけじゃないですか。「2作目全然おもんなかったね」みたいになるかもしれへんけど、ちゃんと向き合わなければいけないと思っていた。

(撮影:長谷川美祈)
太宰を読んだとき、「ダウンタウンやん」と思った
バラエティー番組「アメトーーク!」で初めて「読書芸人」が放送されたのは2012年。「文学好き=暗い、ダサい」という自意識を逆手に取った企画だった。出演した又吉は、推薦本の1冊に太宰治の『桜桃』を挙げている。「おもろいもん勝ち」のお笑いの世界と、太宰に代表される近代文学は、又吉の中でどうつながっているのか。
――又吉さんが書かれたものを読むと、太宰治のような近代文学の作家と、テレビで見て憧れたお笑い芸人、どちらも同じように影響を与えている気がします。
それはあると思います。僕はダウンタウンさんがすごく好きだったんですが、中2で太宰を読んだとき、「ダウンタウンやん」と思いました。
自分では感じているけど人前では恥ずかしくて言われへんこと、いっぱいありますよね。僕が人に秘密にしていたことを、太宰は次々と暴いていってるんですよ、『人間失格』で。何十年も前に。自分の感覚として持っているものが、明確に切り取られて表現されているという驚きが、お笑いの先輩たちの番組を見てもあったし、近代文学を読んでもありました。
だから、僕からしたら、文学とお笑いは最初からすごく近いんです。

(撮影:長谷川美祈)
たとえば、「太宰の短編でね」と、書かれていることをしゃべると、みんなすごい笑ってくれるんです。
――ほう。
「そんなん書いてんの、めっちゃおもろいやん、読んでみるわ」と言ってくれるんですが、「読んだらむずいな」って。
――はははは。
それが特に近代文学の作家に多くて、これをおもしろいと感じてくれる感覚をみんな持ってるのに、うまくいってない。もったいないことになっているなということは感じていました。
だって、ハイブランドのパリコレのショーでモデルさんが着てくる服のほうが、(日常で着る現実的な服より)もしかしたら難解かもしれない。でも、色とか形とか、見ているだけでもおもしろいですよね。文学や演劇も同じで、難しいとされるものも、もっとみんな協力的におもしろがったらいいのに、と思う。

登場人物のひとり、野原は、永田の同級生。「一緒にいろんなものを好きになってきた、こいつにおもんないと言われたら終わり、という人物」(又吉)。ちなみに、太宰治に『斜陽』の執筆を依頼した編集者は、野原一夫という(撮影:長谷川美祈)
――又吉さんは今、極めて例のないポジションにいらっしゃると思います。一方で、太宰治も、自ら「太宰治」を演じていた部分もあるのではないかと思うんです。
はい。
――又吉さんもそういう演技意識はありますか。自ら「文学者」を演じているような。
どうでしょう。そこはもしかしたら天然かもしれません。でも僕はやっぱり自意識過剰やから、何をやったら恥ずかしいか、全部わかっているつもりなんです。この現代で、「太宰好き」と公言して、中央線沿いに住んで、着物を着たら、もうアウトなんです。絶対おもんないですよ、そいつ。迷いがあるならやめたほうがいい。でも、僕の中には迷いがなかった。

――どんな演劇を見てきましたか? 「マームとジプシーも見ますし、チェルフィッチュや、ポツドール、五反田団、ヨーロッパ企画なども好きで見に行っていました」(又吉)(撮影:長谷川美祈)
――それはいわゆる「キャラ」とは違いますか。
演じている意識はほとんどないですね。それで、テレビに出るようになると、トピックとして扱われるじゃないですか。「又吉が普段、着物を着るらしい」。みんなから変わり者と見られたときに初めて、そこに対する自意識が生まれて、キャラになってしまう。僕が信じてやっていた行為がキャラになってしまう、「又吉が又吉やってんな」になるから、それ以降はできなくなりました。
ほんまのことを言えば、「太宰好き」と言うのはめちゃくちゃ勇気いりますよ。
サッカーでも、「サッカー選手3人しか知らんなかでマラドーナ好きって言ってるんじゃないねん」という意識がありましたが、「本が好きで、いっぱい読みます」と言いながら、「好きな作家は」という質問に「太宰です」と答えるのは、けっこう勇気がいります。
――「本当はわかってないんじゃないか」と思われそうで。
もう少し相手が「え、誰ですか?」というような作家を言いたくなりますよね。でも僕は太宰と言い続ける。なんでこんなに難しいことやってんねやろと思いながらも、誤解されている作家でもあるから。

(撮影:長谷川美祈)
僕、太宰の小説を100回ぐらい読んでるんですよ。中学生のときに読んだ1回と、大人になってから読む何十回とでは、同じ景色でも違う景色に見えているということがあると思います。本って書かれてることが一緒やから、何回読んでも一緒ってみんな認識してるけど、実は全然そうじゃない。
――読むたびに違いますよね。
そういう意味でいうと、「文学者」というよりは、「文学青年」を演じている部分はあるかもしれません。わざとなめられにいってるところはあります。いついかなるときに、テレビで好きな作家を聞かれても、ほぼ太宰、芥川で返すという。
それは、みんながわかる言葉で、みんなの入り口になる作家を言わないとと思うから。自己満足に終わっても仕方がないので。自分がおいしいと思ったものを人に薦めて、一人でも「ほんまや、おいしいな」と言われたらうれしいですよね。そのうれしさと同じものを、文学でも味わいたいんです。

お渡し会の冒頭、「変な空気になることがあるんで、基本、握手しましょう」と又吉らしいあいさつで会場を笑わせた(撮影:長谷川美祈)
藤田直哉(ふじた・なおや)
文芸評論家。1983年、札幌市生まれ。東京工業大学大学院社会理工学研究科価値システム専攻修了。博士(学術)。著書に『シン・ゴジラ論』(作品社)、『新世紀ゾンビ論』(筑摩書房)、編著に『地域アート 美学/制度/日本』(堀之内出版)、『東日本大震災後文学論』(南雲堂)など。
[写真]
撮影:長谷川美祈
写真監修:リマインダーズ・プロジェクト
後藤勝