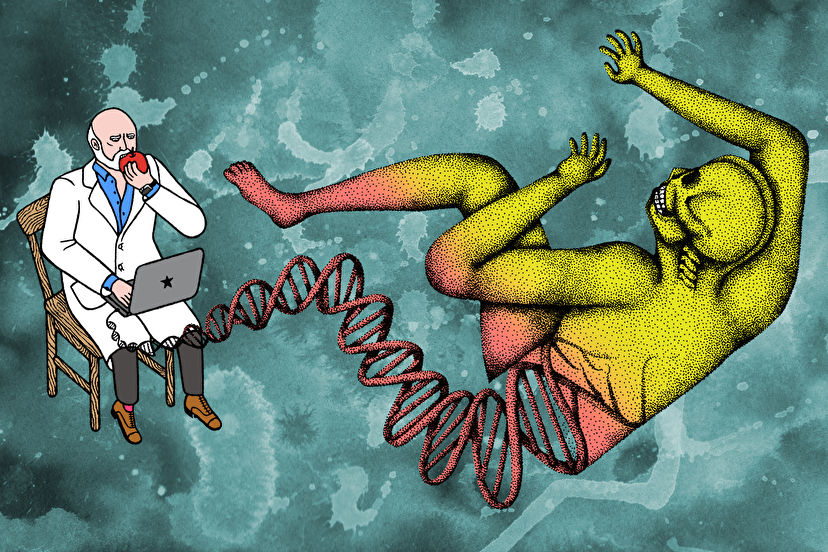恩田陸さんの長編小説『蜜蜂と遠雷』(幻冬舎)が2017年本屋大賞に輝いた。恩田さんは代表作『夜のピクニック』(新潮文庫)で2005年にも本屋大賞を獲得しているが、2回目の受賞は史上初。しかも今回は、直木賞とのダブル受賞という快挙だ。今年で作家生活25年を迎える恩田さん。学園モノ、ホラー、SF、ミステリー……これまでの60作を超える小説は、百面相のような多彩ぶりだが、あくまでも本人は「書く側にいる感覚がない」と飄々としている。長年にわたり多数の読者を魅了する希代の作家が見据える、その視線の先にあるものとは。(ライター・石崎貴比古/Yahoo!ニュース 特集編集部)
デビューから25年、作品数も膨大だが「作家としてまだまだ成長途上」と語る。(写真・殿村誠士)
受賞作は7年間の集大成
「2回も同じ賞をくれるなんて、にわかには信じがたいというか、とにかくびっくり。本屋大賞は、私がデビューして結構経ってから初めていただいた賞でとても感慨深いです。(2005年の受賞作の)『夜のピクニック』は初めてジャンルを意識しないで書いた作品で、自分の中でもエポックメイキングな小説。読書のプロである書店員さんが選んでくださる賞をいただけたことを、これまでも誇りに思ってきました」
『蜜蜂と遠雷』は、雑誌『星星峡』『ポンツーン』(ともに幻冬舎)で7年にわたり連載した作品だ。(写真・殿村誠士)
『夜のピクニック』は、恩田さんの出身校でもある茨城県水戸市の名門、水戸第一高等学校の伝統行事「歩く会」を題材にした作品。一方、今回の受賞作『蜜蜂と遠雷』は、国際ピアノコンクールに挑む4人の若きピアニストたちを多視点で描いた群像劇だ。
「なんせ7年も連載していたので、書き終わったときに感じたのはとにかく解放感。もう書かなくていいんだと(笑)。ピアノコンクールの最初から最後までを描く、という構想自体は12年ほど前からありましたが、その当時の自分の力量では書き切ることが難しかった。この作品で特に目指したのは“音楽を読者の頭の中で鳴らすこと”。以前できなかったことが、現在の私にはできるようになったという手ごたえは感じていました」
直木賞受賞後も、執筆のペースはそのまま。作品ラッシュが続いている。(写真・殿村誠士)
音楽との出会いはピアノから
そもそも、恩田さんの暮らしには常に音楽が身近にあった。父がクラシック好きだったこともあり、自宅にはたくさんのレコードが並び、子供の頃からピアノを習った。青森県の生まれだが、父の転勤に伴い幼少から大学入学まで日本各地を転々とした。飛行機は大の苦手だが、陸路なら車窓を眺めていればどんなに長時間でも気にならないという。それは、列車での引っ越しがほとんどだったからかもしれない。
松本、富山、秋田、宮城、そして水戸。いずれの土地も彼女にとって印象深い場所だ。中でもピアノを弾く楽しさ、そして聴く楽しさを教えてもらったのが秋田時代、小学校6年生の時に師事していたピアノ教師だった。彼が「僕の一番好きなピアニスト」と言って手渡した緑色のジャケットのレコードは1950年に33歳で夭逝したルーマニアの天才ピアニスト、ディヌ・リパッティのもの。当時はそれほどでもなかったが、大人になりその魅力に惹きこまれた。
かつてピアノを弾いていた指先から、いまは無数の物語を紡ぎ出す。(写真・殿村誠士)
中学時代はケイト・ブッシュやクイーンなどのブリティッシュ・ロックに傾倒。早稲田大学在籍時はジャズのビッグバンドに所属し、アルトサックスを吹いた。現在は自分で音楽を奏でることこそなくなったものの、様々なジャンルを聴いている。
「CDは学生時代から現在まで、渋谷か新宿のタワーレコードで買ったものばかり。最近ではイスラエル出身のジャズベーシスト、アヴィシャイ・コーエンのアルバムが気に入っています。東京JAZZフェスティバルに出演しているのを聴いて、かっこいいなと。いろいろな音楽を聴きますが一番多いのはジャズピアノやクラシックピアノかな」
出版された自著には必ず目を通す。「結構誤字とか見つけちゃうんですよね」(写真・殿村誠士)
『蜜蜂と遠雷』にも、全編を通じて様々な楽曲が鳴り響く。当然、恩田さんの仕事中もなにがしかの音楽が流れているように想像するが、執筆中の室内は無音だ。
「BGMとして音楽をかけようとするとうるさくなって消してしまう。執筆するときは執筆だけに、音楽をかけるときは音楽だけに集中しないとダメですね」
「作者は読者のなれの果て」
今年の直木賞・本屋大賞のダブル受賞をはじめ各種文学賞の受賞だけでなく、江戸川乱歩賞の選考委員を務めるなど、作家としての地歩を確かなものにしてきた。執筆のペースも維持している。
「“作者は読者のなれの果て”という言葉がありますが、私はまさにそのタイプ。本を読むことと書くことは、本当は同じことだと思います。読者として面白さを感じたような本を自分でも書いてみたいと思って小説家になりましたが、それほど自分が“書く側にいる”という感覚がない。今でも読者感覚が勝っていて、とにかく本を読んでいないと自分がスカスカになっていく感じがするんです」
「書くことも読むことも好き。作家になってからも、読者感覚のほうが強い気がしています」(写真・殿村誠士)
インプットなくしてアウトプットなし。多彩な作品群を支えるのは、それを上回る膨大な読書量というわけだ。いまも執筆の合間を縫って、平均すると週に4〜5冊は読んでいる。
「作家になるにはとにかくたくさん読むしかないと思います。自分だけの引き出しでは限界があるし、もはや新しい物語のパターンはない。となると、これまでのパターンをどう演出するかが大事になってきます。やはり自分が読んだ分以上のものは書けないでしょう」
「ただし」と彼女は力を込めて言う。
「新しい作品を書く場合、先人へのリスペクトを持っているべきだと思っています。人間って大したことはできませんし、これまでの作家によってあらゆることがやりつくされています。先人たちを超えられるとは思いませんが、彼らがやってきたことを次世代につなぐこと、感動をつなぐことが大切だと思います」
次回作はバレエの世界が舞台
1992年に『六番目の小夜子』(新潮文庫)でデビューした当時はOLとして勤務する傍ら、もっぱら夜間に執筆する「二足のわらじ生活」を送っていた。サービス残業は当たり前の時代の、ハードな日々。1997年に専業作家となってからも完全な夜型で「絵に描いたような不規則な生活」だったが、最近は以前に比べ健康的な毎日を送る。
「執筆は朝と昼に集中して行います。だいぶ健康的なんじゃないかな」(写真・殿村誠士)
『蜜蜂と遠雷』のあとも、2017年2月にファンタジー長編『失われた地図』(KADOKAWA)、短編集『終りなき夜に生れつく』(文藝春秋)、3月には近未来SF『錆びた太陽』(朝日新聞出版)と新作の発刊が続いている。執筆依頼が殺到する日々だが、デビュー当時は小説のタイトルと簡単なプロットを綴ったリストをもとに出版社に「営業」することも。
当時のリストにあったものはほとんどが具現化し、読者のもとに届けられた。現在構想中の物語は、新潮文庫の『マイブック』(1日1ページ1年分の無罫日記帳)にそのタイトルがいくつもストックされている。次回作は、バレエダンサーを主人公にした小説だ。
いまも多くの連載をかけもちしているが、その日に書く原稿はどのように選ぶのだろうか。
「手帳の予定表を見て、締め切りがヤバそうな順に (笑)。昼間はひたすら仕事をしていることが多いですが、毎日必ず外出します。用事がある時は電車やタクシーで移動しますが、1時間以内の距離だったら歩きます。自宅兼仕事場が麻布近辺で、恵比寿や赤坂くらいまでだったら徒歩。散歩して、夕飯のおかずを買って、本屋さんに寄って、という感じ」
「ビールは大好きですね。先日訪れた水戸でも、地元の常陸野ネストビールをたくさんいただきました(笑)」(写真・殿村誠士)
書店では一読者になる
本は必ず書店で手に取って選んだものを買う。近所にある2軒の大型書店の常連であり、新宿に出たらもちろん紀伊国屋書店に足を運ぶ。書店に入ると絶対になにがしかの本を買わないと気が済まない。
「書店では“読者人格”が勝ってしまって、自分の本とかは全然気になりません。あ~置いてあるな~くらいの感じです。目立つ場所に並べ替えたりはしませんよ(笑)。雑誌もいろいろなジャンルを読みます。中でも料理の本を読むのが“趣味”。檀一雄の『檀流クッキング』や湯木貞一の『吉兆味ばなし』のレシピを試したり。活字だけで書いてある料理本は特にいいですよね。何かしら自分の作品に反映されているかもしれません(笑)」
食べるのも好きだが、実は知る人ぞ知るビール党でもある。
「ものすごくいっぱい飲みます(笑)。外で飲むと2軒、3軒は必ずハシゴしてしまうから良くないんですよ。家では、おつまみと一緒にビールを1、2本飲むくらい」
世界的にブームとなっているクラフトビールや、小規模醸造所をテーマとした「趣味」を兼ねた作品が、今後登場するかもしれない?
「確かに流行っていますし、先日訪問した水戸でも常陸野ネストビールをたくさんいただきました。それでも私の定番は、自宅の冷蔵庫に常備してあるキリンのクラシックラガーとサッポロ黒ラベルですね」
祖父江慎の装丁も印象的な最新作『錆びた太陽』(右)。『蜜蜂と遠雷』とはまた全然違う、近未来を描いたSF作品だ。(写真・殿村誠士)
トランプの髪形は嫌い
インタビューの最後に、好きなものと嫌いなものをジャンルを問わず2つずつ尋ねてみた。まずは好きなもの。「う~ん」と唸ってまず出てきた答えは「ソラマメ」。
「この季節はやっぱりいいですよね。それから神保町! 古本屋はもちろんたくさんあるし、喫茶店もたくさんある。最近はいい飲み屋さんもいろいろできましたし」
続いて嫌いなものとしてすぐに挙がったのが、ドナルド・トランプ米大統領の髪形。
「ヅラじゃないらしいんですけど、何となくイラッとしますよね~」
もう一つの嫌いなものは、うんうん唸れどなかなか出てこない。予定調和なコメントばかりの「バラエティー番組」や、かぶれるからとの理由で「山芋」が浮上したが、最終的にノミネートされたのは「ちっちゃい犬」。
恩田さんのサイン。『マイブック』には、この筆致で書かれた構想タイトルがずらりと並んでいるという。(写真・殿村誠士)
「犬は好きなんですけど、チワワみたいなちっちゃい犬は嫌いです。一生懸命歩いても全然進んでないところが嫌い(笑)」
とはいえやはり嫌いというほどでもなく「苦手」なレベル。嫌いと断言できるのはゴキブリくらいのようだ。嫌いなものよりも好きなものがすぐに思い浮かぶからこそ、さまざまな愛すべきキャラクターを生み出し、美しい物語を紡げるのだろう。自分の一生を100パーセントで表すと、現在の自分を「40パーセント」と評し、「これからも悪あがきをして、ベストを尽くしたい」と語る恩田さん。彼女の『マイブック』にストックされた新たなタイトルが、今後も分厚い本となり書店に並ぶのだろう。そして感動は、次世代へとつながれていく。
恩田陸(おんだ・りく)
1964年青森県生まれ。早稲田大学卒。1992年に『六番目の小夜子』でデビュー。2005年『夜のピクニック』で吉川英治文学新人賞および本屋大賞を、2006年『ユージニア』(角川文庫)で日本推理作家協会賞を、2007年『中庭の出来事』(新潮文庫)で山本周五郎賞をそれぞれ受賞。今年、『蜜蜂と遠雷』で直木賞と2017年本屋大賞(主催:NPO本屋大賞実行委員会、オフィシャルメディアパートナー:ヤフー)をダブル受賞した。ホラー、SF、ミステリーなど、さまざまなタイプの小説で才能を発揮している。近作に『錆びた太陽』。
石崎貴比古(いしざき・たかひこ)
1978年茨城県生まれ。神主ライター。東京外国語大学大学院博士後期課程単位取得退学。新潮社『週刊新潮』編集部、『Pen』編集部を経てフリーに。茨城県石岡市の常陸国総社宮で神職を務めつつ、取材・執筆活動を行う。