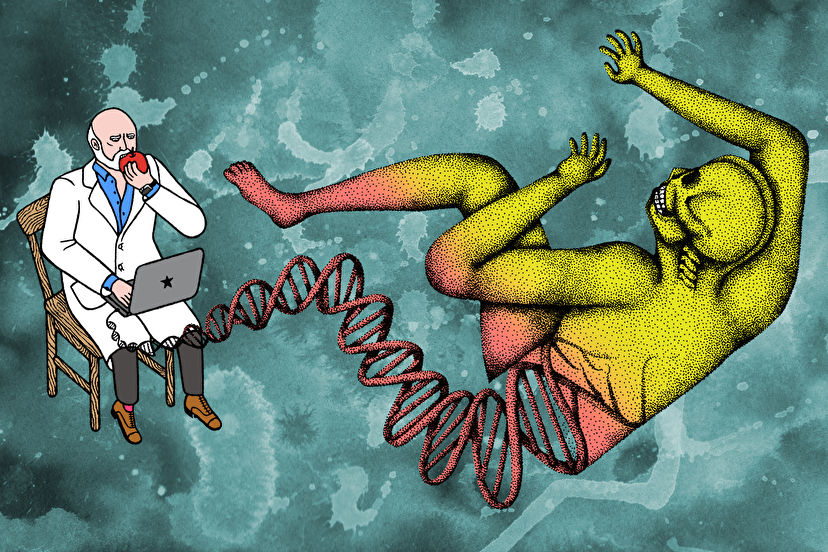『君の膵臓をたべたい』『青くて痛くて脆い』など、著書が続々と映画化され、瞬く間に人気作家の仲間入りを果たした住野よる。そのプロフィールは、非公表だ。男性なのか、はたまた女性か。年齢も、出身地も明らかにしないミステリアスな作家に、ロングインタビューを試みた。作家になって人生はどう変わったか。作品への思い、そしてSNS社会について思うこととは。(取材・文:山野井春絵/撮影:殿村誠士/Yahoo!ニュース特集編集部)
どこかで小説を書く時間と、ずっと酒を飲んでる時間がある昼夜逆転生活
住野よるとは、何者なのか。
午後1時、約束の場所に少し眠そうな表情で現れた住野。聞けば、完全に昼夜逆転生活をしているという。毎日の起床時間は、午後3〜4時。家事や雑用をこなし、仕事をするのは夜から朝にかけて。就寝時間は、朝の7時前後。つまり、いつもならぐっすりと眠っている時間帯だったわけだ。
「夜のほうが静かで、集中して書けるんです。日が暮れたら朝にかけて、どこかで小説を書く時間と、ずっと酒を飲んでる時間があるという感じ。仕事を先にやって、その後朝まで酒を飲んでる時もあれば、夕方から飲みはじめて、いったん気絶して、起きてから朝方まで仕事している時も。こんな酒飲み生活でいいのかなと思いながら、『酒も飲まずにどうやって小説家をやってるの?』と言った偉大な先輩小説家もいるようなので、まあいいかなって」
昼夜逆転生活は、作家を本業と定めた5年前から。それまでは社会人をしながら作家活動をしていた。『君の膵臓をたべたい』が売れた頃、ちょうど仕事を辞めざるを得ない状況と重なった。
「作家になったから仕事を辞めたっていうわけじゃなくて、たまたま。だから、すごくタイミングがよかったんです。『膵臓』が売れていなかったら、就職活動をするつもりでした」
日毎に愛が減っていくような不安がある
作家を目指したきっかけは、10代の頃、有川浩や乙一など、大好きな作家の小説に耽溺した流れからだ。
「小説が好きっていう気持ちが突き抜けて、自分でもつくれたらいいなと思うようになって。作家を意識したのは、大学で進路を考えはじめたときです。ライトノベル作家になりたかったんですよ。で、ライトノベル作家って、著者近影がイラストだったりして、プロフィールを公表しない文化がある。そういう感じで、『膵臓』を宣伝する過程で、性別も年齢もわからないほうが面白いかなと、非公開にしてみたんです。作家のプライベートよりも、作品のほうが前に出てほしいと思いますし」
住野よるには、「本体」と呼ばれるキャラクターが存在し、プロフィール写真として登場する。本人は、一切その実像を世に晒さない。

住野よるの「本体」キャラ(本人提供)
「そもそも、作家の私生活なんて、別に面白いものじゃない。めっちゃ酒飲んでるとか、そういう極端なところだけで十分じゃないですかね」
デビュー当初は、小説家として扱われることが純粋に嬉しかった。編集者に打ち合わせで呼び出されるだけで、特別な気持ちを味わった。やがて専業作家になり、住野の人生は一変する。
「大きく変わったのは、『自分は本当に小説が好きなのか』と自問するようになったことです。書くことも、読むことも。デビュー前のほうが、純粋に小説のことを愛していたと思います。今は、去年のほうが小説好きだったな、先月の方がまだ好きだったなって、日毎に愛が減っていくような不安がある。一緒にいるものを嫌いになるかもしれない、飽きてしまうんじゃないかという恐怖が常にある。一番変わったところで言うと、こういう心境になったことかもしれないです」
小説に飽きてしまう不安。もう自分にはやることがなくなってしまうのではないか。それを住野は「恐怖」だと言う。新作『この気持ちもいつか忘れる』の着地点にも、そんな自分のことを含めた。
「書けない時には、書いたものをいったん忘れるという方法があると思っています。1週間くらいたって読み返してみると、意外と次の一文が出てきたりすることもある。もしくは、のたうち回りながら考える。ほんとに、『うわあ!』って言いながら考える。プロなんだから、どうにかして捻出しなきゃいけない」
生きづらくない人なんてこの世界にいない
幼い子どものように純粋な気持ちを抱いたまま、繊細で、不器用で、家族とコミュニケーションをとるのすら難しい。住野の作品には、そんな生きづらさを抱えた10代から20代の人物が多く登場する。学生時代はあなたもこんなふうに生きづらさを感じていたか、と尋ねると、住野は軽く噴き出した。
「自分も含めて、生きづらくない人なんてこの世界にいないと思っているんですよ。だから生きつらいことに焦点を当てた作品が生まれ続けるんだと思います」
自身も抱えた生きづらさは、住野にとって大切なテーマとなった。若さは苦しい。だからこそ美しい、と住野は言う。
「かたちが決まっていないものは美しくて、面白いと思うんです。若い人たちが揺れ動いているさまを、やはり描きたくなる。僕は、世間では<どうでもいいこと>が、その本人たちにとっては<世界のすべてであるかのようなこと>として描くことが好きなんです。たとえば、登場人物の死そのものは大きな問題ではない。世の中、毎日病気や事故で亡くなっている人はいるわけですから。でもそれを、遠くの景色ではなくて、そこだけにフォーカスを当てることで、どんな小さな世界にも物語があることを伝えたいんです」
住野は、一見<犬も食わないけんかのような出来事>もミステリアスに、登場人物の心の機微に寄り添って描く。クライマックスに用意された激しい感情の描写は、ある意味ミステリーの結末よりもショッキングだ。それは、いつでも、誰にでも起こりうる、リアルな物語だから。読むほどに感情移入し、読者はその世界にからめ捕られる。
「基本的に僕は、登場人物は全員、会ったことがないだけで、この世界のどこかにいると思っています。だから、これまではあまり舞台となる土地の名前など、固有名詞を書かないようにしてきました。読者さんにも、自分の街にこの子たちがいるかもしれないって思ってほしいから」
若さと生きづらさを描きながらも、「できるだけ生きづらい子がいない世の中であればいい」と祈っているともいう。生み出した作品の登場人物への愛情は、人一倍深い。
「生きづらさが学校や仕事場だけじゃなく、家にある人もいる。家族や結婚に縛られることで、苦しんでいる人は多いんじゃないでしょうか。それぞれ一人ひとりが権限を持って生きられる世界じゃないと、僕の本に出てくる子たちも苦しむと思う。みんな違う、でも、相手のことを考えることができる。そういう多様性がきちんと認められる社会であることを願いますね」
ネット上の言い争いは、見ていて不思議で仕方ない
フォロワーが10万人を超えたTwitterのアカウントを、住野は今年、突然削除した。現在は出版社が管理する代筆アカウントが機能している。やめた理由は、コロナ禍の影響も大きかった。
「コロナ禍に入って、SNSでの振る舞い方が、これまで以上に重要になってきましたよね。Twitterに頭と心を割かれ、容量を持っていかれてしまうと感じたんです。『住野よるとしての自分を見せなきゃ』とかプレッシャーを感じていることに気がついた。寂しくもありますが、僕は小説を書くことに注力したほうが読者さん達も喜んでくれると思うんです」
SNSには大きな分断が起きていると思う、と住野は言う。毎日どこかで起こる炎上。コロナ禍で頻発した自粛ポリス。ネット上の誹謗中傷により、深い傷を負う人が後を絶たない。
「べつに、読者の皆さんが誰を支持していようと、どんな有名人が好きでも嫌いでも、どうでもいい。ただ、ネット上で繰り広げられる言い争いとかを見ていると、『今までの人生でどこかが違えば、自分も相手と同じ立場だったかもしれない』って、僕も含め皆が思えたらいいなと思います。そう思えば、簡単に自分の立場を決めることなんてできないと思う。その曖昧さと諦めずに付き合っていきたい」
自身がSNSから距離をとっているように、住野は作品において、これまでSNSを多くは扱ってこなかった。現代の若者にとってSNSは、切り離せないテーマではないのか。
「確かにSNSは本当に巨大なものになっています。現実よりもSNSのほうがメインになってしまっている人もいるんじゃないですか。ただ、少しSNSを描いた『青くて痛くて脆い』も、テーマはそこにはなかったので。今後、ちゃんと描くことがあるとするならば、SNSがなければ存在しないような物語にしてみたいな、と思いますね」
2020年をだるま落としみたいに、全員でなかったことにしたい
映画化・漫画化された作品がいずれもヒットするなど、今、メディアミックスの原作者としても注目されている。
「メディアミックスは、原作ファンの気持ちを傷つけないものであればいい、と思ってます。原作に忠実であってほしいわけではなくて、その作品が持つ価値観を保ってほしいし、何より面白くあってほしい。『か「」く「」し「」ご「」と「』という作品のコミカライズを、二駅ずいさんが手がけてくれているんですが、好き勝手やってもらってるんですよ。二駅さんの能力に惚れ込んでいます。原作にないシーンもガシガシ入ってるし、原作にはない色っぽさがあったりして、それでもやっぱり原作の価値観が保たれている。もちろん二駅さんの能力によるものが一番大きいのですが、原作の持つ意思を伝えられるからというのもあると思います。ただ、映画はとんでもない人数が関わってきますから、全員と気持ちを共有するのは難しい。そこは原作者として、要望をきちんと伝えなければならない面があり、それが自分の責任かな、と思います。原作と原作の読者さんを、大切に思ってくれる人にやってほしいですね」

『か「」く「」し「」ご「」と「』より (c)住野よる/二駅ずい/新潮社
この秋、住野はロックバンドTHE BACK HORNとコラボレーションした長編『この気持ちもいつか忘れる』を発表した。作家とミュージシャンが構想段階から打ち合わせを重ね、創作の過程も共有。5曲入りのCD付きで発売された。
小説では、異世界との接点で繰り広げられる恋愛、意思の疎通が描かれる。住野の文学、THE BACK HORNの音楽という別世界が重なり合って生まれるものが、物語のテーマと共鳴し、作品の世界をより印象深くする。
「THE BACK HORNのメンバーさんたちと、『境界線を越えたい』という話をしていて。文学と音楽、内容も、境界線を越えて、同時につくられるものが読者さんとリスナーさんのもとに届けばいいな、と。さきほどSNSについてもお話ししたように、今、この世の中を生きる中で、『自分も一歩間違えばこの人の立場だったかもしれない』ということを考えて書きました」
今も新たな作品を、のたうち回りながら、深夜に書き続けている住野。SNSやコロナ禍など、気になる社会的なテーマをどう取り入れていくか、思案している最中だ。
「入学したのに一度も学校へ行けてないとか、内定を取り消されるとか。学生さんたちにとっても大変な年になりましたよね。2020年をだるま落としみたいに、全員でなかったことにしたいくらい。若い人たちの選択肢が、こういう状況で潰されていくさまを見るのは苦しい。でも、もしかしたら、今後の人生においては、何が幸せかはわからない。大学にちゃんと行けなかったから逆によかった、ということもあるかもしれない。少しでも、若い世代の可能性が広がっていく世の中になっていけばいいと思っています」
揺れ動いて傷つきながら、希望を探し続ける人間を、本気で応援している作家。それが、住野よるだ。作者本人が「実在している」という物語の主人公たちは、すぐそばにいるかもしれないし、あなた自身かもしれない。
住野よる(すみの・よる)
高校時代から執筆を開始。2015年のデビュー作『君の膵臓をたべたい』が大ベストセラーに。著書に『また、同じ夢を見ていた』『よるのばけもの』『か「」く「」し「」ご「」と「』『青くて痛くて脆い』『麦本三歩の好きなもの』など。この秋、小説家×ミュージシャンのコラボ作品『この気持ちもいつか忘れる』をTHE BACK HORNと刊行した。