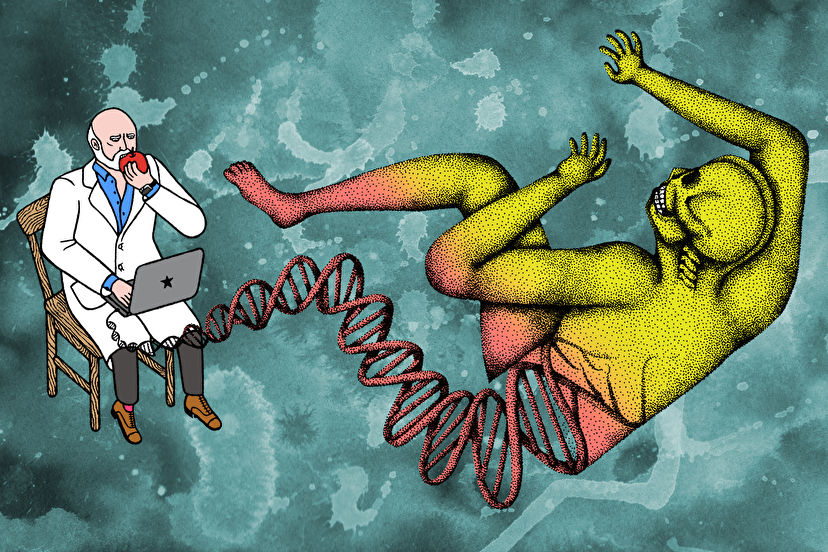アルコール依存症に苦しんだ過去から復活、フランス漫画界から高い評価を受ける高浜寛。今年は、手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞した。自分の仕事を「過去に生きていた名もない人たちの足跡を掘り起こして、その人を生かすこと」という。天草島の緑深い山あいの家で、話を聞いた。(取材・文:長瀬千雅/撮影:宮井正樹/Yahoo!ニュース 特集編集部)
異色の作家の受賞
今年4月、『ニュクスの角灯(ランタン)』(リイド社、全6巻)で、第24回手塚治虫文化賞のマンガ大賞を受賞した。年間通じて最も優れたマンガ作品に贈られる賞で、最終候補作にはベストセラー作品『鬼滅の刃』も挙がっていた。
もともと「地味な作風」(本人談)で、高い画力と物語作りのセンスから玄人筋では評価が高かったものの、一般的な知名度が高かったわけではない。選考委員の一人で仏文学者の中条省平もこの作品を、「高浜寛という作家を、知る人ぞ知る異色の存在から、もっと大きなスケールの、普遍的な物語の面白さと感動とをあたえてくれるマンガ家へと脱皮させ」たと評した(2020年5月20日付「朝日新聞」夕刊より)。
「40歳をすぎて、私も中堅の自覚ができてきました。自分のことばかりではなく、全体のことを考えていく責任が出てきていると思います。その世代なりにあげていかなければいけない成果があるとも思いますし」

たかはま・かん/熊本県天草生まれ。筑波大学芸術専門学群卒。著書に『イエローバックス』『まり子パラード』(フレデリック・ボワレとの共著)、『泡日』『凪渡り――及びその他の短篇』『トゥー・エスプレッソ』『蝶のみちゆき』『SAD GiRL』『エマは星の夢を見る』『ニュクスの角灯』『愛人 ラマン』など。ほぼ全ての作品がフランス語訳され、イタリア、スペイン、ドイツでも多くの作品が出版されている。今月28日に、『扇島歳時記』第1巻が発売される
主な舞台は、19世紀末の長崎とパリ。西南戦争で親を亡くした美世は、「私なんか」が口癖で、自分の意見を言うことに慣れていない。長崎の輸入道具屋で働き始めた美世が店主の百年(ももとし)をはじめ、まわりの大人たちの導きで、人生を切り開いていく。随所に、豊かな線で表現される当時の衣装や習俗が挿話として登場する。
しかしこれが単に美世の成長物語にとどまらないのは、百年の恋人、ジュディットの存在だ。パリの高級娼婦であるジュディットは社交界の花形だが、生活は荒れていて、アルコールに依存している。物語の終盤、美世との出会いによって、ジュディットが「光の方へ」歩き出す勇気を得るシーンが美しい。
作家性が強く、扱う題材も地味だった初期作品群と比べて、この作品は娯楽としてのマンガの楽しさにあふれている。
「エンターテインメントですよね。みんなに『少女マンガだ』って言われます。ラストのドタバタも少女マンガらしい。若い人を励ますような気持ちで描いたかな」
その気持ちの裏側には、アルコール依存に苦しんだ、若いころの経験がある。
「若いころは家族と離れて、北関東の学園都市で生活していたので、問題を相談できるような年上の女性が少なくて、健康なほうにいけなかった。幸いにしてサポートしてくれる人たちと出会うことができたし、考え方も成熟してきて、かつての自分がなぜ生きづらかったのかがいまはわかる。そうすると、同じように苦しんでる若い人たちのことが見えるようになってきて」

フランス漫画界との出会い
もともとマンガ家になろうとは思っていなかった。大学2年生のとき、飲み会でさらっと描いたマンガを面白がった友人が、あるメジャー青年誌に持ち込んだ。
「私の知らない間に見せにいく約束を取り付けてきた。面白いけど上質紙に描いてあるから、ケント紙に描き直して持ってきませんかと言ってもらって、持っていったら賞を取ったんですよね」
担当編集者がつき、デビューを目指して準備を始めるが、途中で編集長が代わり、作品が採用されなくなった。
「私は、老人を主人公にしたりして、なにげない日常のストーリーを描いていた。でも、編集部から売れるものを描いたほうがいいと言われて。売れるものってなんだって聞いたら、若者が主人公でとか、恋愛要素があったりとか、ひと夏の成長物語だったりとか。当時はそういうものにあまり興味がなかったんですよね」
「対極のところに行ってみよう」と、青年誌「ガロ」に持ち込むと一発で賞を取り、掲載が決まった。大学卒業目前の冬のことだ。
マンガアシスタントの経験はない。そのころ、フランス人マンガ家フレデリック・ボワレが「ヌーベルまんが」を提唱し、バンドデシネ(フランス語圏のコミック)とマンガの中間のような作品を発表していた。高浜は、日本に住んでいたボワレにメールを送った。
「『ヌーベルまんが』は、『日常を描く』という活動だったんですよね。SFとか、非日常的なものではなく。そのときの私はそうだそうだと思って、私もマンガ家だし、チャンスがあったら誘ってくださいって言ったんです。そうしたら、何か一緒にやりませんかという話になって」

「海外でも評価されるマンガ家」と形容されることがあるが、より正確には、日本とフランスのハイブリッド。フランス語圏ではバンドデシネ作家として受け入れられている
高浜は、ボワレとの合作『まり子パラード』を描き上げる。そして、出版社を探すためにフランスの国際的なマンガマーケットであるアングレーム国際マンガ祭に持ち込んだ。大手出版社カステルマンが興味を持ち、ボワレとの共著だけでなく、高浜自身に描くチャンスを与えてくれた。
「あとはずっとカステルマンで描いてて、気心の知れた人が別の出版社に移籍するとそっちでもまた仕事をくれるようになって。常に何か仕事をしているような感じになりました」
アルコール依存症に
若くて才能のある作家の登場にフランスのメディアも注目し、渡仏するたびにいくつもの雑誌やテレビの取材を受けた。その中には、ファッション誌の「ELLE」など、高浜自身が憧れて読んでいたような有名な雑誌もあった。
「がんばったらその先にあるような世界がいきなりやってきて、しかも思っていたのと違ったから、パニックになってしまったんですよね。長旅で疲れた頭で、同じような質問に何度も答えて。知らない人ばかりで気も使うし、通訳をはさんで何日も何日も、テレビやって雑誌やってラジオやって。そのたびにお酒を飲んでた。そうしないとこなせなくて」

日本でも、「ガロ」で描いた短編が高く評価された。「ガロ」が休刊したあとは、「マンガ・エロティクス・エフ」などのオルタナティブなマンガ雑誌で連載を持ち、締め切りに追われて徹夜が続く。
お酒を手放せなくなっていたころ、あるアート誌の取材を受けた。いつものように徹夜明けで、アルコールをキメてから出かけていった。掲載号が発売されたとき、自分の写真にショックを受けた。
「1ページまるまるの写真は、すごいむくんだ顔をしてて。適当に着ていった服の胸元がけっこう深く開いてて、こんな服着ていかなきゃよかったとか、いろいろ思ったりしましたね。別のときは、頭がハゲかけたこともあったし。20代の女性としては『これは厳しい』と思いました(笑)」
不眠にも悩まされ、睡眠導入剤を服用するようになった。だるくてだるくて、起き上がれない。1日に2時間ぐらい仕事ができればいいほうで、連載が続けられなくなった。
「まだ準備ができていないうちに、過大な評価をされてしまったんですね。少女時代が終わって、女性としての人生が始まったばかりのころに」

崩れていく自分を観察
お酒と薬をやめることができたのは、32〜33歳のときだ。何年も深い底をただよう間には、発作的に薬を過剰摂取して救急車で運ばれ、一命を取り留めたこともあった。いっぺんにやめられたわけではなく、当初は薬をやめてもお酒はやめられず、むしろ増えたときもあった。
「最終的にはちょっと幻覚みたいなのを見たときに、もうこれは浮上しなければまずいと思って。そこからパタッとやめて上がってきたんですけど」
自立への第一歩として、親元を離れ、熊本市内に家賃1万2000円の激安アパートを借りた。自助グループと病院に通い、うなぎ屋でアルバイトをしながら、『四谷区花園町』という作品を描き上げた。

2013年に『四谷区花園町』を刊行。翌年に『蝶のみちゆき』を描き上げ、さらに翌年、『ニュクスの角灯』の連載をスタートさせた
「(アルコール依存から回復する前とあとでは)180度変わりましたね。その前は一人では立てない状態、そのあとは一人でちゃんと立ってる状態。以前は、何かに依存しないと立てなかった」
高浜は、「お酒を飲んだ自分」を観察したことがある。
水底で暮らした長い年月を経て、断酒に成功したのが2011年ごろ。それからお酒は一滴も口にしていなかったが、2016年の熊本地震に遭い、古いアパートは全壊。翌月に住む場所は見つかったが、しばらくして半年ほどスリップ(再飲酒)した。
「どんなふうに崩れていくのかを、興味を持って観察している自分がいたんですよね。最初の1、2カ月は仕事ができていたけど、3カ月、4カ月と経つうちに、長編の構成を頭の中でキープすることが困難になってくるんです。パースがゆがんで絵もうまく描けなくなる」
『愛人 ラマン』執筆へ
スリップから抜け出したころ、大きな仕事が高浜のもとに舞い込んできた。フランスの作家マルグリット・デュラスの自伝的小説『愛人 ラマン』の漫画化だった。

旧知のフランス人のエージェントから「小説の漫画化をやってみない?」と提案された。「『愛人 ラマン』はどうかという話になったとき、私も『それしかないよね』という感じだったんですよね」
デュラスの『愛人 ラマン』が日本でベストセラーになったのは、1992年のことだ。ジェーン・マーチ、レオン・カーフェイの主演で映画化もされている。デュラスが仏領インドシナ(現在のベトナム)で過ごした少女時代を振り返る。貧困家庭の白人の少女と裕福な中国人青年との性愛は、センセーショナルだと話題を呼んだ。
デュラスは1996年に亡くなったが、フランス文学に詳しい野村昌代(アンスティチュ・フランセ東京メディアテーク主任)によれば、「フランスでは現在も評価が高く、その恐るべき才能、作品のクオリティーの高さから、よく読まれている」という。
高浜は高校生のころ、デュラスにはまってよく読んでいた。
「(小説の)少女とあまり変わらない年齢で読んだんですね。面白かった。『自分たちのことが書かれている』と思って読んでいました。『少女が年をとるとこうなるんだ』というのを見せられたような気がして。なんとなく自分もその呪いにかかったような感じがしました」
40歳をすぎて読み返すと、違う感想を持った。
「あの少女のことを、自分よりも経験があって、大人の世界を知っていて、しらけた感じで生きてるんだと思ってたけど、ほんとうは絶望的な状況に置かれていて、そのせいであんなにはすっぱでつっぱってたんだってことが、いまわかったという感じでしたね。当時はよくわからなかった」
高浜版『愛人 ラマン』は今年1月にフランスで発売された。翌月日本語版を刊行。高浜が描く少女はやせていて目の下にクマがあり、とても美少女には見えない。映画でジェーン・マーチが演じた、未成熟な色気がただよう少女ともまた違うキャラクターだ。最初から最後まで、登場人物のほとんど誰も笑顔を見せず、うだるような暑さの中で、行き場のない思いと苛立ちが沈殿していくさまが、オールカラーの独特な色彩で表現されていく。
「つらい状況って、どうやって耐えるか、どのくらい耐えればいいのかがわからないから、怖い。人が亡くなったときは心の痛みはこれぐらい続くんだ、でも耐えていれば絶対に薄れていくんだとか、そういうことを教えてくれる人を見つけるのが難しい。昔だったら、母親がいて父親がいて、祖父母がいて、両親が機能しなくてもおじさんおばさんとか、いろんな大人が身近にいたからなんとかなったけれども、いまはそういう環境のほうが珍しくなっている」
「単純に希望を持つことって大きいですよね。で、希望を持ってる人のそばにいるっていうことも大きいかもしれない。誰か牽引力のある人がそばにいれば、その人に引っ張られてみんないいほうにいくってこともあるだろうし。でも都会ではなかなかそうなりにくい気がします」
山あいの仙人のような暮らし
昨年、仕事場を熊本市内から天草に移した。山あいの一軒家に夫と二人で住み、マンガを描く。犬2匹と猫3匹、山羊2匹を飼い、井戸の水を飲む。

「(コロナの影響は)ここにいる分にはあまり感じないですね。もともと週に1、2回、町へ買い物に出るくらいで。DVDを借りに行ったりはしますけど」
「山に住まないといけない」と思った理由をこんなふうに話す。
「このあたりは植林された山じゃなくて、原生林が残っているんです。過去に健康を害して仕事ができなくなった経験があり、それを元どおりに修復するのにとても時間がかかったので、最初から害になる要素の少ないところで暮らしたいと思いました。それに、町にいると絶対必要なわけではない、細かな予定が入りすぎてしまう。仙人みたいな人は必ず山に住むでしょ?」
月の半分は、「月刊コミック乱」と「トーチweb」に連載中の新作「扇島歳時記」の執筆に集中する。主に使うのはシャープペンシル。基本的にペン入れはせず、黒鉛の芯の硬軟を自在に操って、ニュアンスに富んだ線を描く。

連載中の「扇島歳時記」の舞台は、『ニュクスの角灯』から10年ほどさかのぼった長崎。共通する人物も登場する
もともと、描きたいことはどんどん浮かぶほうだ。アルコール依存から回復してからは、生まれ故郷の天草と、自身のルーツがある長崎を、歴史をさかのぼって丹念に取材している。
「扇島歳時記」のために長崎・出島の詳細な見取り図を作成し、『ニュクスの角灯』では大浦慶という実在した女性実業家を登場させるなど、フィクションの中に綿密に取材したノンフィクションを巧みに織り交ぜる。
「最近はもう、マンガ家といっても歴史マンガ家なので。歴史マンガ家のすることは、過去に生きていた名もない人たちの足跡を掘り起こして、その人を生かすこと。歴史を調べていると、向こうから飛び込んでくるんです。人知れず亡くなった人とかが、描いてほしいとメッセージを送っているのかもしれない」

「扇島歳時記」のノートの1ページ。絵や演出のうまさに定評があるが、本人は「取材してシナリオをつくる作業が好き。絵を描くのは2番目」と言う
次回作の構想を楽しそうに話す姿を見ていると、描けない時期があったとは思えない。「描けないことは苦しかったですか」と聞くと、少し考えて、「待たせていることがしんどかったですね」と答えた。カステルマン社が「描き下ろしで」と依頼してくれた中編は、描き上げるのに5年かかった。
どの時代を描いていても、高浜の作品には「いま」がにじむ。『愛人 ラマン』で描かれた少女の絶望は「いまもあまり変わらないと思う」と言う。
「20年前よりも状況が悪くなっているかもしれません。どこか依存症みたいな子がたくさんいますよね。ツイッターを見ていると、いろんな人の不安定な情緒がぽんぽんぽんぽん目に入ってくる」
ただ、そこで感受するつらさや病みを、そのまま作品にしようとは思わない。
「そういうのを描けばいまの人たちの共感を得られるのかもしれないけれども、私はそれが必ずしも良いことだとは思わないんです。それより、過去に生きていた人たちがどういうふうに健康的な暮らしをしていたかとか、どういう考え方をしていたかとか、そういうことを描いたほうが、読んでくれた人が本当の意味で前向きになれるんじゃないかと思っています」

長瀬千雅(ながせ・ちか)
1972年、名古屋市生まれ。編集者、ライター。