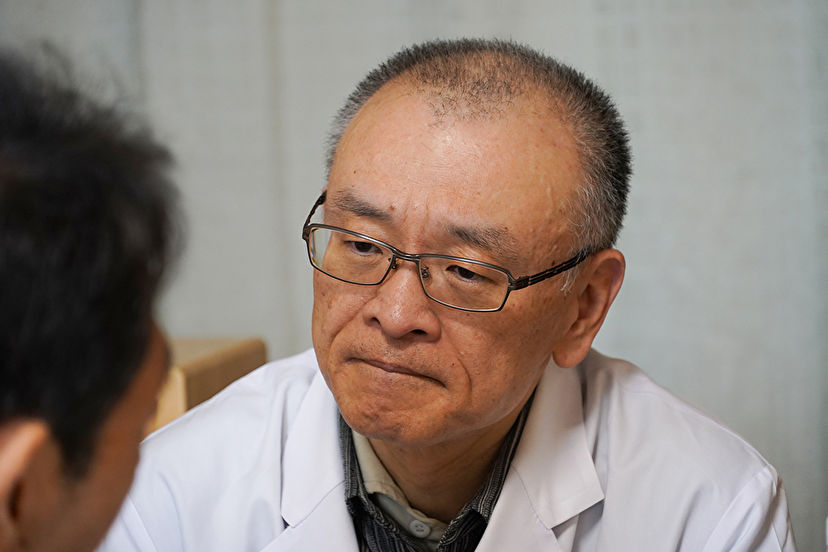武藤将胤さん(33)は6年前、「ALS(筋萎縮性側索硬化症)」と宣告された。運動神経が老化し、徐々に体が動かなくなっていく難病である。有効な治療法は確立されていない。「時間は有限。だったらALSの未来や社会を明るくすることに使おう」。病気と闘いながらチャレンジを続ける武藤さんを取材した。(ノンフィクションライター・古川雅子/Yahoo!ニュース 特集編集部)
声を失う
1月中旬。東京都港区のオフィスは移転したばかりで、筆者が取材をしていると観葉植物が届いた。
武藤さんはわずかに動く首を振って、配達人に会釈した。手元のレバーを指で操作して車いすを方向転換し、大きな絵が掛けられた部屋の隅に視線をやると、スタッフに指示した。「こっちに、運んでもらうよう、伝えてください」。かすれた声でゆっくりと、一語一語を絞り出す。

手足に加え、口やのどの筋肉も衰えている。インタビュー中に数度、口腔内に溜まった唾液を脇につくヘルパーに拭いてもらっていた(撮影:幸田大地)
武藤さんは2019年2月に気管切開手術を受けた。肺に空気を送ったり、痰を吸引したりするために、のどぼとけの下を切開して気管に穴をあける。ALSは症状が進むと呼吸に必要な筋肉が動かせなくなる。気管切開をして気道を確保しておかないと、やがて呼吸困難に陥る。発話も難しくなるため、スピーチカニューレという空気の流れを調節する器具を装着していた。
取材の6日後に「喉頭気管分離術」という新たな手術が予定されていた。食べ物の通り道と空気の通り道を分離する手術である。この手術を受けると、空気が声帯を通らなくなる。つまり、今度こそ完全に声を失う。武藤さんは心境をこう語った。
「僕はまさに6日後、声を失うことになります。以前、気管切開をするときは、僕は声を失うということが、正直、怖くてたまらなかった。身動き一つできなくなるのに、さらにコミュニケーションも絶たれて、周囲から閉ざされるのか、と。幸い、そのときは(スピーチ)カニューレで、声を取り戻せた。一方で、今回の手術では、声が出せなくなる。それでも、まだまだ活動の続きができると、確信できたのは、これまで、自分自身が、さまざまなテクノロジーと出合って、(発話を代替する)コミュニケーション手段があると、実感できるプロセスを、踏んでこれたからです」

毎日20分ほどかけて、電動車いすで自宅からオフィスへ通勤する(撮影:幸田大地)
「ありがとう」「うれしいよ」「これ、面白いね」。あらゆる感情をその人の体温とともに伝えるのが声である。気管切開手術のあとの「自分の意思が伝わらないもどかしさ、つらさは、想像以上だった」と武藤さんは言う。妻の木綿子さん(36)は、家族としての心情をこう吐露する。
「症状が進むと行動が制限されていき、2人で出かけたりすることもできなくなります。そうするとより一層、声を使ってコミュニケーションを取ることの重みが増していくんです。冗談を言い合ったりとか。そんな何げないやり取りまでなくなっちゃうの?と、いたたまれない気持ちになってしまうんですよね」
スピーチカニューレのバルブをはめて、最初の声を聞いた瞬間、木綿子さんはうれしくて思わず涙を流した。武藤さんはその様子を見て思いを新たにした。
「身近な人の声が聞けないのはこんなにもショックなことなんだと。声は自分だけのものじゃないんだと分かりました」

妻の木綿子さんと(撮影:幸田大地)
ALSとは
日本にはALS患者が約1万人いる(平成27年度の特定医療費(指定難病)受給者数)。いまも原因が分からず、特効薬は見つかっていない。
武藤さんは病気の進行を抑えるために、定期的に点滴治療を受けている。通院するたくま内科・神経内科クリニック(東京都港区)の詫間浩院長によれば、人間の体に張りめぐらされているさまざまな神経のうち、「運動ニューロン」(運動の指令を筋肉に伝える神経細胞)だけが死滅して機能しなくなる病気だという。
「大脳の運動野から脳幹・脊髄へと続くところと、脊髄から筋肉に指令を出す神経細胞、その両方の神経がやられます。したがって、意識や五感、知能の働きは正常なままでありながら、徐々に全身が動かなくなります」

人一倍おしゃれに気をつかう武藤さんは、髪のラインの付け方一つについても好みがあり、妻やヘルパーに細かく伝えてある。また、障がい者と健常者という垣根を取り払うボーダレスなファッションブランド「01(ゼロワン)」を立ち上げた(撮影:幸田大地)
全身の運動の中でも、眼球運動やまばたきは比較的最後まで機能する。ALSが進んだ患者では、視線やまばたきで意思疎通が行われることが多い。しかし、最終的な段階では、それすら奪われることがある。すべての筋肉が完全に動かなくなる、「TLS」(Totally Locked-in State=完全な封じ込め状態)と呼ばれる状態だ。武藤さんはこう言う。
「『TLS』は、ALS患者が恐怖に思う状態です。だからこそ僕は、ボーダレスなコミュニケーション手段を作り出したい。『すべての人生に限界はない』というメッセージを広げていきたい」
異変をはじめに感じたのは2013年秋のことだった。左手がしびれて、左利きの武藤さんは文字が書きづらくなった。グラスを持つ手も震えるようになった。木綿子さんはそのころに武藤さんと知り合った。
「連絡先を交換したら、iPhoneに入力する手が震えていたんです。『緊張しているの?』と聞いたら、『1カ月前からこんな感じなんだ』と」
当時、武藤さんは博報堂に勤めて4年目。「どこから見てもザ・広告マンという印象」(木綿子さん)で、毎晩日付が変わるまで仕事をしていた。仕事の疲れかと軽く考えていたが、日を追うごとに症状は重くなった。2014年3月に東京都内の大学病院で1カ月間の検査入院をしたが、診断がつかなかった。

電動の車いすの肘掛けにコントローラーがついていて、わずかに動く指で操作する(撮影:幸田大地)
右手も震えだし、気づけば食事をするときのフォークでさえ使いにくくなっていた。木綿子さんは「できないことが目に見えて増えていって、さすがに心配になりました」と振り返る。
10月、セカンドオピニオンを受けた東北大学病院でALSと診断された。病名を宣告され、武藤さんの胸に行き場のない感情が渦巻いた。「なぜ、僕の身に?」「なぜ、人生これからという今なのか?」
仙台から東京へ帰る新幹線で、武藤さんは自問自答した。そのときのことをこう振り返る。
「ALSと診断されて目の前に突きつけられたのは、有限の時間だったんです。これまで当たり前に使ってきた時間が有限だというのなら、自分はこの時間を何に使うのか、と」
人工呼吸器を使わない場合、発症してから亡くなるまでの期間はおよそ3〜5年とされている。ひたすら考えて武藤さんが出した答えは、「落ち込んでいる時間ももったいない。ALSの未来や社会を明るくするアイデアを形にしていくことに自分の時間を費やしていこう」ということだった。

2019年12月、東京都内のライブハウスでALS啓発フェス「MOVE FES. 2019」を開催した(提供:WITH ALS)
「WITH ALS」を設立
2015年1月、ALSの啓発団体「WITH ALS」を設立した。同年5月に木綿子さんと結婚。団体として最初に手をつけたのが、眼球の動きだけでDJとVJを同時にプレイするアプリケーション「EYE VDJ」の開発だった。発症する前からDJを趣味としていた。そばで見ていた木綿子さんは「心底びっくりした」と言う。
「夢を語っていると思っていたら、あっという間にプレゼンに出かけていって、技術を受け持つ会社を見つけてきて。どんどん仲間になってくれる人が増えていったんです」
2017年に博報堂を退社して「WITH ALS」の活動に専念するようになった。活動の他にも通院やリハビリでスケジュールはびっしりで、「サラリーマン時代より忙しくなった」。しかし、内心はいつも揺れていた。次第に日常の動作がしづらくなって、移動に車いすを使うようになった。朝、目が覚めると真っ先に体の動きを確認する。昨夜まで動いていた部位がまだ動くか。まぶたの開閉はできるか。指先は動くか。
「この習慣は今も続いています。前の日と同じことが今日もできるか、確かめて安心する。思うように動かせずにドキッとすることもある。それでも続けるうちに、できないことを嘆くよりも、できることに集中しようと思えるようになりました」

(撮影:幸田大地)
2019年、10月と11月に立て続けに誤嚥性肺炎になり、入院が続いた。すでに栄養は胃ろうでとっていたが、夜間だけ人工呼吸器も装着するようになった。入院生活が長引いて筋力が落ち、肺炎になる前は室内ぐらいならなんとか自力で歩くことができていたが、それも難しくなった。
「誤嚥性肺炎によって、自分のやりたかった仕事が頓挫し、呼ばれていたイベントにも立てず、悔しい思いをしました。仕事を継続し、自分が目指すいろんなステージに立てるよう、手術を受けることに決めました」
武藤さんは一つの布石を打った。「声」を保存するのだ。話せなくなるALS患者の“自分の声”を救う共同プロジェクト「ALS SAVE VOICE」を立ち上げ、2019年7月から「視線入力×音声合成」サービスの提供を開始した。音声合成技術は、「コエステーションTM」というサービスを展開する東芝デジタルソリューションズに協力を仰いだ。このサービスを使って、自分の声からあらかじめ合成音声を生成。保存した「声」を、ロボット研究者の吉藤健太朗さん(32)らが開発した、視線入力できるソフト「OriHime eye」と連携させた。視線入力で操作し、自分の声を基にした合成音声を再生するのである。武藤さんは現在、ソフトを使いこなすための訓練を続けている。
「MOVE FES. 2019」ではEYE VDJをパフォーマンスしたほか、脳波でプレイする「BRAIN RAP」を披露した。「たとえ全身が動かなくなっても、表現できる手段をあきらめない」(提供:WITH ALS)
新しいオフィスは、「寝たきりになってもベッドを置いて働ける環境を」という前提で選定した。夜間だけでなく日中も呼吸器をつけるようになっても、将来、オフィスにベッドを置けば吸引もできる。いまは、車いすを机の横につけて座ったまま仕事をしている。車いすに視線入力装置を常に設置してある。声を失っても、たとえ寝たきりになったとしても、ここでこれまでどおりに働き続ける──そのためのオフィスである。
「ALSという病気になって、身体機能をいくつも奪われてきた。それでも、自分のやれることが、どんどん拡張していく。いまは実感をもってそう思えるから、今度の手術を前向きにとらえられるようになりました」
制度の壁と戦う
とはいえ、着替え、食事、排泄、移動など、生活のあらゆる場面に人の手が必要である。毎朝、電動車いすで自宅からオフィスへ通勤する。車いすへ移乗するときは、首ががくっと落ちないように、木綿子さんとヘルパーが二人がかりで頭を持ち上げ、ヘッドレストに乗せる。

出勤前の武藤さん。木綿子さん(左)とヘルパーの女性がサポートする(撮影:幸田大地)
はじめのうち、武藤さんは外部の人に介助を頼むことを拒んでいた。症状が進行するにつれ、働きながら介助を担っていた木綿子さんが体調を崩した。その姿を見て武藤さんは意識を切り替えた。木綿子さんが言う。
「あるとき、主人がきっぱりと言ってきたんです。『今度ヘルパーさんに入ってもらうようにしたからね』って。あんなに物事にこだわりがある人なのに、一度決めればパッと切り替えることができるんですよね。彼にとって大きな転換点だったと思います」
前出の詫間医師によれば、ALSは60代以上の人が多くかかる病気である。武藤さんのように30歳以下で発症する例は5%ほどだ。40歳未満の患者には介護保険制度が適用されない。車いすの購入も全額自己負担となる。障害者総合支援制度に基づく自立支援給付を利用するには複雑な手続きと行政との交渉をしなくてはならない。武藤さんは2017年、クラウドファンディングで資金を集め、40歳未満のALS患者のための車いすのシェア・レンタルサービスを立ち上げた。

オフィスまでの移動中は万が一に備えてヘルパーが付き添う(撮影:幸田大地)
2017年4月から「重度訪問介護」を利用している。「障害者総合支援法」に基づくサービスで、現在は1日24時間のヘルパーによる介助が認められている。ところが、申請は通っても担い手不足でシフトに穴が開く。介護事業所は慢性的な人手不足で、重度訪問介護に手が回らない。
「それなら自分たちで事業所をつくってしまおう」と、2019年1月に重度訪問介護事業所「WITH YOU」を立ち上げた。ALSに限らず重度の障がいを持つ人が対象である。
日本では、ALS患者の約7割が人工呼吸器をつけない選択をすると言われる。つまり死んでいくことを選択する。高齢になってから発症する例が多いこともあるが、患者の心理としては、24時間365日の介護体制に対する不安や、家族に負担を負わせることへの申し訳なさがある。
この状況を打破したい。それが、武藤さんが活動を続ける動機だ。
「人の世話になってばかりで、『自分らしさ』が損なわれると、未来に向かって生きていくのがどんどん怖くなってしまう。ALSはそういう病気だと思います。僕は若い年齢で発症したからこそ、みんなのQOL(生活の質)を支えていくテクノロジーだったり、仕組みだったりをいち早く見つけたい。みんなが使えるようにして、みんなが未来に踏み出せるようにしたいんです」

(撮影:幸田大地)
古川雅子(ふるかわ・まさこ)
ノンフィクションライター。栃木県出身。上智大学文学部卒業。「いのち」に向き合う人々をテーマとし、病や障がいを抱える当事者、医療・介護の従事者、科学と社会の接点で活躍するイノベーターたちの姿を追う。著書に『きょうだいリスク』(社会学者の平山亮との共著。朝日新書)がある。
[写真]
撮影:幸田大地
写真監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝