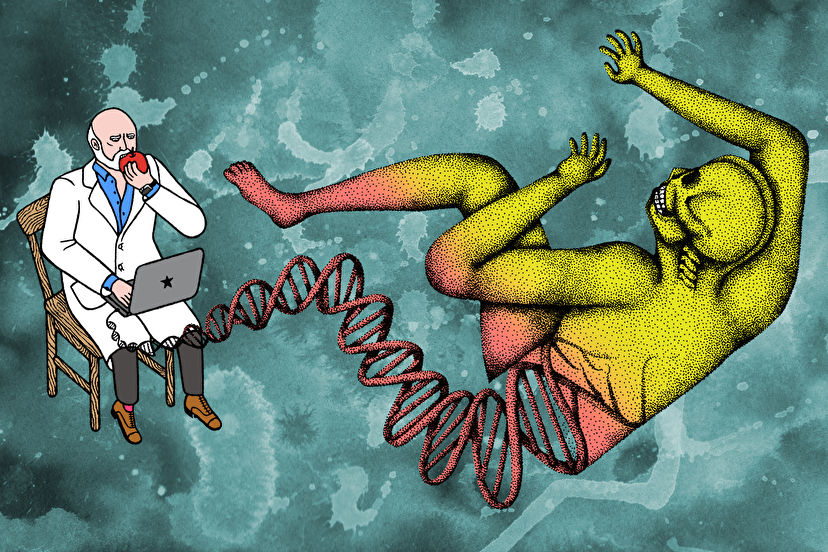親による虐待死、いじめ自殺--子どもを巡る悲しいニュースが相次ぎ、大きく報道されている。その一方で、このようなニュースに慣れてしまってはいないだろうか。2019年の本屋大賞に選ばれた『そして、バトンは渡された』の著者、瀬尾まいこは15年間教壇に立った元教師、そして一児の母でもある。子どもの世界を教師として、母として見てきた瀬尾が描く作品は、大人の優しさや愛を描き、話題になっている。なぜ、瀬尾が描く作品は「優しい」のか。(Yahoo!ニュース 特集編集部)
学校は「いじめ」に気がつくはず
瀬尾は講師として9年、教師として6年にわたり中学校で教鞭をとった。
「自分が教壇に立つ側になってみて、『こんなに生徒のこと見えてるんだ!』という驚きがありました。自分が生徒だったころの振る舞いなんかも思い出して、『全部バレてたんだな』って」
だから、子どものいじめによる自殺の報道の中で、学校側が「把握していなかった」という見解を聞くと違和感を抱くという。
「いじめの問題は、学校側は絶対誰かしら気づいているはずです。中学校で言えば、クラス担任がいて、科目ごとに教科担任がいて、という具合に複数の大人の目がある。教室という閉じた空間で、誰も大人が気づかないということは考えにくいです」
2019年本屋大賞を受賞した瀬尾まいこ
作品には、学校を舞台にした作品も多い。子どもが好きで、大学時代に教職を志した。デビュー作『卵の緒』で坊っちゃん文学賞大賞を受賞した2001年は、教員採用試験になかなか通らず、国語の講師として中学校に勤務していた時期だった。
受賞で「次の教員採用試験の自己PRに書くことができる」と思ったが、その後も2回不合格に。やっと教師になれたのは2004年だった。
「正規の教員になれない時期は、残念ではありましたけど絶望はしていませんでした。不安定な身分ではあるけれど、生活はできるし、まあなんとかなるでしょって。基本的にポジティブ思考の人間なんです」
中学校の教壇に立った経験は創作にも生きている
子どもの中でも中学生が一番「おもしろい」
教師として、生徒にどう向き合っていたのだろうか。
「教師は生徒にとって『通過点』であってほしいというスタンスで接していました。そっと背中を押してあげたり、簡単なアドバイスをしてあとは見守るような。ちょっとしたことで劇的に変わるのが中学生です。過度に干渉しなくてもいい。『種』は子どもたちのなかにあるんです。大切なのは『きっかけ』なんですね」
生徒一人ひとりは個性を持っている。目立つ子、手のかかる子、口数の少ない子……それぞれに「マニュアル」がないからこそのおもしろさがある。
「中学生って、ホントもどかしい時期なんです。100%子どもというわけではないんだけれど、かといって大人にもなりきれない。だからこそ、できることがあるキラキラした時期でもある。そんなふわふわした状態の子どもたちの成長を間近で見られるのが、中学教師の醍醐味かもしれませんね」
「子どもの中でも、中学生が一番面白い」と瀬尾は言い切る
毎朝、10分間の「朝読書」の時間には、瀬尾の著作を読む生徒もいて作品の設定や登場人物のその後について話すこともあった。ほかに担当できる教師がおらず、陸上競技はおろか、運動経験もないなかで陸上部の顧問を務めたことも作品のヒントになった。「ふわふわとした状態の子どもたち」と過ごした教師生活にはやりがいも面白さもあり、小説執筆とも溶け込んでいた。
「妊娠は難しい」35歳で経験した闘病、諦めた夢
正規の教員になって5年目を迎えた35歳のとき、瀬尾は病気になった。闘病のため、大好きだった教師の仕事も辞めた。
「医師から今後の妊娠は難しいだろうと言われて。もう子どもを産むのは無理なんだな、って思いました」
幼い頃から、子どもがずっと欲しかっただけに、ショックも大きかった。そこで、考え方を切り替えた。「自分の子どもを育てるのは無理でも、子どもたちと接する仕事はしたい」と、保育士を目指し、2年で資格を取得した。その間は執筆を一時中断して勉強を重ねたという。
2年間の猛勉強の末、保育士資格を取得した
無事に資格を取り、結婚して生活も落ち着いてきた39歳のとき、そろそろ保育士登録をしようかと思っていた矢先に「想定外」の出来事が起こる。手術後の経過観察のため、半年に一度訪れていた病院でのことだ。
「どうも体調が悪い。おかしいと思って診てもらったら、妊娠していたんです」
診察した医師も「うそやん」と言うくらい、誰もが予想していない事態だった。当の本人も、ただただ驚くばかりだった。2014年、無事に女の子を出産した。一度諦めた「母になる」という夢がかなった瞬間だった。
本屋大賞にノミネートされた段階で、かつて勤務していた中学校の元校長から連絡が来た
「学校だけで会う生徒とは違って、毎日顔を合わせていく存在ですからね。一日の予定ですらままならない。翻弄されながら、それでも毎日楽しくやっています」
子育てに「時間割」は無い。小説を執筆できるのは、娘が幼稚園に通う4時間ほどの間だけだ。教壇に立って生徒に教える立場から、幼稚園に送り出す親の立場になって気付いたことがある。
周囲に人がいるからこそ、書ける「優しさ」
『そして、バトンは渡された』という作品は、実の両親がおらず、保護者が次々と代わり、4度名字が変わった女子高生が主人公だ。一見、悲惨にも見えるこの設定だが、周囲はその主人公を優しく見守る。瀬尾の作品には、こうした大人の「優しさ」を感じるものが多い。その理由を聞くと、「私の周りには悪い大人はいなかった」という答えがかえってきた。
作品名は全て瀬尾が決めている。『そして、バトンは渡された』のタイトルは会心の出来だった
「私の小説は、いろいろな人との出会いから生まれてきました。たとえば中学校の子どもたち、その保護者、同僚の先生だったり。夫や娘もそうかもしれません。近所の町内会でのやりとりのようなことも、作品につながっています」
子どもを巡る悲しいニュースが報道されている一方で、報じられないが、学校や家庭、地域には優しく子どもを見守る「大人」という存在がある。それを体験として拾い、伝えていくことの重要性を感じている。
「わたしにできることは、書くことしかありません。人生にはいろんなことがあるし、しんどいことも多いけれど、私の作品を読んだ人にちょっとでもいい気持ちになってもらえたら。そう願いながら書いています」
それは周囲に人がいるからこそ、書けるという。そのためにも、新しいことにまだまだ挑戦するつもりだ。
「自分が体験したこと、見聞きしたことを書いていきたい。たとえば子育てが一段落したら、何か別の仕事をしてみたくなるかもしれません。今度こそ保育士に、というのはさすがに難しいかなと思いますが」
瀬尾まいこ
1974年、大阪府生まれ。大谷女子大学(現・大阪大谷大学)国文科卒。2001年、『卵の緒』で坊っちゃん文学賞大賞を受賞し、翌年単行本『卵の緒』(新潮社)で作家デビュー。2005年『幸福な食卓』(講談社)で吉川英治文学新人賞を、2008年『戸村飯店 青春100連発』(文藝春秋)で坪田譲治文学賞を受賞。他の作品に『僕らのごはんは明日で待ってる』(幻冬舎)『あと少し、もう少し』(新潮社)『春、戻る』(集英社)など。今年、『そして、バトンは渡された』(文藝春秋)で2019年本屋大賞(主催:NPO本屋大賞実行委員会、オフィシャルメディアパートナー:ヤフー)を受賞。近著に『傑作はまだ』(エムオン・エンタテインメント)。
撮影:殿村誠士