カフェのような外観。ロゴに灯台をあしらい、受付カウンターの足元には舵輪や漁具の浮き玉が転がっている。岩手県宮古市の中心街にある「ゲストハウス3710(ミナト)」。眼鏡店を改装した建物には、宿泊客だけでなく、さまざまな人たちが集まってくる。故郷に戻ってきた「若者」と震災後にやってきた「よそ者」が作ったこの場所は“新しい地元”づくりの拠点だ。東日本大震災から8年。東北沿岸部の被災地では復興工事が徐々に進む一方、人口減少が加速する。そんななか、地域の価値や魅力を見直し、コミュニティーを再生しようとする動きが各地で起こっている。3710に宿泊しながら、復興の新たなかたちを追った。(文・松本創、写真・八尋伸/Yahoo!ニュース 特集編集部)
きっかけは「帰郷した若者」と「よそ者」の出会い
JR宮古駅から徒歩数分。末広町商店街はかつて、周辺町村を含め10万人の商圏を抱えてにぎわった。海から約2キロ。震災では近くの川があふれ、70余りあった店舗の多くが平均1メートルほど浸水した。宮古市の死者・行方不明者は関連死を含め、569人。震災時に約5万9000人だった人口は6000人ほど減った。
その商店街の一角に昨年8月、3710はオープンした。

「ゲストハウス3710」のレセプション
海や港をイメージした内装は、漁業で栄えた港町を象徴すると同時に、「さまざまな人が立ち寄り、また船出してゆく場所」を表している。部屋は2階にある。二段ベッドが並ぶドミトリー(相部屋)を中心に定員18人。シャワーやキッチンは共用で、1泊3000円。1階は宿泊客以外も出入りできるコミュニティースペースになっていて、カフェやバーとしても営業している。「出会いが生まれる、町の玄関」がコンセプトだ。

「3710」の2階にある宿泊客用キッチンと交流スペース
スタッフは4人。「地元に戻った若者」と「よそ者」が2人ずついる。
3710の運営会社「日々旅」で代表取締役を務める加藤洋一郎さん(38)は、宮古の中心部から車で20分ほど離れた田老地区(旧・田老町)の出身。市内の高校を卒業後、東京の大学に進み、京都の大学院で国際政治学を修めた。さらに博士課程へ進もうと海外留学の予定を立て、その資金づくりのために一時帰郷し、実家のガソリンスタンドを手伝っていた時に震災に遭った。

加藤洋一郎さん
取締役の早川輝さん(32)は、福岡県北九州市出身。大学卒業後、ワーキングホリデーでオーストラリアを巡り、帰国した直後に震災が起きた。3カ月後、旅の続きのような感覚で、ボランティアとして宮古に入り、人生が変わる。子供の遊び場づくりや中学生の学習支援をし、その流れでNPO「みやっこベース」を設立。事務局長を務めながら、まちづくりにも関わってきた。
この30代の2人が経営面や許認可申請などをあずかる裏方とすれば、20代の2人は、ゲストへの対応、SNSでの情報発信、イベント企画などの「現場」を担当する。
佐山春さん(26)は、自らを「遊牧民族」と称する。幼い頃から関東や東北を転々とし、地元と呼べる場所がない。震災の時は仙台の高校を卒業した直後で、千葉県の実家にいた。東京の大学で3年生になった2013年、被災地の子供たちと夏休みを過ごすボランティア活動で初めて宮古を訪れ、以後、頻繁に通うようになる。そして、17年9月に移住してきた。

右から加藤さん、佐山春さん、村井旬さん
最年少の村井旬さん(22)は、代表の加藤さんと同じく田老出身。震災当時は中学2年生だった。盛岡市の高校に進学後、地元の復興にボランティアで関わるようになった。大学は県外に進んだが、ほどなく中退。北海道から沖縄まで、アルバイトをしながら1年ほど放浪し、宮古に戻ってきた時にゲストハウスに誘われた。
4人それぞれの震災体験と、その後の行動、少しずつ異なる地元への思い。それらが集まって、3710は生まれた。
「暮らしを誇りに」と目標を掲げ、「日常を開き、その価値に光を当てること」がミッションだという。ゲストを町にどんどん送り出し、地域の人と出会わせる。そうして記憶に残る旅を演出し、地元には多様性と刺激をもたらす。旅行会社のツアーに任せず、土地を深く知る人ならではの見どころや体験を提案する「着地型観光」の発想がある。
国際政治学から地域観光へ
2月15日。田老の人たちがかつて「万里の長城」と誇った巨大防潮堤の上で、代表の加藤さんが大学生8人に語りかけた。
「田老の歴史は、津波と、そこから立ち上がろうとする人びとの歴史です。東日本大震災では、宮古市内の地区で最多の181人が亡くなりましたが、1896年の明治三陸地震では1859人、当時の人口の82.6%が亡くなっている。生き残った17.4%の末裔が私です。先祖が生き延びてくれたおかげで、今みなさんにこうして話ができています」
田老地区の防潮堤の上で、加藤さんの説明を聞く大学生たち(撮影:松本創)
学生たちは、復興庁のインターン制度で宮古に滞在中。地元企業で1カ月余り研修を受ける間、3710に泊まっている。
加藤さんは、自分の言葉と体験を通じて震災を伝えようと、しばしばガイド役を務める。町の代名詞である大防潮堤はもちろん、4階まで津波をかぶり、下層階は柱だけになった震災遺構のホテル、繰り返し襲う津波に耐え、「田老人の不屈の象徴」といわれる三王岩……。
学生たちに配られた資料は、英語で書かれていた。加藤さんは震災後、国家資格の「通訳案内士」を取得し、外国人観光客向けに話をすることも多い。大学院時代、国際政治学の英語論文を読み込み、その後の留学に備えていくつも検定試験を受けてきた。それが今、役に立っている。
ゲストハウスをつくろうと思ったきっかけも英語だった、と加藤さんは振り返る。
震災の1週間後。田老地区の自宅も経営するガソリンスタンドもすっかり流され、瓦礫を片付けていた時、外国人の記者が来た。

田老地区を高台から望む加藤さん
「うちの前でたばこに火をつけようとしたので、『ガスが漏れて爆発するかもしれないからやめろ』と止めたんです。すると、『英語ができるなら津波の様子を教えてくれ』と言われ、取材になった。何度か取材を受けるうちに思ったんです。今まで自分のためだけに勉強してきたけれど、地元のためにも生かせるんじゃないか。インバウンドを呼び込み、自分の言葉で震災を伝えられるんじゃないか。それには、宿泊施設もあったほうがいいな、と」
加藤さんにとって、かつて地元はわずらわしく、生きづらい場所だった。30年ほど前、前身の田老町は人口約5500人。閉塞感があり、価値観は古く、話の合う相手もいない。早く都会へ出て、広い世界で学びたいと思っていた。望みがかない、東京の大学、京都の大学院で安全保障政策の理論研究に打ち込んだ。論文が学内の賞を受け、そのまま博士課程に進んで研究者になる選択もあった。
だが、ふと立ち止まる。25歳の時だ。
「ちょっと不安になったんですよね。社会でまともに働いた経験もなく、専門分野しか知らないままでいいんだろうか。いったん田老に帰って、家業を手伝うのもいいかもしれない。それなら留学資金も貯められる。30歳ぐらいまでに学問の道に戻れたら、と」

津波に襲われた当時の姿をそのまま残す田老地区のホテル。震災遺構として保存されている
5年ほど働き、そろそろ留学に踏み切ろうとしていた矢先、津波に襲われる。壊滅した故郷を目の前にして、海外に行くことなどできなくなった。ガソリンやプロパンガスを扱う家業は、救援車両や復興工事の重機、それに、山あいの仮設住宅に追いやられた被災者を支えるライフラインだった。
一方で、学問への思いも断ち難い。コツコツと英語を磨き、地元の知人と読書会を開き、勉強会に参加した。関心は次第に、国際政治から震災復興や地域の再生、その手段となる観光へと移っていった。震災から4年後の2015年、読書会のメンバーだった現・取締役の早川さんらと「宮古観光創生研究会」を立ち上げた。商工会議所が支援してくれ、ゲストハウスの構想が動きだす。
早川さんは言う。
「僕もオーストラリアを旅した経験から、ゲストハウスに興味を持っていたんです。外国人が安く気軽に利用でき、長期滞在できる。宮古にもそんな場所があれば面白い、と」

3710に置かれたパンフレット。外国語のものも多い
商店街を回って物件を探し、開業資金の一部はクラウドファンディングで集めた。目標額200万円を超え、約300万円に達した。東北の被災地で同じような活動を続ける仲間の支援が大きかったという。これに加え、加藤さんと地元の知人が出資し、株式会社「日々旅」を設立した。
早川さんは、NPOの活動で知り合った若者を2人連れてきた。それが佐山さんと村井さんだ。こうして4人がそろい、3710は開業した。
震災後に見つけた「地元」という価値観
2月16日の土曜日。3710のコミュニティースペースに30人余りが集まった。
宮古では初開催の「いわて若者会議」。岩手県の沿岸部で地域と深く関わる人たちの話を聞き、地元づくりのアイデアと可能性を探るイベントだ。震災をきっかけにUターンやIターンで岩手に住む人たちがトークゲストに呼ばれた。

「いわて若者会議」でのトーク
故郷の洋野町に戻り、海産物のブランド化や日本酒の販路拡大に取り組む女性。東京からボランティアで入った陸前高田市に居を移し、地域づくりのNPOを立ち上げた男性。司会の女性は、東京から久慈市へ移住し、観光海女となって地域をPRしているという。NHK朝の連続ドラマ『あまちゃん』を地でいくようだ。
3710の若いスタッフ2人もトークに加わった。
「遊牧民族」の佐山さんは、宮古に来るきっかけとなった「僕らの夏休みProject」の活動を紹介した。子供たちにサッカーを教えたり、一緒に工作をしたり、読み聞かせや紙芝居をしたり。30年前に途絶えた地域の祭りを復活させたこともある。そこで生まれた地域とのつながりが、ゲストハウスの仕事にも生きている。

「いわて若者会議」に集まった参加者たち

「いわて若者会議」で
佐山さんはもともと、小学校の教員になりたかったという。だから、これからも子供に関わり続けたい。3710を地域ぐるみの子育て拠点にしたいと考えている。
「地元への愛着って、子供の頃の思い出が大事なので、いろんな体験を作って次世代の記憶に残る町にしたい。それと、親のサポートですね。20代前半の若者なんだけど、早くに結婚して子供ができ、育児のためにいろんなことを諦めてしまう人が、この町には多いんです。そういう人しか残っていない。だから、もっと一緒に楽しみながら地域で子育てができればいいな、と」
最年少スタッフの村井さんは、田老での生い立ちから、紆余曲折を経て3710にたどり着くまでを語った。
中学では生徒会長。震災の日は、3年生を送り出す卒業式の準備中だった。自宅を流されたが、当初は現実味がなかった。喪失感が募ってきたのは、盛岡の高校に進み、地元を離れてからだ。早川さんの「みやっこベース」に参加し、たびたび帰省して町を見つめ直した。大学時代から中退後にかけては、全国を旅してゲストハウスを泊まり歩いた。その経験が今につながっている。
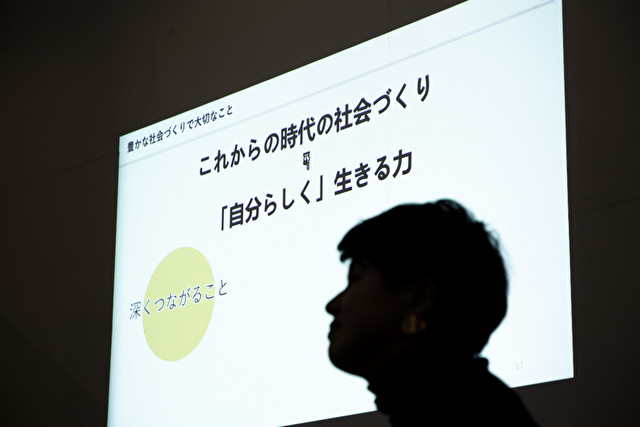
「いわて若者会議」で
「ゲストハウスって、入口が広く、人と人の垣根が低いから、自然と交流が深まるんです。ある県では地元の祭りでみこしをかつぎました。よく聞けば、一緒にかついでいる人が、もとはゲストハウスのお客さんで、移住者だったりする。そうやって外の人を呼び込むことで、まちづくりの一端を担っているんですよね。大学はコミュニティーデザイン専攻だったんですが、どこか第三者的な関わり方だった。僕はもっと当事者に近い立場で、自分も楽しみながらやりたい。ゲストハウスは、それにぴったりなんです」
3710で開かれた「いわて若者会議」は、明るさと活気にあふれていた。「地域や社会のためと気負うより、まずは自分が楽しもう」「人口が減少するからこそ、豊かになるまちづくりがある」「儲けることばかり考えてたら何もできない」……。
“新しい地元”をつくるということ。それは、震災を経て彼らが見つけた価値観や生き方と深くつながり、彼ら自身の自己表現にもなっているように見えた。
希望と絶望の先取り
それでも現実は厳しい。
国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、震災前年の2010年に27万4086人だった岩手県沿岸部12市町村の人口は、2045年には14万4139人になる。ほぼ半減だ。宮古市は、5万9430人から3万3688人へ。人口減少は日本全体の問題とはいえ、東北沿岸部はとりわけ著しい。

三陸鉄道北リアス線の田老駅で。3月23日には、久慈─盛(大船渡市)の163キロが全てつながる
3710代表の加藤さんも「ゲストハウスで交流人口を増やせば流れが変わる」と単純に考えているわけではない。
震災前に約4400人だった田老地区の人口は、最近ついに3000人を切った――。そんな情報も耳に届く。二つの小学校の一つは廃校が決まり、高齢化も進む。灯油やガスの配達で毎日回っていれば、衰退は肌感覚で分かる。高台にできた新しい団地にも空き家があり、集合住宅は家族用よりも独居用から埋まっていく。
「希望と絶望を先取りしている気がするんです」と加藤さんは言う。
――3710の取り組みが希望だとすれば、絶望とは?
「明るい取り組みを進めていても、下支えするコミュニティーがどんどん細っていく。田老では津波直後から『これでは町じゃなく、集落になっちゃうね』とよく言われました。それが現実になる可能性が高い。私自身、震災後に結婚して子供が生まれた今の状況で、いつまで田老にいて、この仕事を続けられるか正直分からない」
「だとすれば、田老という町があり、津波に抗って大防潮堤を造った人たちがいたという歴史を早く外の世界に伝えておきたい。ここに豊かな暮らしがあったことを人びとの記憶にとどめたい。ゲストハウスは、そのために自分ができる地元への最後の貢献かもしれない、と思うんです」

震災前の田老地区の全景。「道の駅・たろう」に掲示されている
加藤さんは最近、「もうすぐ復興が終わる」という言葉を地元でよく耳にする。道路や高台移転などの大型工事が2020年度には終了するという意味らしい。だが、本来の「復興」とは何か、インフラ復旧だけを指すのか。違うだろう。どんな町の姿を描き、暮らしを残すか。中身を議論し、仕組みをつくっていくべきだ。そう加藤さんは考えてきた。
昭和三陸地震の後、生き残った田老の人びとは「必敗の覚悟」で大防潮堤の建設を進めた、という。作家の髙山文彦氏が『大津波を生きる 巨大防潮堤と田老百年のいとなみ』に記している。自然の猛威に勝つことはできないが、それでも、少しでも被害が軽減するように、死者の魂が鎮まるようにと祈るようにして、全長2433メートルに及ぶ「X」字型の防潮堤を築き上げたのだ、と。
人口減少の大波には勝てないのだとしても、数十年先に「絶望」が待っているとしても、「必敗の覚悟」で復興の中身を描き、地元に提示する。
加藤さんらにとって「ゲストハウス3710」は、そういう存在なのかもしれない。

3710での交流会。地元の人を招き、笑顔もはじけた
松本創(まつもと・はじむ)
ノンフィクションライター。新聞記者を経てフリーに。関西を中心に、人物ルポやインタビュー、コラムを執筆。著書に『ふたつの震災 [1・17]の神戸から[3・11]の東北へ』(西岡研介氏との共著)、『誰が「橋下徹」をつくったか 大阪都構想とメディアの迷走』『軌道 福知山線脱線事故 JR西日本を変えた闘い』など。
[写真]
撮影:八尋伸
写真監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝



















