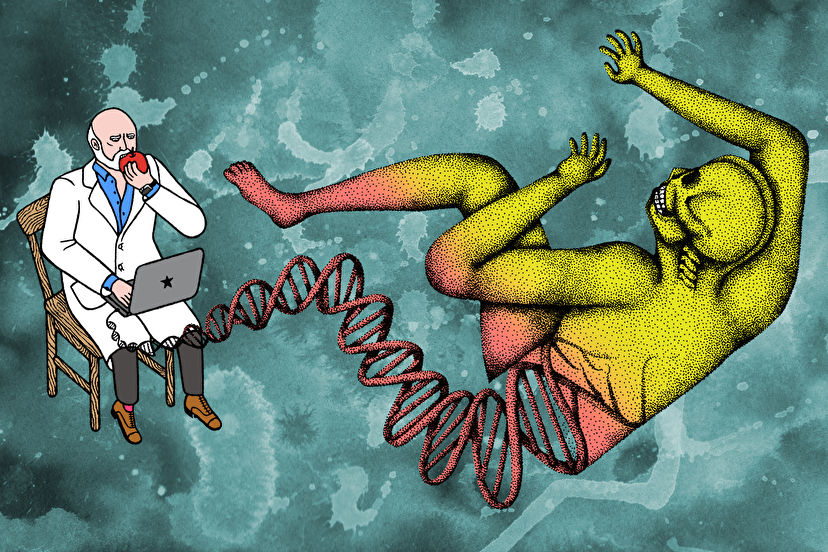『パレード』『悪人』『横道世之介』『さよなら渓谷』『怒り』……。数々の小説が映像化される作家・吉田修一。20年以上にわたり、純文学、エンタメの垣根を越えて書き続けてきた。実際に起きた事件を題材にすることも多く、作品は現代社会の様相を浮き彫りにする。世の中の「今」をどのようにつかむのだろうか。(取材・文:瀧井朝世/撮影:藤原江理奈/Yahoo!ニュース 特集編集部)
(文中敬称略)
書けるか分からない人物を書きたい
1997年にデビューし、昨年、作家生活20周年を迎えた吉田修一。芥川賞受賞作のような純文学作品からスパイが活躍するエンターテインメントまで、彼ほど、作風を広げてきた作家は珍しいだろう。次に発表するのはどんな小説なのか、全く予想できない書き手だ。
「いろんなタイプの小説を書きますねとよく言われますが、自分では違うものを書いている意識はないんです。いつもあるのはただ、“この人”を書きたいという感覚です。例えば、『悪人』(2007)だったら清水祐一という地方に住む青年、『横道世之介』(2009)なら世之介というバブル期に上京してきた大学生を書きたかったし、書くならああいう書き方しかなかった」

映画『悪人』で、殺人を犯した清水祐一を演じる妻夫木聡(右)と、彼と逃避行に及ぶ女性を演じた深津絵里(左)。©2010「悪人」製作委員会
でも、“書ける”と思う人物は書きたくない。書けるかどうか分からないと感じるからこそ、チャレンジしたくなるという。
「夏、子どもが川に飛び込んだりする時に、“去年はこの岩から飛んだけど、今年はちょっと高いところから飛ぼう”と思うじゃないですか(笑)。あの感じです。“ちょっと別の岩に挑戦してみたい”ということを毎回続けてきたんだと思います」
2002年に芥川賞を受賞した『パーク・ライフ』は都市小説と呼ばれ、“純文学作品にスターバックスが登場した”と話題になった。一方で『悪人』や『怒り』(2014)では殺人事件を絡めながら地方での生活の閉塞感を描き出すなど、作品には常に時代性、あるいは社会性が感じられる。しかしそれは、意識したうえでのことではない。

「現代の日本に暮らしていれば、何を書こうが現代性は自然と出てくるはず。小説にスターバックスを書いたのだって、普段自分が行っていたからですし、『東京湾景』(2003)でお台場や湾岸を出したのは、昔湾岸の倉庫で働いていたからですし(笑)。わざわざ意識して何かを書くというよりも、逆に何も考えていないから現代性が出てくるのかもしれません。僕はただ、ディテールを積み重ねているだけです」

それを言うなら映画化作品のほうが時代性が表れている気がする、とも。これまでに『パレード』(2002)、『悪人』『横道世之介』『怒り』など多くの作品が映像化されており、今後も『犯罪小説集』(2016)を元にした『楽園』(2019年公開予定)、『太陽は動かない』(2020年公開予定)が発表されている。
「僕がディテールを細かく積み上げていった小説から、映画監督やプロデューサーが本能的にテーマをつかみ出しているように感じるんです。つまり、小説はディテールから始まってテーマが表れてくるけれど、映画はテーマから広がってディテールが作られていく。僕の頭の中ではそういうイメージです」
“芯”だけが残った時に犯罪は起こる
「小説を書くために生活をしていない」と言う。どういうことかといえば、小説の題材を探しながら日々を生きてはいない、ということだ。ただ、『横道世之介』で描かれる駅ホーム転落事故や、『さよなら渓谷』(2008)のレイプ事件、『太陽は動かない』(2012)で書かれた幼児ネグレクト事件は実際のニュースを知ったことが元になっているし、『橋を渡る』(2016)に至ってはセウォル号沈没事故をはじめ実際の時事問題が多分に盛り込まれている。

2014年4月16日、韓国の大型旅客船セウォル号が沈没。完全沈没までに50時間以上あったにもかかわらず、乗員・乗客476人中295人が死亡し、9人が行方不明になった(写真:ロイター/アフロ)
「不思議なことに、気になるニュースは自然と目に入ってきて、いつまでも残るんです。普段テレビはドキュメント番組以外、ほとんど見ないんですけれど、その番組も調べて見るというよりは、たまたまネットを見ていて、“あ、今日インパール作戦の番組があるから見よう”となったりしますし。それも小説のためではなくて、自分の興味として見よう、という感覚です。そうしていると、自分の中に気になる出来事として残っていくものがある。そこから物語が膨らんでいくんです。誰かから“こういう面白い事件があったから小説を書きませんか”と言われても書けない。唯一、『犯罪小説集』(2016)という短編集だけは、意識的に実際の事件を元に書きましたが、自分で題材とする事件を選ぶと似通ってしまうと思い、最初に担当編集者に多めに選んでもらい、そこから自分で選択しています。なので、この作品だけは他の作品と違って、少し歪(いびつ)な印象があるんですよね」

振り返ってみれば、初期の頃から吉田の小説には、主軸であろうとなかろうと犯罪が影をさすことが多い。それはなぜか。
「いろんな作りごとや嘘を取っ払った後に残る世界と、犯罪の世界というのが、すごく近く感じるんです。犯罪は人間のにおいがするというか、人間のいろんなものを取り払っていって、本当に芯だけが残った時に犯罪は起こる気がするんですよね。そういう意味で惹かれるものがある。もちろん興味本位で書いているわけではありませんが」

小説『怒り』は2007年に起きた「リンゼイ・アン・ホーカーさん殺害事件」に触発された作品。渡辺謙(右)、宮﨑あおい(左)、綾野剛、妻夫木聡、広瀬すず、松山ケンイチ、森山未來などのキャストで映画化された。©2016映画「怒り」製作委員会
登場人物を通して世の中が見える
では例えば、新作『国宝』の発端はどこにあったのか。これは前回の東京オリンピックの1964年から始まり現在に至るまでの、類いまれな美貌に恵まれた歌舞伎役者の物語だ。長崎の任侠の一門に生まれ、やがて上方歌舞伎の世界に足を踏みいれ、数々のスキャンダルに見舞われながらも己の道を邁進していくという、特異な人生を歩む立花喜久雄の一代記。〈~でございます〉などが使われる口上調の文体で、煌(きら)びやかな世界の光と闇の強烈なコントラストを克明に文字にして刻んでいく。これが歌舞伎の知識がほぼない状態からのスタートだったというから驚きだ。
「初めての新聞連載だった『悪人』から10年、また同じ朝日新聞で連載をするということで、前作を超えたいと思いました。それで、これまで書いたことのないスケールの大きなものにしようと考えた時、歌舞伎の世界がピタッとハマったんです。歌舞伎は全く詳しいわけではなく、むしろ未知の世界だからこそ興味が湧きました」

つまり、次に川に飛び込む足場として、これまでとは全く違う岩場を見つけたというわけだ。
「裏方の視点から歌舞伎の世界を書いた小説や映画はわりとあるので、僕はど真ん中、つまり“一番真ん中に立つ人で書いてやろう”と思いました。実際の歌舞伎のど真ん中は立役なのかもしれませんが、選んだのは女形のど真ん中です。一代記を書くのも初めてですし、歌舞伎の舞台という視覚的に華やかなものを文章化するのもチャレンジです。この文体も初めてですが、本当に2、3カ月かけていろんな書き方を試して、結局、一行読めばこれは伝統芸能の世界の話だと分かる、この文体にたどり着きました」
では、全く歌舞伎の知識のないところから、どのようにして梨園の奥深い部分まで描き出せたのか。そこには、強力な助っ人との巡り合いがあった。
四代目中村鴈治郎(左)と(写真提供:吉田)
「準備期間のうち一番大きかったのは、知人に四代目中村鴈治郎(がんじろう)さんを紹介してもらえたことでした。“歌舞伎の世界を舞台にした小説を書きたいんです”と言ったら、“じゃあ、黒衣の衣装を作ってあげましょう。それを着て舞台裏にいれば目立たないから”って。鴈治郎さんは毎月どこかの舞台に出演されているので、歌舞伎座はもちろん、博多座、御園座や、地方の舞台にも一緒に回らせてもらって、成駒家の弟子の一人のつもりになって楽屋にいさせてもらったんです。楽屋から舞台に荷物を運び、鴈治郎さんが出ている時は舞台袖に正座して観て。夜は飲みに連れていっていただいたので、まさに歌舞伎役者の一日を近くで見ることができました。役者の疲れ具合や笑い方といった何気ない面をそばで見させてもらえたのはよかったですね」
書き始めると、一場面一場面、どうしたら煌びやかになるか、挑戦するうちにストーリーが先へと進んでいった。波乱に満ちた道を、頂点だけを目指して進む主人公の喜久雄がやがて見る景色とは――。
「最終的にどこに行き着くのか、自分でも分からないままに書いていました。書き終わってからようやく、自分はこのラストシーンを喜久雄に見せたかったんだと思いました。後付けですが、喜久雄の人生はすごく現代的な気がします。というのも、彼ほどの天才的な役者さんは、現代では生きづらさを感じてしまうと思うから」

『国宝』は昭和から平成にかけての芸能史としても読むことができる。伝統芸能の世界を舞台にしても、遠景に時代の移ろいを書き込み、そしてたどり着く現代のありようをわれわれに見せてくれる。つまり『国宝』は今の時代に生きる作家だからこそ書けた一作なのだ。
「1960年代から現代までの世の中の変化はなんだと思いますか? と聞かれても、答えられない。でも喜久雄という人間を通してなら書ける。それと同じで、“こういう事件がありましたが、それについてテレビでコメントしてください”と言われても、たぶん言葉が出てこないんです。でも、何かの事件を知ってそれが心に残ると小説に書いてみたくなるし、書けるんですね」
若い頃に見たリトルロック高校事件の写真
文章を書くのは小説とエッセーだけで十分、だからSNSはやらない。自分で感じたことを、小説以外で発信したいと思ったことはない。しかし意外なことに、他人のSNSは見ているのだという。「新刊が出た時はエゴサーチしますよ」と、率直に言ってのける。とすれば批判的な感想や、的外れな意見も目に入ってくるのではないだろうか。
「僕、全然平気なんですよ。そのへんは打たれ強い。別に参考にするとかということではなくて、ただ気になるので見ているだけです。前におかしかったのが、『太陽は動かない』が出た時だったか、郊外に向かうガラガラの電車で、“吉田修一”でエゴサーチしたんですよ。そうしたら一番上に出たのが、“今、目の前に作家の吉田修一が座ってるよ”というツイート。“ん!?”とパッと前を見たら、学生っぽい男が知らーん顔して座っていて。ガラガラだったから、どう考えてもその人しかいないんですよ。声かけるわけにもいかないし、お互い20分くらい澄ました顔で座っていましたね」
そう、おかしそうに語る。

ただ、そうしてネットを眺めているのなら、たとえば#MeToo運動や女性蔑視など差別的表現に対する繊細さが増すなど、世の中の人々のモラルや意識の変化も目の当たりにしているはずで、作品上でのそれらへの配慮は深まったりしないのだろうか。
「昔から変わりません。僕は以前から、そういうことに関しては、自分なりに丁寧に向き合ってきたつもりでいます。というのも、差別や何かのニュースを見たりした時に、いつも頭に浮かんでくる写真があるんですよ」
それは、若い頃に見たリトルロック高校事件(米アーカンソー州)の写真だという。教育機関の人種分離の撤廃が進むなか、1957年に起きた騒動を写真家のデイビッド・マルゴリックが撮影したものだ。

1957年9月4日、リトルロック高校に登校するエリザベス・エックフォード(中央)。黒人学生の登校を阻止するために送られた州兵と、反対する白人学生に囲まれた。背後で罵声を浴びせる女子生徒は、ヘイゼル・ブライアン(右)。40年後、2人は和解した(写真提供:ZUMA PRESS/アフロ)
「それまで白人の学生しかいなかったリトルロック高校にはじめて黒人の女の子が登校する時の様子を撮ったものなんですが、すごい顔をして、おそらく“帰れ”と叫んでいる白人の女子学生が写っている。その顔を見た時に、本当に“こんなふうにはなりたくない”と思ったんです。たぶん、彼女にとって自分の行動は学校を守るための正義なんですよ。自分の正しさを表現した顔がああなるのかと思ったことが、鮮烈に記憶に残っています。しかも、40年後に同じ写真家が撮った2人の写真もあるんです」
みんながいなくなった後に見る景色
社会の価値観は変わっていく。だから自分なりに極力気を付けているつもりではいる。しかし、安易に世の中の影響を受けはしない。大多数の意見を常に把握しておこう、とも思っていない。
「小説家は“個人”の仕事だと思うんですよ。要するに、一人でやっていること。読者ももちろん一人で、“読書”には一対一の関係が成り立っている。だとしたら、大勢で一緒に見る景色よりも、みんながいなくなった後、たった一人で見る景色の価値も信じたい。もしかすると、そっちのほうが、本物の景色という気がします。みんなにどう見えているかではなくて、自分に見える景色を信じる。それが正しいか正しくないかは分かりません。でも、きちんと自分で考えて、責任を持ちたい。だからこそ、そうなれるように、まずはいろんな人の声を聞くべきだと思うんです」

吉田修一(よしだ・しゅういち)
1968年、長崎県生まれ。97年に『最後の息子』で文学界新人賞を受賞し、デビュー。2002年には『パレード』で山本周五郎賞、『パーク・ライフ』で芥川賞を受賞。純文学と大衆小説の文学賞を併せて受賞し話題に。作品は英語、仏語、中国語、韓国語などにも翻訳。2016年から芥川賞選考委員。最新作は『国宝』。