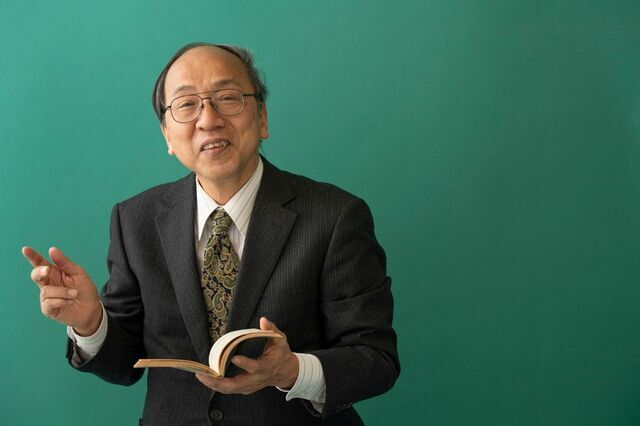出世のために最高裁の顔色をうかがう…実は日本以外にはほとんどない裁判官の「ヒエラルキー的キャリアシステム」
裁判官と「法」の関係
ここで、裁判官と「法」の関係についてもふれておきたい。 裁判官は、認定された事実に法を適用して判決を行うとされる。これは、大筋では正しい。 しかし、実際には、事実認定自体評価的な作業であり、法の適用についてはさらにそういえる。また、現実の裁判では、裁判官の判断は、総合的な直感でもたらされる部分が大きい。これは、たとえば執筆や研究等の総合的な創造作用一般についてもいえることであり、脳神経科学者等自然科学者の多くも肯定している。 もっとも、判決を書く際には、経験則(経験から帰納された物事に関する知識や法則)を前提とする事実の積み重ねによって結論が導き出されたように書かなければ、説得力がなく、検証も難しいので、そうする。しかし、これは、裁判官にとっては、実際には、後付けの検証過程なのである(陪審員裁判の場合には、基本的に、結論だけがブラックボックスで示される。「市民による裁判なのだからそれでよい」との考え方に基づく)。 「リアリズム法学」の代表格の学者・実務家(弁護士、裁判官、行政官)、ジェローム・フランク(1889~1957)は、こうした裁判官の判断過程を直視し、「法」が固定した不変のものであってそこから演繹的に結論が導き出されるという伝統的な考え方をドグマとしてしりぞけた。そして、社会・人文科学一般の分析を援用しながら、実際には、裁判官こそが、法を欲し、法を創造し、また、変更しているのであり、書かれた「法」は、裁判官が判断を行うに当たっての「一つの素材」ないしは「判断を規整する一つの枠組み」でしかないとした。 彼は、判決は、「法律」と「事実」によって決定されるというよりも、いずれかといえばむしろ、「(広義の裁判過程において裁判官に与えられる)刺激」と「(裁判官の)人格」によって決定されると定式化した。ここで、「刺激」というのは、裁判官の外側から裁判官に働きかける諸要素であって、証拠、法律のほか、世論等の社会的な諸要因をも含み、「人格」というのは、裁判官個人に属する諸要素であって、性格、各種の偏見ないし嗜好、習慣ないし性癖等を含むと考えられる。 要するに、フランクは、法的判断とは、法をその規整の枠組みとしながらも、本質的には、裁判官の個人的な価値選択であり、政策判断であり、その全人格の反映であると論じたのである(以上の記述については、フランクの著作『法と現代精神』〔棚瀬孝雄・棚瀬一代訳。弘文堂〕、『裁かれる裁判所』〔古賀正義訳。同〕のほか、田中成明ほか『法思想史〔第2版〕』〔有斐閣〕を参考にさせていただいた)。 フランクのリアリズム法学は、アメリカにおける哲学流派、哲学的方法の代表的なものであるプラグマティズムの系譜を引いている。私自身の思想もプラグマティズムから大きな影響を受けており、また、フランク同様理論と実務の双方にたずさわってきた人間だという事情もあって、私には、うなずける部分が大きい。 もっとも、フランクの考え方が当てはまる度合は、単純・定型的な事件の場合ほど小さく(そうした事件では、事実認定も簡単であり、法の適用も一義的である。たとえば単純な貸金事件等)、社会的価値、大きな正義の実現にかかわる事件ほど大きくなる。 よくいわれる「裁判官の良心」(憲法七六条三項)というものの実質も、こうした裁判過程の社会科学的な考察を基盤にしないと、単なるイデオロギー論争になってしまうおそれがあることには、留意していただきたい。 * さらに【つづき】〈「日本的」右派も「日本的」左派も共有する 「裁判官幻想」…多くの一般人が知らない、「裁判と裁判官をめぐるリアルな真実」〉では、裁判・裁判官をめぐる儀礼と幻想について、くわしくみていきます。
瀬木 比呂志(明治大学教授・元裁判官)