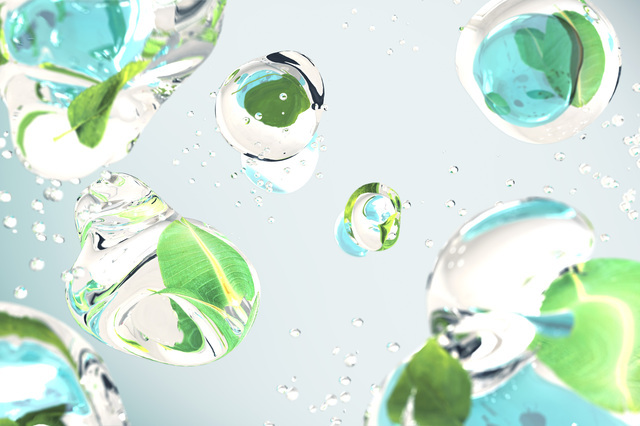人類究極のナゾ、「言葉」とはなにか…日本の哲学者が出した「驚きの答え」
明治維新以降、日本の哲学者たちは悩み続けてきた。「言葉」や「身体」、「自然」、「社会・国家」とは何かを考え続けてきた。そんな先人たちの知的格闘の延長線上に、今日の私たちは立っている。『日本哲学入門』では、日本人が何を考えてきたのか、その本質を紹介している。 【画像】日本でもっとも有名な哲学者がたどり着いた「圧巻の視点」 ※本記事は藤田正勝『日本哲学入門』から抜粋、編集したものです。
不可思議な「言葉」
一般に「言葉とは何か」ということを考えてみると、二通りの理解が成り立つように思われる。 第一に考えられるのは、言葉は、考えるための、あるいは考えたものを表現するための道具である、という理解である。つまり言葉は、あらかじめ存在している思考の内容──それは日本語とか英語といった具体的な言語、自然言語以前のものと言わざるをえないであろう──に形を与えるものであるという考えである。 それに対して、第二に、思考は言葉を通してはじめて成立するのであり、言葉は思考の単なる道具ではない、という考え方も成り立つ。つまり、思想は言葉という形をえて、はじめて思想として成立するのであり、それ以前に純粋な思想というものがあるわけではない、という考え方である。 この二つの考え方は、それぞれ次のような考えに結びついている。 第一の見方は、私たちが日本語なり、英語なり、自分の言語(母語)を使う以前に、つまり、水とか、木とか、土とか、あるいは water とか、tree とか、soil といったことばを使う以前に、言いかえれば、ある事柄にそういう名前をつける以前に、もの、あるいは世界が客観的に区分(分節、articulate)されていて、それぞれに、いわば偶然的な仕方で、たとえば日本語であれば「水」という名前を、英語であれば “water” という名前をつけているのだ、という考えと結びついている。ここでは言葉は、一つの符牒として、つまり道具とみなされている。
ものは言葉で分節される
それに対して、第二の見方の方は、ものは言葉以前にあらかじめ分節されているのではなく、言葉とともに、はじめて分節される、つまり言葉によって世界の見え方、あるいは世界の現れ方が決まってくる、という考えと結びついている。 具体的な例を挙げて説明することにしたい。たとえば「青い」ということばをとってみると、まず、それに対応するものが世界のなかに客観的に存在しており、日本語を使う人はそれを「青い」ということばで、英語を使う人は “blue” ということばで言い表しているというようにも考えられる。 しかし厳密に見てみると、どうもそうではないことがわかってくる。日本語ではたとえば「草木が青々と茂っている」と言ったりするが、実際には緑色のことである。「青信号」といったことばもそうであるが、「青い」という日本語は、緑色系統の色をも指すことばとして使われてきた。黄色(yellow, gelb...)にせよ、赤(red, rot...)にせよ、それぞれの言語でそれが指す範囲は少しずつ異なっている。 別の例を挙げれば、日本語では樹木と材木をともに「木」と表現するが、英語では樹木の方は “tree” 材木の方は “wood” と、ドイツ語では樹木は “Baum” と材木は “Holz” ということばで表現される。そして “wood” や “Holz” ということばは材木という意味だけでなく、森という意味をももっている。それに対して日本語の「木」や「材木」が森という意味で使われることはない。 こうした例を手がかりに考えると、以上に挙げた二つの見方のうち、第二の見方の方が、言葉の本質をとらえていると言えるであろう。日本語なら日本語、英語なら英語、ドイツ語ならドイツ語というように、それぞれの言語において、いわば一つの連続体であるような知覚対象(自然)が、独自の仕方で区分(分節)されているのである。つまり、それぞれの言語においてそれぞれの仕方で、知覚対象に切れ目が入れられ、そのそれぞれに独自の名前(青や赤、blue や red)が付けられているのである。 さらに連載記事〈日本でもっとも有名な哲学者はどんな答えに辿りついたのか…私たちの価値観を揺るがす「圧巻の視点」〉では、日本哲学のことをより深く知るための重要ポイントを紹介しています。
藤田 正勝