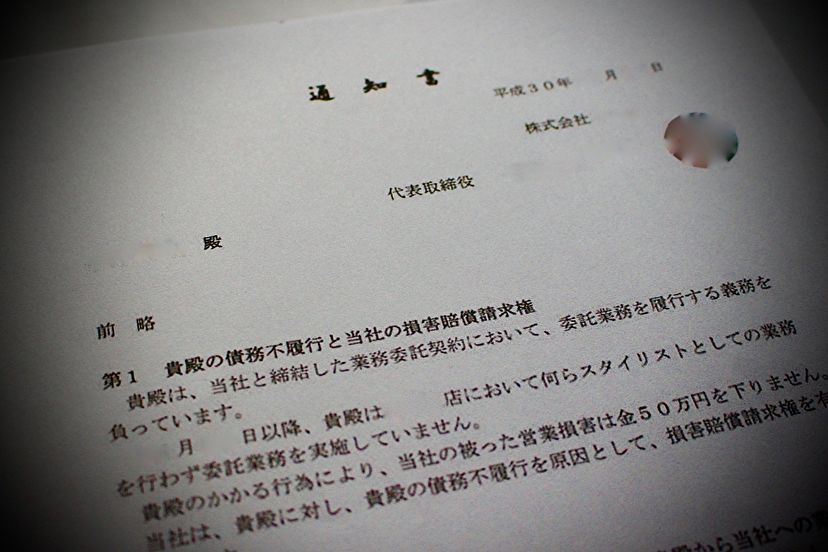正社員と同じ仕事、同じ責任なのに、賃金は半分でボーナスも手当もない――。非正規労働者が4割を占める現在、そうした思いを抱くパートや契約社員、嘱託社員は少なくない。こうした中、民主党政権下で決まった改正労働契約法20条が2013年4月に施行され、有期契約労働者と正社員の間で労働条件に不合理な差を付けることが禁じられた。そして今、これを「武器」として、非正規労働者が勤め先を相手取り、差額賃金などの損害賠償を求める「20条裁判」が相次いでいる。働き手が自身の手で格差を是正することはできるのだろうか。原告たちを訪ね歩いた。(藤田和恵/Yahoo!ニュース 特集編集部)
昼食は地下鉄駅ホームのベンチで
地下鉄のホームを数分おきに電車が行き交う。そのたびに人波が揺れる。平日の正午過ぎ。手元の携帯用温度計は30.5度を示していた。蒸し暑い。ホームに置かれたベンチの端をなでると、指先が真っ黒になる。車輪とレールの摩擦によって飛散した鉄粉だ。
地下鉄のホームはいつも人で溢れる(撮影:藤田和恵)
地下鉄駅売店の販売員・後呂(うしろ)良子さん(63)は毎日のように、このベンチでお昼を食べる。
「売店の中は狭くて飲食はできませんから。ホームでおにぎりかサンドイッチを食べるしかないんです」
後呂さんは東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員だ。入社から11年。この間、1年ごとの契約更新を繰り返してきた。手取りは毎月約13万円で、正社員に支給される家族手当や住宅手当、退職金はない。ボーナスも5分の1にすぎず、退職金を含めた賃金の合計額は正社員の半分に満たない。
駅の売店で働く後呂良子さん(撮影:藤田和恵)
一人暮らしで、家計はカツカツだという。同じ売店勤務の正社員の中には、連れ立って地上の飲食店へとランチに出掛ける人もいる。後呂さんは「私には外食なんて、とうてい望めないぜいたくです」と話した。
「トイレに行けないから水分を取りません」
賃金や待遇に大きな差はあっても、仕事の大変さは契約社員でも正社員でもほとんど変わらない。
朝、シャッターを開け、パンや菓子、飲料などを並べる。マグカップや地下鉄の模型、文房具といった何種類もの土産物も一つ一つラッピングする。終日、立ちっぱなしで接客を続け、商品の発注や補充、売上金の計算も担う。
開店すると、販売員は店を離れられない(撮影:藤田和恵)
「早番」と「遅番」を交代でこなし、労働時間は1日約8時間。原則、1人で切り盛りするため、昼休みなどを除くと、トイレにも行けない。後呂さんによると、膀胱炎を患って辞めた同僚もいたし、尿漏れパッドや替えの下着を準備している人も多いという。
「私は、朝はできるだけ水分を取りません。閉店後は真っ先にトイレです。1人態勢なので、風邪くらいじゃ休めません。いつだったか、勤務の前日に脚にやけどをしたんですが、あの時も当たり前に出勤しました」
働く後呂さん(撮影:藤田和恵)
責任感と緊張感は時に正社員以上です、と後呂さんは言う。
「新しい売店に移る時、契約社員の友人たちは事前に休みを返上して自腹で勤務先に行って鍵の保管場所などを確認します。私も売店が変わるたびに、たばこの位置をイラストに描いて頭に叩き込みます。新宿駅の売店では、万引きの多い時間帯を割り出し、売り場から目を離さないようにして被害額を大幅に減らしたこともあるんですよ。なぜそんなことまでするか、分かりますか? 契約社員はいつだって、雇い止めにおびえているからです」
正社員との格差是正のために提訴
後呂さんら60代の契約社員4人がメトロコマースを訴えたのは、2014年5月である。差額賃金など計約4560万円の損害賠償などを求める内容で、拠り所は労働契約法20条などだった。
東京メトロの本社ビル(撮影:藤田和恵)
この条項は、政府が進める「同一労働同一賃金」の考え方にも合致しており、有期契約労働者(非正規)と無期契約労働者(正社員)の労働条件に不合理な格差があってはならない、と定めている。
裁判はどうなったか。
この3月、一審の東京地裁で後呂さんらは敗訴した。判決は「(非正規と)正社員とは業務内容や責任の程度に大きな違いがある」とし、給与などの格差はあって当然と結論付けている。
判決の分かれ目は、何と何を比較したか、にあった。裁判所は後呂さんたちの労働条件を、売店で働く正社員約20人ではなく、本社総務部などを含む約600人の社員全員と比べたのだ。管理部門などのデスクワークと販売員の仕事は違って当たり前であり、売店と本社との人事異動もほとんどない。
なぜ、本社の正社員にまで比較対象を広げたのか。後呂さんは「会社を勝たせるために考え出された理屈としか思えない」と振り返る。
東京地裁が入る裁判所庁舎(撮影:藤田和恵)
判決はまた、「正社員に対する福利厚生を手厚くし、有為な人材の確保・定着を図ることには合理性がある」とも断じた。原告たちはこの点にも納得できない。
「私たち契約社員は役に立たない、無能な人材だと言っているのと同じことです。会社と司法はどこまで私たちを差別するつもりなんでしょうか」
郵便配達の現場でも
郵便配達の現場でも、同じ問題は起きている。猛烈な暑さが続いていた7月、浅川喜義さん(46)に会った。二の腕から先が真っ黒に日焼けしている。正規か非正規かに関係なく、この季節、多くの郵便配達員は同じように日焼けする。正社員と変わらぬ仕事をしている証なのに、年収は正社員の3分の1ほどだという。
浅川喜義さん。二の腕から先が見事に日焼けしている(撮影:藤田和恵)
浅川さんは日本郵便の期間雇用社員で、東京・晴海郵便局で働いている。契約は半年更新ながら、勤続10年のベテランだ。通常の配達区に加え、速達や時間指定郵便物などを配る広域の「混合区」も任される。その経験を買われ、正社員の新人の教育係を務めることもある。
日本郵便では雇用形態に関係なく、全社員に年賀はがきや暑中見舞いはがき「かもめーる」などの販売ノルマが課せられる。浅川さんはこれもこなし、ここ数年は正社員を含めた局員約250人のうちベスト5以内の成績を維持しているという。客とのトラブル対応にも雇用形態の区別はない。
暑中見舞いはがき「かもめーる」(撮影:藤田和恵)
仕事内容は正社員と同じどころか、期間雇用社員のほうが大変なこともある、と浅川さんは訴える。
「配達業務が最も忙しいのは年末年始です。正社員は祝日の代休や『計画年休』を制度として取得できるので、年が明けると、順番に連休を取る。その穴は僕らが埋めるしかありません。期間雇用社員が一息つくことができるのは、4月に入ってからですね」
非正規の割合は半分近く 重要な戦力
日本郵便によると、同社の正社員は約20万人で、期間雇用社員は約18万人。非正規雇用の割合は半分近い。郵便配達の現場では、期間雇用社員は欠かせない戦力と言ってよい。
待遇はどうだろうか。
日本郵政本社。同じ建物内に千代田霞が関郵便局がある(撮影:藤田和恵)
日本郵便の親会社・日本郵政によると、正社員の平均年収は2012年にグループ会社全体で約606万円だった。これに対し、期間雇用社員は約227万円。年末年始勤務手当や住居手当、夏季・冬季休暇などは正社員だけだ。ボーナスも年間で約100万円の差がつく。
浅川さんは、日本郵政公社が民営化された2007年に入社した。当時は「民間会社なら正社員になれるかもしれない」との期待があったという。実際、2010年には亀井静香郵政担当相(当時)が「基本的に希望者は正社員としていく」との方針を示し、約10万人を正社員にする構想も持ち上がった。
現実には正社員化の門は狭く、浅川さんも登用試験の不合格が続いている。「それなら、せめて正社員並みの待遇を」と、浅川さんら期間雇用社員3人は2014年5月、差額賃金などを求めて日本郵便を提訴した。
浅川さん(撮影:藤田和恵)
西日本でも同様の提訴が大阪地裁で行われ、原告8人は働きながら会社を相手に訴訟を続けている。結婚し、子どもを育てる原告の中には賃金だけで生活できず、一時的に生活保護を受給していた人もいるという。
浅川さんはこんな体験談も披露してくれた。
「いわゆる合コンに参加した時。僕が非正規雇用と分かった途端、女性がサーッと周囲から引いていきました。僕自身、結婚願望はあまりないんですが、仮にあったとしても『相手とみなされていないんだ』と思い知らされました。人並み以上に働いても、給料や待遇がこのありさまでは……彼女たちの判断は正しいと思いますよ」
郵便は多くの非正規の働き手に支えられている(撮影:藤田和恵)
浅川さんらが原告の裁判は9月に東京地裁で判決がある。大阪地裁での裁判は同じ9月に最終弁論がある。
定年後再雇用のベテランドライバー
最後にもう1人、「20条裁判」の原告を紹介しよう。ドライバー歴30年以上の山口修さん(63)。セメントや液化ガスの輸送を手掛ける神奈川県の長澤運輸でトラックのハンドルを握っている。
山口さんは2014年10月1日の朝を今も忘れない。
午前3時、枕元の目覚まし時計を止めた。「きょうも寝過ごさなかった」という安心感、「これからハンドルを握る」という緊張感。いつもと同様の朝だったが、この日を境に給料は3割減った。前日の9月30日に定年退職し、再雇用による1年契約の嘱託社員へと身分が変わったからだ。

神奈川県の本牧ふ頭。多くのトラックが行き交う(イメージ:アフロ)
仕事は定年前と「寸分違わず同じ」である。乗車日数も、売上額も、走行距離も。「バラ車」と呼ばれるセメント運搬用のトラックも、乗り慣れた車両を充てられたという。変わったのは、500万円から360万円に下がった年収だけだ。
山口さんら嘱託社員ドライバー3人は労働契約法20条を根拠に裁判を起こし、会社に差額賃金などを求めた。2016年5月の東京地裁判決は全面勝訴し、同年11月の東京高裁判決は逆転敗訴だった。東京高裁の裁判官は、仕事内容などを同じと認めながら、「定年後再雇用者の賃金減額は広く行われ、社会的にも容認されている」として、原告の主張を退けたのだ。
ベテランドライバーの山口修さん(撮影:藤田和恵)
「社会は賃金減を容認? 冗談じゃない」
山口さんは裁判官の判断に憤っている。
「いったい誰が賃金減額を容認している、っていうんですか。多くの人は不満に思いながら我慢しているだけです。裁判官は勉強不足だし、現実社会を分かっていない。定年後に労働条件を下げて働く人がいるにしても、それが平気なのは給料も右肩上がりで、退職金も十分に支給された大企業の人くらいじゃないですか」
トラック業界の年収はもう何年も横ばいだ。その中で山口さんは5人の子どもを育て、この春には末の子が大学を卒業した。それでも毎月約4万円の教育ローン返済は続いており、家計に余裕はない。

山口さんはトラックのハンドルを30年以上握っている(イメージ:アフロ)
「昔のように60歳前に子育てが終わる時代じゃない。年金があれば安心という時代でもない。裁判の行方を気にする40代、50代のドライバーは社内にもいるんですよ」
山口さんは「渋滞に遭っても、割り込みされても、あおられても、何をされても腹を立てない。それがプロのドライバーなんだ」と話す。再雇用後もプロとして会社に貢献しているとのプライドがある。そして、格差解消は後輩たちのためにもなる、との信念がある。
それが、働き続けながら会社に物申す原動力になっているという。
弁護士「このままでは使えない法律に」
日本郵便を相手取った裁判の原告側代理人、棗(なつめ)一郎弁護士は労働契約法20条について「労働者自身が格差是正を訴えることができる初めての武器」と解説する。
棗(なつめ)一郎弁護士(撮影:藤田和恵)
ここで紹介した裁判で、被告側は「労働条件の相違は、両者の業務内容及び責任の相違等に基づく合理的なもの」(メトロコマース)、「定年後再雇用として新たに有期労働契約を締結するものであり、『期間の定めがあること(嘱託社員であること)』を理由として労働条件の相違を設けているわけではない」(長澤運輸)などと主張し、裁判所もそれらを認めた。この3件を含め、労働契約法20条をめぐる裁判は全国で7件あり、今のところは原告敗訴が多い。そのため、棗弁護士は「このままでは、せっかくの20条が使えない条文にされてしまう」と懸念する。
施行から間もないせいか、法律が定めるようにそれぞれの労働条件を比較、判断したとは思えない判決が目立つ――。そうした批判は、労働組合にもある。例えば、トラック運転手らを支援する全日本建設運輸連帯労働組合の小谷野毅書記長はこう批判する。

労働契約法に依拠した訴訟は相次いでいるが……(イメージ:アフロ)
「賃金は労働の対価です。(山口さんの訴訟の判決のように)年齢が高いから賃金を下げてよいというお墨付きを裁判所が与えるなんて、絶対に許されません。同じ責任で、同じ仕事なら、できるだけ格差をなくそうというのが法律の目的だったはず。最近の判決は『少しでも仕事内容が違えば格差も仕方がない』と言わんばかりです。これでは20条のできた意味がありません」
非正規の未来を「美しく、気高く」
話はメトロコマースの後呂さんに戻る。
地下鉄の売店で働き、裁判を起こした彼女は以前、契約社員の同僚が定年退職を迎えた時、契約社員の仲間と一緒にランの花を贈ったことがある。同社では正社員の退職時には、会社による送別会が開かれ、退職金が支給され、花束も贈られるのに、契約社員には何一つないと知ったからだ。
贈ったのは、紫の花を次々と咲かせる種類の洋ランだった。花言葉は「美しく気高い」。今にもほころびそうなつぼみに、非正規労働者の未来を託したいと思ったという。
後呂さんはこう話す。「判決はゴールじゃない。私たちが声を上げることで、非正規労働者が立ち上がるきっかけになれば」(撮影:藤田和恵)
訴訟は現在、東京高裁で審理が続いている。
藤田和恵(ふじた・かずえ)
北海道新聞社会部などを経て、現在フリーランス。
[写真]
撮影:藤田和恵、イメージ:アフロ