わが子を虐待や暴力などで傷つける親がいる。そんな親を「毒親」と呼ぶ。つらい言葉を延々と浴びせる心理的虐待も行為のひとつで、近年問題になってきた。そんな毒親が高齢化し、介護を必要としたとき、子はどうすればよいのか。著書『毒親介護』を上梓したジャーナリストの石川結貴さんに毒親介護の実態や向き合い方、回避の仕方を聞いた。(ライター・堀香織、ジャーナリスト・森健/撮影:長谷川美祈/Yahoo!ニュース 特集編集部)
毒親が介護状態に――悩む子どもたち
「『毒親』という言葉は、米国のコンサルタント、スーザン・フォワードの著書『毒になる親』(邦訳は1999年)がもとになったとされています。フォワードによれば、毒親とは子どもに悪影響を及ぼし、その心身をむしばみ壊してしまう存在。日常的に暴力をふるったり、ののしったり、必要な世話を怠ったり、支離滅裂な言動で振り回したりするような親、と考えるとわかりやすいと思います」
ジャーナリストの石川結貴さんはそう語る。これまで30年近く、貧困や教育問題、児童虐待など、現代家族の問題を取材してきた。近年取り組んできたテーマは、「毒親」が高齢化したときの介護問題だ。
「超高齢化時代になって介護の問題も日常化し、誰かが高齢者のケアをしなくてはいけない。その役割をまず担うのは家族ですが、家族がすべてできるかというと難しい。家族の関係が壊れていることも珍しくないからです」

石川結貴(いしかわ・ゆうき)。ジャーナリスト。1961年静岡県生まれ。家族・教育問題、児童虐待、青少年のインターネット利用などをテーマに取材。著書に『スマホ廃人』『ルポ 居所不明児童〜消えた子どもたち』『ルポ 子どもの無縁社会』『誰か助けて〜止まらない児童虐待』など多数。
自分を傷つけたり、愛してくれなかったりした親が老い、介護の必要に迫られる。世話をするのか、関わりを避けるのか。子どもの立場からすると対処に悩むだろう。石川さんは、そんな毒親をもつ50代を中心とする20人ほどに取材を重ねてきた。
取材相手は探しまわる必要がないほど周囲にいたという。
「かつて30代のときに取材した人が50代になって介護の問題に直面していたり、あるいは、何年も会っていなかった人から突然メールがきて『いま親のことで苦しんでいる』と告げられたり。この問題でつらい思いを抱えている人はたくさんいるんだと思いました」
耳を傾けてみると、話は重い内容ばかりだった。
暴力と暴言の父親が認知症に
工務店を経営する48歳の男性は、幼い頃、父から暴力と暴言を受けていた。しつけと称した殴る蹴るが日常で、角材を持ち出して「めった打ちに」されたこともある。30歳のとき、当の父が脳出血で右半身が麻痺し、言語障害に。男性は実家に1日おきに泊まりこんで面倒を見ていたが、父は傍若無人の振る舞いをやめないばかりか、契約しているデイサービスの利用者とたびたびトラブルを起こす。そのうち認知症と診断され、徘徊までするようになった。さらに思わぬ展開になった。父と同居している母まで変貌したのだ。母は、認知症になった父に対して虐待をはじめたうえ、息子である男性を非難するようになった。
男性は石川さんに対してこう嘆く。「親父のことで大変な思いをしてきて、今度はおふくろがこんなで、いつになったら楽になれるんだろう」
58歳の女性は、母と弟と妹の4人で暮らす。3DKの賃貸アパート。妹は離婚して出戻り、女性と弟は未婚だ。女性が11歳のときに両親は離婚した。母は3人の子どもを育てるためさまざまな仕事をしたが、悩ましい面もあった。男性との交際にだらしなく、お金の一部を貢いでいたからだ。女性は母の愛人男性から性的な被害を受けるなどつらい日々を重ねた末、大人になって家族と絶縁。しかし、40歳で精神状態を悪くし、実家に戻って母たちと暮らすことに。だが、4年ほど前、暮らしが一変した。母が心臓疾患で入院し、さらに翌年には腰の骨を骨折、歩行障害が出て要介護2の認定を受けた。家族の経済状態も悪くなり、母は「あんたなんか結婚もできなくて」などと女性をののしりだした。
女性は「殺してやろうかと黒々とした感情」も覚えるが、家を出ることはできない。介護に追われて働くことがままならず、結果的に母の年金に頼っているためだ。女性は「母の言い草にはすごく腹が立つんです。だけど、今の暮らしとか、この先のことを考えると……」と言い淀む。

石川さんは、介護をしている家族が10組いたら、うまくいっているのは1組か2組で、あとの8、9割は大なり小なり問題を抱えていると言う。
「老人ホームのパンフレットの表紙を飾る、定番の写真ってあるでしょう? 車椅子のおじいさんの周りを息子とその妻、孫が囲んでいて、みんなでにっこり笑っているような。そんな幸せな介護の図ってレアケースなんだと思いますよ」
毒親を介護する子どもの話を聞いていくなかで、ある傾向に気づいた。毒親を引き受けているのは、基本的に真面目で優しい人だということだ。
「複数のきょうだいや親族がいたとき、要領のいい人は逃げちゃうんです。それは毒親だけでなく、ふつうの親子や家族関係でもそうで、真面目で優しい人が一生懸命関わりがち。ところが、そういう人ほど親から正しく評価されず、逃げたきょうだいのほうが褒められたりする。報われないまま面倒を見ることで、介護する子どもはますます精神的に追い詰められてしまうんです」

憎しみを感じる人は35.5%
取材を進めるなかで、石川さんは「毒親には2つのパターンがある」ことにも気づいたという。
ひとつは、長年にわたって暴力や暴言が絶えない、はた目にも明らかな「毒親」。もうひとつは、毒親だと認識していなかったものの、いざ介護が始まってみて「うちの親は毒親かも」と子どもが気づく「隠れ毒親」だ。石川さんは「隠れ毒親」のほうが、より厄介だと指摘する。
「明らかな毒親の場合は、『離れるなり捨てるなりしても仕方がない』という視点を本人がもてるし、周りからも『ひどいね』と認めてもらいやすい。でも、隠れ毒親の場合、一見するといい親なので、ただの過剰反応のように思われてしまう。それでひとり、袋小路にはまってしまうんですね」
もとより親が毒親かどうかにかかわらず、「介護」にストレスはつきものだ。
日本労働組合総連合会(連合)が2014年に実施した「要介護者を介護する人の意識と実態に関する調査」によれば、日々介護に従事する家族などの介護者の「ストレスの有無」を見ると、「非常に」と「ある程度」を合わせてストレスを感じている人の割合は80.0%に達する。
また、「憎しみの有無」では「感じている」が35.5%、「虐待の有無」も「ある」が12.3%もあった。しかも「ストレスの有無」と同様、在宅介護の困難を訴えている人や認知症の症状が重い家族を抱えた人ほど、憎しみを感じる度合いが高くなる。
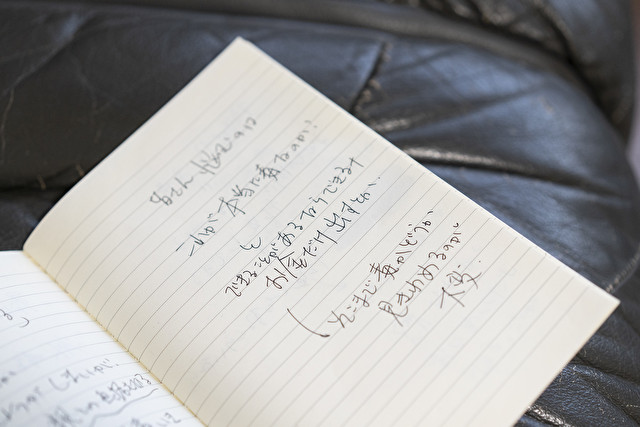
認知機能が低下したり、持病や障害を抱えたりしている高齢者は支援を必要とする。だが、親子の間に愛情がある場合でさえ、「介護」という支援は負担が大きい。
まして、幼児期に愛された記憶がない子、毒親にひどく苦しめられてきた子にとって、介護は負担どころか、親との戦い、あるいは自分自身との戦いといっても過言ではないと石川さんは言う。自分自身との戦いとは、責任感と憎悪の二つに引き裂かれそうな葛藤だ。
「単純化すると『嫌いな親を介護できるのか』とまとめられるのかもしれませんが、子の親への思いは複雑です。嫌いだけど愛されたい、苦手だけど放っておけない、と揺れ動く。そこに葛藤がある一方で、世間からの親孝行プレッシャーや自分自身の責任感や罪悪感もある。だから、お見舞いに行ったり、施設を探したり、あるいは呼び寄せて同居したりする」
ところが、そうして懸命に介護をするなかで、子ども時代の憎しみがよみがえったり、目の前の親が自分を苦しめる存在に思えてしまったりすることがある。
「すると、その苦しみを誰にも打ち明けられず、失業や生活苦、離婚、親族との絶縁などで、自分の生活が崩壊していく。多くの人がそうなってしまう前に、毒親介護という問題を社会に発信しなければいけないんじゃないかと思ったのが、本を書く大きなモチベーションでした」

認知症の問題を理解し、咀嚼する
では、実際に毒親の介護に苦しむ人は、どうしたらいいのか。第一にすべきは「視点を変えること」と石川さんはアドバイスする。
例えば、ご飯をぽろぽろこぼしながら時間をかけて食べる親がいる。子の側に葛藤や憎悪があると、「これは自分を困らせるためにわざとやっているに違いない」と考えてしまうかもしれない。だが、それは親が老いて認知機能が低下した結果、起きている現象の可能性が高い。
石川さん自身、認知症の専門医から「壁に自分の便を塗りたくる」という異常行動がなぜ起きるのかを教えてもらい、納得できたという。
排便の機能が衰えると、便が出きっていない感覚があり、指で触って出そうとしてしまうことがある。認知機能が保たれている状態であれば、汚れた指を水で洗ったりトイレットペーパーで拭いたりできる。だが、認知症になると、そうした普通の行動が思い出せない。そこで壁に塗って、自分の指をきれいにしようとするのだ。
「つまり、認知症がどういう病気なのかをあらかじめ学んでおけば、それは症状のひとつだということがわかる。であれば、トイレの壁にビニールでも張って、自由に塗らせてあげて、汚れたらそのビニールをはがせばいい。手間はかかるけれど、毎回怒鳴るという無駄な疲弊をしなくて済むわけです。『親の嫌がらせではないか?』という思い込みはいったん捨てて、視点を変えてみる。そして、病気の詳細について調べ、自分にできる対応策を実行すると、少しずつ楽になると思います」

とはいえ、自らの視点を自分で変えるのは言葉で言うほど簡単ではない。ケアマネジャーやヘルパーに相談したり、家族会に参加して同じような境遇の人と愚痴を言い合ったりと、他者との関わりの中でヒントをもらうのもよい方法だと石川さんは言う。
次に大事なのは、「健康的なあきらめ」だという。健康的なあきらめとは、老年学を専門とする桜美林大学の長田(おさだ)久雄教授の言葉で、個人的な関係だけで親子関係を捉えず、「親はもう老いている。今さら仕方ない」と広い範囲で受容していくことだという。
直接介護している自分はまったく感謝されないのに、ときどき遊びにくるだけのきょうだいが1万円渡しただけで、「あの子は小さいころから優しくて」と親が大喜びする。そんな不公平な関係が続けば、「なんで私がこれだけ頑張っているのに」と怒りの感情に結びつき、親子の関係性もきょうだいの関係性も破綻する。
「人間誰しも自分がしたことに対して報われたい。『こんなに一生懸命やっているのに、なぜ(親もきょうだいも)感謝の一言がないのか』『報われないなんて冗談じゃない』と思っていたとしたら、苦しいだけです。ならば、『何も報われないのに、私、よくやってるよ、えらいよ』と自らを認め、褒めてあげてほしい。それが健康的なあきらめの本質です」

「捨てるか、関わるか」の二者択一
最後が「捨てる」。言い換えれば「逃げる」「縁を切る」。人聞きの悪い言葉に聞こえがちだが、石川さんは「『捨てる』という選択肢を知っておくのは大切」と言う。
「『親を捨てる』なんて言うと非難されるかもしれません。しかし、親への憎しみが募り、自分が壊れそうになっているなら、『捨てる』ことを考えたほうがいい。遠距離介護を支援するNPOの方も語っていましたが、毒親のせいで破滅するくらいなら、自分の人生を優先していいのです」
そこで大事なのが、自身と毒親との関係の「見極め」だ。死んでも関わりたくないほどの存在なのか、少しくらいは助けてやろうと思えるのか。気持ちの整理ができない場合は、高齢者の生活や介護の相談窓口である地域包括支援センターを訪ねてみる。そこで自分の親がどのようなサービスを利用できるのかを確認するとともに、虐待など親からされたことを包み隠さず伝え、そのうえで自分が今後親と「関わる」か、「捨てる」かを考えてみる。
「捨てる」のであれば、必ず親が暮らす自治体や地域包括支援センターを通じて介護サービスを含む各種手続きをしておくことだ。やみくもに介護を放棄すると保護責任者遺棄罪などに問われる可能性もあるからだ。ただし、石川さんは捨てることを積極的に推奨しているわけではないと言い添える。
「ひどい親もいますからね。そんな親から逃げられないと思いつめて、悲劇的な結末になるぐらいなら、逃げたほうがいいということです。子どもの世話にならなくても医療や介護は受けられるんですから」

逆に「関わる」と決めたのであれば、関わる範囲をあらかじめ想定し、自分にできることとできないことを整理する。例えば、「施設入所の場合に、身元保証人にはなる」とか、「月に3万円の援助をする」「万一のときに葬式だけは出す」などだ。
「『これなら我慢できる』と犠牲にできる部分の折り合いをつけて、関わる範囲を決めればいいんです。自分の生活、自分の人生をしっかりと守るためにも」
介護の先に救いもあるはず
厳しい介護に向き合う人たちを取材してきた石川さんだが、「介護で学べることってあるんじゃないかと思うんですよ」と付け加えた。
「それは私自身の経験から得ました。ただし、ちょっと変わったケースでした」
石川さんは夫と離婚後、やむを得ない事情から元夫の母の介護をすることになった。法的にも血縁上も他人の関係だったが、認知症で要介護3になった「義母」に関する全責任を負うことに。「絶対に無理」と思っていた排泄の世話をし、介護施設への入所後は入所費用を支払い続けた。当初2、3年と考えていたが、期間は結果的に11年間に及んだ。その間、決してきれいごとでは済まない局面もあり、「義母」に対して「早く死んで」と思ったことも数え切れない。一方で、「赤の他人」のはずの義母との関わりから得た喜びもあったという。

「『義母』は99歳で亡くなったんですが、最後のほうは皺だらけの手を合わせて、『お母さん、これから幸せになるんだよ』と何度も私を拝む。その姿を見たら涙が溢れて、心が浄化されたようでした」
そんな経験があったから、毒親を介護する人たちへの取材はより深く、熱いものになったという。
「結局、介護をしたことへの救いは、自分の中にあるんじゃないかと思うんです。『やっと死んだ。せいせいした』ではなく、『いろいろあったけど、私なりに頑張った』『少しでも面倒見られてよかった』と思えたら、その後の人生が変わってくるんじゃないかと思います」

堀香織(ほり・かおる)
ライター。大学卒業後、『SWITCH』編集部を経てフリーに。『Forbes JAPAN』ほか、各媒体でインタビューを中心に執筆中。単行本のブックライティングに是枝裕和著『映画を撮りながら考えたこと』、三澤茂計・三澤彩奈著『日本のワインで奇跡を起こす』など。鎌倉市在住。
森健(もり・けん)
ジャーナリスト。1968年東京都生まれ。早稲田大学卒業後、総合誌の専属記者などを経て独立。『「つなみ」の子どもたち』で2012年に第43回大宅壮一ノンフィクション賞受賞、『小倉昌男 祈りと経営』で2015年に第22回小学館ノンフィクション大賞、2017年に第48回大宅壮一ノンフィクション賞、ビジネス書大賞2017審査員特別賞受賞。
[写真]
監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝
















