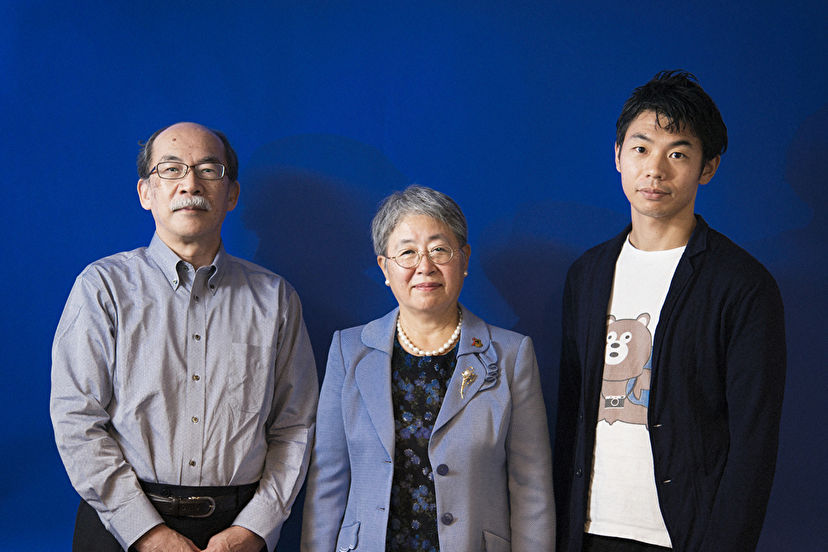親が子どもを虐待する可能性があるかどうか。その情報を児童相談所(児相)や警察などの関係機関が共有する。市民も"虐待"を感じたらすぐ関係機関に通告する――。そうしたことは、虐待をなくすためとして、広く社会に浸透してきた。「虐待のリスク」を把握するために、子どもに関わる機関が親子の様子を内々にチェックしていることも次第に知られるようになり、"監視"が張り巡らされた状態に違和感を抱く親もいる。子育ての現場で何が生じているのか。まずは、関東地方に住む30代の母親の話から始めよう。(文・写真:益田美樹/Yahoo!ニュース 特集編集部)
初めての子育て 相談を何度も利用していたら......
杉山菜月さん(仮名)は、子育て相談を利用していたことを複雑な気持ちで思い返している。地元自治体の主催とあって、安心して足を運んでいたという。
「長男を授かったばかりでした。『困ったことがあったら相談してね』と優しく声を掛けていただいて。それで、いろいろ話しました。初めての子育てなので、離乳食のこととか。母乳が足りているのかも不安で、細かく質問して。それが原因で"不安が強い母親"と思われてしまったのかもしれません」
どういうことだろうか。
自宅で取材に応じる杉山菜月さん(仮名)
話は3年ほど前にさかのぼる。子育て相談を利用しているさなか、生後10カ月だった長男が義理の両親宅で頭にけがをした。つかまり立ちからの転倒だった。分厚いじゅうたんも敷き、家族も見ている中での出来事だったという。
「けいれんを起こしたので、すぐ救急車を呼びました。診断結果は薄い硬膜下血腫。幸い、長男は意識が回復し、おっぱいも飲めました。脳外科の先生からも『このくらいの年の子にはよくあること』と言われていたんです」
後日、眼科で眼底出血が確認され、事態は一変する。病院は「揺さぶられ症候群(SBS)」の疑いがあるとして児相に通告し、児相は虐待の疑いがあると判断した。
「第三者(義理の両親)もいた中での転倒なので、きちんと話をすれば、事故だと分かってもらえると思ったんです。でも、『親の安全義務違反』と言われ、長男は病院で2カ月間の一時保護です。その後の4カ月間は乳児院にも入りました。離れ離れでつらかった」
ところが、本当に大変だったのは施設入所が終わってからだったという。
事故から後の記録を菜月さんは保存している
児相との約束で、常に第三者に見ていてもらう必要があり、実家の両親と同居することになった。認可保育園にも通わなければいけなくなり、行き帰りにも「第三者」の目を入れるため、ベビーシッターも依頼した。
「入れ代わり立ち代わり、関係機関の家庭訪問がありました。突然の同居で、家族の間もぎくしゃく。シッターさんも、希望日の全ては難しくて......。経済的にも負担でしたが、精神的な苦痛がすごかった。虐待なんてしていないのに、どうしてこんな目に遭うんだろう、って」
菜月さんはさらに、思いもしなかったことを知る。病院のカルテを開示請求したところ、自治体との情報共有によって「産後うつ」と判断されていたのだ。
「自治体への聞き取りの結果だそうです。児相からは(支援の場への)参加が多いからだ、と。自治体の子育てイベントによく行っていたし、顔なじみの保健師さんもいたから、その方たちに尋ねてもらえば、逆に虐待の疑いは晴れると思ったんです。でも、そうはなりませんでした」
長男の一時保護が決まった際の通知
鑑定を依頼した別の病院の医師は「事故によるけが」と判断し、一時保護から1年1カ月後、児相も「家庭に問題はない」として介入を終えた。新たに出会った保健師からは「産後うつという見立ても、疑われたのもおかしい」と励まされ、菜月さんは平穏な日常を取り戻した。
それでも、当時を振り返ると、複雑な気持ちになるという。
信頼して通った子育てイベントなどで、職員が自分やわが子のことをひそかにチェックし、その情報が関係機関と共有され、結果的に児相による「親子分離」につながっていた--------。思いもしなかった"リスク監視"の当事者になった菜月さん。そのわだかまりは今も消えていない。
「虐待と思ったら通告。全国民の義務」
虐待の防止は、法律でも定められている。児童福祉法第25条は、要保護児童発見者の通告義務を明記。児童虐待防止法は、通告しなければならない児童について、2004年の改正で「虐待を受けた児童」から「虐待を受けたと思われる児童」に範囲を広げている。
児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」は匿名でも受け付け可能で、2019年12月からは通話料も無料化された。厚生労働省も「児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください」と呼び掛ける。
そうした結果、例えば、大阪府警の「児童虐待の現状」によると、認知件数と通告児童数は2010年代に入って急増。2018年には「府民の皆様の児童虐待に対する関心の高まりなどにより」、それぞれ6457件、1万1119人に達し、いずれも過去最高を記録した。

大阪府警本部庁舎
「児童虐待の通告はすべての国民に課せられた義務」と呼び掛ける団体も少なくない。児相や警察といった関係機関が全てのケースの情報を共有すべきだ、と訴える団体もある。
NPO法人「シンクキッズ 子ども虐待・性犯罪をなくす会」(東京)もその一つで、関係機関による情報共有の義務化を求めている。これまでに計約3万5000人分の署名を集め、義務化の要望書とともに国に提出するなどの活動を続けてきた。
現状でも児相などの関係機関は、地方自治体が設置する「要保護児童対策地域協議会」の中で、情報を共有している。ただし、全てのケースの情報が共有されているわけではない。例えば、児相は虐待が疑われるケースのうち、共有が必要と判断するものに限り、警察に伝えている。
同NPO法人の後藤啓二代表理事(60)は、これでは子どもの安全を守れないと主張している。
NPO法人「シンクキッズ 子ども虐待・性犯罪をなくす会」の後藤啓二代表理事
「活動には批判もあります。警察に情報を共有したら、(自治体などは)『親との信頼関係を損ねる』とか言って。でも、虐待死はいつまでたってもなくならないじゃないですか? 情報を共有しないために、救えるはずの子どもを救えてないんです」
親に知らせず、各項目をチェック
虐待防止が、子どもに関わる専門職の重要課題になって久しい。例えば、児童虐待防止法施行の2年後、2002年には厚労省の事業として「子ども虐待予防のための保健師活動マニュアル」が作成された。「子どもに関わるすべての活動を虐待予防の視点に」という副題の通り、虐待の防止を「最優先課題」に据え、「乳幼児健診等の場において虐待ハイリスクの親子を把握する」などと強調。その後、この内容に沿った講習会や実践が広がるきっかけになったという。
「子ども虐待予防のための保健師活動マニュアル」
このマニュアルに記された「虐待ハイリスクの親子」を現場はどうやって把握しているのだろうか。菜月さんと同じような「わだかまり」が生じる源が実際に存在しているのだろうか。
保健師として26年のキャリアを持つ大和田良美さん(仮名、48)が取材に応じてくれた。現在は、関東地方の自治体の児童福祉部門で働いている。児童福祉は18歳までの子どもを見る部門だ。
大和田さんの部署では、2019年度から「プランニングシート」と呼ばれるチェックシートを使い始めたという。厚労省の調査研究事業として作成され、2018年に公表。正式名を「在宅支援共通アセスメント・プランニングシート」といい、厚労省も利用を推奨している。
大和田良美さん(仮名)
大和田さんは「いろいろな項目があって、気に留めておく内容をチェックします。細かな解説があり、人による記入のブレはほとんどありません」と話す。
実際のモデルを見ると、「子ども・家庭・養育の様子」欄では、「子ども」「養育者」「養育状況・態度」「家庭」「サポート」の5分野・計23項目について、それぞれに該当の有無や程度をチェックする。
例えば、「養育者」の「性格的問題」の項目では、「衝動的・未熟・攻撃的・偏り・共感性欠如・人との関わり嫌い・被害的・その場逃れ・嘘が多い」という選択肢があり、該当すればマルで囲む。シート上で要因を全体的に整理し、担当者の会議で子どもが置かれた状況が危険か安全かを11段階で評価する仕組みだ。
「プランニングシート」のモデル
モデルでは、項目ごとの支援方針も示されている。例えば、「家庭」分野について「家族不和」の項目にマルが入れば、支援方針として「父にも会い、子どもと母を守れる方法について、また父としての思いを確認する」などが示されている。
乳幼児健診などを行う母子保健の部署と異なり、基本的には親からの電話相談がケース対応の始まりとなる。電話やその後の接触で得た情報を基に「プランニングシート」を埋めていく。
「相談を直接受けた職員でなくても、シートを見れば状況がすぐに分かるようになり、業務の効率化も進みました。もちろん、シートのみに頼っていると、見立て違いも起きます。子どもと会えなかったり、母親がアンケートに適当に答えたりすることもある。だから、専門性、経験が大事なんです。親から(面会を)拒否された時にも引かずに前に出ていく強さ、表情や言葉から必要な声掛けを見極める感覚も要ります」
ノートを開いて説明してくれる大和田さん
大和田さんは続ける。
「でも、シートを導入した結果、誰がやっても均一なチェックができるようになった。その利点は大きいです。組織としての判断にも役立ち、死亡事故などが起こったとしても、どういう根拠でどういう支援をしていたのか、記録が残っているから検証もできます。学校などとも、支援方針について意識統一をしやすいですね」
ただし、こうしたチェックをしていることを母親らに知らせることは特にないという。菜月さんのような母親が思いもしなかった"リスク監視"の目は、とにかく虐待を防ごうという現場の地道な努力と重なり合っている。
「監視という言葉は使いたくないけど」と専門家
リスク把握に注力する現場の現状に警鐘を鳴らす専門家もいる。「冷静にあり方を考えてほしい」と言うのは、上野加代子・東京女子大学教授(社会学)。児童虐待防止対策の問題点について発言を続けている。

上野加代子・東京女子大学教授
「今はSNSなどがありますから『乳児健診の場では気を付けてふるまわなければいけない』とか、母親同士で情報交換しています。職員の側も『虐待のこととかチェックしてませんよ』という印象を与えながら、実際はやっぱりチェックしているわけです。演じ合う関係です」
「子育ては大変な仕事ですから、いろんなストレスがある。初めての子どもだったら心配ごともたくさん、相談したいこともたくさんです。それなのに相談したら『育児不安』としてチェックされ、記録に残る可能性がある。監視という言葉は使いたくないですけど、そういうチェック・システムが大きく進んでいると思います」
上野教授によると、虐待対策は海外が先行していて、例えば米国では1960年代から虐待とその発見が大きな社会問題になった。しかし、通告を奨励し、リスクで判定する対策については、倫理面と効果を疑う議論が起きた。それが日本では紹介されていないという。
現場で使用するチェックシートは、機関によって異なっている。中には、親の失業や生活保護といった事項、シングルマザーや継父の存在、障がいの有無といった事項など必ずしも本人に責任のない、場合によっては差別的と思われるチェック項目もあるという。

上野教授
上野教授は言う。
「虐待絡みでなければ、これらのチェック項目は差別的ととらえられるはずです。でも、子どもの命を守るということで必要だとされている。支援のためとか、気づきのためのリストとか現場では言われているわけですけど、実際には虐待の判定時に使われるわけですから」
あるシングルマザーが虐待の疑いを掛けられたケースでは、シングルマザーであるという状況が「クロ」判定の材料にされた、と本人が苦しんでいたという。上野教授の元には、そういった情報や相談が当事者から寄せられている。
リスク把握に気を取られすぎ?
保健師でもある大学教員の多田寛子さん(仮名)は、非常にセンシティブな内容だからとして匿名での取材を希望した。「リスクの把握ばかりに気を取られ、寄り添いや支援が手薄になっている」というのが、看護師を育成している多田さんの主張である。
大学教員の多田寛子さん(仮名)
多田さんは2000年代の初め、虐待のリスク評価に関する講習に参加した。
「保健師は母子に寄り添う支援者なのに、『これって、お母さんたちと接しながら犯人捜しするってこと?』って疑問を感じました。でも、当時は『虐待をなくせ』という意識が広がり、周りに同じような疑問を口にする人はいませんでしたね」
あれから約20年になる。
「最近、ある自治体に学生を連れて行き、現場を見せてもらった。すると、保健師さんがちょっと疲れた感じのお母さんと少し話した後、シート上で『子育てで失敗、つまずき』にチェックしていたんです。学生も『こういう人は子育てで失敗した母親なんだ』とうなずきながらメモを取っている。でも、後でそのお母さんに声を掛けると、『あの保健師さんは話しづらかった。相談しても私が知りたいことは返ってこなかった』と言っているんですね」
虐待やその疑いを知った場合はすぐ通報するよう促す掲示。至る所で見掛ける
多田さんの学生は、看護師の卵たちだ。教科書通りにリスク把握の有効性を教えつつ、「リスク把握に偏重しすぎている」という批判的な視点も伝える。
「学生の反応ですか? 4分の1は『先生がおかしい』と言いますね。一方で、自分はリスク評価などされたくないという学生も4分の3いる。健診ではリスクを調べられ、社会からは(虐待しているかもしれないというだけで関係機関に)通告されてしまう、と。看護師としてバリバリ仕事がしたい学生にとっては、完璧な母親役を担うのは無理な話に聞こえるのでしょう。子どもを産んだとしても施設に預けたい、って言いますね。それほどまでに子育て世代には生きづらい環境なんです。深刻な問題だと思います」
冒頭で紹介した菜月さんは、2人目の子どもの計画は「なし」にしたと話す。
「ずっと希望はしていました。でも、長男でいろいろありましたから、やっぱり無理かな、と。虐待はいけないことだし、リスク把握も疑い段階の通告も、虐待防止のためにあるのは分かります。でも、怖いなと最近思うんです。相談すればリスクをチェックされる今は、親による自発的な相談に水を差すし。それってどうなんでしょうね?」
益田美樹(ますだ・みき)
ジャーナリスト。元読売新聞記者。英国カーディフ大学大学院(ジャーナリズム・スタディーズ専攻)で修士号。フロントラインプレス所属。