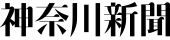人口約370万人を擁する日本最大の基礎自治体、横浜市。開港の地として、また東京のベッドタウンとして発展を続けてきた。そこには、時代ごとに直面する都市課題に対応し、まちづくりを支えてきた「黒子」がいた。1966年に設立された横浜市住宅供給公社だ。高度経済成長期には、住宅不足に対応すべく団地などを整備。供給が一段落してからは、闇市があった駅前の再開発や、人口減が進む住宅地の地域活性化の取り組み、団地の建て替えなど、その役割を変えながら貢献してきた。まちをつくり、つなげ、再生する―。横浜市住宅供給公社の歩みや果たした役割、そしてこれからについて、当事者の「証言」を元に語りたい。
「横浜にこんな場所があるとは」
「横浜にこんな場所があるとは。聞いてはいたが、行ってびっくりした。ちょっと不気味で、入りにくかった」。京急杉田駅東口の再開発に携わった同公社の米山進さん(65)は、かつての駅前の様子をこう振り返る。

再開発事業に取り組んだ米山さん
杉田駅周辺は、戦後しばらくは非常ににぎわっていたが、上大岡駅(港南区)など近隣駅周辺の開発が進むにつれ、相対的には地盤沈下が進んでいったという。杉田駅前は、バスの往来に支障をきたすほど道が狭く、木造の住宅や店舗などが密集していた。かつてあったアーケードの奥側には、戦災を免れた闇市が残っており、飲食店などがひしめいていたという。戸板に商品を掛けるなどして売る「戸板商売」という業態の店も見られたそうだ。

1959年の杉田駅前
再開発の機運が高まったのは80年代。米山さんが担当になった87年から、現地のヒアリングが始まった。「事業を進めるための調整が大変だった。仕事のほとんどは交渉でしたね」。約0.6ヘクタールの土地に、地主が16人、借地人が43人、さらに58人もの借家人がいて、入り組んだ権利関係は複雑を極めた。関係者は権利上の立場ごとに、また場合によってはそれを超えて集まって勉強会を重ねた。特に店舗などを営業する借家人らが推進役となり、再開発のための準備組合に参加していった。各権利者は、建物の立地や老朽化の度合い、商売の状況・年齢などからそれぞれ再開発参加への賛否も分かれ、合意形成にも苦心した。「夕方6時から、翌日の午前3時まで交渉したこともある。相手の依頼で、補償金として多額の現金をカバンに入れて持っていったこともあった。研修旅行や付き合いでよく酒も飲んだし、いまだにご家族との交流もあります」と語る。苦労は尽きなかったが、地元の関係者との密度の濃い交流も、今となってはよい思い出となっている。

現在の京急杉田駅前
こうして95年、かつてのアーケードの場所に「プララSUGITA」がオープン。物販や飲食店などの店舗に、集合住宅が併設された。プララから商店街を抜けた先にあるJR根岸線新杉田駅周辺とともに、地域の核として機能するようになった。「両駅をつなぐ商店街の活性化にも繫がり、街は変わったと思う。関係権利者の参画や事業手法についてなど、本当に課題が盛りだくさんだったが、だからこそ、当時として他のモデルケースになった。再開発は時間がかかるので、民間はなかなかやりたがらないが、交通拠点など再整備が必要な地域では今後も取り組む意味はあるのではないか」
時代に対応し変化する役割
この杉田駅東口の再開発事業は、50年以上にわたる同公社の歴史における一大転換点だった。66年の同公社設立から5年間、横浜市の人口は年間約10万人のペースで急増していた。住宅は不足し、郊外の乱開発などの都市問題も顕在化した。当時はその名の通り「住宅供給」のための事業にまい進。野庭団地(港南区)などを手がけていった。80年前後に住宅不足が解消に向かうと、広さなどの質を追求する方針に転換していった。都市計画に詳しい横浜市立大学の中西正彦准教授は「一般的に、住宅供給公社の存在意義の一段階目はここで終わったとも言える。全国には、その先の試行錯誤の中で、役割の転換がうまくいかずに破産や解散に至った住宅供給公社もある」と指摘する。

横浜市住宅供給公社が手がけた野庭団地
杉田駅東口は、横浜市住宅供給公社が取り組んだ初めての再開発事業だった。「複数の地権者が関係してくる再開発は、権利調整がものすごく難しい。民間の事業者は尻込みしてしまうことも多い」。中西准教授はだからこそ、「京急線とJR根岸線が走っている杉田地区がよくなれば、横浜全体にとってもメリットが多い。民間が出て行きにくい時、そういう地域に入っていくのは、公的な存在である公社の役割だろう」とその存在意義を評価する。
その後、バブルの崩壊を経て人口減の時代に突入。横浜市も今後、同じ道を歩むと考えられており、高度成長期前後に建てられた集合住宅などの老朽化も進む。同公社はそうした新たな時代状況を踏まえ、人口減と高齢化が顕著に進む金沢シーサイド地区(金沢区)で、大学や地域住民と連携したエリアマネジメント「あしたタウンプロジェクト」に参画。他の地域でも、既存の団地の管理を請け負ったり、建て替えたりといった取り組みを進めている。住宅を造るだけでなく、地域をつなげ、再生する役割も拡大させているのだ。

横浜市立大学の中西准教授
民間の隙間を埋める存在に
大都市・横浜の発展や変化とともに、その時代に応じた役割を果たしてきた同公社。「2000年代には、全国的に公社という存在そのもののあり方が問われた。その中で横浜市住宅供給公社が現在も活躍の場を広げているのは、公社が横浜のまちづくりに貢献できるという整理ができたからだと思う」。中西准教授は続ける。「人の生活を住環境から支えるときに、どうしても民間では埋められない隙間が生じる。公社は、意識的にそこを補う取り組みを続けているし、そこに存在意義が見いだされたのでしょう」
今後は、これまで民間事業者が追求してきたような大きな利益が出にくい「地道な仕事」が増えてくると分析している。「再開発を進めるにも、開発後も見据えて長期的に伴走してくれる存在が必要。その先導的な役割を果たすのが公社だと思います」。同公社の米山さんも「変化の早いまちづくりに参画していくためにも、これまでの経験を踏まえて、不動産を見る目や開発のノウハウを引き継いでいくべきだ」と話す。
造ることに加え、造ったものをどう活用するかが問われる時代。住まいに関するノウハウを持ち、その変化に機敏に対応し続ける「黒子」の挑戦は続いていく。