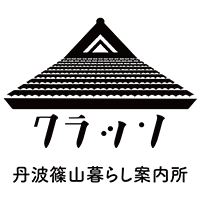人を呼び込む「豊かな暮らし」――背景にある土地の力 「どこにもない田舎」目指す丹波篠山市

美しい田園風景が広がる兵庫県丹波篠山市。どこにでもありそうな田舎のまちに、「豊かな暮らし」を感じて移り住む人が増えてきている。
神戸や大阪から北に約1時間。山々に囲まれ、田畑が広がり、清流にはカワセミが飛ぶ。人口は約4万人。絵に描いたような「田舎」の兵庫県丹波篠山市。今、そんなまちに移り住んだり、起業したりする人が増えている。「豊かな自然」は地方ならばどこでも共通する売り文句だが、「このまちでないと」と感じた人々は、いったい何に引き寄せられたのか。キーワードは「自分らしい、豊かな暮らし」――。
R-1ファイナリスト 土肥ポン太さんも農業
「正直、農業辞めようかなと思ってたんですよ。吹けば消えそうだった火が、ここに来てまた大きくなった。この土地のブランドと土の力がそうさせてくれた。僕にとってのパワースポットですわ」――。寒風吹きすさぶ真冬の畑で笑ったのは、吉本興業に所属し、「R-1ぐらんぷり」で決勝に進出した経歴も持つお笑い芸人・土肥ポン太さん(50)だ。土肥さんは今、丹波篠山市で、日本農業遺産にも認定された特産「丹波黒大豆」の栽培に励んでいる。
稼げなかった若手時代に八百屋でアルバイトをし、培ったノウハウをもとに青果業者として独立。自ら農業も始め、土を耕してきた。昨年まで大阪府内の別の場所で農地を借りてきたが、知人の紹介もあって丹波篠山で新たな農地にたどり着いた。

丹波篠山に農地を借り、特産の黒大豆を栽培している土肥ポン太さん。農地は高台にあり、眺めも気に入っているそう。
「いや、ほんまにすごいですよ。黒大豆に栗、山の芋、米――。どれも『丹波篠山産』と言うだけで都市部では全然受けが違います。あと東京の人と商談している時に、『黒豆は丹波篠山と決めています』って言われたことも。このブランドは全国区です。そこに芸人・土肥ポン太もセットにさせてもらって、いろんな野菜を全国に売り出したいと考えています」
土肥さんが言うように、主に関西圏で丹波篠山と言えば、黒大豆をはじめとした「食の宝庫」として認識されている。そのため、新たに農業を始めようとする人の移住も多い。先人たちが長年かけて培ってきた「丹波篠山ブランド」の賜物だ。

立ち枯れで熟成させる黒大豆。「今回の出来は全然だめでした」と笑う。
青果業に加えて、数年前から農業も始めた土肥さんだが、自然相手の大変さを味わったり、なかなか事業として軌道に乗らなかったりと、一時期は農業を辞めようと考えていたそう。そんな折、丹波篠山にやってきた。すると、特産の黒大豆が完熟する前に味わう「丹波黒枝豆」は即完売。収穫体験の「枝豆狩り」も大好評を博した。吉本の師匠からも「格別や」と太鼓判をもらい、再び、農業に対する思いに火が付いた。
「黒大豆が好評だったのは、僕の技術やなくて、土地の力です」と言いつつ、「ここに来てからいろんなアイデアが浮かぶんですよね。丹波篠山の名前が付いた飲食店もやってみたいし、もちろん野菜の加工品も作りたい。夢が広がっています」
農業、そして、丹波篠山への熱い思いを語る土肥さん。「あ、農業の話ばっかりしてしまいましたが、芸人を引退したわけじゃありませんよ」と苦笑し、「どんな仕事でも受けるような年齢ではないけれど、農業や丹波篠山のことを発信するような仕事がしたいと思っています。もちろん、笑いも交えて」――。
移住者数が過去最多に 意外にも多い「起業」
市が開設し、移住相談に応じている「丹波篠山暮らし案内所」を介して同市に移住した人は、2021年度12月までで過去最多の132人。10年前の20人から6倍以上となっている。急増したのは20年度(124人)で、19年度から一気に約50人増えた。増加の流れはコロナ禍と重なる。在宅勤務やリモートワークが普及したことで、都市部でなくても生活できる時代に入ったこと、そして、人生設計自体を考え直し、広々とした土地でゆったり暮らしたいという人が増えているという。
メールや面談などで調査した移住理由トップは、自然豊かな土地でのセカンドライフ。続いたのは意外にも「起業」だ。就農や子育てよりも割合が多い。地方で起業する人とはどのような思いを持って移り住むのか。
「文化が残っているのは地方」 重伝建のまちで笑顔

築100年の古民家を改装したゲストハウスを運営している仲田さん。
市の中心部から東へ車で20分ほど。京都から兵庫へ抜ける旧街道沿いにある福住地区は、宿場町のたたずまいを色濃く残しており、文字通り、軒が連なる町屋群は、重要伝統的建造物群保存地区にも指定されている。その一角にあるのが、築100年の古民家を改装した「アオアシゲストハウス」だ。同県芦屋市出身で、元丹波篠山市地域おこし協力隊の仲田友香さん(34)が起業し、運営している。
「景色が良いところで、食べ物を自分で作る。そこで感じたことを他の人とシェアする。そんな、自分たちが描いた暮らしをしたいと考えた結果、たどり着いたのが丹波篠山でした」
仲田さんは大学を卒業後、会社員に。その後、中南米やヨーロッパ、アフリカなど夢だった世界各地を巡る旅に出た。費用は最低限のため、料金の安い現地のゲストハウスなどを定宿にしたという。
初めのうちは観光地を巡った。しかし、そこである事実に気づく。「どの国に行っても都会は似ていたんです。均一化されているというか。そして、『その国の文化』が残っているのは、いつだって地方でした」。同じ思いで地方に来た見知らぬバックパッカー同士、ともに食事を作りながら語り合い、交感する。国籍も生い立ちも考え方も違う人々とのふれあいは刺激的で、仲田さんの人生に大きな影響を与えた。この体験から、帰国後、日本の地方で古民家を活用したゲストハウスを作ることを決意。ようやく見つけた理想の物件は、歴史と文化が詰まった福住地区にあった。

宿場町のたたずまいを色濃く残す福住地区。重要伝統的建造物群保存地区にも指定されている。若者にとっては、新鮮な景観。
起業直後にコロナ禍となったが、幸いなことにゲストハウスの運営は順調に進んでいる。ドミトリー方式から、一棟貸しに切り替えたことも奏功した。「都市部からゲストハウスに来られる方でびっくりしたのは、カエルやサワガニを見つけただけで喜ばれたことです。よく考えると、都会の真ん中でカエルはなかなかいませんよね。それにバーベキューや薪ストーブ、花火も好評です。都会では火を使えませんから。こちらでは当たり前のことに魅力を感じてもらえています」
今、仲田さんの体には新しい命が宿っている。「引っ越してきてすぐ近所で暮らす方から、『赤ちゃん待ってるで。早くしてくれんと、年取るから面倒見られなくなる』と言われたんです。その時はまだ子どもを考えていなかったので笑ってしまいました。そのあと、赤ちゃんができたことを報告すると、抱き着いて喜んでくださいました。とってもうれしかった。地域みんなで子どもを育てようと思ってくれる。本当に温かい地域に来られてよかった。私は理想の生活をかなえられたと思っています」
「ちなみに」と言って仲田さんが付け加える。「生まれてくる子どもは都市部で育った私たち親と違って、生まれも育ちも丹波篠山っ子。この子が将来、『都会が良い』と言っても、それはそれで認めてあげたい。自分で選択できる子供になってほしいと願っています」――。重伝建のまちなみを背に充実感いっぱいの笑顔が広がった。
芸術家も移り住む 「生産から創作へ」

旧家を改装し、ギャラリー兼工房にしている児玉さん。市外の作家も足を運ぶことが多く、移住相談にも応じている。
起業する人のほかに、近年、目に見えて増えてきているのが芸術家の移住。神戸市出身のガラス作家・児玉みのりさん(54)もその一人だ。「生活していて気持ちいいんですよ。自然や土地の力なんでしょうかね」
2018年、旧家を改装したギャラリー兼工房「so arrow」をオープン。遠目には地方でよく目にするかやぶきの古民家だが、近くで見ると驚く。本来、縁側がある場所がガラス張りになっており、中に入るとモダンなギャラリースペースにさまざまな作品が並んでいる。
もともとものづくりが好きだった児玉さん。会社勤めをしながら、陶芸やガラス工芸に打ち込んでいた矢先、阪神淡路大震災で被災し、自宅は全壊した。当時は紙コップや紙皿が求められた時。ガラス作品どころではなかった。それでも復興の途中でさまざまな人に出会い、震災を乗り越え、生かされたからこそ、「中途半端なことはできない」と覚悟を決めた。東京ガラス工芸研究所に入所。卒業後は愛媛県の作家のもとで修業し、京都府で工房を構え、さらに腕を磨いてきた。
いつかは地元の兵庫に帰りたいという思いがあり、移住先を探すことに。条件はいくつかあった。まずは、工房を構えられる敷地がある物件。それと工房を訪ねてきてくれた人に、おいしい食べ物やおすすめできる場所があること。京都・大阪・神戸などの百貨店で催事をするため、どこにもそれなりに近い場所。そうして選んだのが丹波篠山だった。

もう一つの重伝建「河原町地区」の町家を会場に開催されている「丹波篠山・まちなみアートフェスティバル」
もう一つ、「影響が大きかった」というのが、福住地区と同じく重伝建に指定されている同市河原町地区などで開かれる芸術の祭典「丹波篠山・まちなみアートフェスティバル」の存在。伝統的な町屋を会場に、内外の作家たちの作品が並ぶ一大イベントだ。今も生活の場である町屋と現代的なアートの融合は、唯一無二の空間をつくりだす。
児玉さんも出展したことがあり、「この土地に『受け入れてもらった』という感覚になりましたね。よく考えると、作家がつながることができる、ものづくりで人がつながるまちってとても珍しいと思います」とほほ笑む。
アートフェスのように、丹波篠山には芸術家を引き付ける要素がある。800年の歴史を誇り、日本遺産にも認定されている焼き物「丹波焼」。そして、同市はユネスコが創設している「創造都市ネットワーク」のクラフト&フォークアート部門に加盟していること。加盟理由は丹波焼のほか、城下町や農村部の景観、村の神社に息づく祭礼などをもとに市民が文化・経済活動を営んでいるという点だ。
簡単に言えば、固有の文化と産業が結びつきながら地域に根付き、それらを今も継承しているということ。芸術もある面では産業。それが暮らしに根を張り、芸術を受け入れる素地がある土地だからこそ、芸術家も自然と集まってくる。
児玉さんのもとには、市内外から多くの人が訪れる。作品のファンだけでなく、丹波篠山に移り住んで活動しようとする作家の姿も見られる。「良い物件があれば教えて、という人が何人もおられて」と苦笑する児玉さん。「これから丹波篠山はもっとおもしろい場所になっていく気がします。それに作家ってどんな作品を作っていても自分のカラーがあるから、いろんな人が移り住んで、カラフルな個性があるまちになればいいなぁと思いますね」
最後に、丹波篠山に移り住んだことで作家としての活動に変化はあったかと尋ねてみた。児玉さんはガラス張りの向こうにある木に降り立った野鳥を眺め、しばらく考えてから笑った。
「そうですね、ガラスっておもしろいなぁって。以前は作品を作ることを『仕事』と思っていましたが、今は純粋に作品づくりを楽しめている気がします。同じものづくりでも、『生産』ではなく、『創作』しているという感じでしょうか。そんなふうに思うのは、やっぱり、この土地の力だと思いますね」
手塩にかけたものを 移住者も共に担い手に
3者3様。丹波篠山に引かれた理由はそれぞれだが、この土地で「豊かな暮らし」を見つけた満足感が、3人の笑顔からにじみ出ていた点は共通していた。
「丹波篠山ブランドの進化」に努める市ブランド戦略課は、「丹波篠山ブランドは、昔からここに暮らす人々が手塩にかけて作ってきた良いものや暮らしそのもの。田舎は全国どこにでもあるけれど、『ここにしかない田舎』として際立たせたい」と言い、「そんなまちの取り組みに共感していただいた方が、ここで自分らしい暮らしや生き方を見つけてもらえたなら、これほどうれしいことはない。そして、その人々がまたブランドの担い手になっていくことを願っています」と期待を寄せる。
また、「全国の皆さんにこうしたまちづくりを、『ふるさと納税』などで応援していただきたい。返礼品の価格競争ではなく、ここで生み出される良いものを通して、このまちを理解し、共感してもらえたら」と呼び掛けている。