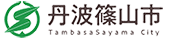地方移住の「リアル」は? 生活費下がり仕事も創出 若い世代増える兵庫県丹波篠山市の場合

豊かな自然が広がる兵庫県丹波篠山市。近年、若い世代の移住が増えている。移住した人々は田舎でどのような生活を送っているのか?
コロナ禍を機に加速したといっても過言ではない地方への移住。従来は都市部で暮らした人々が定年後に「のんびり暮らすため」という印象があった田舎暮らしだが、「3密回避」やリモートワークの導入によって、若い世代も地方に目を向け始めている。人口約4万人で、農村風景が広がる兵庫県丹波篠山市も2021年度、コロナ前と比べて約3倍となる206人が移住しており、うち30、40代が約6割となっている。そこで気になるのが、田舎暮らしの「リアル」。これまで同市への移住者で多かった60代や農家、芸術家などではない3家族を訪ねた。
リモート機に移住 ゲストハウス運営も

神戸市から移住した宮野さん一家。自然に囲まれた生活を味わっている
2022年7月、神戸市から丹波篠山市大山地区に移住した宮野健一さん(41)と妻の菜穂美さん(33)。コロナ禍以降、健一さんの仕事がリモートワークになったことから、「住む場所を問わないなら、子どもたちが大好きな自然の中で思いっきり遊べる土地へ」と移り住んだ。丹波篠山には縁もゆかりもない二人。なぜこの地で暮らすことを決めたのか。
移住を思い立ってから、いろんなまちのことを調べたそう。まずは会社がある大阪まで出勤するのにほどよい距離にありながら、自然が豊かなこと。そして、自治体の移住者へのフォロー体制。「丹波篠山は大阪まで電車で1時間と少し。私たちが調べた中では移住者への補助メニューが最も充実していて、『移住者を大事にしてくれる』と思えました。それと先に移住し、その土地に根差した活動をしている人々の発信に触れたことも大きいですね」
購入した物件は築約60年。400平方メートルの敷地に母屋と離れ、倉庫がある。水回りや床などはリフォームしたが、神戸の持ち家を売却したお金で十分まかなえた上、市からの助成も活用できた。里山に囲まれ、清流が流れる。野辺には山野草が萌える。そんな環境の中で子どもたちは日々、自然と戯れる。健一さんは、「とても広くて、花火もバーベキューもし放題。都会だったらあり得ません」とほほ笑む。
買い物は個配やネットショッピングも活用しており、不便さはまったく感じていない。一方で田舎ならではの人間関係の「距離感」には、戸惑ったこともあったという。「久しぶりの移住者ということもあってか、ウェルカム具合がすごくて。どう対応したらいいのかわからないこともありました」と健一さん。菜穂美さんも、「都会は知らない人ばかりで、子どものお迎えでも保護者同士で話をすることはほとんどなかった。その常識のままで来てしまったので、最初のうちは付き合いが苦手だと思われたかもしれません」と苦笑する。
「けれど、逆に言えば声をかけてもらえるので地域で孤立しない。子どもたちのこともかわいがってくれて、遊び場やカブトムシがいる木など、地元の人でないと知らない情報ももらえる。移住して数カ月で、都会にいた10年分よりもたくさんの友人や知人ができました。少しずつ順応していっている感じですね」

春にも本格オープンする「古民家ゲストハウスSatoyama」。築100年超だがリノベーション済み
東南アジアや中南米など、何度も海外に足を運び、各地のゲストハウスで現地の人や旅行者との交流を楽しんできた旅行好きの夫妻。自宅の向かいにある築100年超ながら、リノベーション済みという日本家屋の所有者と縁ができたことから、菜穂美さんが「古民家ゲストハウスSatoyama」として運営することになり、春にも本格オープンする。移住前から市が開講する起業スクール「篠山イノベーターズスクール」に通って、子どもたちの自然遊びを事業化する計画を温めており、ゲストハウスのアクティビティーとして自然体験を提供することになった。
菜穂美さんは、「自然の中でゆったりした雰囲気を楽しんだり、目いっぱい遊んだり。全身で丹波篠山を味わってもらえる場所になれば」と言い、健一さんは、「『暮らすように泊まる』という価値観。静かに暮らしている人たちに観光を押し付けるのではなく、来てくれた人に大山地区を楽しんでもらい、それが結果的に地域や地域経済への貢献につながればうれしいです」。移住の地で新たなスタートを切る二人の目がキラキラと輝いた。
いつかは実家に コロナがきっかけで

子どもたちと共に実家にUターンし、小さな洋菓子店を始めた森本さん夫妻
里山に川、田んぼに畑――。視線をどこに向けても豊かな自然が映り込む丹波篠山市大芋(おくも)地区に2022年4月、一軒の洋菓子店がオープンした。味わい深い日本家屋が建つ家の敷地内にポツンとたたずむ小さなコンテナが「Woods・b おくものお菓子屋さん」だ。営んでいるのはこの家で生まれ育った森本武史さん(37)と妻の里実さん(34)。3月に兵庫県西宮市からUターンした。
丹波篠山特産の黒豆が入ったパウンドケーキに、発酵バターの芳醇な香りが広がるクッキー、子どもたちが大好きな恐竜化石や昆虫をあしらったアイシングクッキーなど、さまざまなお菓子がずらり。毎週木、土曜日や予約で、シフォンケーキやモンブランなどの生菓子も登場する。「ご近所の皆さんがとてもよくしてくださって。農作業の合間に軽トラでスイーツを買いに来てくれる人もいます」
大学卒業後、神戸市に本社を置く大手菓子メーカーに就職した武史さん。パティシエとして菓子製造に励む中、同僚の里実さんと結婚した。愛知県の工場に転勤し、製造から管理する立場に移ったことから、「やっぱり現場でお菓子を作りたい」と考えて退職。個人店に入り、腕を磨き直した。その後、子どもが生まれ、両親がいる実家に近い土地に戻ろうと同じ兵庫県の西宮に移住。培った技術を生かし、大阪市の結婚式場でウェディングケーキ製作などを担った。そんな矢先に降りかかったのがコロナ禍。式場のキャンセルが相次ぎ、1カ月ほど自宅で待機することもあった。
アパートの一室にこもり、子どもたちとお菓子を作る日々だったが、出来上がったお菓子の写真をSNSに載せると、友人たちから「食べたい」という声が相次ぎ、独立開業の光を見た。

手間暇をかけて作る洋菓子の数々。農作業中の人が軽トラックで買いに来ることもあるそう
開業の地に実家を選んだことについて、武史さんは、「もともといつかは帰りたいと思っていたけれど勇気が出なかった。コロナ禍がタイミングになりました」とにっこり。里実さんは、「以前から帰省するたび、豊かな自然環境や、お父さん、お母さんが作る野菜の味に感動していた。子どもたちを育てる場所としてすごくいいな、と」とほほ笑む。
お菓子には時間と手間をかける代わりに、それ以外はなるべく費用をかけないようにと、まずは工房と店舗が一体となった小さなコンテナで「ぼちぼち」スタート。都市部で開業した場合と比べて10分の1ほどの資金で事足りたという。移動手段の車は必要になったが、生活コストは下がり、「物欲も少なくなったかも」(里実さん)。子どもたちは野山で遊び、たくましくなった。
「田畑など、父と母が守ってきた大事なものがたくさんある。それを守りながら、仕事をしていきたい」と誓う二人。「田舎で開業することに私たちの価値があると思う。ここにお店があることで人が集まり、地域の良さも発信していけたら」と前を向いている。
DIY動画がヒット 複業で「現代版の百姓」

購入した自宅をセルフリノベーションした日根野さん夫妻。DIYの様子を発信した動画がヒット
さまざまな仕事とともに生活の拠点を地方に移す人々がいる一方、移住したこと自体が一つの仕事に結びついた人もいる。
2020年、神戸市から丹波篠山に移り住んだ日根野豪さん(33)と妻の真奈美さん(33)は、築約40年の民家を購入し、自分たちでリノベーションする「DIY」の様子をYouTubeで発信したところ人気に。現在、YouTubeのチャンネル登録者数3万5000人超、Instagramのフォロワー数は8万人に達し、企業とのタイアップ案件なども相次いでいる。「コロナ禍もあって、いわゆる『おうち時間』が増えたこと、地方暮らしやリノベーション、DIYに関心が高まっていること。そんなトレンドにはまった感じです」
熊本県出身の豪さんと兵庫県出身の真奈美さんは、それぞれ仕事をしていた神戸市で出会って結婚した。30歳を迎えたことを機に、「働き方や生き方、人生を見つめ直そう」と脱サラ。フリーランスになれば住む場所を問わずに仕事ができると考えていたことや、ともに地方出身のため、「いつかは田舎でのんびり」と温めていた地方暮らしの時期を早めた。
フリーランスとして時代のトレンドを読むことや、発信力を鍛える練習にと配信したDIY動画は、しばらくして火が付き、みるみる登録者数を伸ばす。最近は、先輩移住者として地方暮らしのポイントなども配信している。

「DIY夫婦」として動画を発信する2人。「もともと不器用なんですけどね」と苦笑い
SNSのほかにも、クラウドファンディングを活用して築100年超の古民家の一部を改修したコーヒー焙煎所を開設したり、同市では珍しいコワーキングスペースを運営したりと、さまざまな活動を収入の柱に据える。「お百姓さんの『百姓』は、百の仕事をするという意味があるそう。そういった意味で、複数の仕事で生計を立てる『複業』の自分たちは、現代版の百姓だと思っています」と豪さん。
共働きだった都会時代の収入には、まだ追いついていない。それでも高額の家賃や仕事のストレスを発散するための買い物などが必要でなくなり、全体的な生活コストが下がっているため、「生活水準に変わりはない」という。
子どもも生まれ、「今、とても幸せ」とほほ笑む真奈美さんは、「忙しくなってしまうと都会にいた時と変わらないので、自分たちで仕事の量を70%と決めています。残り30%の余裕があるからこそ、何か新しいことにチャレンジしたり、いろんな本を読んで刺激を受けたりすることができますから」と語る。
ネットを活用した仕事は場所を問わないが、「都会に戻ることはない」と声を合わせる。「都会は歩いているだけでたくさんの人とすれ違い、辺りを見渡せばたくさんの広告やお店があって、あくまで僕たちにとってだけれど、『情報過多』だった。神経への刺激が多くて疲れるというか。そういう意味で、このまちが自分たちのサイズ感に合っているんですよね」
「家庭菜園をしながらのんびり」や「農家として特産を栽培する」など、これまでの「田舎暮らし」とはまた違った道を歩む夫妻。「近所の方から野菜をもらったり、移住者への助成があったり。受けられる恩恵はありがたく受けながら、仕事は外に取りに行く。そんな暮らし方もあるということを知ってほしいし、地方移住に一石を投じることができればと思っています」
充実の移住補助 地方に目で「チャンス」
移住・定住促進に力を入れる丹波篠山市。取材した人々の声にもあったように、「若者定住支援住宅補助金」(最大126万円)、「空き家バンク活用住宅改修補助金」(最大50万円)などの補助メニューを充実させ、移り住もうとする人々を支えている。担当する市創造都市課は、「移住の地に丹波篠山を選んでいただけて、とてもありがたい。コロナ禍の中で、地方に目を向けてもらうことは、市にとってはチャンスでもある」と言い、「地域と手を携えて、田園や自然、農などを生かした生活を営んでもらえたら」と期待している。