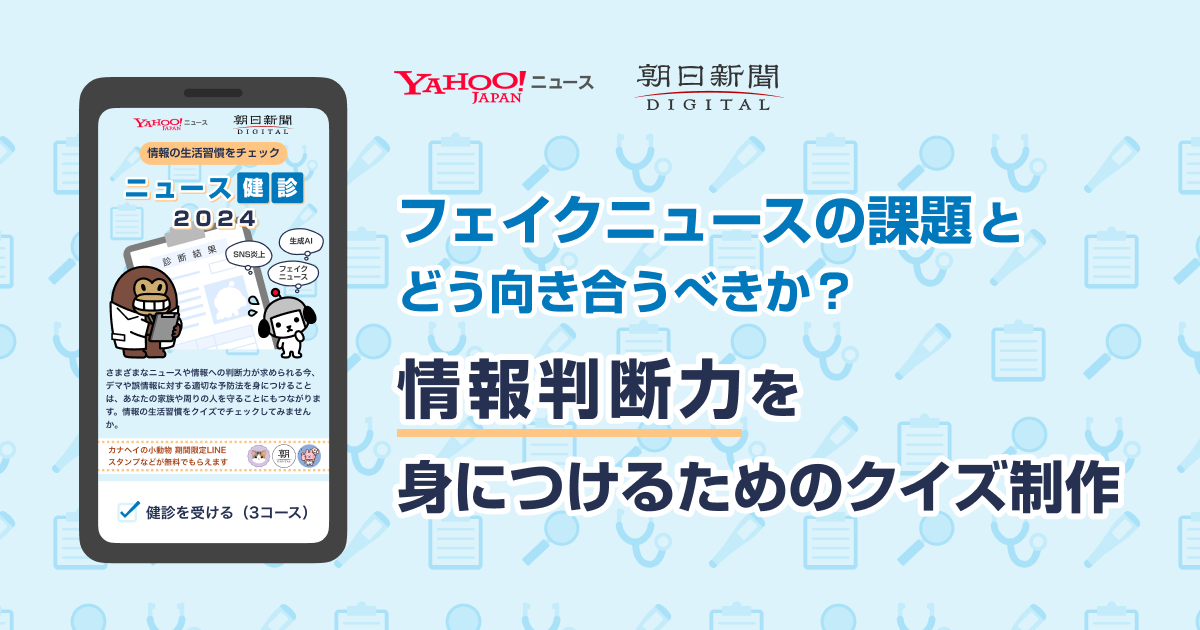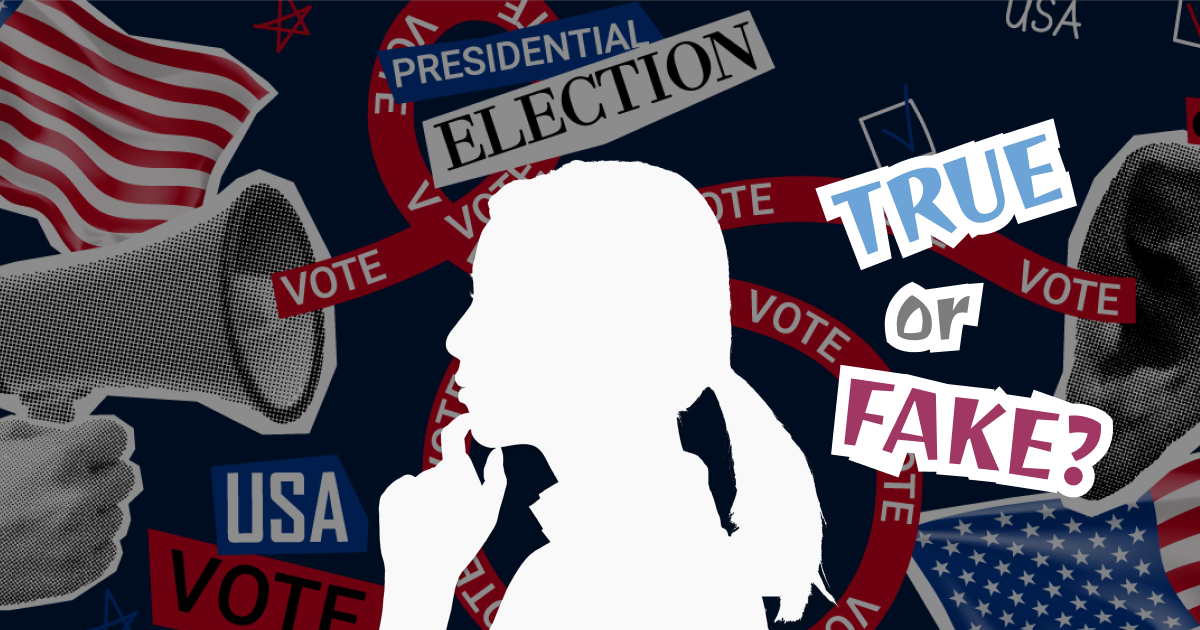ネットで戦争を伝えるには――8歳で体験した空襲の記憶と「この世界の片隅に」をつくった記録

ヤフーでは、社会課題の解決に向けて真剣に取り組む人たちをお招きする講演会「UPDATEチャレンジャーズ」を始めました。社員限定のこの講演会には、ゲストを通して社員がヤフーのサービスや、企業として「何ができるか」を考えるきっかけにつなげたいという狙いがあります。
第1回のゲストには、第一部に8歳で東京大空襲を体験し、語り部としてYahoo!ニュースとともに記憶を後世に伝える取り組みをされている二瓶治代さん。第二部に、映画「この世界の片隅に」の片渕須直監督をお招きしました。
ネットでできることとは
ヤフーでは、第二次世界大戦の記録と記憶を伝える100年間のプロジェクト「未来に残す 戦争の記憶」で、2016年夏から「空襲の記憶と記録」を公開しています。
Yahoo!ニュースの取材やケーブルテレビ局から提供を受けた空襲を体験された方々の証言映像、時事通信社から提供を受けた都道府県別の空襲の被害のデータを掲載しています。 第一部では、このプロジェクトを担当する宮本聖二と、二瓶治代さんに体験を次の世代へどう伝えていくか、お話していただきました。
東京大空襲の前日3月9日、「また遊ぼうね」と友達と別れた
二瓶さんの体験は「空襲の記憶と記録」で映像に残しています。

- 宮本
-
私たちは戦争を伝える手法の一つとして、インターネットでできる限り効果的に戦争を伝えていきたいと思っています。二瓶さんは、戦争を体験していない世代が「語り部」となり、戦争を伝えようと取り組んでいると聞きました。

- 二瓶さん
-
東京大空襲・戦災資料センターでも映像で証言を残していますが、対話がないのが欠点です。戦争を体験した本人ではないけれど生の声で伝わり、聞いてくれる人の反応がある。記録に残すことだけでなく、語り部と両方でいきたいと思っています。

- 宮本
-
人が前に出て伝える、その道具としてインターネットを使うこともできます。技術的に進んで、今とは違うスタイルで「戦争を伝える」サービスもできると思うので、そこも「UPDATEチャレンジャーズ」に集まった人に考えてほしいですね。

- 二瓶さん
-
私は戦時中は子どもでしたが、戦後の混乱も知っています。戦時中もひどかったけれど、戦後も大変でした。すぐに平和はやってこないんです。これからまた生まれてくる子どもたちが、平和に大きく育つことができるような時代を私たちと一緒につくっていきたい、そのためにも考えるきっかけにしてほしいと思います。
伝えるための記録
第二部では、片渕須直監督が戦時中の暮らしを描くためにどんなプロセスをたどったか。また、インターネットと映画の可能性について、宮坂学社長とお話いただきました。
資料、記録が「戦時中」をつかむ橋掛かりになる

- 宮坂
-
実は僕は監督の2009年の映画「マイマイ新子と千年の魔法」の舞台になった山口県防府市出身です。映画では小さな頃に見た景色が100%再現されていて驚きました。空き地のほんの一瞬映った木に見覚えがありました。

- 片渕監督
-
山口県防府市の昔の様子が写っている航空写真が見つかって、小学校がたくさん写っていたので、いろいろ考えて市内のすべての学校の開校記念日を調べたんです。すると、ちょうど昭和31年頃のものだと分かりました。理詰めかもしれませんが、知らない世界をものにして絵に描けるようになるまでは、パズルを解く面白さがあってすごく楽しいです。

- 宮坂
-
片渕さんは絵を描く前の時間の掛け方がすごいですね。

- 片渕監督
-
昭和30~40年代は想像がつくんですが、昭和20年、戦時中になると断層を飛び越える感覚です。想像はできても感触として捕まえることができない異質な世界。橋掛かりを作りさかのぼって、戦前や戦時中を理解していくというのはかなり大きな作業です。
例えば、「もんぺ」だって戦時中の途中まで女性は履いてない。理由が当時の雑誌にあって「かっこ悪いから」。なぜ履くようになったかというと、空襲が始まって逃げるときに危ないからです。明快な理由が、当時の資料で分かりました。

映画のために集めた資料の一部を説明する片渕監督

- 会場からの質問
-
ヤフーでは戦争をドキュメンタリーの手法で伝えています。そういった映像コンテンツへの可能性はどう考えますか。

- 片渕監督
-
東日本大震災を扱った短編アニメーション「花は咲く」では、震災の「し」の字も描かないようにしようと考えました。日本のどこにでもある風景、そういうものを描いて、見てくれた人が自分の町が写っていると思いをかけてくださるかに賭けた。見てくれる人に期待してよかったと思っています。

- 宮坂
-
直接的な表現の方法もありますが、受け手の想像力に期待するということですね。

- 片渕監督
-
もちろん体験されている人の聞き取りも大切ですが、当時の資料から得ることもあります。客観的なアーカイブは充実した形で、いろんな事実が並列して存在することに意味がある。戦時中にこういう暮らしをされていた人がいて、それはこの時代だったからなんだっていう客観的な記録があったら、突然ふに落ちるものが増えてくるんじゃないかなと思います。
「Twitterがなかったら全部が無だった」ネットで開いた映画の可能性

- 片渕監督
-
2009年公開の「マイマイ新子と千年の魔法」も順風満帆ではありませんでした。
大人を前提に映画を作ったつもりだったのですが、配給会社の方針で、親子が見に来る映画だからと上映の最終回が17時。大人が見に来ようがなかったんです。
なおかつ宣伝のための予算もなく、この映画の存在を知る術が世の中にない。そこで始めたのがTwitterでした。
フォロワーの多いアニメの研究家やライターが味方になってくれ、「見に行ったほうがいいよ」とつぶやいたり、投稿をリツイートしてくれたりしました。
契約上の公開最後の週、映画館での上映最終回が午前9時からだったんですが、9割の席が埋まっていた。それもネクタイを締めた人たちで。
レイトショーも自分たちで用意してTwitterで投稿していたら、午前7時から整理券を取りに来る人が並んで。結果、1年上映しました。
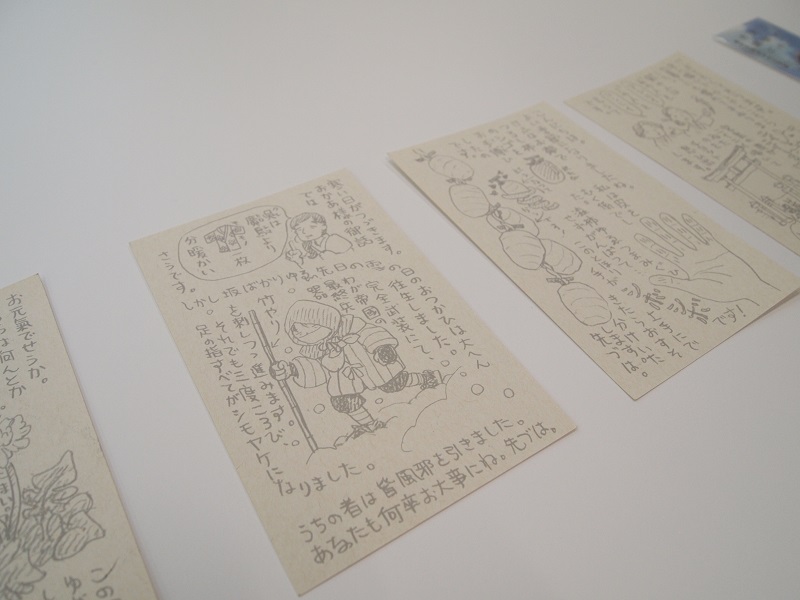
クラウドファンディングの出資者に届いた、すずさんからの「手紙」

- 片渕監督
-
「この世界の片隅に」という作品も、「マイマイ新子と千年の魔法」のファンに紹介していただきました。できてもいない映画のポスターを貼ってもらったり、イベントをしたり。その繰り返しで、手がけ始めてから4年半でクラウドファンディングにたどり着きました。
Twitterをやってみようと思わなかったら全部が無だった。何も存在してなかった。「こんな作品がここにあるんだよ」と伝える手段を自分たちで持つべきだなと思いました。

- 宮坂
-
今後、インターネットで可能性を感じているところはありますか。

- 片渕監督
-
映画は映画館の席を埋めてもらわないと上映されなくなる。しかし、インターネット上で話題にされ続けている限り、お客さんが来てくださって、映画館で映画が写り続けていられる条件を作ることになるんです。

- 宮坂
-
こんな映画があるよと伝える役割をインターネットがもっとできると、映画の世界ももっと豊かになると考えていらっしゃるということですね。

- 片渕監督
-
昔は雑誌の「ぴあ」で、東京近郊で上映する映画の全タイトルが載っていました。インターネットは見たい映画の情報しか入らないのが弱点で、一覧表示されるものがあるといいなと思います。いらない情報まで見せてくれるような場所は、映画には限らずいろんなものを広げてくれることになると思います。
編集後記
東京大空襲を体験した二瓶さんのお話と、戦争を体験していない片渕監督が映画で表現した戦時中。どちらも多くの人に考えさせる、伝わるものです。この2つを結ぶのが「記録」だったということが、片渕監督が講演で見せてくださった、とても緻密で膨大な量の資料で分かりました。改めて、記憶と記録をアーカイブし、未来へ残す必要性を感じました。
お問い合わせ先
このブログに関するお問い合わせについてはこちらへお願いいたします。