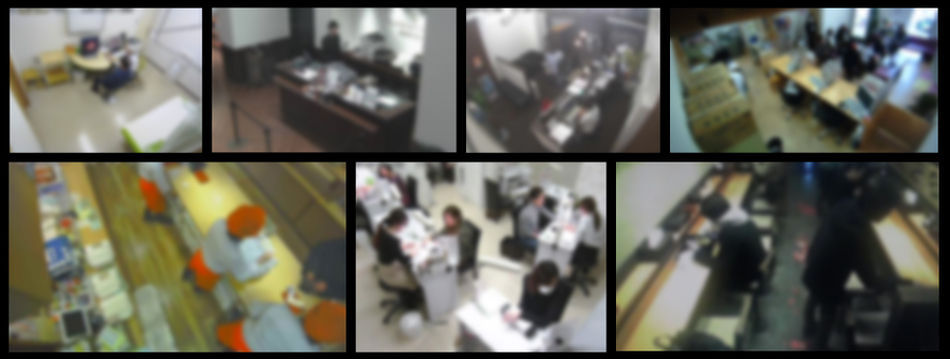華麗な着物を身に着けてお座敷に上がり、芸を披露し客を楽しませる。“女性の仕事”と思われがちな「芸者」という職業を、男性ながら続ける人物がいる。東京・大森海岸駅近くの芸者置屋「まつ乃家」の女将、栄太朗さん(32)だ。知られている限り、日本で唯一の女形芸者で、「男性でも女性でもなく、『栄太朗』としてお客さまと付き合う」と語る。その生き様に迫った。(文・桑原利佳/動画・ASHI FILMS/Yahoo!ニュース 特集編集部)
まずは下の動画で、女形芸者・栄太朗さんの「美しさ」を堪能していただきたい。
色っぽい流し目 「男に見えない」
春まだ浅い3月初めのある夜、東京・品川の屋形船「船清」が年2回開催する恒例イベントがあった。お台場から隅田川をさかのぼり、スカイツリーを望むコースで、食事をしながら芸者とお座敷遊びが体験できる。所要時間2時間30分で1万800円。この種の船遊びとしては、お手頃価格だ。
この日の参加者は約70人。「船清」の女将・伊東陽子さんに続いて、3人の芸者があいさつに立った。
「男ですが芸者をやっている『まつ乃家』の栄太朗です」
栄太朗さんがこう切り出すと、初めて参加した男性客は、「男性には見えない……」と驚いていた。

屋形船のイベントで参加者を楽しませる栄太朗さん(撮影:John Enos)
栄太朗さんはお酌してまわり、ときに踊ってみせ、三味線を弾きながらうたい、冗談を言って笑わせる。全員を前にマイクでお座敷遊びの説明をしているときでも、離れた席の客の小さな動きを見逃さず、「なにしてるの~?」とすかさずツッコミを入れて笑いを取った。場の雰囲気を読むのがはやい。

参加者と会話を弾ませる栄太朗さん(撮影:John Enos)
「船清」の伊東さんは、栄太朗さんについてこう語る。
「屋形船では一度にたくさんの方をもてなします。栄太朗さんには、多くのお客さまを同時に楽しませる軽快な話術があります。男性でも、違和感なく彼の話に引き込まれていく。それに彼の流し目は、女性のお客さまも魅せられるくらい色っぽい。外国のお客さまも今はとても多くなっていて、『栄太朗さんにお願いしたい』という依頼もあります」

屋形船の「船清」の女将・伊東陽子さん(撮影:John Enos)
イベントが終わるころ、栄太朗さんの胸元には、客からの「心付け」のお札がたくさん挟んであった。
23歳の決断 「大変なほうを選んだ」
女性の格好をした男性の芸者は、これまでも存在していた。性社会・文化史研究者の三橋順子さんの著書『女装と日本人』には、明治時代から彼らの存在は知られ、戦後にはあちこちの温泉地で活動していたことが書かれている。彼らに共通するのは唄や踊りに優れていたことだという。

栄太朗さんは8歳から踊りの稽古を始めた(撮影:John Enos)

指先の繊細な動きに思わず引き込まれる(撮影:John Enos)
栄太朗さんは、置屋の女将だった母・まりこさんに言われて10歳からお座敷に出て、踊っていた。
「初めは女性の格好をするのがイヤでしたが、当時は人手も足りず、踊らなければ明日のごはんも食べられないだろうという思いでした。ただ、僕は不器用なので、いまさらほかの仕事はできそうになく、芸者という仕事をありがたく思うようになったのです」

踊りに太鼓、いまも週2、3日は稽古事に通う。右が栄太朗さん(撮影:John Enos)
転機は、がんに侵された母の死。
「決断を迫られました。置屋など明日なくなっても誰も困らない仕事です。自分は男だし、続けるべきか、このまま終わらせるべきか、正直、悩みました。そのとき意識したのが、死に際に母が言った『楽か大変かで言ったら、大変なほうを選んでもらったほうが私はうれしい』という言葉でした」
栄太朗さんが23歳のときだった。

栄太朗さんの母・まりこさんの遺影(撮影:John Enos)
花街の盛衰 芸者は15人ほどに
上村敏彦著『東京 花街・粋な街』によると、大森海岸に花街ができたのは明治期。海水浴場ができたことを機に人が集まるようになり、次々と料理屋が開業、1898(明治31)年に最初の芸者置屋ができた。花街は1930年代に最盛期を迎え芸者も380人になったが、それも太平洋戦争勃発まで。戦後に少し息を吹き返すも、1966年に200人はいた芸者は減り続け、1980年代前半には花街は「終焉した」と本書には書かれている。しかし、その火が消えたわけではない。「まつ乃家」はこの大森海岸の花街と地続きで栄えた、「大井海岸」と呼ばれた花街のあった場所にある。
大森や大井が花街として栄えた当時を知る、最も古い置屋「由の家」の女将・のぼるさんが振り返る。
「私がお座敷に出た1967年当時は、大きな料亭がいくつも軒を連ねていてね。毎日2、3件のお座敷があってとても忙しかった。お座敷で会う芸者衆も毎回違って、名前を覚えるのも大変で(笑)。料亭もとても広くて、お客さまをお手洗いにご案内すると、ときどき自分たちの部屋が分からなくなって、仲居さんに『ちゃんと覚えておいてね』と怒られたものです」

芸者置屋「由の家」の女将・のぼるさん(撮影:John Enos)
現在、置屋は四つになり、芸者の数も今では4店合わせて15人程度。のぼるさんは「みんな副業なしにはやっていけない」と言う。
「女性たちの心意気がつくる街」
「由の家」の芸者だった栄太朗さんの母・まりこさんは、2004年に独立し、芸者置屋「まつ乃家」を起した。芸者衆10人を抱え、衰退しきっていた街を再び盛り上げようと、懸命に働いた。
栄太朗さんは語る。
「僕が物心ついたころには花街はなくなっていて、わずかなお客さんしか残っていませんでした。母と芸者さんたちは、それでもどうしたら街を再び華やかにできるかを一生懸命に考えて、『なんとかしてやろう』という気概にあふれていた。かつて『大井海岸』と呼ばれたこの街は、女性たちの心意気がつくる街でした。だから僕は、昔の地名の『大井海岸』を使い続けています」

現在、栄太朗さんは、自分のほかに4人の芸者を抱えながら、「まつ乃家」を切り盛りしている(撮影:John Enos)
僕は「客寄せパンダ」です
まりこさんらの思いを継ぐ。それが、栄太朗さんの大きな原動力になっている。今も芸者としてお座敷に出続けるのは、「男が芸者をしていることで、メディアが面白がって取り上げてくれるから」だと言う。
「僕は『客寄せパンダ』です。僕らが芸者をやめてしまったら大井海岸の文化が死んでしまう。だから『やめない』というのが僕の目標です」

化粧は、背中を塗ること以外は自分でする(撮影:John Enos)

30分もすると芸者「栄太朗」ができあがる(撮影:John Enos)
栄太朗さんは、お座敷遊びをもっと多くの人に知ってもらおうと、さまざまな試みを始めている。「まつ乃家」で月1回企画する会費制の大宴会をはじめ、新年会や忘年会、イベントなどへの出張営業……。冒頭の屋形船での営業もこうした取り組みの一つだ。さらにブログやSNSでも情報発信し、最近では女性客や外国人客が増えてきたという。
今回の屋形船でも約3分の1は女性客だった。栄太朗さんが、伝統的なお座敷遊びの一つである「金毘羅船々(こんぴらふねふね)」(台の上に置かれたお椀を取る遊び)で対戦したい人を募ると、あちこちで手が挙がる。その挑戦者のほとんどが、お座敷遊びにはこれまで縁がなかったはずの女性たちだった

屋形船で舞を披露する栄太朗さん。女性客の姿も多い(撮影:John Enos)
かつては「お座敷で男性だということは内緒にしていた」と言う。「芸者」とはどこまでいっても女性の仕事であり、自分も客から“女性であること”を求められていると考えていたからだ。
今は違う。
「お座敷でも、昔はお客さまの9割9分が男性でした。今は平均して2割くらいが女性です。だから、それぞれ接し方は変えています。例えば、男性のお客さまに接するとき、努めて声を高くしたり女性っぽくしゃべったりはしない。お酌のしぐさは少し女性っぽくしても、男の心境で会話をします。女性のお客さまに接するときには、さっぱりとした女の友人のような感じにする。お客さまの好みに合わせて、そのときどきでバランスを取っています。僕が追い求めているのは、男性でも女性でもなく、『栄太朗である』ということです」
男性でも女性でもなく「栄太朗」として
「栄太朗である」とは?
「僕は男なので、これから年を重ねることでひげが濃くなったり、のどぼとけが目立ってきたりする可能性があります。そうなれば、男性の格好でお座敷に出ることになるかもしれない。そのときにもお客さまとの関係を続けられないとダメだと思っています。そのために、男性でも女性でもない『栄太朗』という人間としてお客さまとお付き合いしていく必要があるのです」
芸者の仕事は、まずはきれいであること、そして芸ができること。「古くから続く芸者文化を今に残してお客さまの前に現れるというのは、ある意味『お芝居』であり、夢を売ること」だからだ。

化粧を終えた栄太朗さんが鏡を覗く(撮影:John Enos)
「一番大事なのは人と人とのつながりを大切にすることです。お客さまと近付きすぎず、離れすぎず。長く関係を保つうちに、格好はどうでもよくなってきて、人間としてのお付き合いに変化してくる。そういうお付き合いのお客さまがいらっしゃる限り、10年後、20年後もここにいなければいけないと思っています」

(撮影:John Enos)
【文中と同じ動画】
桑原利佳(くわはら・りか)
雑誌や書籍、ウェブサイトの編集者兼ライター。ニュース週刊誌「AERA」の編集スタッフなどを経てフリーに。現在、THE POWER NEWS編集部に所属。
ASHI FILMS
望月冬子とJohn Enosによる制作プロダクション。米CNNなどでドキュメンタリー制作を行う。2017年、ギリシャの難民キャンプを題材にしたショートドキュメンタリーで、ニューヨークの映画祭Long Island International Film Expo (LIIFE) のドキュメンタリー部門に入賞。ashifilms.com