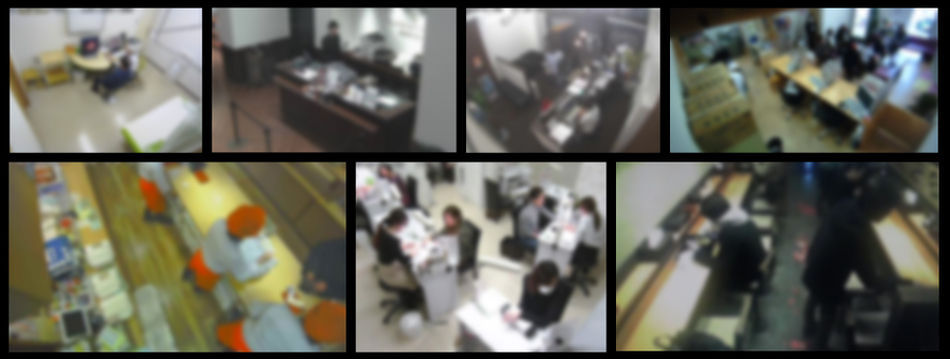山本宏樹/deltaphoto
「オレらがいなかったら、うめえ魚は食えねえよ」 築地市場“最後の初セリ” 仲卸のプライド
2018/01/12(金) 10:12 配信
オリジナル年明けの築地市場(東京)を彩る「初セリ」が、最後の年を迎えた。1935年に日本橋から移転して開場した築地市場は、戦中から戦後の高度成長期、そして現在まで日本の食を支え、「築地ブランド」を確立した。今年10月に豊洲に移る予定の「築地」。その記憶と文化は、どう受け継がれていくのか。築地とともに生きてきた“住人”たちに聞いた。(文・鈴木毅/動画・ASHI FILMS/Yahoo!ニュース 特集編集部)
まずは初セリの活気と、関係者らの想いを動画(約6分)で見てほしい。
マグロ買い 磨かれたセンス

初セリを前に、各地から集まった生鮮マグロが並んだ(撮影:山本宏樹/deltaphoto)
市場用語で「大物」と呼ばれるマグロを扱う卸売・中卸業者にとって、築地の一年は恒例の生鮮マグロの「初セリ」から始まる。
1月5日、セリ場に並んだ生マグロの数は436本。不漁だった昨年の約1.5倍になった。今年も不漁が心配されたが、年末になって天候が回復し、ふたを開けてみれば例年並みの数が確保できた。

尻尾の断面は脂の状態を見る重要なヒントとなる(撮影:山本宏樹/deltaphoto)

仲卸業者たちは、マグロを確認しては、こまめに「下ヅケ帳」に書き込んでいた(撮影:山本宏樹/deltaphoto)
セリに参加する仲卸業者たちは、まず、並んだマグロの獲れた場所、漁の方法などの情報を確認し、外見をチェックする。そして手カギと懐中電灯を持ち換えながら、尻尾の断面で脂の状態を見たり、腹の切り込みから身の状態を見たりして、目当てのマグロを見極める。これこそ彼らにとって勝負どころ、「下ヅケ」と呼ばれる事前チェックだ。
実際に切ってみなければマグロの最終的な良しあしは分からない。それだけに、彼らのセンスと経験値による“目利き”がものをいう。

別のセリ場では冷凍マグロがずらり(撮影:山本宏樹/deltaphoto)
生マグロ専門の“名手”
仲卸業者たちがマグロの前に屈みながら一本一本、丹念にチェックするなか、セリ場をぶらぶら歩いているだけのように見える長身の男性がいた。時折、足を止めてマグロを見やる。そして、後ろを付いて歩く若者に一言、二言、話し掛ける。会場をパトロールしているかのようだ。
彼の名は、小川文博さん(64)。生マグロ専門の仲卸「西誠」の社長だ。同業者も一目置く、その道44年の“名手”である。

セリ場を歩く西誠の小川文博さん親子(撮影:鈴木毅)
築地の水産部門で600弱の仲卸業者がいるなか、マグロ仲卸は200程度。そのうち生の天然マグロだけを専門に扱う業者はほとんどいない。小川さんはとにかく「生」にこだわり、冷凍モノや養殖モノには一切手を出さない。後ろの若者は息子の和宏さん(30)だ。

「築地であろうと、豊洲であろうと、われわれのやる仕事は変わりません」(撮影:John Enos)
小川さんは言う。
「言葉で説明するのは難しいんですが、魚を買うことは感覚的なもので、感性が必要です。歩いているだけで、いい魚はすぐに目星がつく。魚に呼ばれて足が止まるんですよ」
鐘が鳴った
朝5時すぎ、卸売業者代表の年初あいさつなどが終わり、全員で恒例の手締めをすると、セリの始まりを知らせる鐘が鳴らされた。

一瞬の静寂から初セリが始まる。セリ人の大きな声が響き渡った(撮影:山本宏樹/deltaphoto)

毎日のセリはこの鐘の音から始まる(撮影:山本宏樹/deltaphoto)
台に上がったセリ人が声を張り上げ、独特の調子でマグロの番号と価格を告げる。帽子に鑑札のプレートを付けた仲卸業者たちは無言のまま指の合図で数字を示し、競り落としていく。この場所で長年行われてきた、いつも通りのセリの風景だ。

今年の初セリの最高値は3645万円。仲卸「やま幸」が落札した405キロの青森・大間産クロマグロだ(撮影:山本宏樹/deltaphoto)
築地に入荷される生マグロはクロマグロ、メバチマグロなど5種類。日本はマグロの漁獲量、輸入量ともに世界最大級だ。
小川さんは語る。
「こんなにたくさんのマグロが入ってくる市場は築地のほかにありません。だから全国の建値市場(他の市場で取引する参考価格を形成する市場)になっているわけです」
市場の主役

仲卸業者たちが店を構える仲卸売場。雑然とした雰囲気が魅力の一つだ(撮影:John Enos)
市場の主役は、卸売業者と仲卸業者だろう。築地市場には全国から1日1600トン超の水産物が集まる。深夜に入荷すると、まず「大卸」と呼ばれる卸売業者のところに集められる。築地で水産物を扱う卸売は7社。彼らが朝方にかけて、魚種ごとに「セリ」や「相対(直接取引)」で仲卸業者などに販売していく。
質の良しあしを見極めるのが仲卸だ。買い付けた商品は、市場内にある自分の店で小分けにして並べる。仕入れに来た料理人や魚屋、スーパーマーケットなどの小売業者が扱いやすく、消費者が食べやすい形にさばいて提供する。一匹のマグロをさばいて部位ごとに的確に販売するのは、プロの技がなければ難しい。

初セリ最高値のマグロは、すぐに店に運ばれて解体された(撮影:山本宏樹/deltaphoto)
小川さんは3代目社長。祖父が大正時代に創業したころから天然の生マグロにこだわり続けてきたという。
「マグロは面白い魚で、同じ種類でも一つとして同じ味はない。大きい魚だから個体差がすごくあるんです。時期と獲り方によってもまったく違う。同じ定置網で獲れても夏と秋では違うし、場所が西か北かによっても違う。同じように見えてもそれだけ違うから、きちんとした下ヅケをして、ちゃんと中身が想像できないといけないのです」

セリに出されるマグロには、獲れた場所、漁の方法などの情報が書かれている(撮影:山本宏樹/deltaphoto)
仲卸としての仕事の本質は、品質や味を見極め、需給を判断し、安心・安全を担保しつつ提供していくことにある。
「天然の生マグロは脂に甘みがずっと口のなかに残ります。そして本当に鮮度のいいマグロは香りがある。頭を切った瞬間にプーンと香ってくるような。マグロのおいしさは個体の力。産地の力ではありません。ブランドに振り回されず、ちゃんと評価するのがわれわれ仲卸です」
築地市場80余年の歴史

1970年ごろの初セリの風景。初荷を運ぶ後ろに、台に立った競り人(右上)が見える(所蔵:築地魚市場銀鱗会)
築地市場のルーツは、江戸時代の1603年ごろにできた日本橋魚河岸(うおがし)にある。
移転のきっかけは、1923年に起きた関東大震災。壊滅した市場の代替として、当時の東京市が海軍省用地だった築地に臨時魚市場を開設したのが始まりだ。食料の供給と物価を安定させるため、中央卸売市場の制度が必要とされていた時期と重なる。利権の調整などを経て、築地市場は1935年に正式開場した。

1970年、築地市場の岸壁に着いた船から荷降しされたマグロ。これからセリが始まる(所蔵:築地魚市場銀鱗会)

正式開場して間もない1937年ごろのセリ。仲卸の旦那衆が山高帽にステッキの姿で集まっている(所蔵:築地魚市場銀鱗会)
築地への移転で混乱、「今と同じ」
築地には、市場の歴史資料などを管理する「築地魚市場銀鱗会」という団体がある。事務局長を務めるのは女性誌の編集者だった福地享子さん。築地市場に魅了されて編集者を辞め、仲卸業者で12年ほど働いた後、7年前に現職に就いたという。

編集者から築地の世界に飛び込んだ福地享子さん(撮影:Yahoo!ニュース 特集編集部)
「建物は、バウハウス(ドイツの合理主義的・機能主義的なモダン建築)など欧米デザインの影響を受けています。鉄道輸送に対応するため、貨物列車が市場の中まで入れるように建物は扇形に弧を描いてますが、当時、日本橋から移ってくる仲卸業者たちは、こんな使いづらい建物では商売にならないと猛反対しました」

貨物列車の引き込み線に沿って扇形を描く建物が特徴的な築地市場(撮影:John Enos)
開場時は日中戦争前夜で、間もなく日本は戦争に突入。市場も戦時体制のなかに組み込まれた。福地さんは言う。
「開場から4、5年はいわゆる市場らしい空気だったけど、その後は戦時の配給所みたいな形に変わっていくわけ。戦後はGHQ(連合国軍総司令部)の統制下に置かれ、米軍のクリーニング工場がつくられた。戦争の始まりからGHQの統制が解除されて完全に市場機能を回復するまでの20年ほどは、築地にとってエアポケットのような時代です」

「築地を去るからには、やっぱりこの土地のことをきちんと知っておきたい」と福地さん(撮影:Yahoo!ニュース 特集編集部)
その後の築地市場は、日本の高度経済成長期に合わせて急速に発展した。1960年代になると物流の主役は鉄道からトラックに。
元水産庁の官僚で東京財団上席研究員の小松正之さんが解説する。
「すでに1970年代ごろから築地市場は手狭になり、移転して近代化すべきだという話が具体的に出始めました」

いまも時間があれば築地に立ち寄るという小松正之さん(撮影:John Enos)
築地市場で水産物の取扱数量がピークを迎えるのは1980年代後半。国内の漁業生産量は年間1200万トン台になり、世界の水産物が集まる一大拠点となった築地は日本の食文化をリードしていく。しかし、バブル崩壊後の景気低迷、世界的な水産資源保護の流れのなかで漁業生産量は年々減少。近年は3分の1の400万トン台にまで減った。年間80万トン以上あった築地の取扱数量も、半分近くまで落ち込んでいる。

築地の一日は未明から始まる(撮影:山本宏樹/deltaphoto)
市場を取り巻く時代の変化は著しい。近年では自社で流通機能を持つ大型スーパーや外食産業などが力をつけ、セリや相対でも彼ら「売買参加者」の存在感が増した。1社で大量に買い付ける彼らの登場で、市場の持つ価格調整機能の仕組みは変わりつつある。
それでも築地を支えているのは、仲卸業者たちの強いプロ意識だ。
小松さんは言う。
「彼らの技術は天下一品です。マグロの切り身も絶品。イクラでもスジコでもイカでも何でも、高品質なものを売ってくれる。鮮度維持の仕方、凍結・解凍方法も教えてくれる。おいしい食べ方も教えてくれる。そのプロフェッショナリズムには、いつも驚かされます」
自信のない魚は売らない
築地最大級の仲卸の一つ、「山治」の山崎康弘社長(48)は、こう熱く語ってくれた。

山崎康弘さんは8年前に父から社長を継いだ(撮影:John Enos)
「僕らはプライドを持ってやっています。絶対に危ない魚は売らないし、自信のない魚は売らない。自信のない魚だったら、きちんと相手に説明して持って行ってもらう。おいしくない魚は売れない。築地がそれをやったら、お客さんが買いに行く場所がなくなります。だから、僕らは失敗が利かないんです」
山治は1958年に父が創業した。「物心がついた時には築地にいた」という山崎さんは、小学校の友だちがミニカーやラジコンで遊んでいるとき、イセエビやカニを触っていた。学校から帰ると市場の店で魚をさばいて、それから遊びに出掛けたという。

山治は、ひときわ大きな看板を掲げる(撮影:John Enos)
山崎さんは大学卒業後、2年間の海外留学を経て24歳で家業に入った。先代のときは貝類専門。今は約320種類の商品を扱う。
「われわれは、漁師が送ってきたものを値付けして売っているだけじゃなくて、良いもの、悪いものを目利きしてきた。100匹の魚がいたら100匹違う。魚から出てくるパワーが分かるんです。たかがイワシ、たかがサンマ、たかがアジかもしれないけれど、最高の味がある。漁師は魚を獲るプロだけど、魚を見る目はない。仲卸があってこその魚食文化です。それが、僕らが伝えていかなければならない技術なのです」

「20代で初めてセリに出たときは、手が震えました」と山崎さん(撮影:John Enos)
自らの技術への自信があるからこそ、山崎さんは「築地の魚は世界一」と言い切る。
「オレらがいなかったら、うめえ魚は食えねえよ、と自負しているんで。これを次代に伝える責務があると思っています」
豊洲で生き残るために
築地の仲卸「堺周商店」の酒井衛専務(62)も、先を見据える。
「実際に豊洲に行くことになったら、さらに商売の形を変えないと生き残れないんじゃないかと思っています。どこに行ってもやっていくしかない」

酒井衛さん。「変化を恐れるより、自分が変化していかないと」(撮影:John Enos)
堺周は1889年に日本橋魚問屋として創業した老舗だ。当時「6大問屋」と呼ばれた中で、現在も残る唯一の大手仲卸である。酒井さんが力を入れているのは、アワビやカニの高級路線。最近では、和食ブームの影響もあってアジアへの輸出が好調だという。

おいしいカニは一目で分かるという。「僕らはプロですから」と酒井さん(撮影:John Enos)

「毎日新しい魚が入ってきて、毎日状態が違う。とにかく面白い」(撮影:John Enos)
酒井さんは築地で生まれ、地元の小学校に通い、築地で働いて38年。大学でフランス文学を学んだインテリでもある。
「バブルの時代を越え、仲卸の数もピークの3分の1くらいに減った。豊洲に行ったら、さらに半分になってしまうでしょう。人口減少やネット通販の隆盛などいろいろな要素もありますから」
築地の移転問題は、仲卸の存続問題でもある。市場機能を近代化させるという命題のもとで、伝統的な仲卸の機能はこれまでどおり働くのか。
「そのうちネットで注文したお刺し身がドローンで届くような時代になるかもしれない。そこに自分たちも参加できるのか、あるいはそこに負けるのか。生き残るために、南極からアワビを持ってくるとか、火星からカニをもってくるとか、とんでもないことをいろいろ考えて、新しい種を仕掛けていかないと」
40年前の記憶 技術の伝承

築地には80余年の歴史が積み重なっている(撮影:John Enos)
冒頭に紹介した小川さんは20代でセリ場に出始めたころ、2代目社長だった父親に付いて回った。
「技術を受け継ぐと言っても、非常に難しいものです。現場で魚を見ることで覚えていくしかない。私も日々、父が買った魚が実際に切ってみてどうだったか、それを自分で蓄積していきました」
いま当時の自分と同じように、息子の和宏さんが傍らにいる。
「この魚の腹がいいとか、鮮度がいいとか、感覚の話をしています。この感じをつかんでくれればいい。昨年は(和宏さんが)自分で選んで2本買いました。そうやって学んでいく。これからの市場をつくっていく世代ですから」
文中と同じ動画
鈴木毅(すずき・つよし)
株式会社POWER NEWS取締役。1972年、東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒、政策・メディア研究科修了後、朝日新聞社に入社。「週刊朝日」副編集長、「AERA」副編集長、朝日新聞経済部などを経て2016年10月末に退社
ASHI FILMS
望月冬子とJohn Enosによる制作プロダクション。米CNNなどでドキュメンタリー制作を行う。2017年ギリシャの難民キャンプを題材にしたショート・ドキュメンタリーで、ニューヨークの映画祭Long Island International Film Expo (LIIFE) ドキュメンタリー部門に入賞。ashifilms.com
[写真撮影]John Enos、山本宏樹/deltaphoto、鈴木毅
[写真所蔵]築地魚市場銀鱗会