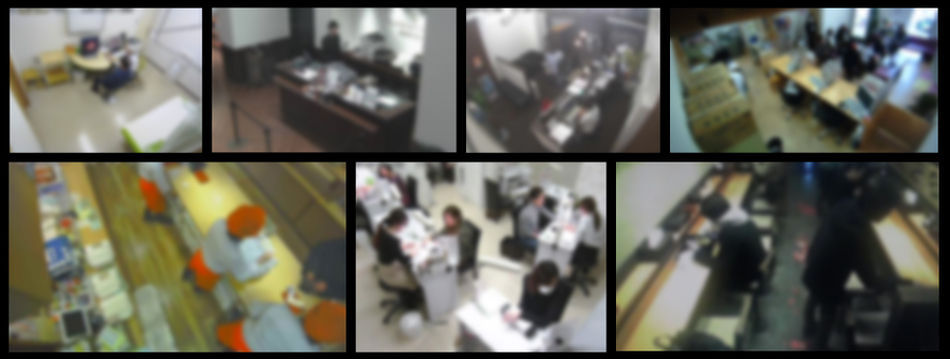「なんで俺、ここに? 外に出たいんだけど。外に出てもいいんでしょ?」。介護施設に暮らす78歳の男性は取材中、何度かそう繰り返した。男性は認知症を患っている。自分の置かれた状況が分からず、自分の意思を的確に伝えにくい。男性の本当の意思は何か。周囲もそれをくみ取ろうと、試行錯誤が続く。さらなる高齢化社会へ一直線の日本。2025年には認知症高齢者が約700万人に達すると言われるなか、その意思をどうやって把握するのかが大問題となって横たわっている。(Yahoo!ニュース 特集編集部)
「問題行動」の奥底に意思がある
神社の前を通り過ぎ、小高い丘を登りきると、「銀河の里」は見えてくる。岩手県花巻市にある民間の福祉施設。認知症高齢者のグループホームや特別養護老人ホームを運営している。周囲には田畑が広がり、自然環境は抜群に良い。


「銀河の里」の施設群=上。周囲は緑が豊か=下(撮影:竹内弘真)
入所者は約50人。言葉を発することもできず、意思疎通がままならない人も多い。この施設には大きな特徴がある。認知症高齢者の行動を尊重し、施設の事情や都合によって管理しない点だ。外部からは放任主義のようにも映る。
そんな施設にウタさん(92)が入所したのは、3年前だった。長年、小学校の教師を務めていたという。

ウタさん。入所して3年になる(撮影:竹内弘真)
スタッフの今野美稀子さん(26)はウタさんとしょっちゅう夜中まで話し込む。今野さんはウタさんの入所時をこう振り返る。
「娘が迎えに来るはずだけど来ない、って。娘は殺されたんじゃないか、軍隊に入れられたんじゃないか、って。電話をかけないといけないとか、手紙を書かなきゃいけないとか、心配して(施設内を)捜しているんです」
妄想をしゃべり続けるウタさん。その相手を今野さんは昼夜を問わず続けた。そうするうち、ウタさんの意思がなんとなく分かってきたという。

スタッフの今野美稀子さん(撮影:竹内弘真)
「20歳前後の若い頃の娘さんを心配していたんです。ウタさんがその年齢の頃、ちょうど日本は戦争中。(娘さんだけではなく)ウタさん自身の少女時代のことも心配している。殺されたんじゃないかとか、軍隊に入れられたとか、そういうのは戦時中の心配じゃないですか? (ウタさん自身が)一番つらかった時代をやり直しているんじゃないかと思ったんですね」
そしておよそ1年半後、ウタさんは妄想をしゃべらなくなった。今野さんは、十分にやり尽くして満足したのではないか、と考えている。
「いろいろ我慢しないといけない時代を経てきた人たちが、ようやく自分のやりたいことをやっているんじゃないかな、と。それを思い切りやって、自分を出してもらいたい。家に帰りたいと歩いていく人がいれば(私たちスタッフは)付いて行くし、夜中ずっと起きていれば、ずっと一緒に動いています」


ウタさんと笑顔で話し合うスタッフの今野さん=上。「銀河の里」には約50人の入所者がいる=下(撮影:いずれも竹内弘真)
切なる願い「社会的役割あったあの頃へ」
つじつまの合わない会話を延々と続けたり、便を壁に塗り付けたり。そうした問題行動を銀河の里のスタッフは「スイッチが入る」と表現する。そして一度「スイッチ」が入ると、ここでは危険がない限り止めず、昼夜を問わずスタッフが見守り、本人の気が済むまで徹底的に行わせるという。なぜ止めないのか。その背後には、本人の「本当の意思」が隠れていると考えているからだ。
この施設の宮澤健理事長(61)は言う。

「銀河の里」理事長の宮澤健さん(撮影:竹内弘真)
「意思ということで言えば、『社会的役割があったあの頃に戻してくれ』というのが意思だろうと思うんです。そこに戻ろうとする人は『帰る』などと言いだす。『(何かを)取られた』と言いだすのは、そういうものが無くなっちゃったから。それは切実な願いなんですよ。それこそが意思なんです。なのに、それを妄想とか、帰宅願望とか言って切り捨てているわけです」
SDMという新しい試み
認知症患者や知的障がい者らについてはこれまで、「自己決定の能力がない」という受け止め方が多かった。「でもそれは違う。そうした人たちにも自分のことを自分で決める能力がある」と考え、活動する人たちもいる。
その一つがオーストラリアで実践されているSDMという活動だ。「Supported Decision-Making」の略語で、日本では「意思決定支援」などと呼ばれている。
家族や友人、地域の人々を加えた数名で「支援チーム」をつくり、本人を交えて月に数回、定期的にミーティングを重ねる。そうした対話を半年間継続し、本人の意思や希望を把握する流れだ。

東京で開かれたSDMのワークショップ(撮影:横関一浩)
実はこの9月、SDMに関するワークショップが東京で開かれた。SDMの第一人者でオーストラリア在住のシェア・ニコルソンさんも参加。知的障がい者や支援のボランティアらも参加し、実際にSDMの実践も試みた。
いったい、どんなコミュニケーションを繰り広げたのか。その様子を動画で見てほしい。「銀河の里」の様子も盛り込んだ8分超。「人の本当の意思とは」を考えさせられる内容になっている。
「どんな人にも意思表明の力ある」
ニコルソンさんはこう言う。
「どんな人でも意思を表明する力を持っています。言葉をうまく話せない人にも意思はあるのです。でも、その夢や希望をくみ取ることができるかどうかは、聞き手の力量にかかっています」
聞き手の力こそが必要――。その言葉に従い、会場では以下のようなやりとりが続いた。質問と対話を繰り返し、時間をかけて少しずつ心理的な壁を崩していく。それがSDMの特徴だ。答えているのは知的障がいのある男性だ。

シェア・ニコルソンさん(撮影:横関一浩)
――もしお金がいくらでもあったら何をしたいですか?
「野球に行きたい」
男性は、好きなプロ野球チームの応援で名古屋や東京に行ったことがある。
――大きく考えてみて!
「もっと大きく考えるのね?…だったら大リーグに行きたいです」
実践の中で、ニコルソンさんは「Think big!(もっと大きく考えて)」という問いかけを繰り返した。なぜだろうか。
「大きく考えてほしいのです。お金や体の障がいのことで、不可能だと諦めてしまっていることをです。想像力を豊かにして考えなければ、自身が経験してきた限られた世界から抜け出せないのです」

「大きく考えてみて」という問いかけも交えながら、対話の中に心の奥底を探る(撮影:横関一浩)
飯能市の試み 市民の力で意思をくみ取る
認知症高齢者の意思を把握するさまざまな取り組み。その取材のため、埼玉県飯能市にも足を運んだ。ここでは、市と社会福祉協議会が中心になって「成年後見人」の役割の一部を一般市民に担ってもらう試みが、2011年度から始まっている。
成年後見人は民法で認められた仕組みだ。認知症や知的障がいなどにより十分な判断能力を持たない人に対し、その人が不利益を被らないように法的な援助者をつけることができる。その成年後見人は、弁護士や司法書士などの専門職が就き、財産管理などを担うのが一般的だ。
「本人に寄り添っていない専門職が支援者となるより、長年、地元で同じような生活をしてきた市民の方が本人の思いをくみ取りやすい」。飯能市社会福祉協議会の理事で、司法書士の高橋弘さん(61)はそう話す。

認知症の高齢者にも「意思」はある(写真:竹内弘真)
では、この「市民後見人」はどんな形で認知症高齢者と接しているのだろうか。飯能市内の特別養護老人ホームで、入所者の男性(78)に会った。かつては建設の仕事に就いていた。重い記憶障がいがあり、今はほとんど外出することもない。日中は窓から見える工事現場を眺めながら過ごしている。
男性は、なぜ介護施設に入っているのか理解できていないという。取材中も「俺、なんでこんなことされているの?」と口にした。
この男性の市民後見人が中村修さん(65)である。社会福祉協議会に登録されている市民後見人約70人のうちの1人。5カ月前から男性の担当となり、取材時が3度目の面談だった。

「市民後見人」の中村修さん=右。記憶障がいのある男性と丁寧に対話する(写真:竹内弘真)
――ここで2年経ってどう思ってる? 出たいとか?
「出たいとは思いますね。テニスをね、よくやってたからね。テニスやりたいなと思うけど。あと、外行きたいですよ。歩いていけますから、ゆっくりだけどね」
――運動したい?
「したいですよ。何もしないでここにいるだけでね…」
この日の面談で「男性はスポーツ好き」だと分かった。中村さんは言う。「スポーツ番組を録画して見せてもらうとか、施設にお願いできないかなと。(この男性は)『同じ場所に死ぬまでいるのか』と思ったことがあると思うんですよ。(本人の希望を引き出して実現させる取り組みは)施設側もできてないと思うので」
認知症高齢者は日常の行動範囲も限られてくる(撮影:オルタスジャパン)
市民後見人として認知症高齢者の希望をどう引き出し、どう実現させていくか。中村さんには不安もある。
「ひと月ごとですからね、様子を見にいけるのは。行ってお話しできる時間も10分か多くて15分くらいなので、なかなか難しいですよね」
認知症高齢者700万人時代まで、あと8年ほど。その意思をくみ取る仕組みを社会全体でどう整えていくか。残された時間はそう多くない。
文中と同じ動画
[制作協力]
オルタスジャパン
[写真]
撮影:竹内弘真、横関一浩、オルタスジャパン
最終更新:10/29(日) 18:40