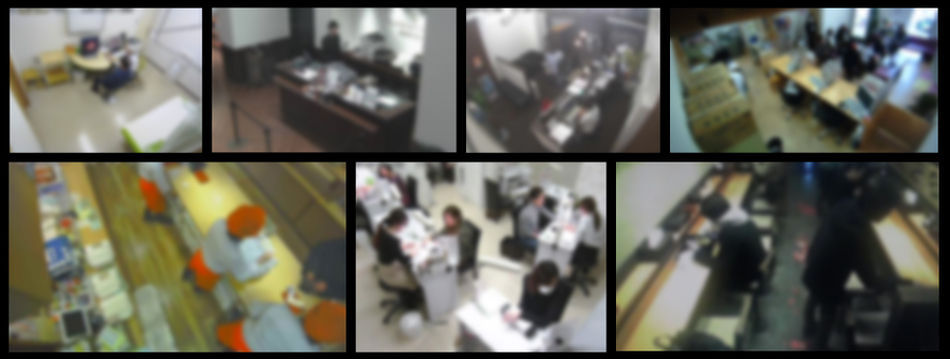沖縄を代表するロックバンド「紫」のリーダー、ジョージ紫さん(68)は「自分は何者か」を考え続けてきた。父は米軍属で、母は日本人。沖縄の人たちと一緒に街に住みつつ、米軍基地内のアメリカンスクールに通った。近所にはアメリカの悪口を言う人がたくさんいて、逆に学校では、沖縄や日本の悪口を言う者がいた。「だから三つあるんですよ、アイデンティティーが。アメリカと日本と沖縄」―。
今から45年前の1972年5月15日。その日までの27年間、沖縄は米軍の統治下にあった。日本から沖縄に行くにはパスポートが必要で、通貨はドル、自動車は右側通行。街には英語があふれ、水は「アイスワーラー」で給料日は「ペイデイ」だった。「アメリカ世(ゆ)」とも呼ばれるそんな日常を生きた人たちはいま、何を思っているだろうか。ミュージシャンやレストランの経営者たちを訪ね、「沖縄の今」を考えた(Yahoo!ニュース 特集編集部)

米空軍嘉手納基地。ひっきりなしに軍用機が飛ぶ(撮影:大城弘明)
沖縄ロックのさきがけ
沖縄発の音楽は今、日本のミュージックシーンで常に一定のウエートを占めている。その潮流は1970年前後から始まったのかもしれない。「コンディショングリーン」「喜屋武マリー」といった沖縄のロックバンドやミュージシャンが全国区になり、「紫」も多くのファンを集めた。オキナワンロックの代表格だったその「紫」の音楽はどうやって生まれたのだろうか。
ジョージ紫さんが語る。

ジョージ紫さん(撮影:大城洋平)
「米軍占領下の沖縄バンドは、米兵が遊びに来るクラブで演奏していたわけ。米兵の数がすごくて、数えきれないくらいのクラブがあって。バンドを入れたらお客さんが来るのが分かっているから、(経営者は)下手でもいいからバンドを入れる。でも、下手な英語だったり下手な演奏だったりすると、米兵は『ぶー』。ビール瓶が飛んでくるかもしれない。だから、みんな演奏も発音も一所懸命に練習し、発展していった。それは間違いないと思います」

ジョージ紫さん(左)は今も沖縄で音楽活動を続けている(撮影:大城洋平)
沖縄の音楽は米軍統治下の27年間に米国の大きな影響を受けた。それを担ったミュージシャンたちはどんな思いを抱えていたのだろう。それをまず、動画(約7分)で紹介しよう。ジョージ紫さんは動画の前半に登場する。
地上戦、土地強制収用、ベトナム戦争の出撃地...
第2次世界大戦で地上戦のあった沖縄は、そのまま米軍に占領され、1972年の「復帰」まで米軍の施政下にあった。その初期、米軍は基地の建設や拡張のため土地を強制収用し、地元住民をその土地から追い出していく。また政治・行政面でも「琉球政府」に最終的な自主決定権はなく、米兵の犯罪を取り締まる権限も無かった。
米軍による土地の強制収用で、ブルドーザーに押しつぶされた家(写真:宜野湾市立博物館提供)

1970年12月20日に今の沖縄市で起きたコザ暴動。米軍人による交通事故をきっかけに、圧政や人権抑圧に抗議する地元住民らが暴徒化した(撮影:吉岡攻)
1960年代後半から70年代にかけ、沖縄の米軍基地はベトナム戦争の出撃拠点になったこともあり、米兵の数は急増した。戦地への往復を続ける米兵は、沖縄で音楽や飲酒などに一時の快楽を求めた。一方、殺人や強姦、暴行、傷害、住居侵入などの犯罪は日常的に起き、沖縄では「反米・反基地」の機運や「本土復帰」への渇望が強まり、「独立」を声高に叫ぶ人たちもいた。
米兵向けの飲食店 「ペイデイ」の思い出
沖縄市の「CAFE OCEAN」は米空軍嘉手納基地の東側、通称「ゲート通り」沿いにある。基地のフェンスまで、わずか数百メートル。軍用機のごう音が店内でもひっきりなしに聞こえてくる。

嘉手納基地近くの「OCEAN」。看板には米軍統治下の面影が残る(撮影:大城弘明)
屋良鶴子さん(87)は1967年からここで米兵向けの飲食店を経営してきた。最初の店名は「Suzette」。サンドイッチなどの軽食やアルコールを出し、1日に1000ドルほどを売り上げていた。「2000ドルで家が買えた」と言われた時代。とくに給料日の「ペイデイ」はにぎわい、テーブルにドル札を積み上げて飲み続けた米兵もいたという。
「あのころはジュークボックスがありましたよね? 店には白人が多かったからほとんどカントリーを入れるんです。ジャズなら別ですけど、黒人はカントリー嫌いですから、白人が居ると、黒人は店に来ないです」

屋良鶴子さん(撮影:大城弘明)
1970 年前後は、米国本国でも黒人差別が厳然と残り、黒人の権利擁護を訴える「公民権運動」が燃えさかっていた。屋良さんの店が「白人専用」だったわけではないが、沖縄の飲食店も自然に「黒人・白人のすみ分け」ができていたという。
「米軍統治下、辛くはなかった」
敗戦の年、屋良さんは15歳だった。3月ごろ、「米軍が上陸してくる」と聞き、歩いて4日ほどかかる場所に家族らと避難。日米双方で約20万人、沖縄の民間人だけで約9万4千人が死亡するという沖縄戦を生き延び、屋良さんは捕虜になった。そして戦後はしばらく、米軍基地内のPX(購買部門)でレジ係として働いていたという。

「OCEAN」の店内。歴史を物語る品々がある(撮影:大城弘明)
「当時はチップがとてもたくさんありましたね。そのチップで本国(日本)の大学に行く人もいれば、家族を養う人もいた。給料は1カ月20ドル。チップは40~50ドルになっていたから給料よりか多かった。本当に助かりました」
沖縄戦を経て27年間の米軍統治。その時代と本土復帰は屋良さんにどう映ったのだろうか。
「日本に戻って良かった。みんな復帰が当たり前だと思っていましたしね。(米軍統治下の生活は)辛かった? それはありません。基地で働いて仕事もあるし、食事もたくさんあるし。(敗戦の混乱が)落ち着いたら自分で商売をしましたでしょう? 生活に困ったことはないです」


開業当時の屋良さんの店。背後には当初の店名「Suzette」の看板。嘉手納基地の門に続く「ゲート通り」に面している=上(写真:屋良鶴子さん提供)。現在の「ゲート通り」=下(撮影:大城弘明)
「(復帰への)不安はありましたよ。商売がどうなる、どういう暮らしをしていくのか。でも良かった。沖縄には今までずっと基地があって、いろいろな政治問題もあると思うんですけど、良かった」
「Aサイン」の店で
米軍統治時代の沖縄には「Aサイン」と呼ばれる飲食店があった。米軍の審査を経て営業許可を取得した店で、今で言う風営法の許可店に似ている。屋良さんの店も「Aサイン」だったし、藤浪睦子さん(69)の「ジャッキーステーキハウス」もそうだった。

藤浪睦子さん。今も店に出る(撮影:大城弘明)
ステーキ店は1953年に父が開業させた。豊かさを求めて奄美群島の喜界島から渡ってきた父。店は嘉手納基地の近くにあり、最初は「ニューヨークレストラン」という名だった。61年に那覇市に移転する際、父と仲の良かった米兵の名を冠し、今の「ジャッキー」にしたという。
当時は、若い米兵相手にサンドイッチなど軽食を売っていた。そんな貧しい米兵も「ペイデイ」には羽振りが良くなり、高いステーキを注文する。基地周辺の店は急に忙しくなり、床の泥で客の急増が分かるほどだった。

藤浪さんが保存している「Aサイン」の許可証(撮影:大城弘明)
Aサインを取得するには「皿は拭かずに煮沸消毒する」といった細かな決まりを実行する必要があった。それらも含め、戦前戦中の日本にはない文化や考え方が沖縄には浸透した、と藤浪さんは振り返る。
「当時の日本、本土はお箸が主流じゃないですか? それがフォークとナイフだからね。5歳、6歳の沖縄の子どもらが『上手に使えた』って、アメリカ人がチップくれた。1970年代の話ですよね」

現在の「ジャッキーステーキハウス」(撮影:大城弘明)
多くの沖縄県民が好むステーキも、米国文化の影響だという。
「うちの店には96歳のおじいちゃんもいらっしゃいます。この前は80代くらいの女性4人がL(サイズのステーキ)を。肉文化ですよね、沖縄は。サンドイッチ屋さん行ったら、年寄りが孫を連れて来てる。これは、よそじゃ考えられないよね、って」
基地はプラスだった でも本当は無い方が
沖縄の本土復帰と言えば、本土ではすぐ「基地問題」を連想する。米兵向けの商売を長く続けてきた藤浪さんは基地をどう考えているのだろうか。

広大な嘉手納基地(左側)と住宅密集地(撮影:大城弘明)
「私は特別なイメージは何もないですねえ。沖縄の人はやっぱ、基地があったおかげで働ける場所があるわけですよ。現金が入る。そういう意味では良かったとは思うんですけど、ただ、いろんな問題が起きるから大変だなあ、とは思います」
ここで取材に同席していた藤浪さんの妹、伊波よし子さん(63)が口を挟んだ。「ジャッキー」経営陣の1人でもある。伊波さんの考えは、姉と微妙に違うニュアンスを含んでいた。

藤浪さん(左)と妹の伊波よし子さん(撮影:大城弘明)
伊波さんが言う。
「(基地は)危険ありますからね。小学校も基地の近くにあるし、やっぱり、無い方が本当は良い。でも基地に助けられている方もいて、こればっかりは...。私たちもこういう仕事して今があるので、正直、本当に難しいですね。今でも兵隊さん、店にいらっしゃいます。全然抵抗無いし、好きですよ」
米兵好みの音楽か、「俺たち沖縄音楽」か
米軍統治下の「Aサイン」バーで歌っていたロックバンドは数多い。海兵隊の好みに合わせてパフォーマンスを重視するバンド、「紫」のように本格的なロックを披露するバンドなど、それぞれが腕を競い合った。
そんな中、照屋林賢さん(67)は音楽の方向性を考え、探しあぐねていた。

照屋林賢さん(撮影:大城洋平)
照屋さんは高校生の時からベースを弾き、卒業後は本格的に音楽を勉強しようと東京に行く。ところが、曲のアレンジに沖縄風のフレーズを使ったところ、メンバーに疎まれ、沖縄に戻った。
「(東京に行く前にAサインバーで)演奏したのはほとんどカントリーです。米兵がめちゃくちゃ喜ぶんですよ。ロックやるよりめちゃ受ける。ばか騒ぎするんですよ。アメリカ人って、カントリーが自分たちの音楽。ロックもそうだけど、それをアメリカ人でもない僕らが演奏する。やっぱ、悔しい部分があって。彼らは俺らの音楽を聞かないしね」
1970年ごろのコザ市。中心街には英語のネオンがあふれ、ロックやカントリーが響いた(撮影:吉岡攻)
三線や島太鼓をアレンジ
東京から戻った照屋さんは1987年、「りんけんバンド」でデビューした。沖縄の伝統楽器「三線(さんしん)」を自ら弾き、「島太鼓」なども採り入れた。沖縄音楽と現代音楽を融合させ、「沖縄ポップ」という新しいジャンルを作っていく。
「東京から戻った時に『自分がなぜここにいるのか』も含め、自分の目標とか、はっきりした意見を持つようになった。沖縄が抱える問題についても。で、やっぱ、俺は沖縄の音楽をやるんだ、と。沖縄の文化とか工芸とか、沖縄の諸々に関して、当時のアメリカ人って全く興味を示さなかった。だから、とても悔しくて。(自分の音楽には)その影響が一番大きいかもしれないですね。『俺たちは俺たちなんだ』って」

沖縄では米国人の姿がどこにでもある。多くは軍関係者だ。北谷町で(撮影:大城洋平)
沖縄の人は最も大事なものを忘れている、と照屋さんは考えている。
「沖縄は結局、何かに巻き込まれていく環境になっている。経済も政治も基地も。アメリカ兵の行動を見ればすぐ分かるけど、完全に沖縄は植民地。何度、僕らが同じ説明しても彼らには分からない。良いやつもいるんですよ。だけど、沖縄はしっかりしないと、この先もっと先細りして、沖縄じゃなくなる」
「世 世 世」で問うた「沖縄」
りんけんバンドの曲に「世 世 世 〜YOU YOU YOU〜」がある。1993年の発表で「ゆーゆーゆー」と読む。
「世(ゆ)」は、沖縄の言葉で「時代」の意味だ。「唐世(琉球王朝時代)」「大和世(戦前の日本統治)」「アメリカ世(戦後から復帰までの27年間)」の三つの「世」を経験した沖縄を表現した。今は、その「アメリカ世」が終わり、沖縄は再び「大和世」を迎えている。

りんけんバンドを率いる照屋さん。この北谷町の海岸にライブハウス、スタジオ、レストラン、そしてホテルから成る複合施設を建設中。新しい沖縄の音楽を生み、発信する場にするという(撮影:大城洋平)
ロックバンド「紫」を率いたジョージ紫さんは、日系2世の父と沖縄出身の母の下で育った。日本とアメリカの両方の目。その目線でジョージ紫さんは「人種・国籍によるいがみあいに意味はない」という思いを込め、歌い続けている。りんけんバンドはどうだろうか。「ゆーゆーゆー」はどんな曲で、何を歌っているのだろうか。それをもう一度、動画で見てほしい。
本文中と同じ動画です
[制作協力]
オルタスジャパン
[写真]
撮影:大城弘明、大城洋平、吉岡攻
提供:宜野湾市立博物館、屋良鶴子