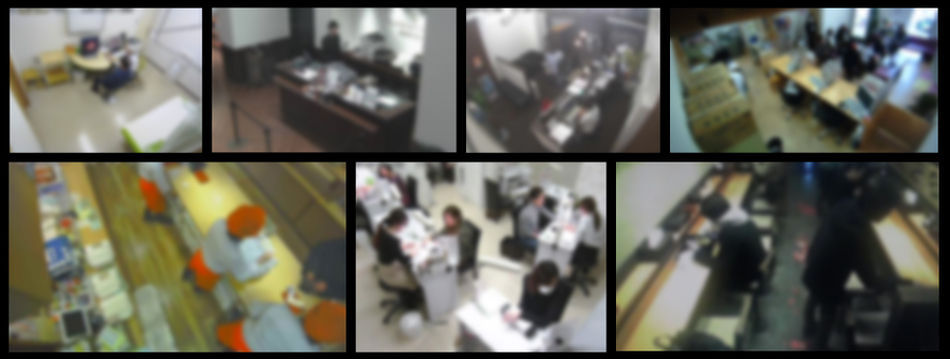「がん」は長年、日本人の死因1位だ。2人に1人はがんにかかる。医療の発達により「不治の病」ではなくなってきたが、がんと診断された後に仕事を辞める人の割合は3割を超える。がんが判明したとき、今の仕事を継続できるかどうか、職場の理解や支援制度はどうか。健康な人はふつう、そこに思いを巡らすことはない。あなたも「自分は大丈夫。絶対、がんにはならない」と思っていないだろうか。(Yahoo!ニュース編集部)
「一番の心配はお金のことだった」
「精巣がん」が見つかったのは、2007年4月だったという。「緊急入院だったので、心配する暇もなかった」。名古屋市に住む田中孝憲さん(41)は、9年前の出来事を鮮明に覚えている。機械系エンジニアで自動車部品の設計などを手掛けていた。当時32歳。経験も積み、働き盛りだった。
手術を受けた田中さんは順調に回復し、翌月の5月には職場復帰も果たす。体調も戻り、以前と同じように仕事を続けたという。状況が一変するのは、病状が再び悪化した秋からだ。がんの転移が判明したことから、仕事を休んで入院し、抗がん剤の治療に専念することになったのだが――。

30代前半で「がん」と診断された田中孝憲さん(撮影:長谷川美折)
入院は4カ月間に及んだ。抗がん剤の副作用がつらかったと言う。「吐き気、倦怠感。毛が抜ける。倦怠感が一番つらい。イライラ、元気が出ない。(薬による)発熱も辛かった」。それと並行し、生活も苦しさを増していく。
基本給は入院中に出なくなった。その状態で、治療費や入院費用がかかった。毎日の生活費もある。「普通に仕事してその収入で生活するのとは、訳が違った」と田中さんは振り返る。蓄えの余裕は無くなり、健康保険の傷病手当金で暮らす日々が続く。「手当が無ければ大変なことになっていた」ところを、今度は思いもしなかった出来事に襲われてしまう。「退職」である。

離職理由を説明する書類には「休職期間満了」と記されていた(撮影:長谷川美折)
入院中の田中さんに対し、会社は「休職期間が過ぎた。退職してもらうしかない」と告げた。寝耳に水の話だったが、結局、退職願にサインせざるをえなかった。
生活は一気に苦しくなった。田中さんは語る。
「退職後は、後から入ってくる傷病手当金、失業保険、貯金の切り崩し。後は親からの援助。働かないと生活できないので、派遣として働いた。一番の心配はお金のこと。今思えば、会社の人に詳しく話して理解してもらいたかったが、安心して話せる人がいなかった」

田中さんは「会社にはがん治療に対する理解がなかった」と振り返る(撮影:長谷川美折)
「生きることを感じるためにも、仕事は大切」
新たにがんと診断される人は年間約85万人を数える。そのうちの約3割が働く世代(20歳~64歳)だ。
仕事との関係でみると、さらに衝撃的なデータもある。静岡県立静岡がんセンターの研究班による2013年の調査によると、がんになった人の34%は仕事を辞めているのだという。

がん患者の3割が自ら「退職」という道を選んでいる
仕事と治療。その両立の難しさを前に、多くの人が自らのキャリアを頓挫させてしまったと考えられている。
岐阜県に住む横山光恒さん(46)もそうした1人だ。システムエンジニアだったちょうど10年前、悪性腫瘍が見つかり、手術と治療でおよそ14カ月間休職した。復職したものの、2階級降格となり、収入も激減。ついには、退職勧奨を受け、2011年に退社に追い込まれた。

がん治療がきっかけで退職を余儀なくされた横山光恒さん(撮影:長谷川美折)
横山さんも治療費や生活費に苦しんだ。その一方で、お金より大切なものがあるとも感じた。「生きていることを感じるためにも仕事はとても大切」だったからだ。実感を込めて、横山さんはこう言う。
「ずっと仕事ばかりやって、言えないくらい残業もやって、頑張っていたつもりだったが、病気で働けないとなった時、意外と企業は理解がないんだな、と。『がんだから』と言われてしまうと、もう努力のしようがない」
そうした経験をもとに、横山さんは今、NPO法人・がんサポートセンター(岐阜市)の副理事長として活動している。「仕事を辞めなくて済むような、がんであっても働けるような手伝いができないか」と考え、がん患者の支援を続けている。

横山さんは右脇下に悪性腫瘍が見つかり、摘出手術を受けた(撮影:長谷川美折)
がんサポートセンターのように「がんになっても仕事を続けることができるように」という動きは、実は各地で芽吹いてきた。同じ東海地区で活動する支援グループ「ブリッジ」。医療関係者やキャリアカウンセラーらが集まり、患者の就労支援に携わる。
「ブリッジ」は2015年、がんと告知された時点で働いていた327人を対象にその実情を調査している。仕事を継続している人も200人近くいた。だが、離職者も133人いた。しかも辞めた人のうち、ほぼ半数は「仕事を続けようと思えば、そうできた人たち」だったという。企業の論理ではなく、自ら身を引く。その理由を代表の服部文さんはこう分析する。
「がんだから辞めないといけない、と。『がん=死』のイメージがすごく強い。医療の進歩で5年前、10年前とは全然違っていることを含め、正しい情報を知ることが大事」。医療の進歩を知らずに早々に諦める人、がんと知った衝撃から壮絶な闘病生活の準備を始める人、家族らから働くのは無理と言われる人......。そういった人々の状況は、正しい情報を知ることで変わると、服部さんは考えている。

病院内のがん相談支援センター。患者に正しい情報を伝えるのも役割の一つだ(撮影:長谷川美折)
がん治療と仕事の「両立」を支援する新たな動き
医療現場でも、「がん患者と就労」をめぐる取り組みは始まっている。その現場を見るため、名古屋第二赤十字病院を訪ねた。乳腺外科副部長、赤羽和久医師は乳がんの専門家だ。
「検査が全部終わって、こういう治療を、と話したとき、すでに仕事を辞めている人が結構いた。早まって辞めなくていいんじゃないか、と。病気を苦にして、中身をまったく知らないうちに辞めていく。臨床現場からすれば、それだけはふせぎたいな、と」
医師のプライドを感じさせる言葉だった。

「がん患者と就労」の問題に取り組む赤羽和久医師(撮影:長谷川美折)
では、赤羽医師は何を試みているのか。
「がんを告知するとき、まず仕事のことを聞き、辞めなくていいですよ、と付け加えます」。がんは不治の病。かつてはそんなイメージが強かったが、いまは変わりつつあるからだ。がんの種類によっては十分に治癒が見込めるし、長期にわたって付き合える病気になってきている。
赤羽医師は「仕事をすぐに辞めなくていい」と患者に告げたあと、期間を定めた治療計画を表にして示す。その資料があれば、職場の理解も得やすい。「がんだから」ではなく、最新の知見と技術に基づいて、当人にも雇用主側にも、貴重なキャリアを中断させないように、と訴えかける仕組みだ。

名古屋第二赤十字病院の診察室。がん患者は自分自身と向き合わなければいけない(撮影:長谷川美折)
日本で「がん対策基本法」ができたのは、2006年のことだ。それから10年。がん患者の離職が多いことに対しては、所管の厚生労働省にも危機感がある。そのため、同省は今年2月、ガイドラインを策定した。闘病しながら働けるようにするためで、就労中の患者と医師、企業などの連携を進め、情報交換を密にするよう求める内容だ。
労働基準局安全衛生部の中村宇一・室長補佐はこう言う。
「がん患者が仕事を続けられるという共通認識が、なかなか社会の中に広がらないので、まずは仕事と治療は両立できることを世の中に分かってもらおう、と。どうすればいいのか、企業の現場でもよく分からない、という声があるので、企業にも取り組めるような形を示そうとガイドラインを作りました」

会社のサポートが「がん患者」への光明となる可能性もある(撮影:長谷川美折)
企業側の意識も少しずつ変わってきた。
医療に関する電話相談を担う「ティーペック」は東京都内にオフィスがある。2014年から、がんになった社員に対する支援制度を社内に設けた。通常の有給休暇とは別に、がん治療に特化した有休を月2日まで取得できる。時差出勤や病状に応じた配置転換にも応じる。
人事部長の大神田直明さんによると、がん治療のために有休が不足した社員が出たことが、制度導入のきっかけだったという。その社員は欠勤扱いとなり、賃金カットの状態に置かれていた。
「人事部が(そういう社員がいることを)見つけたのがスタートです」
高度ながん検診の受診補助も行う。当然、企業の負担は増すが、ティーペックは「負担」と考えなかった。大神田さんはこう言った。「社員の健康にかける費用は、費用でなく投資。安心して働く社員のほうが絶対に生産性も高いと思います」
※冒頭と同じ動画
[制作協力]オルタスジャパン
[写真]
撮影:長谷川美祈
写真監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝