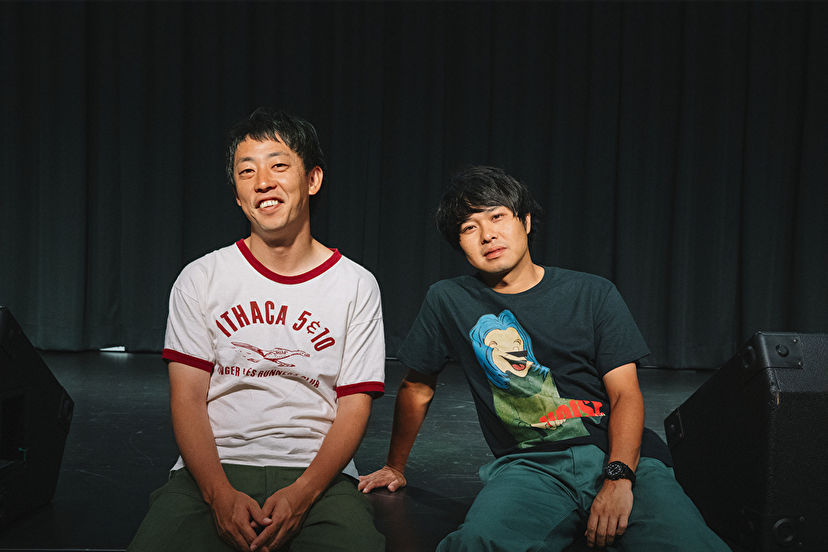映画『君の名は。』をはじめ、数々のヒットを放ってきた映画プロデューサー・川村元気(40)。小説家としてもベストセラーを生み、最近は脚本家や監督も務めている。現在は新海誠監督の最新作『天気の子』、ハリウッド版『君の名は。』などを手掛け、東京オリンピック・パラリンピックの開閉会式の演出にも携わる。国内外で複数の仕事をこなし、ヒットを連発できるのはなぜか。仕事術に迫った。(取材・文:Yahoo!ニュース 特集編集部/撮影:大河内禎)
(文中敬称略)
自分が新人になれる場所を探す
26歳の時、初めて企画・プロデュースした映画『電車男』(2005年)が大ヒット。以来、『告白』『悪人』『モテキ』『おおかみこどもの雨と雪』など、話題作を世に送り出している。2016年、『君の名は。』は社会現象になり、興行収入は日本映画の歴代2位となる250億円。全世界で累計400億円を記録した。
初小説『世界から猫が消えたなら』(2012年)は140万部を超えるベストセラーに。脚本家デビュー作となる『映画ドラえもん のび太の宝島』(2018年)は「映画ドラえもん」シリーズ歴代最高の興行収入となった。
現在は、映画『天気の子』の公開が迫るなか、4作目となる新作小説『百花』を出版。NHK Eテレで放送している『オドモTV』の総合演出や、東京オリンピック・パラリンピック開閉会式のプランニングなど、多数のプロジェクトに取り組んでいる最中だ。

川村が2017年に設立したSTORY株式会社のオフィスで
さまざまな仕事を、どう選択してきたのだろうか。
「自分が新人になれる場所を探す、ということです。『どうなっちゃうんだろう、これ』みたいな不安から始まって、分からないことを分かろうとするプロセスの中で、決定的なことを見つけて生み出していこうとしています」
「『仕事。』という対談集で、宮崎駿さんや坂本龍一さんなど、巨匠たちに『30代の頃、何をしていましたか?』って聞いて回ったんです。そしたら皆さんに割と共通点があって。人から突拍子もない企画を振られたり、偶然やる羽目になったりした時に、ブレークスルーがあることに気付いたんです。なので、『できないです、無理です』と言いながらも、そのことについて考えているうちに、斬新なアイデアを思い付く。やり始めると誰よりもムキになって頑張って、やがて新しいところへたどり着く。『自分のやりたいこと』にこだわる今のトレンドとは逆かもしれないですけど、『僕はこれをやりたい』と選んだ道は緩やかな下り坂な気もしていて、むしろ過剰に主体性を持たないほうがいいんじゃないかと思っています」

オフィスのデスクには、川村が買い集めたさまざまなおもちゃが並ぶ。オリンピックのトラックをモチーフにした木製のおもちゃ
ハリウッドと日本の違いは
今、川村にとって「新人になれる場所」はハリウッドだ。『君の名は。』はハリウッドで実写映画化が決まり、プロデュースに参加している。「スター・ウォーズ」新シリーズの監督としても知られるJ・J・エイブラムスと川村が共同でプロデュース。監督は『(500)日のサマー』のマーク・ウェブだ。
「当たり前ですが、ハリウッドでは僕のことなんて誰も知らないわけです。打ち合わせをしていて、『日本人の何者でもない少年がやってきて、いいアイディア出すじゃん』って思われる瞬間が楽しい。その時に初めて、J・Jとかマークが『仲間だ』と認めてくれる瞬間があって、それが楽しいですね」

ハリウッドと日本映画界の違いを実感することはあるのだろうか。
「違う部分は“余裕”です。時間も掛けられるし、お金もある。それから、世界中の人が見る前提になっていること。だから、『多様性の世の中で、主人公の少年少女が2人とも白人っていうのはあり得ないよね』という議論になる。ネイティブアメリカンの女の子とシカゴに住む男の子って発表されているんですけど、『そのシカゴの男の子も白人なの?』と。日本だと、当然どっちも日本人。人種をどう考えるかという視座が入ってくるのは、全く違うなと思います」
「あと職種を明確に区切るのは日本くらいだなとも感じます。例えば、今アカデミー賞に最も多くの作品をノミネートさせるプロデューサーの一人はブラッド・ピットですし、J・J・エイブラムスは元々『アルマゲドン』の脚本で出てきて、『LOST』のようなシリーズドラマも作るし、『スター・トレック』や『スター・ウォーズ』の監督もして、プロデューサーもやる。みんな“フィルムメーカー”という大きな枠でやっているんですね。僕も日本ではそう名乗らないけど、フィルムメーカーっていうのが自分の仕事なんだなと感じるようになってきました」

最近は国内と海外の仕事が「半々くらい」だと言う。2018年には、東京藝術大学教授の佐藤雅彦らと製作した初監督作品『どちらを選んだのかはわからないが、どちらかを選んだことははっきりしている』が、カンヌ国際映画祭短編コンペティション部門に選出された。プロデュースした『未来のミライ』はアカデミー賞の長編アニメ映画賞にノミネートされ、アニー賞の長編インディペンデント作品賞を受賞している。
「自分の作ってきたものが、同時多発的に海外とつながった。『君の名は。』にしても、『未来のミライ』にしても、海外を強く意識することもなく、ドメスティックに作ってきて。『あ、別に(国内と海外を)分けなくていいんだな』と思いました」
「自分の見たいものを作る」と決めている。
「見たいものは、二つあるんです。一つは『集合的無意識』。みんなが感じているけれど、なぜだかまだ表現されていないもの。もう一つは、最先端のテーマを古典的な手法でやること。そういうものは、ユニバーサルに届くんじゃないかと思っています」

『世界から猫が消えたなら』は世界15カ国で出版された。左から米国版と英国版。「イギリスの文学祭で記者や読者とQ&Aをしていても、日本で取材を受けているのと印象が変わらなかった。『日本的だね』みたいな感覚で読まれているわけではないんです」
『どちらを選んだのかはわからないが、どちらかを選んだことははっきりしている』は、「論理的な構造から、映画的な感情を生み出す」という実験的な試みだ。実の父を知らない息子と、その父が暮らす町へ旅に誘う母親。道すがら、いくつもの選択肢が現れる。2人いる町民のどちらに道を尋ねるか、青色と黄色の飴玉のどちらを舐めるか、父親に声を掛けるか否か――。どちらを選択したかは描かれず、選んだ後の2人の姿が映し出される。
「数学的な論理から映画を作るというのは新しい手法ですが、撮影や演出、編集は、オーソドックスな映画的手法を採用しました。入り口はロジックだけれど、最後は人間ドラマに見えてくる、奇妙な映画になっています。佐藤雅彦さんは、論理や物事の伝わり方をさまざまなメディアを使って表現する人。僕は物語に興味があって、いろいろな形で届けている。論理の佐藤さんと物語の僕が組んでカンヌに呼んでもらえたというのは、面白い実験でした」

『どちらを~』は14分の短編。黒木華、柳楽優弥が出演した。東京藝術大学大学院映像研究科の佐藤雅彦研究室から生まれた映画制作プロジェクトだ
人間を形成するのは記憶
「分からないからこそ」取り組んでいるのが小説だ。「いくら書いても分からない“沼”」だと言う。
「書けば書くほど、まだ先があるんだなっていう気がするから、やめられないんでしょうね。映画はみんなで頂上を目指してわいわい作る、山登りのような楽しさがあるんですけど、小説は一人で潜る。書くという行為を通して、自分自身の知りたいことに向き合う。だから、切実に自分が知りたいことを書きます」

最新小説『百花』で描いたのは、認知症の母親と、その息子だ。自身の祖母との会話が執筆のきっかけになった。
「5年前に祖母が認知症になりまして。会いに行ったら『あなた誰?』って聞かれたんです。それから祖母のところに通って、自分の思い出話をしていて。僕のことは忘れたり思い出したりしているんだけど、ある日、『海で大きい魚を釣って楽しかったよね』って言ったら、祖母が『湖だよ』と。家に帰って写真を見ると、確かに湖だった。いかに自分の記憶が曖昧か、気付いたんです」
「そもそも、『あなた誰?』ってすごい問いですよね。『僕の名前は川村元気で、映画を作っていて、好きな食べ物はシュークリームです』みたいに話したところで、果たして自分であることを証明できるのか」

考えを深めていくうちに、人間を形成するのは記憶だと思うようになった。
「『理系に学ぶ。』という本で、人工知能研究者の松尾豊さんと対談をしたんです。松尾さんは『人間を作りたい』と話していて。『人間を作るってどういうことなんですか』と尋ねたら、AIにひたすら記憶をさせるんだと」
「自分がもしも『面白い物語を書く作家のAIを作れ』と言われたら、ありとあらゆる作家の小説を記憶させた後に、『愛』という言葉や記憶が抜け落ちたAIを作ると思ったんです。自分の中にない愛というものを埋めるために、ありとあらゆる表現を使って愛を表し、そこに個性や作家性が生まれる。普段一緒に仕事をしている人たちを見ても、その人の欠損しているものが作家性になっているんですね。何を覚えているかではなく、何を忘れているかがその人の個性なんじゃないか。そして最後まで忘れられないものは何なのか――。そんなことを考えながら、小説を書きました」

これまで、小説執筆の際に多くの取材を行ってきた。今回もたくさんの人に会った。
「認知症の方に100人くらいお会いして、お話をさせていただきました。それから国内外の介護施設を10カ所ほど。有吉佐和子さんの『恍惚の人』(1972年)という傑作小説がありますけど、そこから40年以上経っているのに、認知症に関するイメージがアップデートされていない印象があったんです。なったら地獄で大変で……という。でも今、認知症患者は500万人もいるんです。これからますます認知症は日常になっていく。今の認知症、そこに向き合う人々の物語を描きたいから、ひたすら取材をしました」
「忘れるということを、肯定したいと思った。祖母が忘れていくことは悲しかったけれど、それを悲劇だとは思いたくない。認知症を通して見えてくる、人間と記憶について、親子について、エンターテインメントとして書きました」

多岐にわたる仕事をしながら、小説を書く。「そんな自分だからこそ書けるものがある」と言う。
「毎日取材しているようなものなんです。日々作り手の頭の中を覗いている。映画の脚本を一緒に作りながら、その脚本家の忘れられない記憶を聞けたりする。俳優やミュージシャンや映画監督などの記憶にも触れることができる。毎日の仕事と、小説のための取材を合わせれば、サンプルの数がすごく多い。そうやって数が増えていくと、東京だからとか日本人だからじゃなくて、普遍的なものにたどり着けるんじゃないかと」

スクランブル交差点で海が見える
今、進行中のプロジェクトは「50くらい」。それだけの仕事をどうやって並行しているのか。
「僕の仕事は“ストーリーテリング”なので、映画でも小説でも広告でも、いつも物語について考えている。物語って、そのことだけを考えていても浮かばない。物語を書く前に、何かに“気付く”ことが大事なんです。『働くぞ!』と意気込んでも、決定的なことには気付けない。だから割とぼーっとしているんですよ。何かに気付くために、気をずらしているというか。元々、子どもの頃から授業を聞いていないタイプで、次の授業や放課後にやることを考えたりしていたんです。頭を一つのことだけに使うのは、効率が悪いと思っている節があって。海を描きたい時に海を見ていても仕方なくて、渋谷のスクランブル交差点に立った時、そこに海が見えるほうが面白いと思う」

自身の原点だと語る幼少期の記憶がある。
「小学校に入る前、幼稚園にも保育園にも行っていなくて、家にテレビもなかった。社会というものに触れずに育ったんです。それで小学校に行ったら、『世の中に子どもがこんなにいるんだ』とまずびっくりした。ある日、『明日は図工の授業があるから、粘土板を買ってきてください』って先生に言われたんです。僕は色がきれいだと思ってピンクの粘土板を買ったんですけど、次の日学校に行ったら、男子全員が青で、女子がピンクだった。はやし立てられながら、内心すごく怒ってたんです。『そのルールは誰が決めたんだ?』って」
「『ミュージックビデオみたいなスリラー映画』とか『ロックミュージシャンがバンバン劇中で歌うアニメーション映画』『哲学書のようなファンタジー小説』とか、僕がトライしてきたのは、その当時の業界でありえないとされていたこと。僕にとってはそういうものが全部、“ピンクの粘土板”なんです」

少年の頃は泣いて粘土板を買い替えた。今は次々と企画を実現する。
「『ピンクで何が悪い』と頭から言っても誰にも聞いてもらえないので、『そもそも白から考えてみませんか? ピンクか青かは最後に決めましょう』みたいなことはやっています。世間の感覚と切断されて、独断で物を作ろうとは思わないから」
世界中の人が抱えながら、表出していない感情を、物語で浮き彫りにしようとしている。
川村元気(かわむら・げんき)
1979年、横浜市生まれ。上智大学文学部新聞学科卒。2010年、米The Hollywood Reporter誌の「Next Generation Asia」に選出され、翌年に優れた映画製作者に贈られる「藤本賞」を最年少で受賞。2014年に絵本『ムーム』を発表。アニメ映画化され、世界32の映画祭で受賞。著書に小説『億男』『四月になれば彼女は』、対話集『仕事。』『理系に学ぶ。』『超企画会議』などがある。映画『天気の子』は7月19日公開。最新小説は『百花』。